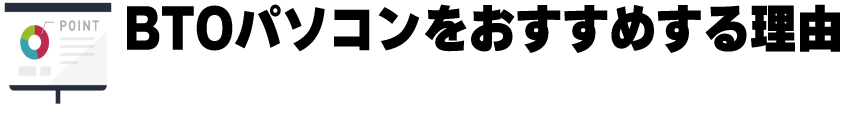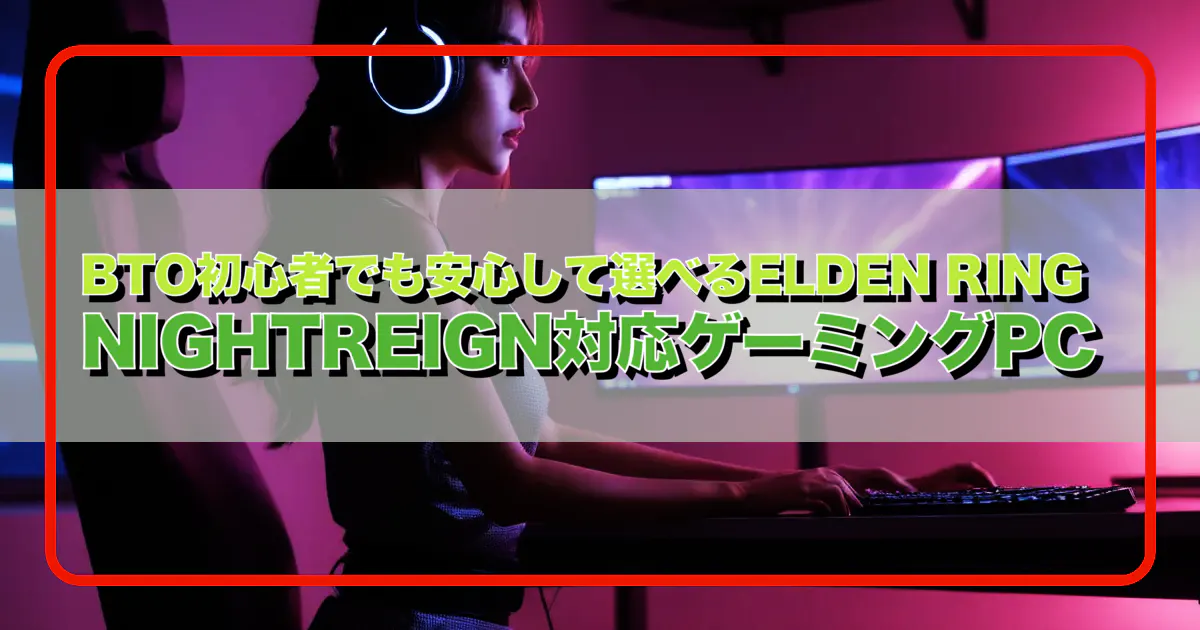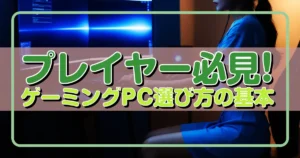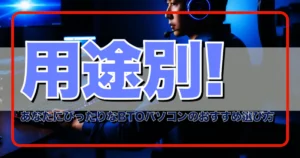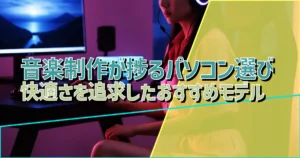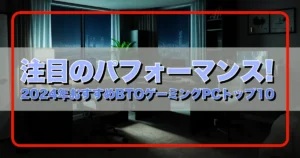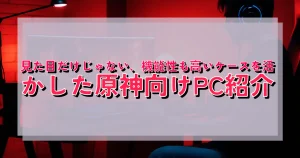ELDEN RING NIGHTREIGNを快適に遊ぶためにチェックしたいPCスペック

CPUはCore UltraとRyzen、実際どちらがプレイに向いている?
ELDEN RING NIGHTREIGNを心から楽しもうと思うなら、やはりCPUを軽く考えてはいけないと強く感じます。
私自身が試して思ったのは、短期集中で滑らかに戦いたいならCore Ultraがいいし、長丁場のプレイを腰を据えて楽しむならRyzenがいい、という結論でした。
性能の優劣ではなく、自分の遊び方にどちらが寄り添ってくれるかが分かれ道になるのです。
たとえば巨大なボスと戦う時、こちらの指の動きがほんの少しでもずれると無駄にストレスがたまる。
Core Ultraはその不安をしっかりと消してくれました。
WQHD環境でも激しい場面でフレームの上下がほとんどなく、妙に安心感がありました。
短時間の戦闘を繰り返すこのゲームでは、その瞬発力が大きな強みになるのです。
大量のキャッシュを持つだけあって、敵がわっと出てきても処理落ちせず、フィールド全体をぐんぐん移動しても止まらない。
ロード時間の短さにも助けられ、流れるように遊び続けられる。
そうなると「このCPUなら長い付き合いになりそうだな」と自然に思えてくるんです。
それは決して大げさではなく、熱中しすぎて時間を忘れるくらい快適でした。
ある時、友人の家でCore UltraとRyzenを並べて試す機会がありました。
夜間の静けさの中でもCore Ultraは耳障りなファン音を出さず、心地よいほど静か。
それに対してRyzenは熱がこもらず安定していて、室内全体が快適に保たれる印象がありました。
そういう部分にメーカーごとの哲学を感じてしまいます。
設計思想の違いですね。
BTOパソコンを組む段階になると冷却の考え方も重要になります。
Core Ultraなら空冷でも十分に静音性を確保できるので構成が非常に組みやすい。
一方でRyzenを使う場合、とくにハイエンドモデルではケースのエアフローをきっちり考えてあげたい。
そこさえ間違えなければ、水冷に頼る必要もないまま長時間のプレイで安定を維持してくれるのです。
だから私はケース選びの一手間が大事だと思います。
面倒でもやる価値はある。
RTX 4070 SUPERと組み合わせて試した時、二つの性格の違いはより鮮明でした。
瞬間の切り返しに強いCore Ultra 7 265Kは、ボタン入力に即応し、攻めのリズムを作るのが得意。
これに対してRyzen 7 9800X3Dは、乱戦や派手なエフェクトが重なるシーンでも落ち着いた動作を維持し、じわじわと強みを発揮します。
どちらを選ぶかは、スピードをとるのか粘りをとるのか。
その選択は自分の性格を映し出されているようで、ちょっと面白くなってしまいました。
未来を見据えると、AI処理の存在は大きな意味を持ってきます。
Core Ultraの持つNPUがWindows環境でのAI加速に絡むと、録画や配信、作業を並行する上で確かに有利です。
しかし純粋にゲーム体験だけを考えるなら、Ryzenの大容量キャッシュがプレイヤーを助けます。
スタッターが少ないだけで、ここまでプレイの没入感が違うのか、と私は驚きました。
負荷を意識せずに遊べることが、どれほど気楽で価値のある体験かを知ってしまったのです。
たとえるなら、Core Ultraは一気に試合を決めにいくバスケットボールの速攻チーム。
反対にRyzenは試合全体の流れを確実に管理するサッカーの守備型チーム。
どちらも勝利する可能性はあり、短期決戦か長期戦かで見え方が変わる。
ただ、特に長い時間かけて遊ぶ時には、その安定度がじわじわ効いてきます。
これは机上の数値を眺めていては分からない実感でした。
だから私は、少なくともELDEN RING NIGHTREIGNを遊ぶならCore Ultra 7かRyzen 7 9700X以上を選ぶべきだと思います。
もちろんフルHDで軽めに遊ぶくらいならCore Ultra 5でも事足りるでしょう。
でも将来的にWQHDや4Kを想定しているなら、最初から余力を意識しておいたほうがいい。
買い替えの手間や気持ちの後悔を減らせますからね。
CPUを選ぶという行為は、単にスペック表とにらめっこすることではありません。
どちらを選んでも間違いにはなりませんが、自分がどんな遊び方をしたいのかを問い直すこと。
そこを外さなければ、本当に納得できる相棒を見つけられると確信しています。
安心感。
没入感。
結局、CPUは単なるパーツではなく、長く付き合う信頼できるパートナーなのだと私は思っています。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43437 | 2442 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43188 | 2247 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42211 | 2238 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38943 | 2058 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38866 | 2030 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35977 | 2177 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33203 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32721 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29522 | 2021 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 2155 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23298 | 2192 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23286 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 21046 | 1842 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19684 | 1919 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17893 | 1799 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15428 | 1963 | 公式 | 価格 |
グラフィックボード選び RTX5060TiとRX9070を比べてみる
ここ最近、友人や同僚とよく盛り上がる話題のひとつに「どのグラフィックボードを選ぶのが正解か」というものがあります。
家庭でちょっとした空き時間に遊ぶにせよ、仕事で溜まった緊張を解きほぐすように没頭するにせよ、やっぱり安心して快適に動いてくれるかどうかは重要です。
性能の数字や広告のうたい文句ではなく、自分の生活にきちんと馴染むかどうか。
これが結局の決め手になるのだと、私は感じています。
私が実際に触ってみて思ったのは、フルHDで十分ならRTX5060Tiで文句なしですし、今後数年間を見据えて4Kやハイエンドの体験を求めるならRX9070を選ぶべきだということです。
まずRTX5060Tiから話すと、コストパフォーマンスの高さは魅力的です。
普段の軽いゲームプレイなら安定して60fpsを確保でき、グラフィックが大きく乱れることもありません。
ああ、安心するなあと思えました。
数か月前に導入して試しに遊んだときなど、「いやこれはすごい」と独り言をもらしてしまったくらいです。
肩肘張らずに遊べる。
その一方でRX9070に触れると、パワーが違うと強く感じます。
特に長時間のプレイや4Kの迫力ある映像では一歩抜けています。
FSR4による映像の繊細さには「なるほどな」と感嘆しました。
電力消費は大きめですが、冷却環境をきっちり整えてやれば不安はなく、むしろその余力が自分にゆとりを与えてくれる。
私はその体験をしたときに、これが本物の投資かもしれないと思いました。
例えば、ゲームをしながら同時に動画を流したり、配信をかけたりするような場面。
普通なら処理が重く感じやすいのですが、RX9070は難なくこなしてくれる。
それが日常を支えてくれる心強さに繋がります。
実際、同僚とオンラインで雑談中に「これ一枚でここまで余裕が出るのはすごいな」と思わず語ってしまい、相手も「本当にそうだよな」と笑いながら同意してくれたことが印象に残っています。
価格の面に話を移すと、RTX5060Tiはやっぱり財布に優しいです。
40代になると趣味に回せる予算も限られてくるので、費用対効果の高さは大きな判断材料です。
しかし、頭をよぎるのは5年後の自分です。
ゲームがさらに重くなった未来を考えると、少し余力を積んでおいた方が結果的に得かもしれない。
その意味で、RX9070への投資は現実的で冷静な判断だと思う瞬間があります。
守りより攻め。
また、発熱や静音性についても忘れてはいけません。
家族が静かに過ごしている夜、書斎で小音量で楽しむならやはり扱いやすさ重視です。
手軽さがありがたい。
一方でRX9070を活かすには強力な電源や十分な冷却ファンが必要です。
条件づけは厳しいですが、その環境を整えてやれば得られる体験の満足度は桁違いです。
私自身、過去にBTOパソコンを組んだ際、冷却対策を軽視したがために性能を十分引き出せなかった苦い経験があります。
あれはしんどかった。
だからこそ、RX9070を使うならしっかり準備して臨む。
だから次はきちんと段取りです。
学び。
あらためて考えると、どちらを選ぶかは単なる性能比較にとどまりません。
日常で安定した軽快さを選ぶのか、それとも未来の重量級ゲームや拡張コンテンツを見据え、余力を積んで楽しみ続けるのか。
自分がどんな暮らしを望み、どんなペースで遊びたいかというライフスタイルの問題に繋がっています。
人生の使い方です。
私は正直、今の生活スタイルならRTX5060Tiが合っています。
仕事に追われている毎日の中で、短い時間に手軽に遊ぶ。
しかし心のどこかで「やっぱり余裕を持つならRX9070か」とつぶやく私もいます。
先日同僚に相談したとき「結局そういうのは後で上が欲しくなるもんだ」と言われ、妙に納得してしまいました。
ズバリ指摘されて笑いましたが、確かにそうだよなあと胸に刺さったのも事実です。
自分がどんな時間を大切にし、どんな未来の景色を求めるか、その一点だけを見つめて選択すれば後悔はないはずです。
RTX5060TiかRX9070か。
それは単に「部品を買う」以上の話です。
日常をどう彩りたいかという問いへの答えです。
そして忘れてはいけないのは、どちらを選んでも一定水準をしっかり超えてくるということ。
選んだ瞬間から、あなたの生活に溶け込み、日々を充実させる相棒になってくれると断言できます。
結局、私たちが求めているのはカタログの数値ではありません。
毎日の慌ただしさの合間にひと息の楽しさを添えてくれる存在です。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49113 | 100929 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32430 | 77302 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30414 | 66101 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27399 | 68249 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26736 | 59644 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22140 | 56240 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16704 | 38983 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16133 | 37823 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15994 | 37602 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14766 | 34575 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13862 | 30555 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13317 | 32041 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは32GBで足りるのか?64GBを選ぶべきケースとは
メモリをどれだけ積むべきか。
この問いに対する私の考えは一言で言えば、使い方次第で明確に答えが変わる、ということです。
例えば、ELDEN RING NIGHTREIGNをプレイすることを主軸に置くならば、32GBあれば十分に満足できる環境が整います。
推奨16GBという前提を考えれば、倍の容量を確保しているわけですし、普通に遊ぶ分には不安を感じることはまずありません。
その安定感は、正直ありがたいと思います。
映像編集や配信作業と同時にゲームを動かそうとすると、32GBという容量に「余裕がない」と実感する場面が出てきます。
特に最近話題の生成AIのような重いツールを並行して使うと、一気にメモリが圧迫されてしまい、心の落ち着きを削られるような感覚に襲われるのです。
私は実際に、高解像度で配信を流しつつ画像生成AIを動かしたとき、32GB環境では使用率が常に張り付いている状態になりました。
パフォーマンスの落ち込みが大きくなくても、「このまま止まったらどうしよう」という不安を胸に操作する時間は決して快適とはいえず、ゲームを純粋に楽しむ余地を奪われた気がしたのを覚えています。
そこで思い切って64GBへ環境を変えたのですが、その体感は想像以上に大きな変化でした。
複数アプリを同時に立ち上げ、ブラウザのタブを気にせず増やせる。
動画を録画しつつ編集、さらに配信までかけ合わせても、まだ容量に余裕が残っている。
もうリソース残量を逐一チェックする必要もなく、「大丈夫だ」と思える。
それは実際に試してこそ理解できる安心の感覚です。
思わず「ああ、こういうことだったのか」と心の中でつぶやいたほどでした。
シンプルにゲームを楽しみたい人には32GBで十分です。
フルHDやWQHD程度の解像度で遊ぶなら、64GBに投資する必要はほとんどありません。
その余剰分をグラフィックボードやストレージに回す方が、はるかに実感できる快適さにつながります。
それに、世の中の多くのBTOパソコンが32GBを基準にしていることを見れば、今の時点での標準的な落としどころは間違いなく32GBだと言えるでしょう。
普段の用途がゲーム中心なら「それでいい」わけです。
それでも私は、過去の失敗からひとつ学びました。
以前、小型で安価なマザーボードを選んだせいでメモリスロットが2本しかなく、後から増設ができないという事態に陥ったのです。
「あの時、ちょっと先を見据えて選んでおけば」と悔やむ気持ちは、今でもはっきりと残っています。
だからこそ、今これから環境を整えようとする人には、目先のコストだけに縛られる危うさを強く伝えたいのです。
しかし、映像編集や配信、さらにAIといったクリエイティブな用途を同時にこなすなら話は別。
64GBは単なる「余裕」ではなく、実際のストレスを減らしてくれる武器になる。
そこに価値があると私は考えています。
肝心なのは自分に問いかけることです。
本当にゲームだけで満足するのか、それとも配信や制作と組み合わせたいのか。
ELDEN RING NIGHTREIGNは60fps上限という仕様もあり、究極的なハイエンド環境を求めるような作りではありません。
そのため「一緒に何を走らせるか」が判断の基準になります。
純粋にゲームだけなら32GB、並行して創作をしたいなら64GB。
単純でわかりやすい線引きではありますが、この問いから逃げることはできません。
後悔。
私はもう、拡張性を見落として安易に選ぶような失敗はしたくありません。
だからこそ、これから環境を組む人には伝えたい。
目先の数千円単位に惑わされず、長期的に「安心して使える構成」を目指した方がいいと。
予算を理由に妥協してしまったときの後悔は、確実に長く残ります。
最終的にまとめてしまえば、単に数字の大きさでメモリを選ぶのではなく、自分のワークスタイルに照らし合わせて判断する、それに尽きると私は思います。
ELDEN RING NIGHTREIGNを快適に遊ぶためなら32GBで十分です。
ただし、配信や編集など多用途を同時進行するのであれば64GBの選択が精神的にも実際的にも快適さを保証します。
安心感。
ストレージはGen.4 SSDで十分?Gen.5を選ぶメリットはある?
私の場合、ゲームを楽しむことが主目的なので、Gen.4のSSDが最適解でした。
実際の挙動を見てもわかりますが、ELDEN RING NIGHTREIGNのような重量級タイトルでさえロード待ちのストレスは皆無。
立ち上げて数秒後には操作できるので、「ここから先は性能を追っても自己満足の世界だな」と思ったほどです。
もちろんGen.5は圧倒的な処理性能を持っています。
むしろそのパワーを必要とするのは、毎日高解像度の動画を扱ったり、AI処理を多用したりしているクリエイターやエンジニアの方々でしょう。
映像制作をかじる私でさえ、大量データを触るときは「ああ、速いほうが絶対助かる」とはっきり思うので、仕事でやる人にとってGen.5は必須レベルなんだと想像します。
セリフ調で言えば「もうGen.5じゃないと話にならない」という場面は確実にあるのです。
ただ、遊び中心の私にとっては話が別です。
自宅のマシンにはGen.4の2TBを載せていますが、快適そのもの。
むしろ職場にあるGen.5搭載機と比べても、その差を体感できることは滅多にありません。
むしろ気になるのはGen.5特有の熱問題。
冷却に気を配らなくてはいけないのが悩ましくて、正直「ちょっと面倒だな」と感じてしまう。
ゲームを楽しみたいのに、ハード面に振り回されるのは違うだろうと思うのです。
だから私は「容量と安定性」を優先しました。
なぜなら、今のゲームってアップデートやDLCでどんどん大きくなっていくからです。
Gen.5の性能を誇るよりも「足りない容量のほうがよほどストレスになる」。
新しいゲームを入れるたびに昔のデータを削除するのは、本当に嫌な作業なんですよ。
せっかくの休日に、遊ぶ前からデータ整理に時間を取られるなんて馬鹿らしい。
楽しいよりも管理している感覚の方が強くなる。
だから容量は大切なんです。
職業的に映像編集や3D制作を行う人なら、「高速なSSDをOS用に、安定感のあるSSDをデータ用に」という切り分けが理にかなうと思います。
例えばシステムはGen.5に任せつつ、ゲームや一般データはGen.4に置く。
これなら性能と現実的なバランスが両立できる。
私は使い分けこそベストだと感じています。
ある意味、無理してどちらかに偏る必要なんてないんですよね。
実際、知人のクリエイターは「私はGen.5を選ぶしかない。
秒単位の時短がそのまま生活の質につながる」と語っていました。
その言葉には納得感がありました。
彼にとってSSDは単なるパーツではなく、成果に直結する武器なんだと。
逆に私のゲーム仲間は「余計な出費するくらいなら4TB欲しい」と普通に話しています。
なるほどなと思いました。
人によって最適解がこんなに違うのだと。
つまり、考えるべきは「最新だから選ぶ」ではなく「自分にとって必要かどうか」なんです。
私の場合はGen.4で十分でした。
ロードは驚くほど速いし、値段も落ち着いてきている。
安心感があります。
2TBの余裕もあるので「このゲームも遊びたいな」と思ったときに、気兼ねなくインストールできます。
削除の心配がないって、想像以上に気持ちの余裕になるものです。
これは実際に体験しないとわからない部分かもしれません。
快適なゲーム生活。
そう感じられる瞬間が何度もあります。
結局のところ、ゲーミングメインの方はGen.4で必要容量をしっかり確保すれば満足できます。
Gen.5は特殊な負荷を抱えるクリエイターや研究者のための選択肢。
冷却や価格を気にせず性能を引き出す必要がある人なら選ぶべきなのでしょう。
でも、私のような「ゲームを心底楽しみたいだけの人間」にとっては、容量に余裕のあるGen.4がベストアンサーです。
体感の快適さ、容量の安心感、そして価格とのバランス。
その三つが満たされれば、余計な悩みすら消えていきます。
だから私は胸を張って言えます。
「性能より容量を優先しよう」と。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
パソコンが初めてでも安心できるELDEN RING NIGHTREIGN対応BTOの探し方

コストを抑えつつ快適にプレイできる構成はどこまで可能か
ゲームを快適に遊ぶ上で大切なのは、最高の性能を追いかけ続けることではなく、自分の生活や予算に見合ったちょうど良い環境を選ぶことだと私は考えています。
ELDEN RING NIGHTREIGNのようなタイトルを遊ぶときに求められるのは、4Kや最高設定ではなく、60fpsを安定して維持できる安心感。
それこそが一番の価値だと思います。
私は20代の頃、給料を無理に削ってハイエンドPCを組んだことがあります。
「最強なんだから間違いない」と思い込んでいました。
けれども実際に遊んでみるとフレームレートは結局60fpsで打ち止め。
数字の上では圧倒的な性能なのに、体感はほとんど変わらない。
あのときの肩透かしのような感覚は今でも忘れられません。
その経験以降、私は性能表やスペック比較よりも「使って心地よいかどうか」を大切にしています。
つまりは必要十分。
それが一番なんです。
フルHD環境なら、現行のミドルクラスGPUで十分対応できます。
RTX 5060やRadeon RX 9060XTあたりを選べば、描画の乱れも気にならずきちんと滑らかに動いてくれる。
CPUもCore Ultra 5やRyzen 5程度で問題ありません。
もちろん数字だけ見れば華やかではありませんが、この安定感こそが長い相棒と言える大切な価値になるのです。
昔の私なら「少しでも上を」と思っていましたが、今はこの安定こそが選び続けたい理由になっています。
気持ちの余裕。
とはいえ、WQHDの解像度に挑戦したい気持ちも無視できません。
その際はGPUを5070やRX 9070クラスにすれば、大きな無理なく楽しめます。
CPUもCore Ultra 7やRyzen 7あたりを選べば十分です。
ここで大事なのは「上を目指すにしても階段を一段飛ばしにしないこと」だと思います。
無理なく、かつ満足できる範囲で揃える。
その姿勢が結局、財布にも精神的にも優しいんですよね。
私はまず1TBからスタートしました。
そして遊ぶタイトルが増えた頃に2TBへ換装。
意外と必要な容量は人によって違いますし、実際に自分がどのくらいゲームを抱えるのか肌で確かめてからで十分。
初期投資を抑えつつ、必要になったときに追加する。
その方が無駄がなく、後悔も少ないんです。
この判断をしたとき、自分も少しは成長したなと感じました。
嬉しい自己満足です。
冷却については昔から水冷に憧れていたものの、実際にはそこまでの必要性を感じませんでした。
最近のCPUは熱設計が優秀で、しっかりした空冷クーラーを選べば安定します。
確かに水冷システムの煌びやかな見た目は魅力的です。
でも夜中に長時間ゲームをしているときに「安定して動作してくれること」の方に心からありがたみを感じます。
見栄えよりも実用。
これが年齢を重ねて実感した真実です。
PCケースの選択も似ています。
LEDで光り輝くケースに心惹かれた時期もありました。
毎回ケースを開けるたびに「やっぱりこれで良かった」と思えるのは、地味ですが実用本位の選択をしたからです。
今の自分なら迷わずそう言えます。
実用性の勝利。
総合的にまとめると、フルHD60fpsを目指すならGPUはRTX 5060、RX 9060XT、CPUはCore Ultra 5やRyzen 5、メモリは16GB、ストレージはまず1TB、冷却は空冷。
これで十分狙った環境を実現できます。
WQHDを考えるならGPUに少し余裕を持たせる程度で良い。
特に4Kを選ぶと大きなコスト増を招きますが、60fps上限を踏まえればそれに見合う価値を感じられる場面は限られます。
欲張った装備は結局持て余す。
そう気づくと自然と身の丈を意識するようになります。
歳を重ねた今、あらためて実感するのは「持続可能な選択」のありがたさです。
かつては贅沢を優先し、後から後悔したことも少なくありません。
でも今では無理のない範囲で環境を揃え、それを長く使い続けることにこそ喜びを感じます。
派手さより安心感。
性能の限界を追いかけるより、自分の生活と調和する選択を。
フルHDから4Kまで滑らかに動かすための性能の目安
ELDEN RING NIGHTREIGNをしっかり楽しむために、最も大切だと私が考えているのは各解像度ごとに必要な性能の水準を押さえることです。
映像の美しさはもちろん重要ですが、それ以上にカクつきやフレーム落ちによる途切れが没入感を奪います。
逆に安定した動作環境が用意できれば、余計なことを気にせずに物語や戦闘に集中できる。
これこそがゲーム体験の質を大きく左右するのだと痛感しています。
フルHDでプレイする場合は、正直なところ最新のミドルクラスGPUと16GBメモリで十分に楽しめます。
RTX 5060やRadeon RX 9060XTあたりであれば、派手な魔法や大規模戦闘でもなめらかに動いてくれますし、CPUもCore Ultra 5やRyzen 5で事足りるのです。
私が初めてフルHDの環境を整えたとき、正直「肩の力を抜いて遊べるってこんなに楽なんだ」と思いました。
だから無理して背伸びする必要はないと感じたのです。
ただし、WQHDに手を出すと話は変わります。
私は以前、この部分を軽く見てしまいました。
その結果、戦闘中に処理が追いつかず、エフェクトのたびにカクつくという失敗を経験しました。
あのときの落胆は今も忘れられません。
結局は予定より早く買い替える羽目になり、教訓として胸に刻まれています。
CPUもCore Ultra 7やRyzen 7クラスを選ぶべきです。
そして真に覚悟が求められるのが4Kです。
ここはまさに妥協できない領域であり、要求性能の高さに驚かされます。
私が4K環境を組んだとき、RTX 4070 SUPER以上のGPUとCore Ultra 7クラスのCPU、そして32GBのメモリをセットアップしました。
さらにNVMe Gen.5 SSDを使ってみたのですが、これは予想以上に効果があった。
数秒のロード時間短縮でも、続けてプレイする中では大きな違いを生みます。
「もう次の場面か!」と思えるこのテンポは、確実に熱中度を加速させるものでした。
これを体験してから、私はロード時間の短縮を軽んじなくなりました。
実際のところ、パーツを選ぶ際に忘れてはならないのが冷却とケース構造なのです。
性能の高さばかりに気を取られると、この部分を見落としがちになります。
過去に私は小さなケースに詰め込み過ぎてファンが常時フル稼働し、騒音と熱に悩まされたことがありました。
その時ばかりは耳にも心にもダメージ大。
ストレスフルで、正直プレイどころではありませんでした。
今になってはっきり言えます。
特に4K環境を目指す方であれば、ケースのエアフローと冷却性能にしっかり投資してください。
私がここまで話してきて思うのは、それぞれの解像度に合った「正解」が確かに存在するということです。
フルHDは気軽に楽しめる安心感、WQHDは安定と快適さのバランス、4Kは全力を注ぎ込む真剣勝負。
それぞれに魅力があり、用途や価値観によって選ぶべき基準は異なります。
ただ、一貫して外せないのは安定して60fpsを確保すること。
これが軸です。
スペックが足りないと、どんなに映像が綺麗でも没入感は損なわれてしまう。
そう思うのです。
フルHDはミドル、WQHDは上位、4Kは妥協なし。
迷ったときでも、この三段階を目安に考えれば判断がブレません。
私自身、以前は情報に流されて回り道をしました。
「やっぱりこれじゃ足りなかったか」と後悔したことも数えきれないほどあります。
だからこそ今はシンプルに考えています。
悩み過ぎると結局選べなくなるんですよね。
最終的にどのレンジを選ぶかは、人それぞれのゲームに対する姿勢や価値観によります。
映像美を徹底的に追い求めるか、安定プレイを優先するか、それともコストとのバランスを取るか。
正解は一つではありません。
ただ、一つだけ共通して言えるのは「安定した60fpsを守ること」だけは絶対に外してはいけない、という点です。
これさえ守ればELDEN RING NIGHTREIGNの濃密な世界は裏切らない。
作品の魅力を余すことなく堪能できる、その確信があります。
私にとっての学びはシンプルです。
信頼できる目安を掴むこと。
そして、お金も時間も決して無限ではないからこそ、後悔しない選び方をしたいと思います。
日常の仕事で培った判断力や経験は、こうした趣味の分野にも必ず生きてくると感じています。
効率を求めつつ、楽しみを最大化する。
私がずっと大事にしている考え方です。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56V

| 【ZEFT Z56V スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DZ

| 【ZEFT Z55DZ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58B

| 【ZEFT Z58B スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58U

| 【ZEFT Z58U スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56E

| 【ZEFT Z56E スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
CPUクーラーは空冷で問題ない?それとも水冷が良い?
多くの人がゲーミングPCを考えるとき、どうしても目が行くのはグラフィックカードやメモリの容量ですが、冷却性能の重要性を軽く見てはいけないと私は心から思っています。
フルHDやWQHDで「ELDEN RING NIGHTREIGN」を遊ぶ程度であれば、むやみに水冷を選ぶ必要はありません。
私が手にした体感としても、よくできた大型空冷クーラーなら静かさと冷却力をどちらも満たしてくれるのです。
理屈ではなく、実際に使ってみると納得できる優位性があります。
空冷の最大の魅力は、とにかくシンプルな構造にあります。
だからトラブルが起きにくいし、長い目で見れば扱いやすさに助けられることが多い。
私は仕事と家庭を両立させる日々の中で、ちょっとした合間にゲームを楽しんでいます。
だからこそ余計な心配を減らしてくれる空冷は、正直ありがたい存在なのです。
壊れにくい、メンテナンスが軽い。
その当たり前の強さが大きな安心感をくれる。
だからといって水冷を真っ向から否定する気もありません。
むしろ条件次第では圧倒的に有利になる。
その理由も自分の体験でよくわかっています。
4K解像度で画質を最高値にして数時間続けてプレイしたり、同時にゲーム配信をしてCPUが休む暇もなく働き続ける場合、空冷だとどうしてもファンの回転数が高まり、耳に付く騒音が気になってしまうことがあります。
一方、水冷では熱を外へ効率的に逃がすため、ファンを必要以上に回さず静かに温度を下げられる。
あの安定感は鮮やかさすら感じる。
いわば高性能の車を高速道路に走らせたときに真価を実感するような感覚です。
状況によって「これしかない」と思える強さを見せつけてくるのです。
実際、私は以前にメインPCへ大型空冷クーラーを搭載していました。
静音性を優先してファンの回転を抑えると、逆にCPU温度が気になって落ち着かない。
この矛盾がストレスで仕方なかったのです。
そこで思い切って水冷へ切り替えたところ、それまでの熱籠もりが嘘のようにスッと改善しました。
ホッと肩の力が抜けたのを今でもよく覚えています。
あの瞬間、この選択に救われたと心の底から思いました。
しかし水冷にも当然のように弱点があります。
ポンプ音が小さく響くことで気になる人もいるし、年単位で使うとメンテナンスの手間や潤滑剤の劣化に備えざるを得ません。
液漏れのリスクも理屈の上では決してゼロにならない。
それでもなお、高負荷における安定した冷却力を目の当たりにしたとき、私は「なるほどこれだ」と素直に納得しました。
水冷が持つ力は確かなものです。
BTOショップのカタログを眺めてみると、多くのモデルに空冷と水冷が並んで選択肢として提示されています。
人の関心はどうしてもGPUやストレージ性能へ偏りがちですが、冷却方式が主要な判断材料のひとつとして紹介されている事実を見れば、それが軽視できない要素であることに気付かされます。
特に最近はケース設計も著しく進歩しており、フロント全体を大きく開けたメッシュ構造や支柱を取り払ったピラーレス仕様など、空冷でも十分にエアフローを確保できるようになっている。
一方で、見た目の美しさを追求する人にとっては水冷のホースやリザーバータンクを見せる構成も魅力的で、性能だけでなく美観にこだわる層からの支持も厚いのです。
ここで大切なのは、「どちらが正解」と単純に決めつけられるものではないということです。
標準的なゲームプレイを快適に楽しみたいなら空冷で十分。
実際に両方を経験してきた私だからこそ断言できますが、空冷は堅実な安心を与えてくれ、水冷は余裕と静寂を保証してくれるのです。
悩むんですよね、本当に。
あれもこれもと欲張って考える私の性格だからでしょうか。
けれど結局のところ、自分の用途や理想を冷静に見つめ直せば答えは自然に出ます。
普段のプレイ環境なら空冷。
それ以上を求めるときは水冷。
このくらいシンプルに割り切ることで迷いも減っていきます。
最後に言いたいのは、冷却方式の「最適解」は人それぞれのプレイスタイル次第だということです。
自分がPCでどう遊びたいのか、どこまで快適さを追い求めたいのか、その素直な気持ちを基準にすればいいのです。
その結果として自分で選んだクーラーは、たとえ空冷でも水冷でも、使っていくうちに確かな愛着が生まれます。
大切なのは納得して選ぶこと。
そして選んだ相棒を信じきること。
これこそが、長くPCを楽しみ続けるための一番確かな道だと私は強く感じています。
ケース選びは冷却性能を優先?デザインとのバランスの取り方
なぜかというと、どれだけ高性能なパーツを組んでも、ケース内の温度管理が不十分なら性能を発揮できないどころか寿命を縮めてしまうからです。
見た目に惹かれてデザイン重視で選びたくなる気持ち、もちろん私にもよく分かります。
ただし実際に経験してみると、その選択が後から自分の首を絞めることになるんですよね。
私も以前、強化ガラスをふんだんに使ったかっこいいケースを見つけて「これしかない」と即決したことがありました。
しかしいざ使ってみると数時間で内部に熱がこもり、ゲームを続けるのが不快になるレベルでした。
冷却ファンを後から追加する羽目になり、出費も労力もかさむ始末。
あのとき鏡に映る自分に「なぜ性能より見た目を優先したんだ」と問い詰めたいくらい悔しかったです。
思い出すと今でも苦々しい。
ここ数年では冷却とデザインが両立したケースが増えてきました。
こうした進化を目にすると、メーカーも課題を理解し、ユーザーが求める声に応えようとしているのだと感じます。
自然体。
私が学生の頃は、PCケースなんてただの箱という認識でした。
それが今や、RGBで部屋を鮮やかに彩る選択肢もあれば、インテリアに溶け込む落ち着いたデザインも選べる時代になっている。
レビューサイトを覗けば「派手さより静音性を求める」という声も多く、趣味やライフスタイルの表れとしてケースが語られているのを実感します。
価値観の多様化と時代の変化がしっかりそこに映っている。
そんな中で私が声を大にして言いたいのは、冷却の吸気と排気の流れを必ず意識すべきだということです。
吸気が弱ければケース内の空気はすぐに熱くなり、排気が追いつかなければパーツは最大の実力を発揮できなくなる。
結果としてファンの音がうるさくなり、せっかく没入しようとしたゲームの世界から現実に引き戻されてしまう。
静音性は単なる快適さの問題じゃないんです。
安心感そのもの。
同僚からケース選びの相談を受けたとき、私は「シンプルでいいからメッシュタイプにしろ」とアドバイスしました。
結局その同僚は冷却性能を重視した製品を購入し、後日「あのアドバイスが役に立ったよ」と感謝してくれました。
そのときの会話の中で、「多少デザインは地味でも安定した冷却の快適さには代えられない」と語っていたのが印象に残っています。
やっぱり中身が大事なんですよ。
私自身、新しいケースを選ぶときはデザインを何度も見比べました。
ただ最終的には「まず冷却、それからデザイン」という優先順位を自分に言い聞かせるしかなかった。
いくら部屋に映える見た目でも、数年使えないなら本末転倒なんです。
長期的な快適さの方が圧倒的に重要。
市販モデルの中には、防音材を貼って静音性を高めつつ、しっかりとエアフローを確保した製品も少なくありません。
さらに標準で120mmや140mmの大型ファンを備え、水冷ラジエーターを搭載可能な余裕のある構造を持つケースもあり、以前に比べれば飛躍的に選択肢の幅は広がっています。
これから先は、家具や部屋の雰囲気と自然に調和しつつも、内部構造では冷却効率を極限まで高めるようなケースがますます主流になっていくでしょう。
外観の美しさと内部の実力、この二つを兼ね備えた存在感。
私も次に組むときには木目調の落ち着いたケースを候補にしています。
仕事机の横に違和感なく置けるのに、真夜中に長時間プレイしても熱で困らない。
それを想像するだけで胸が躍るんですよ。
見た目も冷却も両方を満たした一台を迎え入れることは、趣味としての喜びだけではなく、日々の生活を少し豊かに変えてくれるだろうと信じています。
実際、冷却を軽視するとCPUやGPUのフレームレートは安定せず、快適な環境どころかストレスしか残らない上に部品の寿命も削ってしまいます。
一方、冷却を優先したケースに愛着のわくデザインを選ぶことができれば、ゲームだけでなく作業や仕事にも気持ちよく使い続けられる。
これは数々の失敗と成功を経た私が心から言えることです。
だからこそ後悔しないための秘訣は、この順番を守り抜くことに尽きるのです。
ケース選びで迷ったら、まず冷却性能を見てください。
そのうえで自分のライフスタイルに合うデザインをじっくり楽しんで選べばいい。
もしELDEN RINGのように負荷の高い大作を思いきり遊ぶ予定ならなおさら、冷却性能がプレイ体験を決める一番のポイントになります。
冗談抜きで、見た目以上に冷却が大事なんです。
最後にまとめます。
ゲーミングPCのケースは冷却が命です。
そしてその次にデザイン。
冷却とデザインの両立。
できるだけ予算を抑えたELDEN RING NIGHTREIGN用ゲーミングPC構成例
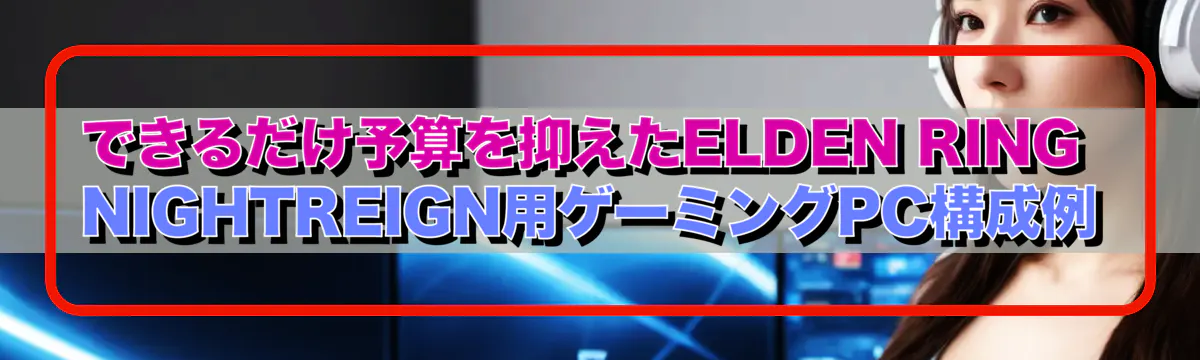
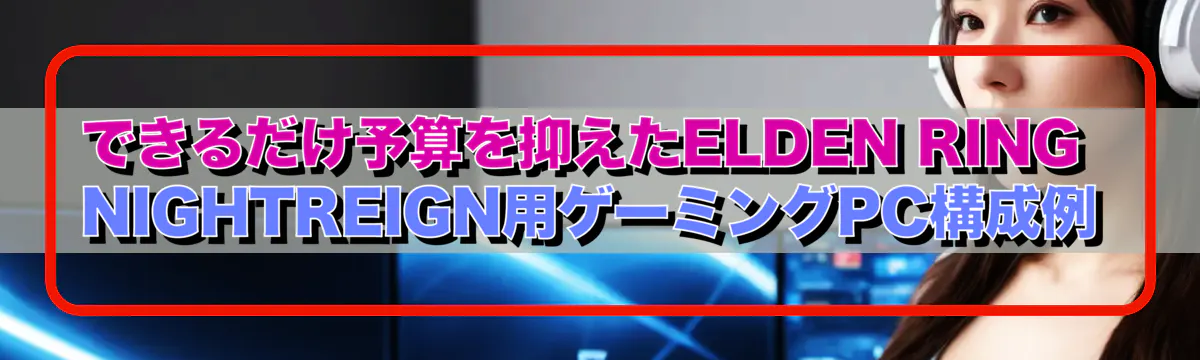
RTX5060Ti搭載モデルの価格とパフォーマンスの釣り合い
派手に見せかけるような個性はないかもしれませんが、実際に手にして使ってみると日常的な満足感がじわじわと湧いてくる。
買い物というのは結局、自分にとって納得できる落としどころを見つけられるかどうかだと改めて感じました。
私は昔から最新パーツに飛びつくタイプではなく、冷静にコストと効果を比べながら選んできました。
とはいえ、安さだけを求めて妥協すると、後から必ず後悔するんですよね。
今回はそういったモヤモヤが一切残らず、むしろ「これで十分以上だ」と思わせてくれたのが5060Tiでした。
実際の体験はというと、フルHDでのゲームプレイでは本当に安定しています。
最高設定にしても動作がカクつかず、戦闘の演出が派手に重なってもフレームレートは安定したまま。
以前は別のカードでプレイしていて、熱暴走やファンの轟音に悩まされたものですが、今はしんと静まり返った部屋の中でゲームを進められる。
パソコンの存在を意識させないほどの静かさには驚かされました。
購入したBTOモデルは20万円前後。
最近はパーツ市場の値上がりが激しく、気づけば40万円越えも珍しくなくなっている状況です。
だからこそ、20万円前後でここまで快適に遊べる環境を持てたことは正直なところホッとしました。
高価な買い物に慣れてしまった人から見れば「中途半端」と映るかもしれませんが、私にとっては十分に現実的で、納得できる選択肢でした。
安心できる予算感。
もちろん性能面の余裕も感じています。
Blackwell世代の設計によって、レイトレーシングやAI描画支援に対応する余力をしっかり確保している。
今すぐそれらが必須ではなくても、次世代を見据えると心強い存在です。
長く使えるカードを選べたという安心は、日々のゲーム体験をより気楽なものにしてくれるのだと思います。
例えるなら、ちょうど良い価格帯の電動自転車を買ったときの感覚ですね。
高級モデルを買わなくても、通勤や買い物に必要な機能を揃えてくれている一台を持つことで、暮らしがすっと楽になる。
豪華さはいらない。
大事なのは確実に役立ってくれること。
ただし、弱点がまったくないわけではありません。
WQHD以上の高解像度環境では少し限界を感じる瞬間がありました。
とはいえ、私は普段からフルHDがメインですから、そこに不満はほとんどありません。
むしろ「自分の生活スタイルに合った選び方をしたな」という満足感の方が大きいです。
必要なものと欲しいものの線引き。
構成面でも納得しています。
今はBTOでもDDR5の32GBメモリにNVMe 1TB SSDが標準搭載のような流れになっています。
それを考えると20万円強でそろうのは妥当だし、むしろ得した気分になりました。
冷却も空冷で十分に安定し、静音性の高さはここまでくると生活の一部に溶け込むレベルです。
ゲームをしていてもファンの音をほとんど意識しない。
不思議な感覚です。
一点だけ贅沢を言うとすれば、ケースのデザインですね。
性能には満足していても、外観はどうしても画一的。
透明パネルや木目調といった遊び心がもっと市販モデルに取り入れられたら、所有すること自体がさらに楽しくなるのにと思います。
まあ、これは完全に趣味の範疇での話ですが。
実際のゲーム体験で言えば、ELDEN RING NIGHTREIGNを含めた最新タイトルをフルHDで安心して楽しめています。
必要十分な性能が手元にあることで、ハード側のことを気にせずシンプルにソフトの世界へ没頭できる。
これは何より大きな価値です。
お金を無理にかけなくても快適に遊べる、その現実が私の生活の中では一番の意味を持ちました。
最後に改めて伝えたいのは、このカードは「性能と予算のちょうどいい交点」にあるということです。
高解像度を目指すのも確かに魅力がありますが、財布を守りながら確実に満足できる環境を手に入れる。
そして今、電源を入れて椅子に腰を落ち着け、無心でゲームの世界に入り込む瞬間に感じるのは「任せて安心だ」という気持ち。
これほど心に響く要素はありません。
その一点に尽きるんですよね。
確かな満足感。
Ryzen 7 9700XとCore Ultra 7、実際の使い心地を比較
ゲーム用のPCを選ぶときに、私が最終的に大事にしたのは「日常の中で違和感なく寄り添ってくれるかどうか」でした。
数字を比較して性能差を論じることはできますが、実際に自分の机で電源を入れ、椅子に腰を下ろしてから数時間過ごしてみないと分からないことが多い。
だからこそ私は、体験をもとに選びたいと強く感じています。
ゲームを立ち上げる時の待ち時間が短く、キャラクターがすぐに動き出してくれる。
正直、こういう快適さは数値だけでは測れないもので、仕事を終えて夜に帰宅したときの癒しに直結します。
日中の疲れを引きずっているときに、PCの応答が遅いとそれだけで気分が沈んでしまう。
逆にスムーズに動いてくれると嬉しくなりますよ。
一方でCore Ultra 7 265Kに触れた瞬間は、思わず「おお、速いな」と声が出ました。
切れ味があるんです。
動画の録画を同時に走らせても、処理に遅れを感じません。
必要な時に力を発揮してくれる頼もしさがあって、そういう性能の立ち上がりの鋭さに惹かれる人も多いと思います。
やはり熱や動作音が気になる場面があり、長時間の使用で静けさを求める私にとってはそこが引っかかりました。
冷却の扱いやすさ。
これが実はとても重要なんです。
これはコスト面でも精神面でも助かります。
余計な投資をしなくても静かに安定して動いてくれるのは正直ありがたいものです。
Core Ultra 7 265Kも処理性能に不足はありませんが、どうしても気温の高い部屋では冷却ファンがうなり声を上げてしまう。
夜中の静けさの中でその音が耳につき、集中力が削がれてしまうことがありました。
私は実際にRyzen 7 9700Xを一週間、自宅で使い続けてみました。
毎晩数時間ゲームをして過ごしても、聞こえてくるのは外の虫の声だけ。
PCの存在を忘れてしまうくらい静かで、その静けさに没入しながらゲームに集中できるのは本当に贅沢な時間でした。
もちろん性能的には不満はなくても、集中したいときに騒がしさがあるのは大きなマイナスです。
どちらを薦めるかと聞かれたら、私はこう答えます。
複数の作業を並行して走らせながらスピード感も楽しみたいならCore Ultra 7 265K。
どちらも強みがあり、弱点もある。
要は自分の生活スタイルにどちらが合うかということです。
スペック表ではなく、「自分の時間をどう過ごしたいか」で選ぶべきなんだと思います。
夜中にひとりでゲームをしていると、わずかな音に気持ちが引っ張られることがあります。
そのときに静けさを守ってくれるPCは、想像以上に心の安定につながります。
さらに忘れてはいけないのは長く使うことで蓄積する疲れです。
性能がいくら高くても、轟音を聞きながらの数時間は意外と消耗する。
だから私は静音性を優先しました。
静けさは正直、贅沢なんです。
ただ、どちらを選んでも大きな後悔にはつながらないと断言できます。
どちらのCPUも最新のゲームを快適に動かせる力を持っている。
それでも最終的には「自分がどんな時間を大切にしたいのか」にたどり着きます。
私は、静けさと穏やかさを基準にしました。
なぜなら落ち着いた時間を過ごすことが、結局は最も自分にとって価値のある選択だからです。
スペックの優劣だけを追いかけると、自分にとって本当に役立つ価値を見失ってしまう可能性があります。
数値の先にあるのは、自分が日常でどんな時間を求めるか。
そこに焦点を当てると、自分に相応しい答えが自然と見えるんです。
結局のところ、私が体感したのは「数字より生活に溶け込む静けさこそ、本当の性能だ」という実感でした。
やっぱり落ち着いた時間が好きです。
2TB Gen.4 SSDでゲームや動画編集はどこまで快適に使える?
2TBのGen.4 SSDを選ぶのは、今の私にとって一番しっくりくる決断でした。
ゲームでも動画編集でも、ストレージの余裕次第で作業の気分はガラッと変わります。
40代になってから、時間や気持ちのロスが何よりつらく感じるようになりました。
だからこそ、2TBという余裕とGen.4のスピードを備えたSSDは、私の作業環境を支える大きな助けになっています。
言い切りますが、これは現時点でとても現実的でありながら確実に満足できる選択だと感じています。
ゲーム環境でのメリットはわかりやすいです。
最近の大作ゲームは平気で一つ50GB以上の容量を食ってきますし、アップデートが積み重なれば一瞬で残りが心もとない状態になります。
結局はインストールとアンインストールの繰り返しで、その度にストレスが溜まっていたんです。
だから2TBを導入したときの解放感は格別でしたね。
まるで押し入れを大きく作り直したみたいに気持ちが軽くなりました。
心の余裕。
そして速度の恩恵。
Gen.4 SSDの転送速度は、体感がはっきりと変わるほどの差があります。
ロードが数秒で終わる。
そのたった数秒が、実際には大きな違いになるんです。
例えばソウルライク系などリトライ回数が多いゲームなら、本当に顕著にわかります。
待ち時間がほぼゼロになることで集中を途切れさせない。
これが想像以上に大きなメリットでした。
「これだよ、これを待ってた」と思いましたね。
同じことは動画編集でも言えます。
私は趣味で4K動画の編集をするのですが、数年前まではSATA SSDに頼っていました。
シークバーを動かすたびに数秒の待ち時間が生まれ、その度に肩を落としていたのを今も覚えています。
でもGen.4にしてからはスッとシークできるようになり、作業が滑らかで自然な流れに変わりました。
作業効率が倍以上に感じられるほどです。
本当に「もっと早く買い替えておけばよかった」と心から思いました。
最近はGen.5 SSDも話題になっていますね。
ただ私は正直そこに魅力を感じていません。
そこに余計なコストやリスクを負う必要はない、と冷静に考えています。
PCを長く安定的に使い続けたい私にとって、機能よりも「着実さ」の方が大事なんです。
Gen.4の2TBならその心配は最小限で済む。
つまり安心感です。
そういうバランスが欲しいんですよ。
実際に運用してみると、ストレージを役割ごとにきれいに分けることができるのも強みでした。
私はOSと最低限のアプリをCドライブ、ゲームをD、動画編集用素材をE、というふうに分離しています。
この形にしてから、システム全体の安定感が増しました。
トラブルも減り、作業に集中できる時間が増える。
こういう小さな積み重ねが、日々の満足度をじわじわ押し上げていくんです。
数字だけでは測れない安心感。
これはベンチマークの値だけを見ていても絶対にわかりません。
使ってみて「余計なストレスが減った」「やらなくてもいい作業をしなくてよくなった」と実感したとき、初めてその価値が腹落ちします。
人間って結局そこなんですよね。
いくら性能数値が高くても、体験が伴わなければ意味がない。
私はそう考えています。
もちろんSSDだけが万能ではありません。
グラフィックが重いタイトルではGPUがボトルネックになることだってあります。
それを体で感じたことも一度や二度じゃありません。
昔は録画データをHDDに保存していて、そのたびに処理が詰まり、イライラしていました。
今ではそうしたトラブルがほとんどなく、作業の流れに身をゆだねられます。
ちなみにSSDメーカーの選び方も気にしてよいと思います。
私はWD製のGen.4 SSDを選びましたが、これが予想以上に安定して高速でした。
大きな動画を書き出す際も、キャッシュ処理を挟んでも止まらない。
以前なら時間を無駄にしていた部分が、今では気づけば終わっている。
自然と「なるほど、やっぱり定番メーカーの信頼性には理由がある」と納得しました。
あの安心感は数値じゃ語れません。
改めて、人に勧めるときにどう伝えるかを考えると、私はこう言いますね。
ゲームも編集も不満のない速度、そして心地よい余裕。
これ以上を求めすぎると余計な出費やリスクに足元をすくわれてしまう。
だからこそ現状ベストなのはこれなんです。
容量を気にせず、思う存分楽しめる日常。
静かな満足。
私は今、その積み重ねが仕事にも趣味にも良い循環を運んできていると実感しています。
2TBのGen.4 SSDは、単なるストレージにとどまりません。
BTOメーカーごとの保証内容とカスタマイズの自由度
長年、仕事と趣味を分けずに同じPCに頼ってきた身として、結局のところ本当に大切なのは「長期間安定して使えるかどうか」なのです。
つまり安心できる保証と、ストレスなく扱える使いやすさ、そして必要に応じて自分なりに調整できる柔軟さ。
この三つが揃って初めて、そのPCはただの道具から信頼できる相棒へと変わっていくのだと実感しています。
冷静に言えば、性能がいくら高くてもそれだけで満足感が続くわけではありません。
サポート対応や修理の体制、そして交換や強化のやりやすさが重なって、ようやく使い続けたいと思えるのだと私は痛感してきました。
国内ブランドから海外メーカー、さらにはショップ系の自作系サービスまで、世の中には本当に多様な選択肢があります。
中でも、まず最初に外せないのがドスパラです。
知名度と歴史が裏付ける安心感があり、配送のスピード感にも強みがある。
夜に注文したものが翌々日には届き、仕事にすぐ使えたのですからね。
やっぱり便利だと素直に思いました。
正直に言うと、カスタマイズ性はあまり充実していないので「自分好みの構成にがっつり手を加えたい」という人にとっては物足りなさを覚えるかもしれません。
また、海外勢の代表格といえばDellです。
このメーカーには、世界規模で積み上げてきたサポート体制があります。
私は以前、業務用にDellのPCを使っていましたが、夜中に動作がおかしくなり、ダメ元でプレミアサポートに連絡したことがありました。
そのとき出てくれたオペレーターの方が、思っていた以上に親身でした。
声を聞いた瞬間、頼れる感じが伝わってきて、「ここまでやってくれるのか」とつい独り言を漏らした覚えがあります。
冷却設計や筐体の作り込みにはかなり自信を持っているのが伝わってきますし、堅牢性も高い。
それゆえに大幅な改造や自由さは少ないものの、こうした会社の姿勢を見ると「長期運用を想定して安定を求めるならこの選択肢だな」と考えるようになりました。
これは40代になってからこそより評価できる価値だと感じています。
そしてもう一つ欠かせない存在が、自作ショップ系の代表であるパソコンショップSEVENです。
ここはフルカスタムに応じてくれる柔軟性が最大の特長です。
数年前、私がそこに相談したときのことですが、担当スタッフの対応がとにかく早くて丁寧でした。
私が「静音性を重視したい」と言うと、すぐに具体的な部品を提示してくれて、その利点や注意点をきちんと伝えてくれたのです。
誠実なやりとり。
その時間は普通の買い物というよりも、一緒にパートナーを作る作業のように思えました。
しかも組み上げられたPCから漂う完成度が高い雰囲気には、手間を惜しまないクラフト精神を感じました。
実際、YouTuberやプロゲーマーが利用することで評価を裏付けている点も、一般ユーザーにとって安心できる材料になっています。
だから私は、この店に対して「ただ買った」というより「一緒に仕上げた」という気持ちが残っているのです。
ここまで三社を見比べると、すべてに良さがある一方で一長一短もあると分かります。
だからこそ、私が友人に相談されたら必ずこう伝えます。
「保証を重視するならドスパラ、安定したサポートを大事にするならDell、そして自分のこだわりを徹底的に反映したいならSEVEN」と。
その割り切り方こそ、実は最も後悔が少なくて済む方法なのです。
私自身、昔はいろいろ迷って時間を無駄にした経験があります。
性能比較に頭を悩ませ、ネットの意見を探し回り、結局は結論を出せないまま時間だけが過ぎていったこともありました。
しかし今は、用途ごとに軸を決めるのが一番効率的なのだと思うのです。
悩むと疲れる。
40代になった今、私はようやく分かりました。
パソコン選びに性能は必要ですが、それ以上に重要なのは安心して任せられるかどうかです。
若い頃は「とにかく高性能ならOK」と考えてましたが、それでは長く使ううちに不満が出てきます。
保証が途切れる不安や、修理の遅さに苛立った経験から、今ではサポートの重みが一層身に沁みています。
結局、パソコンは消耗品ではなく、仕事や趣味を乗り越えて共に時間を過ごす相棒なのだと強く感じるようになったのです。
その視点を持てば、どのメーカーを選んでも自分に合った納得のある関係が築けるはずです。
最後に一言付け加えるとすれば、自分自身が「納得して決めた」と思えるかどうか。
それが一番のポイントです。
パソコン選びに正解はありません。
しかし納得できないまま購入すれば、どんなに性能が高くても不満が残るのが人間です。
信頼できる相棒を自分自身で選び抜いてほしい。
それこそが、ゲームも仕事も、普段の生活までも確実に豊かにしてくれる基盤になるのだと。
ELDEN RING NIGHTREIGNを長く楽しむための拡張性を意識したPC選び


GPU交換に備えて電源ユニットはどのクラスを選ぶべきか
PCを組むときに軽視しがちなものの一つが電源ユニットです。
私は実際にこの選択を甘く見たことで痛い思いをしたので、これから挑戦する方には絶対に伝えておきたいと思っています。
グラフィックボードを将来的に入れ替えるつもりがあるなら、最初から容量に余裕があり、品質のしっかりした電源を選んでおくこと。
若い頃は、やっぱり見た目が派手で目立つパーツが気になりがちなんですよ。
CPUやGPUばかりを必死に調べて、数字や評価を追いかける。
それが楽しくて仕方なかった時期も私にもありました。
でも、黒子役の電源が不安定だと全体が台無しなんです。
遊び始めた瞬間に落ちる。
資料作成に集中したい時に突然フリーズする。
積もり積もって「ああ、やっぱり安物を選んだのは間違いだった」と後悔する。
心底がっかりする瞬間が来ます。
RTX 5070Tiレベルですら600W台が想定範囲、ハイエンドを視野に入れるならなおさら。
理想的な稼働は定格の7割とされるから、750Wクラスでは余裕が足りない。
私はそこをケチった結果、苦い経験をすることになりました。
数年前に構成を組んだとき、650W電源を選んでしまった私は後日RTX 4080 SUPERを導入して初めて自分のミスに気づきました。
ゲームのロードや処理が重い場面で突然ブラックアウトしては再起動の繰り返し。
仕事終わりに楽しみにしていた時間を台無しにされて、その時は思わず机を叩いてしまったんです。
数回そうしたことが起きた時には、無力感だけでなく情けなさが込み上げました。
結局1000WクラスのPlatinum電源に切り替えたのですが、その瞬間「これぞ安定感だ」と思えるほど嘘のように快適になりました。
まさに目から鱗でしたよ。
効率認証もしっかり意識するべきだと思います。
80PLUS Gold以上は、いまや標準と言って良いでしょう。
私の場合、長時間のプレイ中に電源品質がそのまま快適さに結びつくことを痛感しました。
確かに、一時的にコストを抑えるためBronzeやSilverを選びたくなる気持ちも分かります。
電源は寿命の長いパーツですから、最初にちゃんとしたものを購入しておいた方が、未来の自分を苦しめない。
そう強く思います。
900Wから1000WクラスのGoldやPlatinum電源。
これを選んでおけば、静音性も高まりファンが思った以上に静かに回ってくれます。
ケーブル規格の自由度もあり、安心が広がるわけです。
これが未来につながる余裕だと私は実感しました。
心の余裕にも直結する。
いや、本当にそうなんです。
正直に言えば、650Wでも現行タイトルを動かすにも十分ではあるんですよ。
でも次のGPUへの換装、その瞬間に必ず不満がやってきます。
だからこそ私は声を大きくして言いたい。
安く済ませようとすると二度手間になるだけです。
さらに今は補助電源端子の規格自体が移り変わる時期です。
最新の16ピン対応モデルを最初から選んでおけば「合わない?」なんて焦る心配をしなくて済むんです。
こういう小さな配慮がのちのち大きな差になる。
私は電源を見直してからゲームはもちろん、仕事にも恩恵が広がりました。
動画編集やエンコード、資料づくりのようにCPUとGPUをフルに使う作業でも安定性が圧倒的に違う。
これがどれほど安心をもたらすか、体験したときは心から驚きました。
電源ってゲームだけじゃないんですよ。
仕事環境そのものを底上げしてくれるんです。
思わぬ副産物です。
最終的に私が学んだことは、単純ですけど核心です。
それだけ。
900W以上、できれば1000W級を選んでおけば、次にGPUを変える時に余計な不安を抱える必要はない。
長時間のゲームも快適に楽しめる。
日常の作業もよりスムーズになる。
未来への保険みたいなものなんですよ。
安心。
この二つがそろえば、長い付き合いになるPCライフは間違いなく変わるのです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56KA


| 【ZEFT Z56KA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09G


| 【EFFA G09G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56O


| 【ZEFT Z56O スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DAG


エンスージアスト級のパワーを備えるゲーミングPC、プレイヤーの期待に応えるマシン
バランスドハイパフォーマンス、最新技術と高速32GB DDR5メモリで圧巻のパフォーマンスを誇るモデル
話題のCorsair 4000D Airflow TG、隅から隅まで計算されたクールなデザイン、美しさも機能も両立するPC
Ryzen 9 7950X搭載、プロセッシング性能の新境地を切り開く、ハイエンドユーザーに捧げるゲーミングPC
| 【ZEFT R56DAG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
DDR5メモリはまず32GBで良い?後から64GBに増設する考え方
現状のゲーム環境を考えると、DDR5メモリは32GBを用意しておけば十分に戦えると私は感じています。
推奨スペックが16GBとされるケースが多い中で、その倍である32GBを積んでいれば、余計な不安を抱え込むことなくプレイに集中できる。
プレイ中に動作が不安定にならないとわかるだけで、肩の力がふっと抜ける。
安心できるんです。
実際、今売られているBTOゲーミングPCの多くが標準で32GBを採用しており、それ自体が一つの答えを示していると私は思います。
コスト負担も重くなく、必要十分なライン。
それ以上でもそれ以下でもない。
とはいえ、32GBが未来永劫に渡って十分なのかと問われれば、そうは言えません。
ゲームプレイだけなら問題ないでしょうが、同時に配信を走らせたり、動画編集やグラフィック制作に手を広げたりすると、一気に余裕が削られてしまいます。
私自身、過去にPremiereで8Kのデータを扱った際、32GBを軽々突破していくメモリ使用量を目の当たりにし、背筋に冷たい汗が流れた瞬間を今も忘れられません。
そのとき、心の中で「やっぱり64GBにするべきだったか」とつぶやいた記憶があります。
ゲームが軽快に動くことと、制作や仕事を快適にこなせることは、似ているように思えてまったく別の領域なんです。
用途が広がれば広がるほど、メモリ増設の現実味は増す。
だから私は最初からある程度余裕を持った構成を選んでおきたい派です。
この考えに至った理由はシンプルですが、結局後悔したくないんですよね。
メモリを考える上で忘れてはいけないのがマザーボードのスロット数です。
多くのBTO構成は4スロットを備えています。
最初は16GBを2枚挿して32GBとし、のちにもう2枚追加することで64GB構成にしていく。
このやり方が最も自然で、拡張性も高い。
逆に32GBのモジュール1枚だけを差して始めると、確かに増設の余地はあるように見えますが、デュアルチャネルが使えずレスポンスが鈍くなる。
数字だけでは大容量に見えても、体感ではむしろもどかしさがつきまとう。
この違和感、ちょっと嫌なんです。
現行のAAAタイトルでもそこまで食うタイトルはまずありません。
しかし、開発側がリリース後に提供する高解像度のテクスチャパックや、予想以上に負荷のあるDLCで状況が変わる可能性は十分にある。
だからこそ、「今すぐ必要」という意味ではなくても、「将来を見据えた余地を残す」という価値は無視できません。
ここが、安心感に直結する部分だと私は痛感しています。
数年前、私はコスト効率だけを重視して16GB構成のマシンを買いました。
けれど複数のソフトを並行して立ち上げながら重量級のゲームを起動した瞬間、画面が止まりかけるあの冷や汗を経験して、自分の浅はかさを思い知らされました。
あの後悔が私の今の姿勢の原点。
あの時、もう少し投資しておけば違った。
そう振り返るたびに「二度と同じ轍は踏まない」と心に言い聞かせています。
だからこそ私は声を大にして言いたいのです。
ELDEN RING NIGHTREIGNのような作品を心から楽しみたい人、まずは32GBを用意すべきです。
これでしっかり対応できます。
ただし、64GBへ増設できる拡張性は必ず残しておく。
そうすることで、現実的で無理のない選択をしながらも将来のリスクに備えておける。
無理はしない、でも逃げ道は確保する。
この姿勢が大事なんです。
価格の観点から見ても、この判断は理にかなっています。
DDR5が出始めた当初は驚くほど高価でしたが、今では価格は落ち着き、32GBキットが手頃に買えるようになりました。
一方で、BTOショップでいきなり64GB構成を選ぶと、追加費用は意外に大きい。
あの金額差を冷静に見れば、まず32GBで始めて、必要とあれば後から増設するというスタイルが自然です。
資金の使い方には戦略がいる。
安易に豪華な構成を選ぶよりも、必要に応じて賢く強化する。
これが社会人としてお金を扱う上での基本姿勢だと私は信じています。
ゲームも楽しみたい、でも仕事も効率よく片付けたい。
その両立を考えると、32GBを軸にしつつ、64GBに伸ばせる環境を残しておくこと。
これこそがバランスに優れた構成です。
そして、そこに迷いは不要。
安心して長く使えるかどうかがすべてなんです。
つまり、私の考えはこうです。
まずは32GB。
これで当面の環境は十分。
そして未来のアプリや用途の要求に備えて、64GBへアップグレードできる道筋を持っておくこと。
それが費用対効果と性能、安心感の三拍子を取る最良の構え方です。
安心を選ぶこと。
この二つを忘れずにPCを選ぶことが、最終的に自分自身を助け、後悔しない投資につながると私は確信しています。
PCIe Gen.5 SSDを導入したときに感じられる違いとは
私はこれまでGen.4のSSDを使っていて、その速さにも十分満足していたのですが、新しいGen.5を試したとき、待ち時間の短さがこれほど生活に直結するとは想像していませんでした。
40代ともなれば仕事も家庭も忙しい中で自由時間はとても貴重で、その短い時間をどう過ごすかに大きな意味があります。
そこを支えてくれる機材は、正直ありがたい存在なんです。
特に印象に残っているのは、ゲームの大規模なアップデートを行った時でした。
数十GB規模のファイルが短時間で処理されていく様子を目の当たりにすると、思わず「これは助かる」と口にしてしまいました。
以前なら、アップデートが長引いたら「今日はもう無理だな」と諦めて寝ることもありました。
しかしGen.5 SSDのおかげで、夜の限られた自由時間を犠牲にしなくても済んだ。
ちょっとしたことですが、こういうところに大きな違いが出るんですよ。
ただし、すべてが良いことばかりではありません。
Gen.5 SSDは発熱が非常に大きな問題で、正直に言って最初に私は甘く見てしまいました。
あのときの焦りを思い出すと、今では心底こう言えます。
冷却だけは絶対に軽視しちゃいけない、と。
軽視すれば痛い目を見る。
それぐらい重要な要素だと体で理解しました。
コスト面についても正直な話をすると、Gen.4 SSDにはまだ優位性があります。
2TBクラスの製品であれば価格に対して性能は十分以上で、「多少遅くても構わない」という用途ならとても良い選択になるでしょう。
でも、私は長くPCを使うことを考えたとき、やはりGen.5に軍配が上がると思います。
GPUやCPUが次々と新しい世代に移行する中で、ストレージだけが古いままだとどうしても全体のバランスに歪みが出る。
結果として長期的な効率低下につながる可能性が高い。
この視点で投資するかどうかは、大きな分岐点になります。
未来を見据えてお金を使うか、今のコストを優先するか。
そこで差が出るんです。
たとえば一つのゲームしかしない方、あるいは動画編集や大量のデータ処理を行わない方にとっては、Gen.5 SSDの圧倒的な性能は逆に持て余す可能性があります。
宝の持ち腐れですね。
必要以上に高性能を追い求めると、その分のコストも効果も薄れていく。
だから自分がどんな使い方をするのか、はっきり見極めることが重要です。
そうした環境でGen.5 SSDの恩恵を受けたときは、「これはもう手放せないな」と感じましたね。
動画ファイルをコピーするとき、スムーズに処理が進んでいく様子を見るのは純粋に気持ちが良い瞬間でした。
ちょっと大げさですが、仕事効率が確実に上がって、自分の気持ちにも余裕が生まれるんです。
そして何より、今までなら少し構えて取り組んでいた作業が、自然と「やってしまうか」と思えるぐらい気軽に感じられるようになった。
それは40代の私にとって大きな変化でした。
ここで強調したいのは、こうした機材選びはスペックの比較で終わる話ではないということです。
自分の生活リズムにどれくらい馴染むか、自分の時間をどう活かすかを見極める作業なんです。
PCパーツといえば性能比較表を見て決めるものだと思いがちですが、本当の価値はその数字の裏にある「自分の時間との相性」にあります。
だからこそ真剣になるべきなんだ、と私は思っています。
最終的に私が出した答えはこうです。
容量は最低でも1TB以上、そして冷却対策は忘れないこと。
この2つが揃ってはじめて、ゲームも仕事も思う存分に楽しめる環境になります。
そしてその快適さは、間違いなく自分の生活を豊かにする。
時間の使い方に余裕が生まれるからです。
ストレージ選びは本当に大切です。
ここを間違えると、高性能なマシンでも中途半端に感じてしまう。
それが私の実体験から導いた学びでした。
いや、正直に言って戻れるはずがないんです。
静音と冷却を両立できる最新ケースのポイント
どれだけパーツを吟味しても、ケース自体が中途半端であれば本来の力は出せません。
熱がこもれば処理速度は落ちますし、耳障りなファンの音が常に響けば集中の糸がプツンと切れる。
私は長年PCを使ってきて、ようやくそこに行き着きました。
夜中にゲームをすることが多いのですが、そんな時こそケースの出来が露骨に分かります。
隣の部屋に気を遣いながら、けたたましいファンの回転音を聞かされるのは正直きつかったですね。
耳元ではないけれど、心臓に響くようなあの振動音。
ああ、これは失敗した、と苦い顔をしたこともありました。
でも、後に静音性の高い製品に出会えたときは本当に救われました。
カタカタ音が消え、PCが涼しい顔で動いてくれる。
たったそれだけのことなのに、気持ちが軽くなったのです。
昔のケースはどうだったかといえば、選択肢自体が少なく、冷却をとれば「うるさい」、静音をとれば「熱い」、まさに二者択一でした。
それが普通だった。
でも今は違います。
フロント全面をメッシュ化して効率的に冷却できる設計や、騒音を壁で吸収して拡散を防ぐ仕組みまでついている。
GPUに直接風を当てられる仕組みも増えて、まるで別物。
私はその進化の速さに舌を巻きました。
技術の進歩って、本当に頼もしいですね。
印象深い組み方があります。
その時に驚いたのは、冷え方よりもむしろケースの剛性でした。
昔のものはどうしてもパネルが薄く、振動や共鳴で「ビーン」という耳障りな音が出てしまったのです。
でも最近のケースは側板が分厚く、構造がしっかりしているため共振がほとんど鳴らない。
耳に届くのは風を切る低い音だけ。
その違いに、思わず「おお」と声が漏れました。
さらに驚かされたのが三面強化ガラスやピラーレス構造のケースです。
最初は「これは単なる見た目の派手さ狙いだろう」と懐疑的だったのですが、実際に触れて使ってみると、空気の流れを妨げないよう考えられた設計だと分かりました。
ケーブルを裏に綺麗に回せるおかげで内部の風の流れがよどまず、その効果は想像以上。
見た目と機能性のバランスがとれているって、こういうことなんだなと思いました。
しかし実物に触れてみると独特の吸音性があり、低いファンの唸りをぐっと和らげてくれる。
さらに自然な質感でリビングに置いても違和感がない。
意外な発見もあるものです。
ただ、ケースを選べばそれで全て解決、という話ではありません。
それでも優れたケースがベースにあれば、手間をかけた分だけ確実に成果が返ってくる。
私は大型空冷クーラーを新型CPUと組み合わせましたが、その静かさと安定性は驚くほどでした。
水冷じゃないとダメだという思い込みも、すっかり捨て去ることができました。
サイズの選び方にも苦い経験があります。
フルタワーは広くて余裕があり、拡張性も高い。
しかし私には完全に持て余しました。
拡張スロットの半分すら埋まらず、巨大な筐体が部屋のスペースだけを奪っていく。
それ以来、私はミドルタワーを選択しています。
最近のミドルタワーは拡張性も十分で、配線の整理もしやすく、手入れや改修に無駄な苦労がない。
本当にちょうどいいサイズ感なのです。
これこそが理想です。
風を取り込みやすいフロントメッシュ、しっかりとした側板構造、ケーブルが整頓しやすい裏配線の仕組み。
そうした機能を備えるミドルタワーこそ、安定して長く使えるケースの最適解だと私は思います。
仕事にも趣味にも安心して使える環境を求める私たち世代が、結局のところ最も信頼できるのは派手な外見ではありません。
着実に性能と静音性を両立している製品。
それが長く付き合える一番の相棒になるのです。
満足した瞬間の感覚は何とも言葉にしづらいですね。
机に向かい、静かなPCが隣に佇んでいる。
冷えるのに静か。
しかも部屋に自然と馴染む。
その環境を手にした途端、仕事にも遊びにも肩の力を抜いて集中できるようになりました。
結局のところ「たかがケース」と軽んじてはいけない。
ケースひとつで日常の心持ちが変わる。
私はそう実感しています。
ELDEN RING NIGHTREIGN用PC購入前によくある疑問とその答え


ゲーミングノートでも快適プレイは可能?
私は正直に言って、ゲーミングノートでELDEN RING NIGHTREIGNをプレイすることは「条件さえ合えば十分楽しめる」という立場を取っています。
ただ、便利さの裏には避けられない制約もある。
そのひとつが発熱と冷却問題で、ここは本当に軽く扱えない課題です。
ノートを選ぶ以上、この壁をどう受け止めるかが快適さを左右します。
実際に私は痛い目を見ました。
出たばかりのハイスペックGPU搭載モデルを購入し、調子に乗って長時間遊んでいたのですが、気がついたらキーボードの上が熱でじんわり沸いているような感覚になり、思わず「やばいな」と声が出てしまったのです。
その瞬間はゲームどころではなく、机の引き出しから古い扇風機を引っ張り出して強引に冷やす羽目になりました。
結局しばらく後に冷却パッドを買うことで落ち着きましたが、デスクトップなら考えずに済む悩みですし、財布にも余計なダメージを受けることになります。
しかし一方で、最新のゲーミングノートは本当に力強いと思わされる場面があります。
例えば、最新のCoreシリーズやRyzenシリーズの高性能CPUを備えたものに加え、モバイル向けとはいえRTXやRadeonの最新GPUが搭載されていると、フルHDやWQHDで安定して60fpsを確保できることが珍しくありません。
特にこのタイトルはフレームレートが60fps上限と決まっているため、超ハイリフレッシュ対応のモニターを用意しなくてもよく、その点では相性が悪くない。
限界はある。
でも遊べる。
さらに驚かされるのはロード時間です。
PCIe Gen4のSSDを備えたモデルだと、体感的に一瞬でフィールドへ飛び込める印象で、ロード待ち時間のストレスをまるで感じません。
朝少し早く目が覚めて、出勤前の20分ほどを費やし「1回挑戦してから仕事に向かおう」と思ったとき、無理なくサッとゲームを楽しめるのは、私にとって大きな価値でした。
この快適さは、「ノートで良かった」と思えた強い理由のひとつです。
出張時の体験も忘れられません。
地方のホテルの机にノートを置き、自宅と同じキャラクターを動かして冒険を始めたとき、心の底から「これは最高だ」と感じました。
大げさでなく、日常に少し特別な彩りを添えてくれる感覚です。
もちろん、ホテルのWi-Fiが不安定でセッションが途切れて苛立ったこともありました。
でも、有線接続ができた日には落ち着いて快適に進められ、普段の環境と変わらぬ没入を得られたことに強い満足を覚えました。
ただし、過信は禁物です。
同じGPUの型番であっても、デスクトップとノートでは性能差が歴然で、見た目の数字にだまされると「思ったより重いじゃないか」とガッカリするケースがあります。
実際、知人がその落とし穴にハマり、高性能を期待して購入したのに結果的に画質を落とさざるを得なかった話を聞いて、やはり注意が必要だと感じました。
そして忘れてはならないのが騒音です。
ゲームの物語に没入している瞬間に、背後から「ゴォーッ」と吹き荒れるようなファンの音が聞こえると、一気に現実へ引き戻されます。
その音はまるでオフィスで大事な資料を読んでいるときに、突然電話が鳴り響く感覚に近い。
不意の邪魔。
正直に言ってうるさい。
でも避けられない。
だからそこをどこまで我慢できるか、人それぞれの受け取り方次第なのです。
とはいえ、私はこう考えます。
フルHDやWQHDでのプレイを目標にするなら、最新モデルなら十分戦えます。
一方で、4K解像度で最高品質の映像美を真正面から堪能したいというなら、やはりデスクトップを選んだ方が後悔しません。
冷却性も、拡張性も、静音性も、最終的には据え置きの強みだからです。
ゲーミングノートは、携帯性と性能を両立しようとする挑戦者のような存在だと思います。
弱点があるのは認めざるを得ません。
高温。
ファンの存在感。
拡張性の限界。
それでも私は、自由に持ち運べる便利さに強く惹かれます。
だからこそ、自分の環境や価値観を理解して選ぶことが、満足感につながるのです。
もし静かで長期的に安心できる環境を求めるなら迷わずデスクトップを。
要するに、ELDEN RING NIGHTREIGNをノートで楽しむことは決して間違いではありません。
答えはあなた自身が持っています。
惑わされないこと。
初めてBTOパソコンを注文する際の注意すべき点
BTOパソコンを初めて注文する時に一番意識すべきは、安さだけに飛びつかないことだと私は思っています。
昔の私も「必要最低限でいいかな」と考えて安さ優先で選んだことがありましたが、その時の後悔は今でも鮮明に覚えています。
カクつく画面にイライラし、友人たちに合わせて妥協した設定のまま遊んで、結局楽しめないんです。
だから今では声を大にして伝えたい。
ケチってはいけない、と。
私が特に気をつけるのはGPUです。
カタログの数字やレビューを見て「これはコスパがいい」と感じたモデルでも、実際にプレイを始めると「あれ、重いな」と思う瞬間はすぐにやってきます。
以前、数千円を惜しんでエントリークラスを選んだら、画質を落とさないとまともにゲームにならず、結局は何のためにBTOしたのかわからなくなったことがあります。
あの時の後悔は正直、苦い思い出です。
それが自分の中での鉄則になっています。
メモリについても同じです。
私も最初はそうでした。
しかしオンライン協力プレイの最中、メモリ不足が原因で画面が止まり仲間に迷惑をかけたときは、気まずさで冷や汗が止まりませんでした。
必要最低限で切り詰めると必ずどこかでボトルネックになるんです。
だから今は必ず余裕を持って選びます。
推奨値より上を確保する。
それが結果的に心の余裕にもつながりますしね。
ストレージもまた地味に重要です。
私はかつて安さ重視でHDDだけのBTOを組んだことがありますが、起動が遅くロードも長く、せっかくのやる気が削がれてしまいました。
そこで思い切って次はGen.4のSSDを選んだのですが、その快適さといったら本当に別世界で、ゲームを起動するたびに「選んで良かった」と思わされます。
最新のGen.5にも心惹かれましたが、値段と発熱を考えてまだ見送ったのも正解だったと思っています。
冷静な選択が必要なんですよね。
冷却もあなどれません。
以前、小型ケースに詰め込んで冷却を軽視したせいで、CPU温度が高騰し性能が安定せず困った経験があります。
その後、大型空冷クーラーを備えたモデルを導入したら、「こんなに静かで涼しいのか」と驚いたものです。
長時間ゲームをしても温度の上がり方がゆるやかで、稼働音も控えめ。
これは快適さに直結する部分で、軽く考えると地獄を見る部分でもあります。
声を大にして言いますが、冷却は本当に大事です。
ケース選びも同様です。
若い頃はRGBの派手さに惹かれたこともありました。
ですが実際はエアフローや掃除のしやすさの方がはるかに大切だと後で気づきました。
デザイン重視で通気性の悪いケースを選んだ結果、内部は熱がこもり、パーツ寿命を縮めてしまった経験もあります。
「あの時、外見より機能を選ぶべきだった」と心の底から思いました。
電源に関しても痛い思いをしています。
容量も認証も気にせず安価なものを選んでしまい、PCが急に落ちる不安定な状態に悩まされました。
結局後から電源を交換する羽目になり、最初から信頼できるブランドを選んでおけば良かったと深く後悔。
だから今は必ず余裕を持った容量、安定性あるメーカー。
ここをケチると後々何倍も損をします。
バランス感覚も忘れてはいけません。
GPUだけ高性能にしてもCPUやメモリが足を引っ張れば意味がなく、逆にCPUだけ贅沢にしても動きません。
結局、全体の調和が取れてこそBTOの良さを引き出せるんです。
自己責任だからこその奥深さ。
最終的には、自分がプレイしたいゲーム、たとえばELDEN RING NIGHTREIGNのような高負荷タイトルを快適に楽しむために、推奨スペックを満たしつつ、余裕ある構成を選ぶことが一番大事になります。
GPUは中堅以上、メモリは推奨より上、ストレージは高速かつ余裕を確保し、冷却、電源、ケースも妥協しない。
こうしてようやく心から満足できる一台が手に入るのです。
そう考えれば安い投資だと私は感じています。
快適さの積み重ね。
むしろ安心して長く使える一台を手に入れることが、BTO初心者にとって一番失敗を防ぐポイント。
そのためには信頼性あるパーツ選びが何よりも重要になります。
信頼が土台。
私が自分の経験から辿り着いた結論はこの一言に尽きます。
予算を理由に選択を誤ると、後から何倍もの後悔を背負うことになる。
でも、安心と信頼を優先して組み上げた一台は、末永く支えてくれる相棒になります。
胸を張って「買ってよかった」と言えるように、最初から真剣に選ぶべきだと私は考えています。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CO


| 【ZEFT R60CO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GE


| 【ZEFT Z55GE スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WX


| 【ZEFT Z55WX スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FT


| 【ZEFT R60FT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BC


| 【ZEFT Z52BC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ゲーム配信を同時に行うなら必要なスペックは?
遊ぶだけなら動くのですが、配信という要素を足すと一気に壁にぶつかります。
私自身、推奨に近いPCで挑戦して、プレイは快適なのに配信映像が途切れ途切れになり「ああ、これじゃダメだ」と頭を抱えたことがあるのです。
あのときの徒労感は今も強い記憶として残っています。
大切なのは処理に余力があるかどうか。
私はCPUこそが優先だと思っています。
本作そのものはそこまで極端に重いわけではないのですが、配信ソフトが並行して動くことで一気に負荷が跳ね上がる。
例えばCore Ultra 7の265Kを組んだとき、GPUでエンコードをかけてもCPU自体に明らかな余裕がありました。
結果としてブラウザでチャットを開いたり複数のツールを使ったりしても落ち着いたままの動作で、一度慌てたことすらなかったのです。
内心では「この余裕こそ安心材料だ」と納得しました。
余白がすべてを変える。
次に痛感したのはメモリです。
最初は16GBで挑戦しましたが、2時間を超えると裏作業を切り替えるたびに「ん?」と引っかかるような挙動が出てきて、その違和感が気持ちを削いでいったのです。
そこで思い切って32GBに増設しました。
すると一変しました。
配信を続けてもアプリを並列で動かしてもほとんどもたつかず、自然体で進められる。
配信というのは観てくれる人とのやりとりが中心なので、そこに頭を使えない状態は辛すぎます。
設備投資したことで得られた解放感は大きかった。
グラフィックボードに関しては、最上位に手を出さなくても良いというのが私の率直な感想です。
しかし、余裕のないGPUを選ぶと途端に厳しくなる。
私はRTX5070Tiを試しましたが、WQHD配信は問題なく、4Kに切り替えたときでも「お、まだいけるな」と思わせてくれる程度の安定感がありました。
もしミドルレンジに妥協していたら、配信エンコードとの両立でたちまちフレーム落ち地獄になっていたでしょう。
配信をしていて一番つらいのは画面が止まることなんですよ。
気持ちが一気に冷めるのです。
だからこそGPUには一定の余裕を残した方が後悔がありません。
そして軽視されがちなストレージ。
正直に言えば、これは落とし穴でした。
ゲーム自体の容量が30GB程度だったので「まあ、大したことないだろう」と思っていたのです。
ところが配信アーカイブを保存しはじめると、一気に事情が変わる。
フルHDで3時間配信したら50GB近いファイルが出来上がり、SSDの残量を見て「嘘だろ」と動揺しました。
繰り返せば当然溜まる。
だから2TBは最低でも必要だと今は思います。
最新のGen.5 SSDまで求める必要はなく、安定したGen.4 NVMeを選んだ方が安心です。
スピードより信頼性。
結局これが肝心なんですよ。
冷却とケースも重要です。
正直に告白すると、私は一度見た目重視で失敗しました。
デザイン性に惹かれて購入したケースは確かに外観は満足いくものでした。
でも配信中に温度が一気に上がり、ファンがうなりをあげたとき、私の気持ちは一瞬で暗転しました。
静かに会話したいときに背後で「ゴーッ」という音。
もう、これはストレスでしかありません。
それ以来、しっかり風が通るケースを選び、大型空冷を導入しました。
驚くほど静かで涼しい。
静音性は精神的な余裕を生むんです。
CPUは少なくともCore Ultra 7やRyzen 7クラス、メモリは32GB、GPUはミドルハイクラス以上、SSDは2TB、ケースはエアフローを重視。
このラインを越えた構成を作れば、配信に不安を抱えることなく集中できます。
私はそう断言します。
数字の話というのは冷たさを感じるかもしれませんが、実際に配信をしていると気持ちが処理落ちや雑音に揺さぶられる瞬間が必ず出てきます。
そのたびに萎縮し、自分がやりたいことに集中できなくなる。
だから最初から心配の種を潰しておくのが一番です。
私はこれまで何度か「もっと早く対策しておけばよかった」と後悔しました。
でも今は違います。
余裕のあるマシンを組んだおかげで、目の前のゲームと視聴者とのやり取りに集中できている。
不安が消えた時間がそのまま楽しさに変わりました。
やはり最後に残るのは「安心感」です。
そして、この安心感こそが継続の鍵だと感じます。
派手な数字や最新パーツに惹かれる気持ちも分かりますが、それ以上に「自分が落ち着いて続けられる環境」を揃えること。
それが私の実体験から得た結論です。
安心して続けられること。
将来のアップデートを考慮して選ぶならどんな構成が安心か
将来的な拡張やアップデートを見据えてパソコンを組むとき、今の推奨環境だけを追いかけてしまうのは危うい判断だと私は考えています。
理由は単純で、ソフト側が常に進化し続けるのに対して、ハードは一度買ったら簡単には変えられないからです。
最初のうちは快適でも、数か月もすれば追加のコンテンツや想定外の大規模な修正が来て、気づけば「なんだか重くなってきたな」と思う瞬間に必ず出会う。
私自身、何度か同じ過ちを繰り返し、そのたびに小さなストレスが積み重なって「もっと余裕を持って選べばよかった」と後悔したことがあります。
だからこそ、目先だけでなく半年、あるいは一年先まで考えて「少し余裕のある構成」を選んでおくことが、安心感にもつながり、結果的にコストを抑える最善策になるのです。
中でも最重要だと思うのがグラフィックボードです。
推奨環境の水準であれば、たしかに最初は問題なく遊べます。
その結果、せっかくの映像体験がカクついて台無しになることさえあります。
私も過去に、推奨ぎりぎりのGPUで新作に挑戦し、拡張コンテンツ導入直後に急に動作が重くなり落胆した経験がありました。
そのとき痛感したのは「性能に余裕があることが、結局一番の保険になる」という事実です。
たとえばRTX 5070やRX 9070XTクラスを初めから選んでおけば、WQHDや4Kでもしばらくは快適に楽しめますし、将来を心配する必要もなくなります。
それに加えて、CPUも見逃せない存在です。
GPUほど注目を浴びませんが、ここがボトルネックになると台無しです。
私は以前、Core Ultra 7 265Kを搭載した環境を試したことがありますが、冷却をきっちり整えたところ、同時配信してもフレームレートが落ちず、正直驚きました。
同じゲームでもCPU次第で全体の滑らかさが変わると痛感した瞬間です。
安心感が違う。
メモリも軽視してはいけません。
最近の公式推奨値では16GBが多いですが、実際にはそれでは不足しがちです。
ゲーム中に裏でアプリを動かす程度のことがパフォーマンス低下を招き、集中を削ぐ。
だから私は迷いなく32GBを選ぶべきだと考えています。
余裕のあるメモリ容量は、長時間のプレイで大きな安心を与えてくれる。
ストレージに関しても同じで、「最低限あればいい」という考えは非常に危険です。
たとえば最初のインストールが30GBだからといって、そのまま安心できるわけではありません。
DLCやアップデートのたびに確実に容量は膨れ上がり、気づけば数百GBを食っていることさえあります。
実際に私は、容量不足で長年遊んだタイトルを泣く泣く削除したことがあり、その悔しさは今も忘れられません。
だからこそ最低でも1TB、できればGen.4対応の2TB SSDがちょうど良い。
Gen.5は性能的には魅力があっても、熱管理や追加コストの負担が大きすぎ、実際に使う立場だと現実的ではありませんでした。
だからGen.4の2TB。
空冷で十分な場面も確かにありますが、夏場に長時間プレイや配信をすると一気に環境が厳しくなる。
かつて私はCPU温度が急上昇してガタついた画面を前に、汗をかきながら焦ったことがありました。
その後水冷に切り替えた途端、その不安から解放され、静音性も加わって驚くほど快適になった。
安心できる冷却環境こそ落ち着きをもたらしてくれます。
余裕があるだけでプレイの質は全く別物。
さらにケース選びも忘れてはいけません。
けれど結果は悲惨で、通気性が悪く内部温度が高止まりし、パーツ寿命を縮めてしまったのです。
それ以来、私はケースを選ぶ際は「エアフロー」を第一条件にしています。
メッシュ構造のケースは想像以上に効果が大きく、わずか数度温度が下がるだけで動作の安定感がまるで違う。
それに気づいたとき、デザインよりも性能を優先するしかないと悟りました。
こうした経験を振り返ると、最適な構成は自然と見えてきます。
グラフィックボードは中上位クラス、CPUは堅実に性能の高いモデル、メモリは32GB、ストレージは2TB前後のGen.4 SSD、冷却は空冷か水冷を用途に応じて選び、ケースは通気性を第一に考える。
言い換えれば「遊びの余白」が生まれる。
最終的にどうするべきか。
答えはとてもシンプルで「余裕を持つこと」なんです。
目先のコストを削るために最小仕様で組んだらどうなるか。
その答えは、後悔という形で必ず返ってきます。
私はその痛みを何度も味わったからこそ断言できます。
長く安心して遊びたいのなら、一段上の選択をする。
ほんの少し背伸びをするだけで、将来のストレスを大きく避けられる。
これほど確かな投資はそう多くありません。