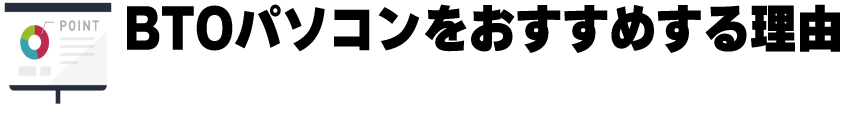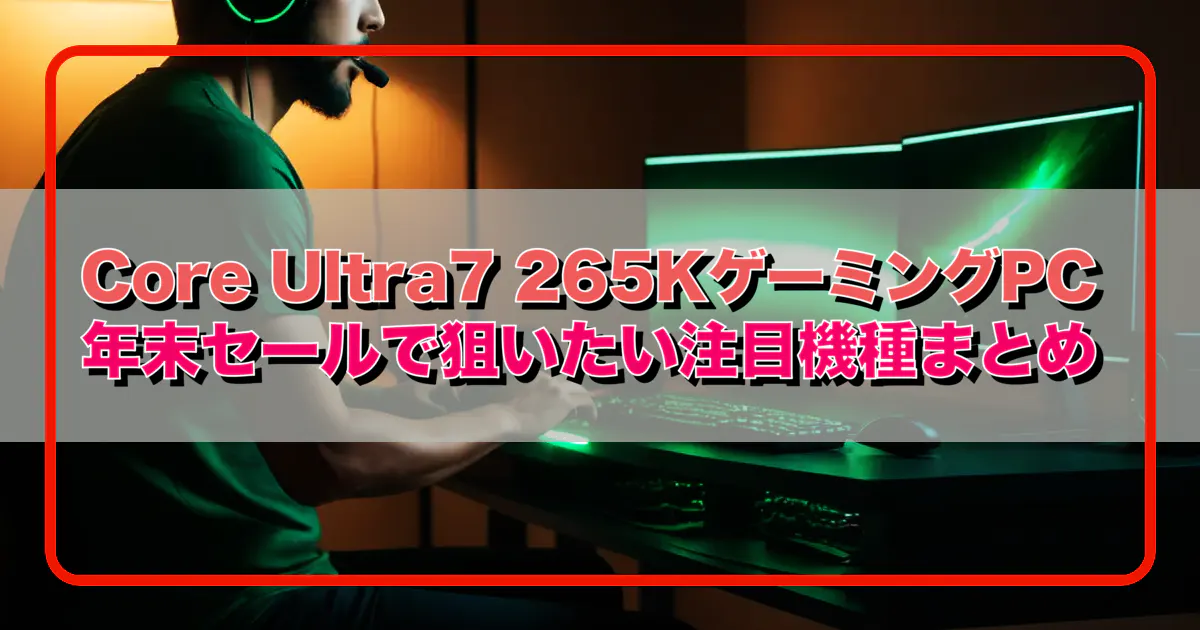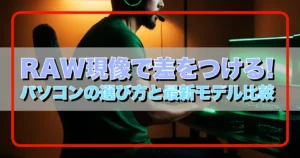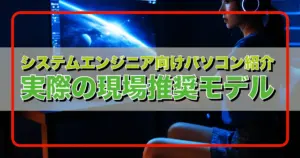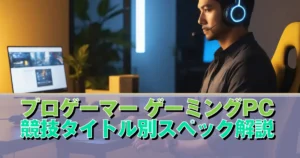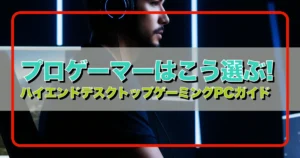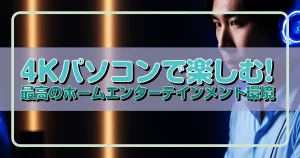Core Ultra7 265K ゲーミングPCを実際に使ってみた感想

最新CPUを触って気づいたこと
実際にこの新しいCPUを使ってみて、私が強く感じたのは「これは長い付き合いができる頼れる相棒になる」という実感でした。
正直なところ、ハイエンドの製品というとこれまでは熱や電力の不安がつきまとう印象が強く、触れるたびにどこか緊張してしまう部分がありました。
ところが今回試したCore Ultra7 265Kは、拍子抜けするほど素直で扱いやすく、肩の力がスッと抜けました。
空冷クーラーを取り付けただけで高クロックを安定して維持でき、耳障りな騒音に悩まされることもなく、毎日付き合う上でのしんどさがほとんどありませんでした。
こんなに自然に扱えるとは思わなかったのです。
正直驚きましたね。
普段、私が気にするのはやはりGPUとのバランスです。
特に4K解像度で最新ゲームを楽しむ際は、CPUが足を引っ張る瞬間があると一気に体験が台無しになります。
しかしこのCPUはRTX 5070Tiとの組み合わせでも余裕があり、映像が途切れるような粗さも見当たりませんでした。
数字的なベンチマーク以上に、「安心して遊びに没頭できる」環境を支えてくれる点こそ価値だと思います。
パフォーマンスが安定しているといつの間にか信頼感が積み上がっていて、結果としてプレイそのものに集中できるのです。
その小さな積み重ねが本当の快適さを生み出すのだと痛感しました。
驚かされたのはゲームだけではありません。
動画編集やAI処理を同時に行ったときでもほとんど負荷を感じませんでした。
ちゃんと応えてくれるのです。
NPUが統合されていることは仕様上わかっていましたが、実際に触れると「やっぱり技術は使ってみて実感するものだな」と強く思いました。
正直、「こういう進化を待っていた」と心から思いました。
メモリとの相性も非常に良く、DDR5-5600の32GBを組み合わせてみました。
以前感じていた細かい読み込みの引っかかりがなく、全体的に処理がスムーズに流れていきます。
特に重たいテクスチャの読み込み時に、思わず「もう終わったのか」と呟いてしまうほどの速さでした。
こうした小さな改善が積み重なると、作業一つ一つの気持ちよさが格段に違ってきます。
結局のところ、人間は数字だけでは納得できないもの。
CPUの温度にも正直驚きました。
高負荷を与えても70度台前半で安定し、クロックを維持し続けてくれます。
以前ならこのクラスのCPUは水冷が必須という先入観しかなくて、自由度の低さに少しうんざりしていました。
しかし今では高性能な空冷クーラーでも十分対応でき、自分好みのケースを選べる楽しさが戻ってきました。
組んだ瞬間から完成品に説得力があり、空冷とケース設計がしっかり噛み合って期待以上の冷却性能が得られました。
パソコンを組み立てながら「これだ」と心の中で小さく叫んでしまったくらいです。
長年自作を続けていても、この誇らしい瞬間は何度味わっても新鮮で、決して飽きることはありません。
オーバークロックも試しましたが、思った以上に安定しやすい印象でした。
レスポンスが軽快で、適切に電圧管理すれば余裕でクロックを引き上げられます。
ただ実際に使っていて思うのは、わざわざオーバークロックを詰めなくても素の性能で十分だということ。
そして私自身、毎日使うなら安定性の方を優先して大事にしたいと思いました。
性能を追い込みすぎるより「ちょうどいい環境」を維持する方がずっと気持ちが良いのです。
ストレージも試行錯誤しました。
PCIe Gen.5 SSDを挿してみると確かに数値は圧倒的ですが、熱の処理が課題になり、実用面を考えると対策が面倒です。
結果として私はGen.4の2TB SSDに落ち着きました。
速度差は普段の利用ではそこまで顕著に感じられず、むしろ発熱も抑えられて扱いやすい。
この現実的な落とし所に気づけたのは経験の積み重ねがあったからこそかもしれません。
このCPUを言葉で表現するなら「力強さと効率性の同居」と言いたいです。
性能を追いながらも扱いやすく、まるでユーザーが長く使うことを意識して設計されているように思えました。
これまで「高性能=暑い、うるさい」という固定観念を見事に覆し、初めてでも胸を張って人に薦められるCPUだと確信しています。
そして私が選ぶ構成は、空冷クーラー、DDR5メモリ、Gen.4 SSDと組み合わせたもの。
このセットなら仕事でも趣味でも十分満足できる環境が整います。
間違いなく今のベストバランスです。
安心感がある。
この安心感を一度味わってしまうと、他を選ぶのは難しくなります。
まるで長い間使い込んだ馴染みの文房具のように、手にすっと収まってしまうのです。
私にとってこのCPUは、単なる部品ではなく、新しい毎日の一部になりつつあります。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43437 | 2442 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43188 | 2247 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42211 | 2238 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38943 | 2058 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38866 | 2030 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35977 | 2177 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33203 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32721 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29522 | 2021 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 2155 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23298 | 2192 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23286 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 21046 | 1842 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19684 | 1919 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17893 | 1799 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15428 | 1963 | 公式 | 価格 |
高fps重視ならグラボはどれを選ぶべきか
高fpsを求めるのであれば、最終的に一番大事なのはやはりグラフィックボードの選択です。
CPUももちろん重要ですが、実際にゲームをプレイしていて「なんだか重いな」と感じる場面の多くはGPUが原因であることが少なくありません。
正直、ここで妥協すると「いや、こんなはずじゃない」と肩を落とす瞬間に直結します。
私自身、そうした失敗を過去に何度も見てきたので、グラフィックボード選びに慎重になりすぎるくらいがちょうどいいと感じています。
私の経験を踏まえると、今実際に候補として残るのはGeForce RTX 50シリーズかRadeon RX 90シリーズです。
一世代前のモデルでも軽いタイトルなら動くには動きますが、高解像モニターや最新のAIを活用したフレーム生成機能との相性を考えると、それ以前ではどうしても性能不足を感じます。
実際に私はRTX 5070Tiを使いましたが、フルHDはもちろんWQHD程度なら「おお、これで十分だな」と思える快適さが得られました。
仕事を終えてささっと起動したとき、その力強さにちょっとした安心感すら覚えました。
ただ、4Kや高リフレッシュレートとなると話は別です。
5070Tiは頑張れるものの、144Hz以上で安定して走らせるには力不足を痛感しました。
そのとき私は、「ここは迷わず5080以上に行くべきだな」と腹をくくることができました。
消費電力が大きく電源コストも気になりましたが、映像の奥行きと表現力は別物で、それを初めて目にした瞬間の衝撃は今でも忘れられません。
あのときの「これはもう後戻りできないな」という感覚は強く心に残っています。
一方で、Radeon 9070XTも侮れません。
特に最新のFSR4によるアップスケーリング技術とフレーム生成機能はかなり進化していて、映像美を重視するAAAのストーリーメインゲームではむしろGeForce以上に「映える」と感じる場面も多かったです。
私にとっては「これはライバル機ではなく、別の選択肢として確立したな」と思えました。
競技性の高いタイトルならGeForceのほうが安心できますが、没入感を重視するならRadeonを選ぶのも非常に面白いのです。
映像に包み込まれる心地よさこそ魅力だからです。
ただし、このクラスのGPUを選ぶとき注意すべきは発熱と消費電力の管理の難しさです。
Core Ultra7 265Kは温度に強い設計ですが、それでもハイエンドGPUとの組み合わせではケース内が一気に熱くなります。
私は過去に750W電源でRTXを無理に動かそうとして、ゲーム中に突然配線が落ち、画面がブラックアウトした苦い経験をしました。
あの時の冷や汗は忘れられません。
以来、電源に余裕を持たせ、ケースファンの追加も必ず検討するようになりました。
安定した運用のためには地味ですが絶対に外せない工夫です。
妥協すると後悔します。
これは本音です。
「まあこれでいいか」と思って買ったGPUにすぐ不満を感じると、結果的にお金も時間も台無しになります。
特に最近のAAAタイトルはグラフィックとフレームレートが両立する前提で設計されているため、中途半端な環境だとその世界観を存分に楽しむことができません。
「やっぱりあのとき一段上を選べばよかったな」と振り返った姿を想像することほどむなしいものはない。
だから私は、最低でも5070Tiや9070XTを選ぶことをラインとしています。
逆に、それ以下のGPUで高fpsを狙うのは厳しいとさえ思っています。
快適さ。
これが本質です。
高fps環境をきちんと整えると、Core Ultra7 265Kの真価もようやく引き出されます。
せっかく20コア以上積んでいるのに、GPUの制約で動きが鈍るのは実にもったいないことです。
私はそうしたアンバランスがどうしても好きになれません。
だからこそ高性能GPUへの投資は「贅沢」ではなく「必要経費」だと考えています。
多少の出費がかさんでも、それはゲーム体験を左右する意味のある支出であり、後悔のない選択になるのだと確信しています。
最終的に残るのは、グラフィックボード選びが単なるパーツ購入ではなく、自分の生活スタイルを支える基盤になっているという実感です。
少なくとも私にとってゲームは一日の緊張を解きほぐす大切な時間であり、その質を落とすのは許せません。
だから私は声を大にして言いたいのです。
それこそが安心をもたらす鍵なのだから。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49113 | 100929 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32430 | 77302 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30414 | 66101 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27399 | 68249 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26736 | 59644 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22140 | 56240 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16704 | 38983 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16133 | 37823 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15994 | 37602 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14766 | 34575 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13862 | 30555 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13317 | 32041 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
DDR5メモリは32GBで十分?それとも余裕を見ておくべき?
私の経験から率直に言えば、Core Ultra7 265K搭載のゲーミングPCであれば、メモリは32GBでも不自由を感じることはほとんどありません。
普段から遊んでいる最新タイトルを高画質設定で問題なく動かせていますし、映像の乱れや処理落ちが出たときの要因は、大抵グラフィックボードか冷却周りに起因しているのが実情です。
むやみに容量を増やす必要性は薄いのです。
もちろん「余裕を持たせたい」という気持ちは理解できます。
私もかつてはメモリは多いほど安心と考えていた時期がありました。
「念のため」が口癖になっていた時代です。
ところが実際には32GBでも十分に安定し、何も不満を覚えない状況が長く続いています。
そのため、ただゲームや日常的な作業を快適にこなすという目的に限れば、追加コストをかける意義はあまり見い出せません。
安心感をお金で買うなら別ですが、費用対効果という観点で考えるなら慎重になるべきです。
ただし、条件が変わります。
ゲーム以外の作業を並行して進める時です。
私が明確に64GBを意識したのは、AAA級の大作ゲームを最高設定で動かしながら、OBSで配信、さらに録画まで同時進行していたときでした。
そのうえChromeのタブを多数開いていたものですから、残りメモリがわずかになり、画面のモニターリングで「おっと危ない」と肝を冷やしました。
その瞬間に「32では余裕が削られる」と体感したのです。
その冷や汗交じりの体験が、64GBを導入する一つのきっかけになりました。
やっぱり余裕があると精神的にも落ち着きます。
ゲーム用途だけなら問題はありません。
実際、今販売されているBTOマシンは32GBを標準搭載とするものが多く、64GBを備えたモデルは動画編集や3D制作を視野に入れたハイエンド寄りの仕様になっています。
「多ければ安心」と思うのは自然ですが、それが活きるのは利用環境がそこまでリソースを要求する場合に限られます。
メモリ増設自体でフレームレートがいきなり伸びる、そういった単純な因果関係は存在しません。
むしろ考えるべきは全体の調和です。
CPUだけでなく、GPU性能、ストレージ速度、冷却性能。
最近私が触れたGeForce RTX5070Ti搭載マシンは、その好例です。
32GBのメモリ構成ながら、最新ゲームを負荷いっぱいに動かしても、遅延も引っかかりもなく爽快に遊べました。
その納得感のある動作こそ、私が言いたい本質です。
とはいえ、AI関連のアプリや複数のクリエイティブソフトを扱うとなれば32GBではたちまち心許なくなります。
実際、画像編集ソフトを複数開きながらAI処理を走らせつつ、さらにブラウジングまで広げると、リソースは一気に逼迫しました。
生成AIの試験利用をしたときのことですが、そのとき初めて「思っていた以上にメモリを食う」と驚いたのです。
未来に向けてAI活用が拡大するのは間違いない。
だからこそ、64GBを最初から選んでおけばよかったと後悔する可能性は十分にあると思います。
安心を担保する、文字通りそういう選択なのです。
つまりこうです。
もし用途がゲームプレイ中心であれば、32GBで十分快適。
けれど、動画制作や配信、AI系の作業まで一緒にしたいのであれば、64GBの方が余裕があって安心。
これはシンプルですが、利用スタイルと構成を一致させることが最も大事な判断基準になるということです。
結局「自分の使い方次第」。
この一言に尽きます。
私が人に相談された場合、いつも同じように答えています。
「ゲームを中心に遊ぶなら32GBで十分。
ただし配信や映像制作に力を入れるなら64GBを考えてみてほしい」と。
選び方を誤らなければ、余計な出費を防ぎつつも、ちゃんと快適性を確保できます。
そこで意識したいのが、自分の将来像をどう描くかということです。
今はしない作業でも、半年後に取り組む予定があるなら先を見据えるのも悪くありません。
逆に変に盛りすぎても、使わない機能が眠って無駄になるだけ。
メモリは数字だけの装飾品ではありません。
必要なのは、何を重視して仕事や趣味と向き合うか。
そこを冷静に考え、投資とリターンを天秤にかけることだと私は思います。
そして、その選択を支えるのは経験です。
無駄に豪華な構成を追いかけない。
そのバランス感覚こそ、長く快適にPCを付き合っていくための秘訣なのだと、私は胸を張って言いたい。
Core Ultra7 265K ゲーミングPCはコスパ的にどうなのか検討

価格と性能のバランスが取れる構成を考えてみた
普段の生活でPCを選ぶときに一番大事にしたいのは、性能を追い求めすぎて生活のバランスを崩さないことだと私は思います。
結局のところ、長く安心して使えるかどうかが重要であって、数字の上だけで優れていても実際の使用感と釣り合わなければ意味がないのです。
私自身も、性能に酔って高額な構成に心が揺れたことは何度もあります。
しかし冷静に考えれば、仕事もゲームも快適に楽しめる範囲で落ち着くことが、最終的には精神的な満足につながると気づきました。
CPUに関しては、Core Ultra7 265Kを選びました。
Ultra9にも一瞬心を動かされましたが、必要以上に上位を目指しても宝の持ち腐れになりかねませんし、電気代や発熱の面でも負担が増えます。
Ultra7 265Kであれば価格と性能の釣り合いが非常に良く、コスト面でも余裕が持てるのです。
正直、初めてその価格を見たときは「本当に大丈夫なのか?」と疑ってしまうほどでした。
けれど実際に使い込んでみると、その心配は無用だったとわかりました。
グラフィックボードも悩みどころでした。
RTX5090を想像すれば、誰でも一度は心が揺さぶられると思います。
私も例外ではなく「やるならここまで行こうか」と気持ちが大きくなる瞬間がありました。
だけど、実際のプレイ環境を頭に思い浮かべると、冷静になれたのです。
WQHDでスムーズに遊びたい私にとって、RTX5070が最も丁度よい落としどころでした。
初めて電源を入れてゲームを立ち上げた瞬間、「あぁ、これで十分だ」と心から思えたのをよく覚えています。
その安心感があるからこそ、逆に気持ちよく投資できたという面も大きいです。
メモリも同じです。
DDR5-5600の32GBで全く不足はありません。
64GBを検討した時期もあるのですが、冷静に考えても私の用途では宝の持ち腐れ。
毎日動画編集をするような生活ではありませんし、大容量を積んだところで普段は遊休資産と化します。
その分をGPUやSSDに回す方が体感としては大きなリターンになる。
悩ましいけれどワクワクする時間。
まさにそれです。
ストレージ選びは比較的シンプルでした。
私は2TBを選びました。
容量も十分で、ロード時間の差を意識することもほとんどありません。
むしろ熱やファンの音が減ったことで、快適さが違うのです。
「数字より使用感」。
この実感は大きいものでした。
冷却についても昔なら水冷一択だったのですが、今は大型空冷クーラーで十分対応可能です。
中でも静音性は大きなメリットで、仕事をしている平日に騒音に悩まされることはありません。
休日にPCの掃除をしていても「もし漏れたら…」と不安になることがない。
それがこんなにも気持ちを楽にさせてくれるとは思いませんでした。
手間が減るというのは、本当にありがたいことです。
ケースも大切です。
一見華やかなデザインに惹かれるのですが、結局は排熱効率に優れたケースの方が快適に長時間使えます。
真夏にゲームをしていても内部が安定し、気持ちが焦らない。
見た目より実用。
そこに行き着きました。
しかし「続けて使うための安心感」を犠牲にするわけにはいかなかったのです。
こうして出来上がった構成は、派手さよりも日常の使いやすさを優先した非常に堅実なものになりました。
CPUにCore Ultra7 265K、GPUはRTX5070、メモリは32GB、SSDはGen.4の2TB、冷却は大型空冷、ケースはエアフロー重視。
この構成なら最新ゲームも業務用途も安心してこなせる。
それが一番の魅力です。
もし友人に「どんなPCを組めばいい?」と聞かれたら、私は迷わずこの組み合わせを提示するでしょう。
大人として、無理のない投資で長く楽しめること。
ここに勝る満足はありません。
趣味として楽しみながらも生活を圧迫しないことは、社会人にとって大切な判断基準です。
その意味でこの構成は、背伸びせずに着実な選択ができたという実感を与えてくれました。
安心感。
これなら胸を張って人に勧められる。
私自身、やっと自分にとっての最適解を見つけたという手応えを感じています。
長く寄り添える相棒になりそうです。
ストレージを1TBと2TBで使った場合の違い
CPUやGPUと比べれば分かりやすい派手さはありませんが、長く使う上での快適さや余裕を考えると、容量の差が最終的な満足度を左右します。
結局のところ、私は2TBを選ぶのが賢明だと思っています。
経験上、1TBでは必ずと言っていいほど容量不足に直面し、ストレスを感じる場面が増えがちだからです。
私が1TBのSSDを使っていた頃の話ですが、最新のAAAタイトルを三本ほどインストールしたらもう半分以上が埋まってしまい、そこに動画編集の素材を置こうとした時には、もう残りが数十GBしかないという有様でした。
そのとき「これ以上は無理か」とPCの前でため息をついた光景を今も思い出します。
そして泣く泣く思い入れのあるゲームをアンインストールしたわけですが、その気持ちはなかなか複雑で、まるで自分の趣味を切り捨てられたようでした。
自分が楽しむために買ったPCのはずなのに、不自由さがつきまとった。
まさに窮屈さ。
その後2TBのストレージを選んだとき、その違いに驚きました。
空き容量の残りを気にせず自由にゲームや編集データを置けることがこんなに解放感をもたらすのかと実感したのです。
あれこれ考えずに保存できるというだけで、毎日の使用感がまるで別物になりました。
容量の余裕が心に余裕を生み出す、それを率直に体験しました。
ここ数年のゲームは本当に大容量化しています。
最近の大作では100GBを軽く超えることが当たり前になりつつあり、追加コンテンツなどを入れればさらに肥大化するのが常です。
1TBだと、インストールするたびに「これは残して、あれは削除しよう」と小さな取捨選択に迫られる。
その積み重ねが面倒で仕方ありませんでした。
一方で2TBなら、そういう細かい我慢を強いられない。
好きに残し、気ままに遊び、気軽に保存する。
その気持ちよさこそが大きな差になりますね。
さらに大容量のSSDには速度や安定性の面での利点もあります。
PCIe Gen.4やGen.5対応のSSDでは、容量が大きいほうがコントローラの動作効率が上がることが多く、転送の安定感に繋がります。
数値だけを追いかければ見落としがちですが、日常的なファイル操作やゲームのロード時間にもじんわり効いてくるのです。
だから私は、ストレージはただの倉庫ではなく、性能に直結する基盤だと理解しておいた方が良いと考えています。
しかし今は随分と価格が落ち着き、BTOのオプションでも1TBとの差が劇的に大きいわけではありません。
むしろ、後から外付けSSDやM.2を買い足してごちゃごちゃと管理するほうが、費用も手間も余計にかかる。
結果としては、最初から2TBを選ぶほうがずっとシンプルで合理的なんですよね。
もちろんすべての人に2TBが必須ではありません。
しかし私のように一台でゲーム、録画、編集といった用途を盛り込みがちな場合は、容量の差が作業のしやすさに直結します。
録画ファイルやスクリーンショットは意外なほどサイズがかさみ、一度に数時間録画すればあっという間に数十GBを食いつぶします。
それでも余裕があるからこそ、不安に駆られることなく使えるのです。
安心材料です。
さらに、容量不足がPC全体の動作に悪影響を及ぼすことも見逃せません。
Windowsは仮想メモリや一時ファイルにストレージを使いますから、残量が減ると全体のパフォーマンスにも影響が出てきます。
せっかく高性能なCPUを選んでも、それを支えるストレージが目詰まりしていたら宝の持ち腐れです。
私はこれを「もったいない投資」と呼んでいます。
PCを組むときは部品単体の性能だけでなく、相互のバランスでトータルの快適さを確保する方が結果的に長持ちします。
そう考えると、2TBという選択は単に容量を増やすというレベルの話ではないのです。
1TBでも動かせますが、頻繁にデータ移動をしたり、整理に追われるような毎日にはしたくない。
私も40代になり、仕事での書類や写真、動画データも増え続けています。
ゲームを楽しみながら仕事のデータも扱う私にとって、ストレージ容量は単なる数字ではなく、毎日のストレスを左右する現実的な要素です。
だからこれからPCを新調する誰かに意見を求められれば、私は迷わずこう答えます。
「最初から2TBにしておいた方が後悔が少ないよ」と。
2TBを選ぶことで得られるのは単なる安心感だけではありません。
データの管理から解放され、作業も遊びも思い切り楽しめる。
そして長く満足できるマシンに育つ。
その違いを一度味わった人にはもう後戻りできないでしょう。
これが、私自身の経験から導いた正直な結論です。
安心感と余裕。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AD

| 【ZEFT Z56AD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AB

| 【ZEFT Z56AB スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EY

| 【ZEFT Z55EY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | be quiet! SILENT BASE 802 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6160K/S9

| 【SR-u7-6160K/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55BX

| 【ZEFT Z55BX スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
電源ユニット選びが後々の維持コストに与える影響
私自身、これまで何度も自作やアップグレードをしてきましたが、結局のところ維持コストや安定性を決めるのは電源でした。
安さに釣られて選んだものは、結局あとからトラブルや電気代で跳ね返ってくる。
そうなると出費はむしろ増え、気持ちばかりが疲れていくんです。
だからこそ、最初に信頼できる電源をきちんと選ぶことが、最も合理的で長期的な節約につながると実感しています。
Core Ultra7 265Kに最新のGeForce RTX 50シリーズを組み合わせるような構成では、消費電力は想像以上です。
ここで電源の質を落とすと、ただでさえ高い電気料金が月々じわじわと膨れあがっていく。
短期的には「得した」と思うかもしれませんが、それは一瞬の錯覚にすぎません。
後から出費と不安で取り返される。
だったら最初から80PLUSゴールドクラス以上に投資する方がいい。
私も過去に甘い考えで廉価電源を選んだ失敗があります。
あの時は「電源なんてただの黒い箱だろう」と思っていたのです。
しかし真夏に長時間稼働させた際、電源が焦げ付いてマザーボードとSSDまで巻き添えになりました。
仕事の資料もプライベートの思い出も一緒に消えました。
絶望でしたね…。
あれ以来、電源だけは絶対に妥協しないと心に決めました。
安定性こそ命だと思います。
Core Ultra7 265Kはオーバークロックにも対応しているため、電力の上下が激しくなることがあります。
その時に余裕のない電源を使っていると、システム全体の不調につながってしまう。
PCゲームだけでなく仕事の最中に落ちたら、冷や汗どころではありません。
「やってしまった」と頭を抱える羽目になるのは目に見えています。
さらにケースとの相性も軽視できません。
私は以前、小型ケースにハイワットの電源を無理やり詰め込んだのですが、エアフローが不足して熱がこもり、効率はみるみる悪化しました。
外見のデザインばかり優先して内部構造を軽視すると、思わぬ落とし穴にはまるんです。
特に流行りのガラス張りケースは熱がこもりやすく、ファンや電源に大きな負担をかけやすい。
結局また電源を買い直すことになり、お金も手間も無駄にしました。
正直、苦笑するしかない体験です。
アップグレードを見据える上でも電源は重要です。
CPUやGPUを交換するたびに出力が不足して、結局ボトルネックになってしまう。
私も新しいグラフィックカードに入れ替えた時、数か月で電源が足を引っ張った苦い経験があります。
「またか」と天を仰ぎました。
結局、最初から余裕のある容量を確保しておけば無用な出費を防げるんです。
最新パーツの進化スピードを見れば、これは言い切れます。
安心をお金で買う意味を、電源選びほど実感できる場面はありません。
私は一時期、安い海外製から国内メーカーのモデルに変えましたが、その差は予想以上。
静音性も安定性も段違いでした。
夜通しパソコンを動かしていても不安が頭をよぎらない。
精神的な落ち着きです。
毎日使う道具だからこそ納得できる買い物が必要だとあらためて思いました。
安心感。
これは何物にも代えがたい。
電源ユニットは単なる黒い箱ではありません。
むしろPCの土台そのものであり、寿命を決める最重要パーツといっても過言ではない。
数年で壊れる安いものを買って取り替えるより、最初から10年設計をうたう製品を導入した方が、圧倒的に長く安心できます。
これは消耗品というより投資対象です。
パソコンをただの道具ではなく相棒と考えるなら、この選択は自然に決まってきます。
私が胸を張って伝えたいのは、Core Ultra7 265Kを軸にゲーミングPCを組むなら、80PLUSゴールド以上、750?850Wクラス、そして信頼性の高いブランドを選ぶこと。
その条件を守れば、長い目で見てコストを大きく削減でき、安心してパソコンと付き合い続けられると断言できます。
この選択こそが未来を支える一番の確実策だと思うんです。
多くの人は新品のPCを組む時にCPUやGPUばかりに目を奪われがちですが、本当に財布に直撃するのは電源です。
私はそこに気づくまで何度も回り道をしました。
だからこそ声を大にして言います。
電源にこそ余裕を持ち、信頼できる製品にお金をかけることが、最終的には一番の節約であり、一番の安心につながるのです。
未来の拡張も考え、最初の選択で後悔しないこと。
Core Ultra7 265K 搭載PCを扱うBTOメーカーを比較

初心者でも選びやすいBTOショップの特徴
Core Ultra7 265Kを選ぶ際に一番悩むのは、正直なところ性能そのものよりも、どのショップと付き合うかだと私は考えています。
もちろん価格やスペックを比較するのは当たり前ですし、誰でもそこから入ると思います。
しかし、長く使うパソコンだからこそ「ここでなら安心できる」と思えるかどうかが、最後の決め手になるのです。
私は過去に何度もBTOパソコンを選んできましたが、失敗も成功もすべて結局はショップ選びで決まっていたと実感しています。
最初にマウスコンピューターについて触れたいと思います。
ここはサポートの安心感が抜群に強いと感じています。
国内拠点での対応というだけでも、トラブル時の心構えがかなり違ってきます。
私が以前、セールでCore Ultra7 265KとRTX5070Tiを搭載したモデルを購入した際、最新タイトルを設定をほとんど下げずにサクサク遊べたときの興奮は、あの瞬間のために投資してよかったと思えたほどでした。
そして、小さなトラブルでサポート窓口に問い合わせたとき、驚くほど早く返事をもらえたのです。
困ったときに支えてくれる人がいる安心感は大きい。
頼れる相棒、そんな印象でした。
次にパソコン工房です。
ここはコストパフォーマンスで選ぶなら外せません。
地方にも店舗があるので、実際に店員さんと顔を合わせて相談できる強みがあります。
その体験が意外と重要なのです。
例えば、私自身が先日店舗に足を運び、展示されていたCore Ultra7 265K搭載PCを触ったとき、カタログでは分からない冷却性能のイメージやケース内部のエアフローの感触を確かめることができました。
店員さんと話しながら「ここは意外と静かだな」とか「このサイズ感なら置き場所に収まるな」と直感的に納得した瞬間がありました。
この肌感覚の納得があるからこそ、価格の安さだけに目移りせずに選べると思うのです。
背中を軽く押してくれるような存在だと感じています。
そして、パソコンショップSEVEN。
ここは一言でいえばこだわり派にぴったりの存在でしょう。
国内生産へのこだわりや、研究機関へ納品した実績などからくる信頼感がありますし、何よりフルカスタムに対応している柔軟さが特徴です。
メモリのメーカーまで明記される細やかさは「なるほど、こういう部品をきちんと選んで使っているのか」と納得させられます。
私が一度、SEVENにメールで構成相談を依頼した際、すぐに返ってきた丁寧な提案は今でも忘れません。
予想以上に親身で、自分が考えていた以上の最適解を提示されたことに感動したのです。
わがままを歓迎してくれるショップ。
そんな印象です。
三社を並べて考えると、それぞれの個性がはっきり見えてきます。
マウスコンピューターは「安心感のあるサポート」、パソコン工房は「コスパと実体験の両立」、SEVENは「徹底して自分の理想を形にするカスタム力」。
いずれも方向性が異なり、人によって魅力の感じ方が変わるのは当然です。
ただ、この三社の中から選べば少なくとも大失敗は避けられると私は思います。
あるいは自分のこだわりを極めたいのか。
Core Ultra7 265KというCPU自体がかなりの性能を持っているため、選ぶGPUや冷却方式によって体験に違いが出てきます。
RTX5070Tiを組み合わせれば最新ゲームが余裕で楽しめるし、RTX5060Tiでも解像度を調整すれば十分快適に遊べる。
そうなると、単に価格だけでなく「安心して運用できるか」「不具合が出たときに誰が支えてくれるか」という判断軸も本当に重要になるのです。
私自身、過去に値段だけを優先して購入し、その後のサポートで泣かされた経験がありました。
保証の対応が遅くて、結局買い直しに近い形になったときのあの悔しさは今でも忘れられません。
焦らない。
これが大切です。
逆に、自分の要望を整理した上で、時間をかけて最も寄り添ってくれるショップを選んだときには、購入後の満足度が全く違います。
例えば、マウスコンピューターで安心を買うのも正解ですし、パソコン工房でコスパを狙うのもアリです。
SEVENで世界に一つだけのPCを組み上げて「これは俺の一台だ」と気持ちを高めるのも立派な選択肢です。
年齢を重ねた私は、今では「後悔しない買い物こそが最高の価値」だと痛感しています。
だからこそ、最終的には自分が何を優先したいかをじっくり見極めるしかないのです。
最終的に得られるものはシンプルです。
安心して使い続けられるという大きな満足感です。
ショップ選びに慎重になった分だけ、その満足は着実に増していきます。
私はこれまでの経験から声を大にして言いたいのです。
パソコン選びはスペックや価格の比較だけでなく、「どこで買うか」という選択が、実際の使い心地や安心感を決める最重要ポイントになるのだと。
時間をかけて自分に合うショップを探してください。
それが失敗を避ける唯一の方法であり、本当に納得できる買い物への近道なのです。
冷却性能を強化したカスタムモデルをチェック
冷却性能をおろそかにしたPC選びは、あとで必ず自分を苦しめることになると私は思っています。
とくにCore Ultra7 265Kのように高性能で発熱量の大きいCPUを使うなら、なおさらです。
スペック表に書かれた数字だけを信じて飛びつくのは危険で、熱処理をどう組み込むかで安定性も快適性もまるで別物になる。
これは、私自身が過去に痛い思いをしたから身に染みていることです。
昔、初めて憧れのゲーミングPCを買ったときの話です。
見た目はゴツくて派手、まさにゲーマー仕様でした。
でも標準の空冷ファンの冷却がまったく追いつかず、連続プレイをするとファンがうなるように回り続けて、騒音が部屋にこだまして落ち着かない。
ゲームどころか気持ちが削がれてしまって、心の中で「やってしまったな」と何度もため息をつきました。
性能以前に環境として耐えられない。
こういう後悔は、二度と繰り返したくないのです。
ただ「性能の高いクーラーを付ければいいんでしょ」と単純に片づけられないのも、この世界の奥深いところです。
たとえば水冷は強力ですが、ラジエーターやホースの取り回し次第でファンの音が大きくなることもある。
さらにはケースのエアフローが悪ければ、せっかくの水冷も本領発揮できないことすらある。
だから私は冷却能力と静音性のバランスを見ながら選ぶようになりました。
うるさいPCは、長く愛せないんですよね。
ここ数年で感心したのは、ガラスパネルを取り入れつつ冷却をちゃんと成立させているPCケースです。
以前は「ガラスは熱がこもる」というのが常識で、見た目と冷却はトレードオフだと思っていました。
でも最近のモデルは前面と天面だけでなく、底面にも吸気や排気の工夫をしていて、見事に弱点を消してきている。
しかもリビングに置いても映えるような美しさを備えつつ、ゲーム中の温度も安定。
正直、眺めているだけで満足感を得られるほどです。
熱という点で見落とされがちなのがSSDです。
PCIe Gen.5対応のSSDなんて、本当に触れないぐらい熱くなることがあります。
そのまま放置すればスピードが落ちたり寿命を縮めたりするのは目に見えている。
初めてSSD専用のヒートシンクを搭載したモデルを見たときは、「ここまで考えてくれるのか」と驚きました。
小さな部品にまで気を配れるメーカーの姿勢に、素直に安心しました。
さらに心に残ったのは、RTX5070Tiと組み合わせたマシンです。
これは単なるスペック比較では分からない領域で、実際に体験して初めて「こういうPCこそ価値がある」と実感した瞬間でした。
静かで強い。
この二つがそろったときの気持ちよさは、何物にも代えがたい。
結局のところ、冷却性能を軽視するか重視するかで、PCの寿命も体験もまるで違ってくるのです。
私は一度、熱暴走で仕事中のデータを失ったことがあります。
あのときの悔しさは、もう思い出すのも嫌になるくらい強烈でした。
その経験以降、「安さで飛びつくのではなく長く安心して使える環境を買う」という考えが定着しました。
冷却設計は単なるオプションではなく、安定動作のための必須投資だと断言できます。
強化モデルを買って後悔したことは、これまで一度もありません。
むしろ逆で、「最初から強化にしておけば、どれだけ快適だったか」と後悔するのは常にノーマルモデルの方です。
多少の初期投資は必要ですが、静かで安定した日常が手に入るなら十分に帳尻が合う。
とくにセールで出てくるモデルなら値差も小さく、満足度は大きい。
そこに狙い目を感じることが多いですね。
要は、Core Ultra7 265K搭載のマシンを買うなら、私は冷却を強化したモデルを迷わず推したい。
その選択が性能を正しく引き出し、静かで快適に長く使える環境をくれるからです。
自分の時間とお金を本当に大事にしたいなら、ここはケチってはいけない。
冷却は安心です。
冷却は信頼です。
何年経っても「これは買ってよかった」と思えるのは、やっぱり冷却にきちんと投資された一台です。
私にとってそんな相棒があること自体が、心強い支えになっているのです。
見た目重視の人に人気があるガラスパネルケース
ゲーミングPCを選ぶときに私が一番大切だと思うのは、やはり性能とデザインの両立です。
正直、昔の私は「見た目なんてどうでもいい、動きさえ良ければそれで十分だ」と考えていました。
しかし今では、その発想はもはや古いと感じています。
例えばCore Ultra7 265Kを搭載したBTOモデルであれば、処理速度も冷却性能もすでに高水準にあり、それに加えて目を楽しませるデザインを選べる時代になりました。
性能が満たされ、次に求められるのが「所有する喜び」なのだと思います。
ガラスケースというと、派手さを求める人向けだと考えがちですが、実際はもっと奥深い魅力があります。
光が反射し、内部パーツを立体的に映し出す様子は、ただの部品の集合ではなくひとつの作品のように感じられます。
特に最新のGPUがガラス越しに存在感を放つとき、「この力を手に入れた」という実感と同時に「美しい機械を所有している」という誇りが胸にこみ上げてくるものです。
その瞬間、自分の中の少年のような心が目を覚ます感覚があります。
私自身、かつては無骨な黒い箱を当然のように選び続けていました。
ところが数年前の展示会で、3面ガラス仕様のPCケースを目にしたときに思わず立ち止まってしまったのです。
「なんだこれは」と口に出してしまうほどの衝撃でしたね。
部屋の空気を変える存在感。
あれを見た瞬間、PCはただの道具ではなく、暮らしの中の風景をつくり出すアイテムになり得るのだと悟りました。
この気づきは、私の仕事や生活に対する考え方まで少し変えてしまったほどです。
最近ではピラーレス構造のケースが特に人気です。
支柱がなく、視界を遮らない設計によって奥まで光が届き、全体の雰囲気が一段と引き立ちます。
仕事を終え、部屋を暗くしてPCを起動する瞬間には、日常から非日常へ切り替わる特別なスイッチを押すような高揚感があります。
この切り替えがあるからこそ、私は日々の忙しさを忘れて趣味の時間に没頭できるのです。
とはいえ、外観だけに気を取られると痛い目を見ることもあります。
ガラスパネルを取り入れる一方で、熱処理という課題は常につきまといます。
Core Ultra7 265Kは確かに優れた処理性能を持ちますが、その分発熱も強烈です。
通気設計を軽視すれば、うるさい騒音と高温に悩まされる。
私も以前、適当に組んでしまった結果、夏場の猛烈なファン音に後悔したことがあります。
あの苦い経験以来、冷却設計には慎重になりました。
場合によっては水冷に投資した方が安心だと、今では自信を持って言えます。
さらに見落としがちなのがケーブルマネジメントです。
これは本当に要注意です。
せっかく透明なケースを選んでも、中が配線でごちゃごちゃしていたら全てが台無しになります。
私も最初にガラスケースを組んだとき、「見えない裏側だから適当でいい」と考えてしまいました。
しかし結果的に裏配線が透けて見えてしまい、完成したときの恥ずかしさは忘れられません。
配線をきっちり整理したPCは、性能の数値とは関係ないのに全体の完成度を大きく底上げしてくれるのです。
面白いのは、デザインの幅が広がっていることです。
最近では木製パネルを使ったケースも登場しています。
これが予想以上にインテリアに馴染むのです。
ガラスや金属だけでは冷たく感じる部屋でも、木の質感が加わると柔らかさと温かみが生まれます。
その結果、リビングに配置しても家族から不満が出にくい。
ゲーミングPCはギラギラ派手に光るものというイメージはもはや昔の常識であり、今は落ち着いた光を楽しむ大人の趣味へと確かに進化していると感じます。
私はこう考えています。
Core Ultra7 265Kを搭載するのであれば、強化ガラスパネルのケースを選ぶのが最適解です。
その上で冷却と配線をきちんと考え抜く。
PCはただの作業道具ではなく、部屋の空気をつくり、自分の存在を映し出すパートナーになる。
これは経験を通して確信していることです。
整った配線や冷却構成、こだわりのケース選び。
その一つひとつが積み重なって最終的には私自身のスタイルを表現します。
オフィスで使う良いボールペンに自然と愛着が湧くように、PCケースひとつで気持ちが変わる。
そういう小さな変化の連続が、不思議なことに実際のパフォーマンスに結びつくのです。
私はこれを身をもって体験しました。
だから声を大にして言います。
ガラスパネルのゲーミングPCは単なる自己満足では終わらない。
むしろ日常を豊かにし、仕事や趣味に前向きな影響を与えてくれる道具です。
目で楽しみ、心で感じ、使うたびに誇りを思い出させてくれる存在。
それが「魅せるPC」なのです。
最高の相棒。
年末セールで狙い目のCore Ultra7 265K ゲーミングPC


実店舗よりオンライン購入が有利な理由
年末の忙しい時期に新しいPCを買おうと考えたとき、私は迷わずオンラインショップを選びました。
理由は単純で、全体的にオンラインのほうが明らかに有利だからです。
価格、在庫の安定、配送スピード、カスタマイズの自由度に至るまで、実店舗に対して強みが多すぎる。
私自身が身をもって体験してきたことなので、自信をもって言えます。
まず伝えたいのは価格の現実です。
店頭価格を見比べてきた私は、正直その差に驚かされることが多いんです。
実店舗では、家賃や人件費など避けられないコストが乗るため、同じスペックでもどうしても割高になる。
特に昨冬、Core Ultra7 265Kを搭載したPCを探していたとき、オフラインとオンラインの差は数万円単位。
あまりの違いに、展示品を前にしながら「いや、これは実店舗で買う意味は薄いな」とその場でスマホからポチっと注文してしまったほどでした。
自分でも笑ってしまいましたよ。
在庫状況の差も無視できません。
店頭で「人気モデルは予約待ちです」と言われ、肩を落とした経験が何度もあります。
仕事の合間を縫って足を運んだのに、手ぶらで帰る憂鬱さといったら…。
オンラインなら複数のショップを横断的に探し、すぐに在庫を押さえられる。
この安心感は本当に大きい。
無駄足。
もうあの感覚を味わいたくありません。
配送の速さは、もはやオンライン最大の驚きポイントかもしれません。
あるとき私がBTO構成で注文したマシンは、翌日に発送通知が届きました。
そのスピード感。
感動です。
店頭で取り寄せをお願いしたら数日、場合によっては数週間。
比べてみれば差が歴然でした。
私は過去にSSDの容量が無料で倍増するタイミングを狙って購入しました。
加えて静音性の高いCPUクーラーまでセットになり「ここまでしてくれるのか!」と声が出ました。
年末特有のセールに重なると、まるで宝探しのような気分です。
ちょっとしたご褒美を得たようで、その瞬間は思わずにやけてしまいました。
比較のしやすさに関してもオンラインは圧倒的です。
実店舗ではどうしても照明や雰囲気に惑わされて、本当に見るべき冷却性能や拡張性を冷静に判断できないことがありますよね。
その点、オンラインではスペック表と価格情報を冷静にチェックできます。
数字と仕様でシンプルに比較。
もちろん、実店舗の良さを否定するつもりはありません。
キーボードの打鍵感やファンの音は、実物でしか得られない要素です。
ですが今やレビュー動画やテスト記事が豊富にあり、むしろ「店舗以上に参考になる」と思うことが多々あります。
特にありがたいのはポイント還元です。
私はオンラインでPCを買うたびに数千円分のポイントを受け取り、その後の周辺機器やアップグレードに活かしています。
ある時は、そのポイントだけでSSDを一つ追加購入できたんです。
積み重ねの成果にニヤリとしましたよ。
会社の経費ではない、自分の財布で買っているからこそ、この差は心に染みます。
サポート面での不安についても、今は心配無用だと感じています。
私は一度、初期不良にあたってしまったのですが、オンラインで手続きを済ませたら数日後には新品が届きました。
そのスムーズさに驚き、むしろ店頭で長々と待たされた過去の経験を思い出して苦笑しました。
形式張ったやり取りより迅速で、効率的なんです。
さらに魅力を語るなら、カスタマイズの自由度です。
CPUクーラーの選択やケースのデザイン、搭載するストレージ容量まで細かく決められるのはやはり最高です。
店頭モデルだと与えられた選択肢の中から受け入れるしかないのですが、オンラインなら「自分だけの一台」を形にできます。
仕事の用途、趣味のゲーム、さらには動画編集まで考慮し、まさにオーダーメイドの体験。
自分の手で未来を設計している感覚があります。
総合すると、価格の合理性、在庫確保のしやすさ、配送の迅速さ、キャンペーンの楽しさ、比較の冷静さ、レビューの信頼性、ポイント還元の長期的な効果、サポート体制の安心、そして自由なカスタマイズ性。
この九つを考えればオンラインでの購入に軍配が上がるのは自然な流れです。
特に需要が集中するCore Ultra7 265Kのようなモデルでは、実店舗との差が一層はっきり見えると思います。
だから、私は断言します。
年末に新しいPCを買うならオンラインがいい。
迷う必要はない。
時間もお金も効率的に使えるし、お得感までついてくる。
最後に届いた箱を開いた瞬間の高揚感。
これがある限り、私はこれからもオンライン派であり続けると思います。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BD


| 【ZEFT Z56BD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake The Tower 100 Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EJ


| 【ZEFT Z55EJ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EKB


| 【ZEFT Z55EKB スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59Q


| 【ZEFT Z59Q スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ Corsair製 水冷CPUクーラー NAUTILUS 360 RS ARGB Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Corsair製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BG


| 【ZEFT Z56BG スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
一番割引率が高い購入方法はどれか
家電量販店の完成品モデルももちろん悪くはないのですが、比較してみるとやはりBTOショップの柔軟さと価格の差には驚かされるのです。
自分の好きな構成を選びながら、しかも同じCPUを積んだPCが数万円も安く手に入るというのは、冷静に考えれば当然に見えて、実際に体験すると「ここまで違うのか」と声が出てしまうくらいでした。
特に年末から年始にかけての時期は、CPUやGPUの相場が露骨に反映される期間です。
数年前までパーツの価格変動にはあまり興味がなかった私ですが、今ではこのシーズンになるとしっかり情報を追うクセがついています。
それくらいセールの効き方は大きいんです。
ときにはグラフィックボードとのセット割引が予想以上に強烈で、ほぼCPU代がタダに見えてしまう瞬間すらあります。
「いやいや、これは買うしかない」と。
突然出てくるクーポンやタイムセールは魅力的ですし、即断即決できる人には非常にありがたい仕組みだと思います。
しかしこちらは基本的に完成品しか選べないので、自分の理想にどこまで寄せられるかを常に考えなければならない。
じゃあ、どちらで買うべきかと言えば、自分が「性能と構成をどこまで自分で決めたいか」に尽きるのです。
価格の推移に関しては、既にcoreシリーズ全体がピーク時から値下がりしてきていて、特に年末のセール時期はほぼ底値と言っていい状況です。
CPUだけを単品で購入して自作をすることも可能ですが、DDR5メモリや最新規格のSSDまで含めて買い揃えようとすると、かえって割高になるのが実情です。
BTOモデルならこれらがセットアップされ、さらにキャンペーンによる割引も効く。
全体で見れば明らかに予算に優しく、安心して選べるという現実を前に、私自身も自作へのこだわりをある程度手放しました。
ただし、展示品や中古品については正直おすすめしません。
私も過去に、安さに惹かれて展示品を購入した経験がありますが、その半年後にファンの異音がし始めて、結局修理に出す羽目になった苦い思い出があります。
新品を選ぶ安心感というものは、値段以上の価値がある。
これは経験をした人にしか分からないでしょう。
あれもまた大切なんですよね。
特に今の大作ゲームは100GBを軽く超える容量を要求してくるので、ストレージの大きさはすぐに生活感のある問題になります。
購入後に「やっぱり容量が足りなかった」と困るより、最初から余裕を持っている方が良いに決まっている。
その意味でも、こうしたキャンペーンはありがたいですし、私が最終的に購入を決めるときの後押しにもなりました。
さらに興味深いのは、年末セールの直前期に各ショップ間で価格競争が始まることです。
スマートフォン市場で新機種が発表されるタイミングと同じように、PC市場も急に活気づく。
正直、あの瞬間の胸の高鳴りはいまだに鮮明に覚えています。
ただし気をつけたいのは在庫のリスクです。
人気構成は入荷数が少ないため、あっという間に売り切れてしまうことが多い。
実際に私自身、あと1日考えようかと迷った末、翌日には売り切れとなり、途方に暮れたことがありました。
だからこそ私が今言いたいのは、BTOショップの年末オンラインセールは迷わず参加してほしいということです。
しかもアップグレード特典やキャンペーンが付いているモデルを狙い、かつセール終了直前まで粘って確認し、そこから一気に決断するのが一番良い。
年末。
財布の残高と画面の価格をじっと見比べながら、カートに入れたまま迷うあの時間。
緊張とワクワクが入り混じったあの感覚は、40代になった今でも変わらず楽しい一コマです。
だから私はまた今年の冬も、PC市場の賑わいを見守りつつ、自分にとって納得できる一台を探すつもりです。
自分だけのマシンを選び抜くあの喜びを、今年もじっくり味わいたいのです。
迷う時間も、また楽しい。
2025年冬にチェックしたいセール対象モデル
2025年の冬のモデル選びで優先すべきは、やはりCore Ultra7 265Kを搭載したゲーミングPCです。
私が実際に使ってきた経験や市場動向を見てきた実感からしても、これ以上にコストとパフォーマンスの折り合いが取れているCPUは、今のところ存在しないと言っていいでしょう。
20コア20スレッドという圧倒的な処理性能を備えつつも、価格は意外なほど抑えられており、仕事と趣味を両立したい人間にとって非常にありがたい存在です。
しかもその「ちょうどよさ」が、実際の使い勝手につながっていると強く感じています。
私自身、業務で資料を作りながら、夜には高負荷のゲームをストレスなく快適に遊べる。
そんな日々を過ごす上で、このCPUは頼れる相棒のように存在感を放ってくれています。
だからこそセールに出てくれば、即断してしまうべきでしょう。
迷っている時間がむしろ損に思えてしまいますね。
GPUに関しても、この冬はRTX5070TiやRTX5060Tiを搭載したモデルが主流になりそうです。
このクラスのカードは実際に触ってみると、4K映像においても驚くほど滑らかで安定しており、ゲーム環境として長く安心できると思えます。
特にeSports系のタイトルは勝敗がフレームレートによって大きく左右されるため、ここでケチると明らかに後悔につながるのです。
私の友人も5070Tiを買ったばかりで、週末にはFPSに没頭しているのですが、話しぶりだけでも満足感が伝わってきます。
一方で気になるのがAMD系、特にRadeon RX 9070XT。
搭載モデルがセール対象として登場することがあれば、私は迷わず注目します。
FSR4のフレーム生成を実際に体験すると言葉どおり新次元でした。
レースゲームで試した時、景色の変化が自然で没入感がまるで違う。
今年の冬にこうしたモデルが店頭に並んでいたとしたら、見逃すのはもったいない。
素直にそう感じています。
さらに見落としがちですが、メモリは侮れない要素です。
今のトレンドは32GBが標準ですが、セールのタイミングでは64GBの大容量に増設されたモデルがほとんど変わらない価格帯で並ぶことがあります。
動画編集や仮想環境を同時に扱う場面では、その差が歴然と出ます。
その余裕が嬉しくて、買った自分を褒めました。
ストレージの選択も、購入後の快適さを決める大きな要素です。
最近ではPCIe Gen.4の2TB SSDを標準搭載したモデルがこなれた価格で出ており、その存在が大きな安心材料になっています。
インストール先をいちいち悩まない、というただそれだけのことが、使い勝手に直結します。
正直Gen.5に惹かれた時期もありましたが、冷却やコストを考えれば一般用途には過剰性能。
結局はGen.4がベストバランスです。
無理に数字を追いかけず、実用性を大事にする。
これが大人の選び方だと思います。
静音性を左右するCPUクーラーも忘れてはいけません。
冷却性能ばかり注目されがちですが、実際に仕事場で利用していると、耳に残るファン音は集中力を削ぐものです。
私は以前、安価なモデルを選んだことでこの音に悩まされ、深夜の作業に苛立つことがよくありました。
それが冬のセールで静音性に優れた空冷クーラーを積んだモデルに切り替えたところ、作業環境が劇的に改善されたのです。
静けさの中で仕事も遊びもできるのは、想像以上にありがたい変化でした。
静寂の価値。
ケースのデザインについても自分のスタンスが問われます。
透明ガラス仕様のケースを選ぶと、内部の美しい配線やライトアップを楽しめて、所有欲をしっかりと満たしてくれます。
ただ一方で、冷却を第一に考えるならば空気の循環を意識した設計を選ぶべきです。
昨年の私はデザイン優先で購入したものの、結果として冷却不足に少々頭を抱える場面がありました。
要は、自分が所有感を重視するのか、快適性を求めるのかを先に決めておくこと。
それが購入後の満足度を大きく左右します。
満足か後悔か。
ちなみに、実際に私が昨年購入したのは、Core Ultra7 265KとRTX5060Ti、32GBメモリ、2TB Gen.4 SSDの組み合わせでした。
20万円前後と少々高いと感じましたが、使い始めてすぐに「これは正解だった」と納得しました。
複数のアプリケーションを並行して動かしても引っかかることなく、夜には最新ゲームを快適に遊べる。
そんな切り替えのスムーズさに、毎回のように満足感を味わっています。
掘り出し物を引き当てた気分でしたね。
結局どの構成が正解なのか、と悩む人も多いでしょう。
私の考える理想は、Core Ultra7 265Kを中核に据え、GPUはRTX5070Ti以上、メモリは32GB以上、ストレージは2TB Gen.4 SSDを最低ラインにすることです。
そのうえで冷却性能やケースデザインといった要素を、自分の好みや利用環境に合わせてカスタマイズする。
これなら後悔しにくく、長い期間にわたって安心して使える構成になります。
結局のところ大事なのは、仕事と遊びの両方を快適に過ごせる環境。
そのために今年の冬のセールは、私にとってもまた大きなチャンスになるはずです。
Core Ultra7 265K ゲーミングPC購入を検討する人のよくある疑問


RTX5070は本当に必要?それとも別の選択肢で十分?
私の率直な意見を伝えると、フルHDでの利用なら間違いなくオーバースペックです。
一方でWQHDや4K、それに高リフレッシュレート環境を本気で求めるなら、5070は文句なしに頼れる存在になります。
その余裕感と安心感をどう受け止めるかで答えは変わるのです。
私は実際に5070を長く使ってみました。
最初にフルHDタイトルを試したとき「いや、さすがに余ってるな…」と苦笑した記憶があります。
確かに過剰性能に思える瞬間でした。
正直、背筋がゾクっとしましたね。
「これが本気のグラフィックカードか」と身体が覚えるような体験で、その差を痛感しました。
ただ、冷静に考えるとRTX5060Tiでも十分に満足できる状況は多いです。
フルHDだけでなくWQHDもそれなりに快適に動かしてくれるし、消費電力と発熱が軽く済むのは大きなメリットです。
私も5070を買ったものの「ちょっとやりすぎたかな」と思ったことがあるほどで、価格差を真剣に考えたら5060Tiに軍配が上がるケースだってあるはずです。
結局は財布との相談になるんです。
でも5070にはやはり目に見えない強みがあります。
新しいアーキテクチャに加え、DLSS4やニューラルシェーダーといった要素は、いずれ来るであろう新作ゲームの未来を保証してくれる。
3年先まで買い替えを予定していない人にとって、その安心材料はすごく大きい。
性能の余裕がそのまま将来の安心感につながるというのは、自分のように長期で使い倒す人間には響くポイントです。
さらにDisplayPort2.1への対応も光ります。
モニターを最新に更新していける人にとっては「どうせなら準備しておきたい」という気持ちに応えてくれる。
以前、せっかくの新モニターが接続非対応でがっかりしたことがあったので、これは切実にありがたい仕様だと思います。
この現実感が大切なんです。
一方で忘れてはならないのが電源やケースの存在です。
5070はそこそこ大きなカードなので、構成を間違うと性能が発揮されません。
昔、私は電源をケチって買った結果、熱でファンが鳴りやまず、休日ごとにストレスを感じたことがあります。
結局買い直す羽目になり「最初から投資しておけばよかった」と後悔しました。
強調して言います、ここに妥協してはダメです。
GPU単体では快適なPCは完成しない。
冷却やエアフロー、配線の整備、この辺をしっかり整えてこそ安定が生まれる。
私も40代になり、若い頃の勢い任せな構成に泣かされた経験をして、ようやく腰を据えて作ることの意味を理解できました。
余裕を作る。
それが大人のPCの組み方だと心底思います。
ライバルとして注目すべきはRadeon RX9070XTです。
FSR4は評判どおりで、DLSS4に劇的に劣ることはありません。
むしろ価格面で納得できるバランスがあり、タイトル次第では「こっちでも十分だろう」とさえ感じました。
ただ発熱やドライバの個性など、クセもある。
でもうまく付き合えば意外に面白い相棒になります。
まさに人間味のあるGPU、そんな印象でした。
では最終的にどうするか。
私が総合して考えた答えはこうです。
WQHD以上で本気の快適さを求めるなら5070で間違いない。
フルHDで留まるなら5060Tiで十分。
そして予算を優先し、自分のスタイルに合った使い方をしたい人にはRadeonも大いにアリ。
要するに「自分がどこまで踏み込むか」の答えをカードに投影するだけなんです。
CPUとの兼ね合いも忘れてはいけません。
Core Ultra7 265Kを活かすなら中途半端なGPUはもったいないし、逆にGPUに振りすぎてもCPUが遊んでしまう。
ここは本当にバランスが大事で「何を優先するか」という一点が後悔を左右します。
私が一番意識しているのは、数字よりも生活スタイルに照らし合わせることです。
5070を選ぶことは確かに魅力的です。
ただし「絶対に必須か」と聞かれれば違います。
フルHD派なら5060Tiで本当に十分。
価格重視ならRadeonも決して悪くない。
その存在感に私も心を揺さぶられました。
無理してでも新体験を追いたいのか、それとも堅実に必要十分を満たしたいのか。
その軸足で自然に答えが見えてきます。
そう考えると単なるパーツ選び以上に、自分自身を映す行為のようにも思えるのです。
楽しいけれど悩ましい。
まさに大人の遊びですね。
まとめるならこうです。
フルHDなら5060Ti、WQHDや4Kなら5070、予算重視ならRadeon。
これが私の最終的な選択肢です。
そしてその背景にあるのは、安心して長く使えることと、自分の現実にピッタリ合うことです。
その二つをどう天秤にかけるか次第で最高の一枚が決まる。
満足感。
最後に言いたいのは、性能表だけを追いかけるのではなく、日常でどんな場面で使うのかをしっかりイメージして選ぶこと。
32GBと64GBのメモリ、実使用だとどちらが現実的か
私はこれまでPCの買い替えやBTOの構成でずいぶん悩まされてきました。
思い返せば、見積もりを何パターンも作っては消し、最終的に「どうせ最適解なんてないんだろうな」と苦笑しながら机の前でため息をついた夜もありました。
その中で今の自分なりに出した結論は、とてもシンプルです。
普段使いがゲーム中心であれば、32GBのメモリがあれば十分だということ。
冷静に振り返るとこれ以上の正解はないとすら思いますし、財布に優しい落としどころでもあります。
最初に32GBを積んで組んだときには、内心「もう当分この容量で困ることはなさそうだ」と胸を張っていました。
実際FPSやMMORPGを長時間レイトレーシングをオンにしたまま動かしても、ほとんど難なくプレイできたからです。
ただ、その裏でブラウザを何十も開いたり、Discordで通話しながらOBSを走らせると、どこか息苦しいようなカツカツ感を覚える瞬間が出てきました。
そのとき「あれ、これって実は心に余裕を失わせてるな」と気づいてしまったんです。
一瞬の小さな引っかかりでも、妙に気持ちがザワッとするんですよね。
こういうところで64GBの意味が出てくるのかと実感しました。
とはいえ64GBとなれば、やっぱりコストが立ちはだかります。
昔より価格は落ち着いてきたとはいえ、まだ気軽に出せる水準とは言い難い。
要は「この余裕代をどう考えるか」なんです。
私はそこが最大の悩みどころになりました。
動画編集や配信をする仲間に率直に聞いてみたのですが、彼らの答えは一様に「64GBは必須」というものでした。
4K動画素材を扱えば読み込みが一気に重くなり、32GBでは引っかかりが増える。
それを減らして編集作業を快適にするには64GBが要るというんです。
なるほどと思わされました。
一方で、単純にゲームを楽しむだけの人にとっては32GBが圧倒的にいい落とし所です。
最近PCを新調した友人たちも口を揃えて「32GBで十分だった」と言っています。
むしろ64GBを選んだ友人は「半分も使ってないよ」とはにかんでいました。
その姿にはちょっとリアルな説得力がありましたね。
要は使い方次第なんです。
もちろん、将来を見据えて考えれば「せっかくだから64GBを選びたい」という気持ちも理解できます。
AAAタイトルの要求スペックは今も急速に膨れ上がっていて、少し設定を上げると簡単にメモリ消費が増えてしまいます。
さらにCPUやGPUの世代交代によって、メモリ回りの足回しがますます重要になっていくことも明らかです。
特にCore Ultra7 265Kのようにメモリコントローラが強化された新世代CPUは、64GBの方がその性能を余すことなく発揮できる感覚がありました。
これを考えれば、将来への投資として64GBを選ぶのも筋が通っているのです。
性能を求める人たちには「数値上の差」以上に「安心できる道具を手に入れた」という心の余裕が大きいのだと思います。
その余裕があるからこそ、趣味や仕事にもっと没頭できる。
だから64GBは単なる数字の問題じゃない。
精神的な支えでもあるんだと、40代になった今なら腑に落ちます。
じゃあどう選ぶか。
普段のPCの用途がゲーム中心なら、私は32GBを迷わず勧めます。
そして配信や動画編集がメインで「とにかく妥協したくない」と思うのなら64GBを目指した方が満足できるでしょう。
さらに余裕がある人は64GBを先行して選んでも損にはなりません。
でも、多くの人にとっては「他のパーツを我慢してまでまず64GBにするべきか」と問われたら、その答えはまだ否だと思います。
GPUを最新のものにすれば、現行タイトルは32GBでも滑らかに動きます。
なのにメモリにだけ無理して投資して、その結果GPUを落としてしまうのは本末転倒だと言わざるを得ません。
だから私は声を大にして言います。
今の主流、特にCore Ultra7 265Kを積んだゲーミングPCを前提にするなら、ほとんどの人にとって最も現実的なのは32GBです。
これが一番バランスが取れた選択肢。
ただし人によって大事にしたいものは違います。
性能という数値だけでなく、買うことで得られる「心の安心感」に価値を見いだすこともある。
40代の私にとっては、その心持ちがとても大切に思えるのです。
自分が気持ちよく使えるか、後悔しないか。
そう考えて最終的な選択をすること。
これこそPCのパーツ選びで一番大事なことだと、今の私はしみじみ実感しています。
265K搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EJ


| 【ZEFT Z55EJ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WQ


| 【ZEFT Z55WQ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54MH


| 【ZEFT Z54MH スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54MZ


| 【ZEFT Z54MZ スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-u7-6160K/S9


| 【SR-u7-6160K/S9 スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
PCIe Gen.5 SSDは今すぐ導入すべき?後回しでも大丈夫?
PCIe Gen.5対応SSDを導入するかどうかについて、私の率直な考えを伝えるなら「今すぐ必須ではないけれど、数年先を見越して準備しておく価値は十分にある」ということです。
現段階では、正直なところゲーミング用途に限っていえばGen.4 SSDでもまだ十分快適に遊べますし、ゲームそのもののロード時間に関しては劇的な差を体感できるわけではありません。
ただ、将来的にはGen.5が前提となるようなソフトやゲームが少しずつ増えていく可能性を考えると、タイミングをどう計るかが投資における大きな分かれ道だと思います。
転送速度の数字を見れば、Gen.5 SSDは14,000MB/s超えという途方もない数値を叩き出すわけですが、数字を見た瞬間は確かに「すごいな」とうなる半面、実際の体感差はそこまでではないのが現実です。
私自身ゲームをインストールしたり大きなファイルをコピーしたときに「速いな」と思った瞬間はありましたが、肝心のプレイ中の快適さはグラフィックカードを1世代上げたときのような感動には遠く及びません。
つまり、性能が桁違いでも恩恵はかなり限定的なんですよね。
それ以上に厄介なのは発熱です。
小さな部品のくせに放つ熱は相当なものです。
私は冷却が不十分なケースで試したら、転送速度が見る見るうちに落ちていき「あれ、こんなはずじゃ」と青ざめたことさえあります。
まさにスロットリング。
慌ててヒートシンク付きのものに交換したら安定しましたが、その一件で学んだのは「性能を引き出す条件整備の大切さ」でした。
冷却環境を甘く見ると後悔しますよ。
価格の問題も大きいです。
Gen.4 SSDの倍近い価格差、これは正直財布に重くのしかかります。
私はコストにシビアな性格なので、2TBクラスでこの差を見ると「まだ待つべきだな」と素直に思ってしまいます。
理想を言えば最新環境を整えたい気持ちはあるのですが、現実とのすり合わせがどうしても必要になります。
こういう判断は、趣味であっても冷静でいたいんです。
ただ未来を見通すと、Gen.5の存在意義は一段と確かになります。
たとえば最新のCore Ultra7 265Kなど、CPU側がすでにGen.5を生かす準備を整えつつあります。
その時、対応しているかどうかで性能の天井が変わると思うと、見過ごすわけにはいきません。
実際に私は、最近遊んだオンラインRPGでGen.4とGen.5を比較したことがあります。
「正直そこまで?」と思う部分もありましたが、時間にして数秒の短縮が積み重なれば長時間のプレイでは大きなストレス差につながります。
わずかな変化でも、未来を垣間見たような手応えを感じました。
分かりやすい比較で言うなら、今一番投資してリターンが大きいのはグラフィックボードです。
次にメモリ。
ここを強化すれば誰でも体感的にゲームが快適になるのは間違いありません。
SSDはあくまで「将来の準備枠」という位置づけで考えるのが無難です。
例えばマザーボードだけGen.5対応を選んでおき、当面はコスパに優れたGen.4 SSDを使い続ける。
そして、いよいよ必要になったときにGen.5を追加すれば十分戦えます。
ゲーム用PCにおけるGen.5 SSDの立ち位置は、必須ではないけれど安心の資産。
冷却と予算に余裕があれば導入して損はないけれど、大半のゲーマーにとっては「まだ先でいい」という選択が合理的です。
基盤だけ用意しておくことで未来の選択肢がぐっと広がりますし、その安心感こそが実は一番の価値なのではないかと思います。
備えあれば憂いなし。
この言葉がしっくりきます。
要するにPCIe Gen.5 SSDを今あわてて導入する必要はありません。
ただし、視野を五年先に広げれば、整えておいた基盤が思わぬ形で役立つ可能性は高いです。
その時になって「やっぱり準備しておけば良かった」と思うのは避けたいですから、私は少なくとも土台部分にはお金をかけるつもりです。
現実を直視しつつ、未来を信じる。
趣味だからこそ、合理と情熱の両方を重ねたいのです。
CPUクーラーは空冷と水冷、どちらを選んだ方が快適?
ゲーミングPCを組むときに一番頭を悩ませるのは、意外にもCPUクーラーの選択です。
CPUやGPUに比べれば後回しにされがちなパーツですが、ここで何を選ぶかで「快適」か「不満足」かの分かれ道になる。
私自身いくつものクーラーを使ってきましたが、最終的に行き着いた答えは、安定して長く使いたいなら空冷、性能を限界まで引き出すなら水冷、つまりその二択に尽きるということです。
空冷クーラーの一番の良さは構造がシンプルなことです。
ヒートシンクとファンだけという単純な仕組みながら、年々改良され静音性も力強さも進化しています。
かつて大型空冷といえば「掃除機みたいにうるさい」と感じた時期もありましたが、最近のNoctuaやDEEPCOOLあたりの上位モデルは拍子抜けするほど静かで、夜中の作業でも気にならないレベルです。
実際にCore Ultra7 265Kを標準クロックで回す程度なら、大型空冷があれば十分で、発熱に悩まされる場面はほとんどありません。
私は初めて導入したとき「これでもう大丈夫だ」と胸をなで下ろしました。
安心感って本当に大事ですからね。
一方で水冷には、確かに心を揺さぶる魅力があるのです。
冷却性能は圧倒的で、ケース内のエアフロー設計にさほど神経質にならなくても温度をぐっと下げてくれる。
例えばCorsairやNZXTの240mm以上の簡易水冷を導入すれば、4Kゲーミングを長時間続けても、あるいはAI処理のようにCPUに高負荷をかけ続けても、温度の上昇は最小限。
それでいて動作音も抑えられているのだから、初めて体験したときは「これはすごい」と素直に感動しました。
そしてケース内に収めたラジエーターとRGBの組み合わせを眺める時間もまた、静かな高揚感をくれる。
性能とデザインの融合。
やっぱりこういう瞬間に胸が高鳴るんです。
ただし、水冷を使い続けていると現実的な課題に出会うこともあります。
最初の数か月は最高の気分でしたが、ある日突然ポンプが故障。
深夜にPCが強制シャットダウンし、翌日の朝一のプレゼン資料が飛んでしまったあの時の絶望感は今でも忘れられません。
正直、背筋が凍りました。
「壊れるときは本当に最悪のタイミングで来るんだな」と痛感した瞬間です。
それ以来、メインでは空冷を使い、趣味機や遊び用で水冷を試すスタイルに切り替えています。
あの苦い経験があったからこそ今のスタンスがある。
経験が選択を変えるんです。
ただ長く安定して使えるか、トラブル時のリスクをどう考えるかまで突き詰めて考えると、最終的に私は空冷に軍配を上げたのです。
定格運用でも静音性が高く、パーツの寿命も延びる傾向があり、コスト的にもバランスが良い。
一方で、常に高負荷をかけながら限界を攻めていきたいという人にとっては、水冷こそ最高の相棒になるでしょう。
攻める覚悟を持つ人には、その冷却力が心強い武器になるんです。
これを理由に選ぶ人も少なくありません。
休日にサブ機を立ち上げ、ガラス越しにRGBが光る様子を眺める時間は、私にとってちょっとした癒やしです。
ですが「ケースは普段ほとんど見ないから」と割り切っている人には、空冷の方が合理的な投資になります。
私自身ももし「今すぐ選べ」と問われたら、迷わず空冷を選びます。
そのくらい安定性への信頼感がしみついています。
もちろんPC環境は人それぞれです。
仕事で高負荷な処理を担うのか、静音重視なのか、それともデザイン性を求めるのか。
条件次第でどちらがベストかは分かれます。
私の場合は「止まったら困る」というビジネス的なニーズを優先せざるを得ないので空冷派に落ち着きましたが、サブ機で水冷を動かしていると「これが本当の贅沢だ」と思ってしまうこともあります。
両方の魅力を知っているからこその楽しみ。
冷却とはPCの土台を形づくるものだと、私は強く思っています。
普段の用途、使う時間、そして置かれる環境。
それでも私がはっきりと伝えたいのは、普段の作業や長時間のゲームを安定してこなしたいなら空冷を選ぶという道。
そして挑戦や限界突破、見た目の楽しさを優先するなら水冷を選ぶという選択。
この二つのどちらに気持ちを預けるかで、自分にとって最良のCPUクーラーが決まると私は実感しています。
ケース選びで性能や使い勝手にどれほど差が出るか
ゲーミングPCを組むとき、多くの人がCPUやGPUに意識を集中させがちですが、実のところ私が何より大切だと考えているのはケースの選び方です。
なぜなら、どんなに高性能なパーツを揃えてもケースの冷却や作業性が不十分だと性能を引き出しきれず、結果的に快適さを損なってしまうからです。
これは机上の理屈ではなく、私自身が痛感した現実です。
過去に安易な選択でケースを決めてしまい、ひどく後悔した経験があります。
これが結論なのだと胸を張って言えます。
数年前、Core Ultra7 265Kを導入したときのことです。
私は当時、見た目重視で選んだ格安ケースに夢中になり、冷却性能の確認を怠ってしまいました。
その結果、ゲーム中は常にファンが全力回転を続ける状況になり、轟音が部屋に響く。
ブオーッという連続音に、正直イライラが押さえられなくなりました。
まさに大失敗。
最近のケースはデザインも進化し、側面や前面が強化ガラス仕様になったモデルが人気です。
ただ見映えが良いというだけではなく、内部のレイアウトに余裕があり、配線の作業性や空気の流れが格段に改善されているのです。
ケーブルがごちゃつくとエアフローも悪化しますから、ケース選びでその成否が左右されるのだと強く感じます。
GPUが年々大型化し、RTX5070TiやRX9070XTといったカードは驚くほどのサイズになっています。
だからこそ、収まるかどうかではなく、しっかり冷やせるか、快適に設置できるか、それを事前に確認しておく必要があるのです。
買ってから「入らない」なんて、本気で青ざめましたよ。
さらに、忘れてはいけないのがストレージです。
Gen.5 SSDは性能が飛躍的に向上しましたが、その分しっかり冷やさなければ熱で性能が落ち込むリスクが付きまといます。
マザーボードのヒートシンクだけで安心していては危ないのです。
ケースのエアフローが整っていなければ、SSDも高温になりやすく、不具合につながる可能性が高まります。
要するにケースはただの箱ではなく、PC全体の土台であり、冷却機構を機能させるための装置そのもの。
軽視できるはずがありません。
実際「ケースでそこまで変わるのか?」と疑問を持つ方もいるでしょう。
はっきり言います、変わります。
温度はケースによって最大10度前後の差が出る場合もあり、静音性においても騒音レベルが大きく変化します。
夜中に書斎で作業したときのことを今でも思い出しますが、安物ケースのファン音が高回転で鳴り続け、集中が途切れるどころか眠気まで吹き飛んでしまったのです。
忌々しい記憶です。
そんな中で印象的だった出来事が、Lian Liのケースを試したときです。
強化ガラスパネルのモデルで、デザイン性に目を引かれたこともありますが、内部構造の完成度に感嘆しました。
エアフローがしっかり考え抜かれており、同じCPUとGPUでも明確に温度が下がったのです。
冷却性能が良いというだけで、ゲーム中のメンタルの余裕がまるで変わる。
恐ろしく快適でした。
あれほどの違いがあるとは予想以上だったのです。
安心感が全然違いました。
それだけではありません。
操作性やメンテナンス性においても差は歴然です。
以前は安価なケースに無理やりパーツを取り付け、ケーブルを取り回すたびに角ばった鋼板に指をぶつけ、切り傷を負うこともありました。
当時は腹立たしく仕方なかったのですが、今では良い学びだったと言うしかありません。
快適に扱えるケースとは、こうもストレスを軽減してくれるのかと目から鱗が落ちました。
以前のゲーミングPCといえば、とにかく派手なRGBライティングで光らせる印象が強かったものです。
しかし今は違います。
木目のパネルを取り入れたモデルや、まるで家具のように部屋に馴染むケースに心を惹かれるようになりました。
リビングや書斎になじむ雰囲気を持つケースは居心地を良くしてくれるので、長時間の作業でも気持ちが落ち着きます。
そう、派手さよりも生活空間に自然に馴染むこと。
大人の選択だと思っています。
率直に言ってしまうと、Core Ultra7 265KのようなハイエンドCPUを長く快適に使いたいなら、ケース選びを第一に考えるべきです。
冷却性能、作業性、そしてデザイン。
すべてが合わさって本当の意味での快適さが実現します。
安さや見た目だけに釣られ、妥協してはならない。
ケースはPCの安定性を大きく左右する、決め手となるパーツです。
私は失敗を重ねてやっと理解できました。
本当に痛い思いをしたからこそ、これからPCを組む方には強く伝えたい。
最後に残るのは自分の満足感と、日常に寄り添える一台かどうかです。
選択を誤れば、後悔が長く続きます。
だからこそ私は声を大にして言います。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |