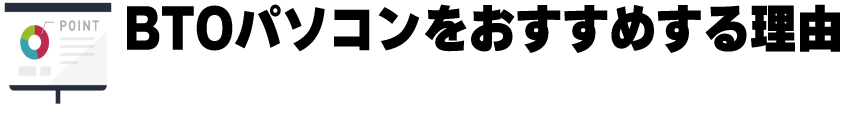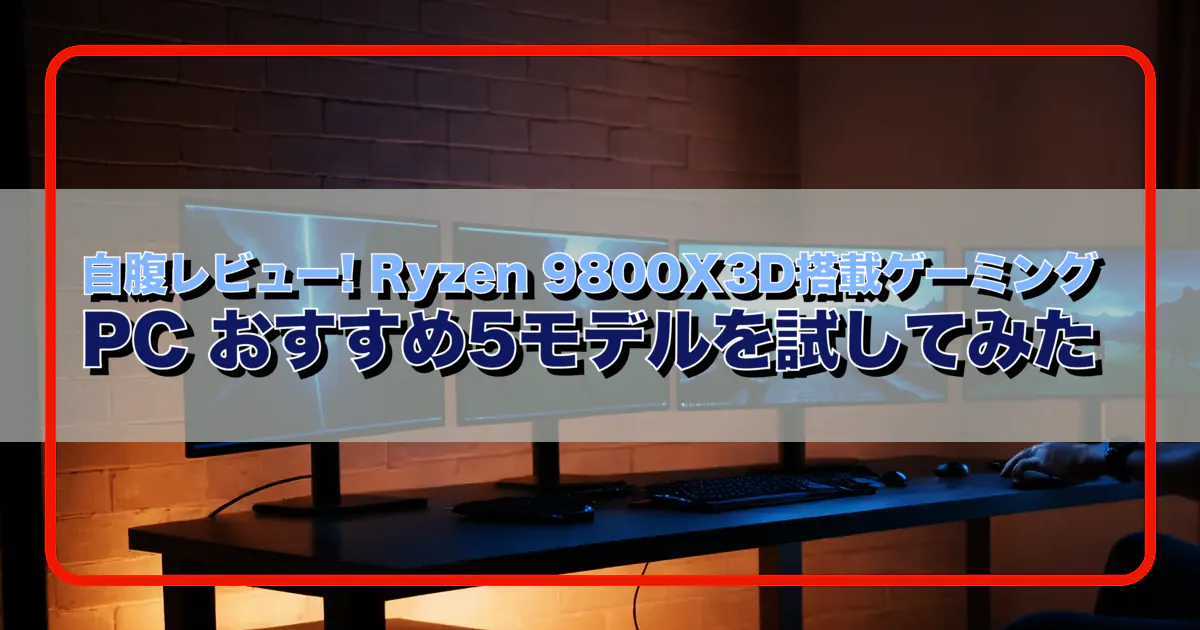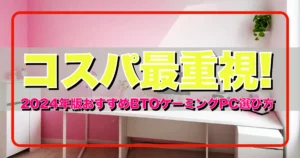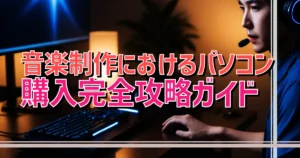Ryzen 9800X3Dでフレームレートは実際どこまで上がるのか検証してみた

RTX50シリーズGPU×Ryzen9800X3Dの実際の相性をチェック
Ryzen 9800X3DとRTX50シリーズを使った構成をあらためて振り返ると、正直に言えばいま手に入る中ではもっとも安心して使える選択肢のひとつだと私は感じました。
どのGPUと組み合わせてもおおむね満足度が高く、少なくとも私は買って後悔することはないと実感しています。
以前は「新しいGPUにCPUが遅れをとるのでは」と懸念していましたが、そうした心配はほとんど必要ありませんでした。
こういう経験をすると、単なるスペック表だけではわからない相性の大切さを身にしみて感じます。
特に手応えを覚えたのは5070Tiや5080と組み合わせたケースでした。
あの途切れのなさは正直気持ちがいいんです。
つい夜更けまで没頭してしまうくらいに。
いや、むしろ年齢を考えて時間を制御しないと危ないですね。
最上位の5090と組み合わせてみると、場面によってはさすがにGPUの力が強く、CPUがほんの一瞬追いつかない印象がありました。
全体的には、これだけのパワーを冷静に受け止める9800X3Dに驚かされました。
思わず「よくやってくれてるな」と、小さく声を漏らしてしまったのはここだけの話です。
少し意外だったのは5060Tiとの組み合わせでした。
GPUとCPUが互いに補い合って、肩を並べて走っているような印象を強く受けたのです。
一方で、クリエイティブ用途で試してみると様子は少し変わります。
多コアモデルである9950X3Dなどと比べれば差を感じた部分もありますし、万能ではないという事実も確認できました。
ですが、この9800X3Dは元々「ゲームで真価を発揮するCPU」としての位置づけが明確なので、そこを理解して選べば失望することはありません。
自分の使い方次第。
その割り切りは必要です。
数週間の使用を通じて確信したのは、「どのランクのRTX50シリーズを組み合わせても損はしない」ということでした。
ハイエンドモデルなら余裕ある映像表現を堪能でき、ミドルレンジでも滑らかさを犠牲にすることなく十分楽しめる。
つまり、ユーザーの好みや予算に応じて幅広く選び、どれを選んだとしても満足度が高い。
そういう懐の深さを感じました。
少し話がそれますが、私は最近、自動運転車に関するニュース記事を読んで思い出したことがあります。
ソフトとハードの連携がぎこちなく、利用者が不安を覚えたという話でした。
これはPCの世界でも同じです。
CPUとGPUがきちんと呼吸を合わせないと、システム全体が不安定になり、ユーザーはストレスを感じてしまう。
だからこそ、この9800X3DとRTX50シリーズの親和性は価値があるんです。
ふたつがまるで長年の同僚のように呼吸を合わせ、信頼して動いている。
私はそこに心強さを覚えました。
また、DLSS 4とReflex 2の組み合わせが生み出す体験も印象的でした。
従来世代では不可避だった微妙な遅延や引っかかりが感じられなくなり、240Hzや360Hzといった高速モニター環境でも快適そのもの。
あまりに自然で、自分が入力した動作に映像が即座に応じるため、まるでゲームの中に吸い込まれていくようで不思議な感覚でした。
では結局どのGPU構成が最適なのかというと、私個人の手応えでは5070Tiか5080がもっともバランスが良いと思います。
性能と価格の釣り合いがちょうどよく、無理せず長く付き合える安心感があります。
5090は間違いなくハイパフォーマンスですが、正直そこまで欲張らなくても十分ではないかと感じました。
逆にコストを重視すれば5060Tiでも満足度は高く、「価格のわりにすごく頑張るな」としみじみ思いました。
結局は使う場面や目的次第。
これに尽きます。
私は今回の検証を通じて、9800X3DとRTX50シリーズは「今季を代表する安定した組み合わせ」だと胸を張って言えます。
ゲームをする際に私が本当に欲しいのは、派手な理論値よりも不安なく没頭できる環境でした。
安定感。
これが何よりも大切なんです。
この構成はその期待をきっちり満たしてくれました。
そして、これこそ実際に触れてきた私の素直な言葉です。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49113 | 100929 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32430 | 77302 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30414 | 66101 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27399 | 68249 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26736 | 59644 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22140 | 56240 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16704 | 38983 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16133 | 37823 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15994 | 37602 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14766 | 34575 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13862 | 30555 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13317 | 32041 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
WQHDと4K、それぞれの解像度で安定感はどう変わる?
これは単純な性能表の数字やレビューサイトの比較では見えてこない、実際に触れて初めてわかる実感でした。
私自身、最初は単なる好奇心で切り替えて遊んでいたのですが、ある瞬間に「なるほど、これは性格がまるで違う」と気づかされたのです。
WQHD環境でプレイしたときに真っ先に気づいたのは、やはり軽快さでした。
特にFPSのように反射神経が求められるゲームでは、200fps前後を安定して叩き出してくれることが多く、その滑らかさは正直感動ものでした。
一瞬の違いで勝敗が決まる場面になると、この安定感が精神的な支えになるのです。
画面の隅で敵影を捉えた瞬間にピタッと滑らかに追従してくれる映像を見て、思わず「うん、これだよ」と声に出していました。
まるで若い頃に買った新しいスポーツシューズを履いた時の軽快さを思い出すような感覚でしたね。
一方で4K環境に踏み込んでみると、今度は全く別の世界が広がります。
その映像美に圧倒される瞬間が何度もありました。
建物の壁に刻まれた細かな傷や、遠くに流れる川のきらめきがあまりにリアルで、ついついプレイを忘れて見入ってしまうのです。
特にRPGをしているときに感じた没入感は格別で、「ああ、この世界で本当に旅をしているんだ」と思わせてくれました。
解像度が高い分GPUへの負荷は確かに増すのですが、Ryzen 9800X3Dのキャッシュ構造が効いているのか数字以上に安定していて、驚くほどカクつきが少ない。
だからこそ、安心して物語を楽しめました。
印象的だったのは、4Kで長時間遊んでいると数字上のフレームレートこそ少し落ちてくる時があるのですが、不思議と遊んでいて不快さを感じにくいという点です。
画面の流れが途切れないため、自然とプレイに集中できる。
映像体験としての充実感がものすごく大きくて、これは数値だけを眺めても絶対にわからない感覚だと実感しました。
競技志向で結果を求めるなら迷わずWQHDです。
勝負の場ではほんの数フレームの差が生死を分けることもあります。
その安定性を武器にすれば、自信を持って挑めるのです。
一方で、映画館でストーリーをゆったり味わうように遊びたいなら、4Kが断然向いています。
映像自体が体験そのものを引き上げてくれるのです。
実際に私はRPGの静かなシーンを4Kで眺めながら、思わず「これは贅沢だ」とため息をつきました。
WQHDは競技用シューズのようなもの。
軽くて速く、無駄なく目的を果たしてくれる存在です。
映像の豊かさを最大限に体に染み込ませてくれる贅沢な環境です。
レーシングシミュレーターを両方で体験したとき、WQHDでは細やかなレスポンスが心地よく、逆に4Kではエンジンの熱気やスピードを全身で浴びるような興奮を味わえました。
どちらを選んでも極端に劣るということは全くなく、方向性が違うだけなんだと強く思いました。
そのうえで、Ryzen 9800X3Dには特有の良さがまだあります。
静かさです。
長時間のゲームでもファンがうるさくならないのは大きな安心感でした。
正直、若い頃は気にならなかったファンの轟音も、40代に入った今では集中力を削ぐひとつの要因になります。
だから、この落ち着きは本当に助かります。
数字では表せない快適さ。
もちろん、完全に欠点がないわけではありません。
4Kの最新ゲームでごく稀にフレームが一瞬落ち込むことがあり、そこのもどかしさは否めませんでした。
GPUやドライバ側の最適化の問題でしょうが、「この実力ならもう一段階伸びるはずなのに」と惜しさを感じました。
しかし、それを差し引いても全体的な完成度は非常に高く、むしろ他の選択肢との差を見せつけていると感じます。
最終的にどう選ぶか。
これは本当にシンプルです。
反応速度を第一に求めるならWQHD。
映像体験の豊かさを求めるなら4K。
私は胸を張ってそう言えますし、どちらを選んでもRyzen 9800X3Dなら期待以上の快適さを提供してくれると断言できます。
安心感。
そう思える機材に出会えることは、決して当たり前ではないと思います。
そして私はあらためて感じました。
性能比較のグラフや数値では語りつくせない「実際に触れてこそわかる良さ」が存在するのだと。
結局のところ、このCPUにはそうした実感を伴う強さがあるのです。
信頼性。
私は心からそう思いました。
CPU性能が効きやすいゲームジャンルを実体験から深掘り
フレームレートはGPUだけの問題ではなく、CPUが想像以上に大きく関わっているのだと、私は実際の使用感から強く感じています。
自宅の環境を更新し、Ryzen 9800X3Dを導入して数カ月、ジャンルごとにCPU性能の影響がはっきりと表れる場面に何度も遭遇しました。
机上のスペック表だけを見ている時には気づかなかった事実が、実際にゲームの中で自分の目と感覚を通じて確かめられたのです。
特にシミュレーションゲームでは、CPUの力が鮮明に表れます。
都市を作るゲームや戦略シムのように、終盤になると数えきれないユニットが同時に動き出す状況では、以前の環境だとどうしても処理落ちが避けられませんでした。
ユニットが勝手に考え、動き、反応する――そんな膨大な演算が積み上がる瞬間に、CPUの力量が問われるのだと身をもって体感しました。
しかし9800X3Dに切り替えてからは、何百というユニットが画面内で入り乱れても大崩れしない。
ぎくしゃくせずに遊び続けられる。
これは実際にプレイして体で確かめなければ得られない安心です。
FPSはさらにシビアです。
ほんのわずかな差が勝敗を決める世界では、1フレームの遅れさえ許されません。
50人規模のバトルロイヤルの最中、過去の環境では撃ち合いで負ける原因が「明らかに機械的な処理落ち」だったこともありました。
自分の腕が悪いわけではないのに理不尽にやられる、それが苛立ちや空しさを生み出すのです。
「今の瞬間は守られている」と信じられる。
これは大げさではなく、プレイヤーの心を支える根拠になります。
安堵した瞬間でした。
MMORPGになるとさらに顕著になります。
広大なフィールドに数百人のプレイヤーやNPCが同時に存在する大規模戦闘では、GPUの描画性能よりもCPUのマルチスレッド処理力がカギを握ります。
群衆戦での滑らかさは、9800X3Dへ移行した途端に明確に変わりました。
あの昔ながらの「カクカク感」が消え去り、風景も戦闘もなめらかに流れていく。
かつて抱いていた不満が一気に払拭され、「ああ、やっぱりそういうことか」と思わず声が出ました。
心の底から納得できる体験でした。
レースゲームでも油断できません。
一見するとGPUが全てを握っているように思えますが、スタート直後に20台以上が密集して争うシーンではCPUに大きな負荷が掛かります。
旧環境ではそこで処理がもたつき、肝心の一瞬でブレーキやアクセル操作が遅れることがありました。
ところが9800X3Dなら違います。
車同士の接触やAIの挙動が重なっても処理に余裕があり、気持ちよく加速できる。
走りながら思わず「これは別物だ」と声に出ました。
爽快感が段違いでした。
最新のRTX 5070TiやRadeon RX 9070XTのような強力なGPUも、CPUが足を引っ張れば性能を引き出せません。
私は仕事帰りの短い時間に集中して遊ぶため、ほんの少しのカクつきやラグが気持ちを冷めさせる。
だからこそ妥協せずに構成を考える必要があると痛感しました。
その積み重ねが満足度を大きく変えるのです。
シングルプレイRPGやアクションアドベンチャーでは、基本的にGPU性能が中心となります。
しかし高解像度や高リフレッシュレートを追求すれば別の話です。
CPUの余裕がそこでも効いてきます。
9800X3Dを過信するつもりはありませんでしたが、実際に遊んでみれば「やっぱり快適さが全然違う」と認めざるを得ません。
小さな違いがやがて大きな満足へつながるのだと改めて学びました。
身にしみました。
私が驚いたのは、ジャンルごとにここまで鮮明な差が表れるという事実です。
これからのゲーム開発ではAIの活用がより一層進むはずです。
そのとき負担を担うのはGPUではなくCPU。
GPUの派手な進化に目が奪われがちですが、実際にプレイ感覚を決めているのはCPUかもしれない。
私は再確認しました。
どう選ぶべきかという点において、私は自分なりの答えを持っています。
もしCPUの働きが顕著に出るゲームを一つでも遊ぶつもりがあるなら、9800X3Dを選んで損はありません。
もちろんすべてのゲームで圧倒的な効果を保証できるわけではありません。
しかしシミュレーション、FPS、MMORPG、レース――この4ジャンルでは間違いなく優位性があります。
そのうえでGPUや高速メモリを組み合わせれば、ゲーム体験は一段階も二段階も高みに届くのです。
遊び終わった瞬間に「ああ、買ってよかった」と心から言える体験。
それこそが9800X3Dの価値です。
妥協はできないな。
その気持ちが、私の選択を後押ししてくれています。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43437 | 2442 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43188 | 2247 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42211 | 2238 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38943 | 2058 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38866 | 2030 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35977 | 2177 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33203 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32721 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29522 | 2021 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 2155 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23298 | 2192 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23286 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 21046 | 1842 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19684 | 1919 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17893 | 1799 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15428 | 1963 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9800X3D 搭載ゲーミングPCを選ぶときに押さえておきたいポイント
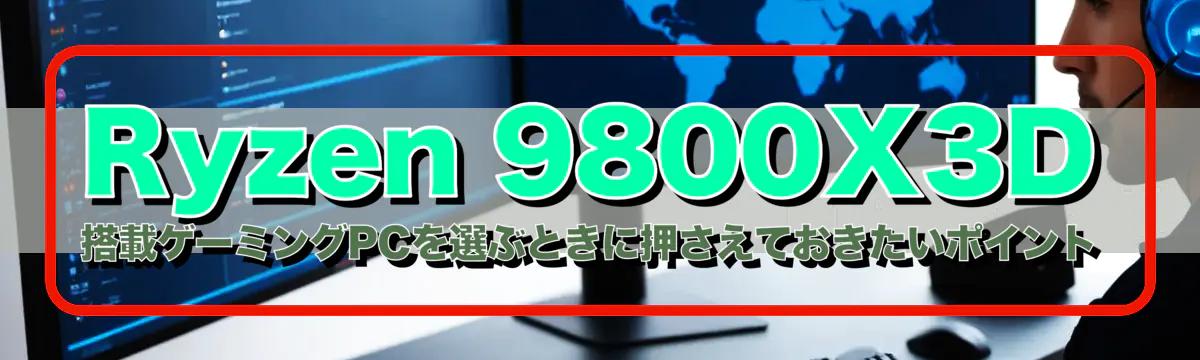
ストレージは1TB派?2TB派?実際に使って感じた違い
Ryzen 9800X3Dを搭載したゲーミングPCを本格的に使い始めて気づいたのは、「ストレージの容量が快適さを根本から左右する」ということでした。
私は最初、1TBで十分だろうと高を括っていたのですが、実際に運用してみると全然余裕がなかったのです。
特に最近のゲームは容量が膨大で、1本で100GBを軽く超えるタイトルも珍しくありません。
そこに追加コンテンツや大型アップデート、さらにMODまで加われば、あっという間に残り容量が赤信号。
私はそのたびに、泣く泣く過去に遊んだタイトルを削除する羽目になりました。
1TBでは明らかに足りない、と。
1TB環境で過ごしていた頃の私は、SteamやEpicでゲームを数本入れるだけで残り容量が目に見えて減っていき、そのたびに圧迫感を覚えました。
遊びたいときに遊べない。
タイトルを消すかどうか悩んで時間ばかりが過ぎる。
私は「また整理か…」と小さくつぶやき、正直うんざりしました。
遊ぶより整理の方が作業っぽくなる。
そんな状態に嫌気が差していたのです。
ところが2TBに切り替えた瞬間、その息苦しさが一気になくなりました。
容量を気にせずに新作を次から次へとインストールできる解放感。
これは想像以上に精神的な余裕を生んでくれました。
私の場合はゲームだけでなく動画編集やビジネス用のプロジェクトファイル、時には数十GB単位の画像素材まで扱うのですが、それらを一台に一元化できたことで、仕事と趣味がスムーズに切り替えられるようになりました。
気づけば余分な手間が減り、毎日の効率が確実に底上げされていたのです。
まさに実感。
Gen.5はカタログ上では確かに速い。
しかし価格が跳ね上がるうえに発熱管理が難しく、ちょっと気を使う必要があります。
それに比べてGen.4は安定性が高く、コストパフォーマンスも優秀。
私が導入したWD製2TB Gen.4 SSDは、半年以上使ってもトラブルらしいトラブルが一切なく、熱暴走の心配もありませんでした。
性能をフルに発揮しつつも扱いやすい。
この安心感が選んで正解だったと私に確信させました。
では1TBでも良い人はいるのか、というと、それはライトユーザーでインストールするタイトルが限定的な人に限られるでしょう。
気分によって遊びたいゲームを選ぶ自由がない。
2TBであれば、それを叶えられるのです。
容量があるということは、遊び方に余裕があるということなんですよね。
CPUやGPUで少し妥協しても、ストレージは2TBを選んでおく方がいい。
性能の高いGPUを積んでいたとしても、容量不足でいちいち古いゲームを削除し、再インストールを強いられるようでは快適さが半減します。
余計なストレスを減らし、本当に楽しむ余裕を作ること。
それが長く使うPCでは大切だと思います。
Ryzen 9800X3Dという強力なCPUを使うのであれば、その力を余さず引き出せる環境を整えるのが当然です。
そしてその条件を満たすのが2TBストレージ。
単に大きな数字というだけではなく、ゲームや作業に「制約がない」という自由を与えてくれる存在です。
実際、私はある週末に大型タイトルを三本同時にダウンロードしたのですが、その際、1TBならば「まず古いゲームを削除するところから…」という面倒なプロセスが始まっていたはずです。
しかし2TB環境では、ボタンを迷いなくクリックするだけ。
これほどストレスフリーな行為はありませんでした。
ストレージ容量がもたらすのは単純な数字だけではないのです。
安心して選べる余裕。
心地よく遊べる環境。
これこそが2TBの本当の価値です。
私は半年使ってみて、そのことを骨身にしみて理解しました。
当初は「ゲームのために少し奮発しただけ」くらいの感覚だったのですが、実際にはビジネスや趣味の効率化も含めて、毎日に直結する投資であったと今では思います。
確かに4TBという選択肢も存在します。
しかし価格とバランスを考えると、多くの人にとって現実解は2TBだと断言できます。
4TBは大容量で魅力的ですが、現状ではコストが見合わず過剰投資になりかねません。
安心して遊べるだけの余裕を持ちつつ、経済的にも納得できる。
その絶妙な落としどころが2TBなのです。
私は自分の体験から強く言いたいのです。
もしRyzen 9800X3Dを中心にゲーミングPCを組むのなら、迷わず2TBを選びましょう。
これが最も安全で、後悔のない選択肢です。
なぜなら、容量の余裕がもたらす安心は、ゲーム体験だけでなく日常生活や仕事の快適さにまで広がっていくからです。
思いついたときにすぐに遊べる、挑戦したいときにすぐ着手できる、そんな自由さ。
これを手に入れられるのは2TBのストレージだけだと私は信じています。
後悔しない未来。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
DDR5メモリ32GBと64GB、使い勝手と価格感のリアルな差
私も実際、この分岐点に長いこと立ち止まりました。
そして今の時点でお伝えできるのは、シンプルにゲームだけを楽しむだけなら、32GBで十分すぎるほど快適に動くということです。
最新のタイトルを高解像度で走らせながら複数のブラウザを開き、裏で配信用のソフトを走らせても、実際のところ大きな不便は感じませんでした。
この時点で「やっぱり32GBで十分だよな」と納得してしまいそうになります。
素直にそう思ったんです。
ところが、用途が変わると話は一気に別物になります。
私のようにオープンワールドゲームをMODで盛り込み、同時配信もしつつ、さらに裏で動画編集を動かし始めると、32GBでは瞬間的に息切れしてしまう瞬間が出てきます。
そこに仮想環境をいくつか同時に走らせたら、もう限界。
数字以上に、余裕から生まれる落ち着きが違います。
「あ、これはもう格が違うな」と心から思わされました。
問題はやはり価格差。
32GBのDDR5を選ぶのが標準的な構成だとすると、64GBは単純に二倍近く掛かることが多いんですよね。
これは本当に財布に直撃します。
正直、この差に悩まない人はいないでしょう。
とはいえ、32GBから64GBへと拡張する費用はSSDを倍にするのと同レベルで、それなりの負担感は残ります。
ここは重く受け止めざるを得ません。
気楽には決められない。
私が当初32GBを選んだのは予算の都合でした。
しかし半年も経たずに動画編集の案件が増え、Adobe系ソフトをフルで動かす必要が出てきて、結局64GBに買い替える羽目に。
あのときの落差は今でも覚えています。
作業が本当に止まらない。
軽快さと安定感。
あまりに違い過ぎて、思わず「最初から入れておけばよかった…」と声が漏れてしまいました。
一方で、私の知人は全く同じRyzen構成で32GBのまま運用していますが、完全にゲーム専用なので不便は一切ないと言っていました。
数百GB規模のタイトルを遊び続けても、困ったことが一度もないらしいんです。
その言葉を聞いて思いました。
「やっぱり使い方次第だな」と。
最近はBTOショップの宣伝でも64GB推しが目立ちます。
確かに今後AIアプリや生成系のツールを積極的に使う見込みがあるなら、64GBを選ぶのは理にかなっています。
メモリを後から増設すること自体は可能ですが、同じメーカー、同じクロック、同じ容量で揃えないと安定性に不安が残る。
昔の私はそこを甘く見ていて、後になって苦い笑いをすることになりました。
整理すると結論はこうなります。
ゲーム専用なら32GBで問題なし。
しかし同時配信や編集、仮想環境など仕事寄りの用途を重ねるなら64GB。
値段の壁は確かに厚いですが、長期的に安心して使えるという意味では、初めから64GBを導入するだけの意義があります。
逆に使わないなら32GBで済ませ、その分GPUやストレージなど他の部分に回すのが理に適っています。
要は、自分の未来像をどう描くか。
その一点に尽きるのだと思います。
私の実体験を通じて分かったのは、メモリ容量の違いは単なる数字ではなく、仕事や趣味にかける時間そのものを左右する存在だということです。
作業が軽快に回ると心の余裕にも直結し、日々の気分まで変えてしまうんです。
この小さな違いが積み重なって後から大きな差になる。
だからこそ「今の用途」で決めるのではなく、「未来の自分」にとって何が正しいのかを描きながら選ぶべきだと強く言いたいのです。
最後に。
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GH

| 【ZEFT R61GH スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61F

| 【ZEFT R61F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G08F

| 【EFFA G08F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60HT

| 【ZEFT R60HT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CQ

| 【ZEFT R60CQ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | be quiet! SILENT BASE 802 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
空冷か水冷か、普段のプレイで体感できる違いをまとめた
空冷と水冷のどちらを選ぶかという話になりますと、私は「結局は空冷で十分満足できるが、水冷ならさらに心地よい」と思っています。
単純にどちらが優れているかという二択ではなく、ライフスタイルや求める快適さによって答えは変わってくるのです。
最新のRyzen 9800X3Dは確かにパワフルですが、その一方で発熱も無視できませんから、冷却の方法ひとつで体感が変わってくることを実際に身をもって感じています。
私が最初に9800X3Dを組んだときは、大きめの空冷クーラーを使いました。
これが予想以上に安定していて驚きました。
生活音に紛れてしまって、耳をすませばわかる程度でしたね。
そのとき思わず「あれ、空冷で十分じゃないか」と心の中でつぶやいたのを覚えています。
一方で、水冷を試してみるとやはり空気感が変わりました。
温度の波がさらに抑え込まれ、長くゲームを続けても静けさが途切れないのです。
だいたい70度前後で安定してくれて、ケース内の熱も広がりにくく、GPUに熱をかぶせにくい。
特に夏の湿気が重たい夜に遊んでいると、部屋全体が熱気に包まれにくく、プレイだけでなく生活そのものが楽になる。
こういう体感的な違いには「なるほど水冷の強みだな」と思わされました。
とはいえ、70度と80度。
この10度の差が常にフレームレートに直結するわけではありません。
グラフが跳ね上がるような劇的な変化はなく、画面の滑らかさが目に見えて変わることは少ないのです。
正直、数時間にわたって重いタイトルを動かしたときくらいにしか差を意識できない。
結局のところ、冷房の効いた部屋で余暇に遊ぶだけなら空冷で満足してしまうんですよ。
これが現実的な感覚です。
水冷が力を発揮するのは、ハイエンド志向の人です。
例えばRTX5090のようなGPUを組み合わせて、AAAタイトルを最高設定で動かすような環境。
そこで水冷を選べば、GPUの温度が安定しやすくなり、全体のパフォーマンスに余裕が出る。
そういう環境を追い求めるなら「これは水冷一択だな」と思います。
攻めの選択というやつですね。
ですが私は仕事も忙しい身です。
夜や週末に少し遊んでリフレッシュする程度。
そこで大切にしたいのはシンプルさと安心感。
空冷は取り付けが簡単で、稼働パーツも少ないから壊れるリスクが少なく、ポンプの故障や液漏れに怯える必要もない。
電源を落とした瞬間、すべてが止まる気軽さがあるんです。
もうこれ以上の安心はない。
私は空冷のこの手軽さに救われています。
本当に。
もちろん水冷にも憧れはあります。
ファンの音すら邪魔だと感じる人には水冷が適しているのも間違いないのです。
私自身も仕事で疲れ切った夜、静かすぎる環境でゲームに没入できたときの気持ちよさを覚えていて、「ああ、これは贅沢だな」と思いました。
ただ、Ryzen 9800X3D自体の設計が優れていることは忘れてはいけない点だと思います。
冷却方法を変えたところで劇的な性能の差は出ません。
つまり問題は性能云々よりも価値観。
静音性を優先したいのか、それとも設置やメンテナンスの容易さを重視したいのか。
私は何度も使い比べましたが、結論はシンプルで、どちらを選んでも後悔はしない。
そういうことなんです。
多くの人にとって、答えは意外なほど明快です。
空冷で十分。
そして水冷ならさらに快適。
その二択。
それだけなんですよね。
だから必要以上に深刻に悩む必要はない。
自分が日々どんな使い方をしているかを考え、それに合った冷却方式を選ぶだけです。
CPUを冷やすという単純な行為の中に、実は自分の価値観が映し出されています。
静けさを求めるのか、楽さを求めるのか、挑戦を楽しむのか。
私はそのことに気づけたのが一番の収穫かもしれません。
考えすぎずに割り切れ。
少なくとも、私がこの数ヶ月で得た答えはこの一言に尽きます。
実際に使って良かったRyzen 9800X3D搭載ゲーミングPCおすすめ5選
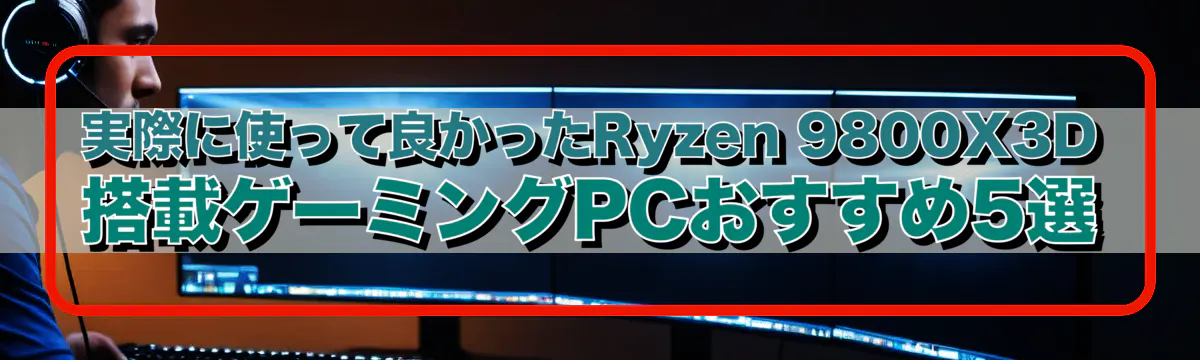
コスパ重視で行くならこれが鉄板モデル
コストを意識しつつも、しっかりした性能を確保できる構成を探しているなら、Ryzen 9800X3Dを軸に組むのがとても良い選択になると私は考えています。
これまで何台ものPCを構成してきましたが、その中でもRTX5060Tiを合わせたモデルは驚くほどバランスが良く、割とシビアに見てきた私でさえ「これは人にすすめられるな」と思える仕上がりでした。
正直なところ最初は、性能を抑えめにした分だけどこか不満が出るに違いないと半信半疑でしたが、実際に触ってみるとその心配はまったく必要ありませんでした。
むしろ、良い意味で裏切られた感覚です。
重量級の作品をWQHDで動かしてみても十分に快適で、不自由を感じる瞬間は思っていた以上に少なかったのです。
数字上の性能をただ追うよりも、本当に満足できるかどうか、そして安心して長く使えるかどうかが大事になってくるのですが、この構成なら間違いなくその条件を満たせると感じました。
だからこそ、やみくもにハイスペックを求めなくてもいいんだと強く思います。
過去に同じ価格帯のPCを使って長時間遊んだときには、微妙な引っかかりに悩まされた経験があるだけに、今回のスムーズさには本当に救われました。
やっぱり安心できる安定感。
最近は1本100GBを超えるタイトルも珍しくなく、1TBではすぐに一杯になってしまいます。
2TBあれば複数の新作ゲームを同時に入れられますし、仕事やプライベートのデータも余裕を持って置いておけます。
転送速度も十分に速くなっており、それでいて価格も以前より手頃になってきたので、満足度は高いですね。
私はよくゲームを遊びながら配信ソフトを立ち上げたり、裏で複数のアプリを動かしたりするのですが、その環境でも全く心配がいりません。
通気性が良く冷却に直結しますし、パーツが映えるのも地味に嬉しいポイントです。
正直、この歳になると見栄や流行よりも実用性を重視するようになるんですよね。
冷却は大型空冷クーラーで十分でした。
実際に高負荷をかけても温度の安定は抜群で、水冷に頼る必要は感じません。
水冷を試したこともありますが、このクラスのPCなら空冷で十分。
メンテナンスが楽なのも、日常的に使う視点からするとありがたいです。
気楽に使えること。
これが一番のメリットですね。
RTX5060Tiは、コストを考えながらもしっかりゲームを楽しみたい人にぴったりです。
特にeスポーツ系のタイトルは高リフレッシュレートで安定して動きますし、重量級の作品も十分にカバーできます。
私はこの構成を選ぶと「無難な安さ狙い」ではなく、「プレイヤー目線で裏切らない選択」をしたんだと感じることができました。
ただし少し余裕を見て長期的に安心したければ、RTX5070を選ぶのも悪くありません。
4Kで全てを快適には難しいものの、DLSSを組み合わせれば十分に戦えます。
私は「どうせ買うなら数年先まで安心したい」と考えるタイプなので、5070にするのも一つの解だと思いました。
やはり、最初にどこまで投資しておくかで後々の気持ちの余裕が決まってきます。
確かに速度は向上していますが、発熱と価格のリスクがまだ気になる状況です。
必要になったらその時に交換すればいい。
そう思うと、今はGen.4で十分という答えに落ち着きました。
割り切れると気持ちが軽くなりますね。
では最適な構成は何か。
私なりの答えは、Ryzen 9800X3DとRTX5060Ti、DDR5-5600の32GBメモリ、2TBのGen.4 SSD、そこに大型空冷クーラーと強化ガラスケース。
この組み合わせなら余計な不安に悩まされず、安心して長く遊べるゲーミングPC生活を送れると胸を張って言えます。
これまで何度も買い替えてきた中で、このモデルは久々に「長く戦える」と思わせてくれるものでした。
最新規格や派手な演出を追いかけるよりも、自分に必要な性能を見極めること。
今回その選び方を意識したことで、納得感のある買い物になりました。
やはり大事なのは冷静な判断。
満足できる買い物でした。
配信も編集もできる、汎用性が高いモデルを紹介
ゲーミングPCと聞くと多くの人は「ゲーム専用」という印象をお持ちかもしれません。
ところが実際に使ってみると、その先入観はあっさり裏切られました。
私はここで断言したいのですが、Ryzen 9800X3Dを搭載したモデルはゲームにとどまらず、配信や動画編集も含めて頼れる存在で、まるで相棒のような安心感を与えてくれるのです。
私自身、この一台に切り替えてからというもの、仕事も趣味も環境が一変しました。
まず一番強く感じたのは、配信と動画編集を同時に進めても動作が不安定にならない点です。
過去にはCPUの性能が追いつかず、エンコード中にゲームがカクつくことが頻繁にありました。
そのたびにイライラし、作業を分けて行うという効率の悪さに悩まされてきたのです。
しかし、このPCでは4K配信を維持しながら裏で録画や編集ソフトを動かしても、重さを感じません。
同時処理での安定感はライバルCPUとの差が歴然で、キャッシュ構造の効果なのか、とにかく処理に余裕があります。
正直、負荷の高い新作タイトルをプレイしながら高画質配信ソフトを回したら落ちるだろうと思っていました。
実際には逆でした。
ゲームは涼しい顔で動き、私は拍子抜けしながら「これはすごい」と唸ったのです。
頼もしさを感じました。
また驚いたのが動画編集の快適さです。
4K素材を幾つも重ねてエフェクトを加えつつ再生しても途切れがありません。
従来のPCではプレビューがガタついて、最終出力を確認するまで不安でした。
でもこのPCはリアルタイムで確認でき、作業効率が大幅に向上しました。
特にPremiereやDaVinciで日常的に作業している人にとって、この違いこそ価値だと痛感しています。
正直、仕事の段取り自体を見直したほどです。
配信を考えると冷却と静音性は無視できません。
私は以前、ファン音がマイクに入り込みリスナーに指摘されたことがありました。
冷や汗ものの体験でしたね。
それ以来、冷却と静音を重視しています。
その点、このモデルは空冷ながらも静音性に配慮していて、配信中でも余計な心配をせずに話すことができました。
機材トラブルに気を取られないだけで、こんなに集中力が変わるのかと実感しました。
ケースのデザインが良いだけで部屋の雰囲気が変わり、気持ちまで前向きになるということを初めて実感したのです。
透明なガラスパネル越しに光る内部を眺めながら仕事をする。
ちょっとした高揚感があるんですよ。
見た目なんて二の次だと思っていた私でしたが、気持ちを整える要素として大切だと今では思います。
さらにストレージ選びで学んだのは、数字だけを追わないことの大事さです。
Gen.5 SSDのスペックには心を動かされました。
けれども、発熱や安定性を考慮してGen.4を選んだ結果、安心感と実用性のバランスが得られました。
私は2TBのGen.4 SSDを積んでいますが、大量の素材を扱っても不安は一度もありません。
発熱でシステムが不安定になる心配もなく、堅実な選択こそが仕事の効率に直結するのだと理解しました。
安定した環境は何よりも大切。
グラフィックボードについても同じ学びがありました。
RTX5060Tiでも十分対応はできるのですが、編集を行う際にGPUアクセラレーションの恩恵を肌で感じるには、もう一歩上が必要です。
そこで思い切ってRTX5070Tiを選んだのですが、ゲームも編集も余裕を持ってこなすことができ、結果的に「少し背伸びして正解だった」と納得しています。
買い物というより投資だったと感じる瞬間でした。
そして忘れてはならないのがメモリです。
以前は16GBで作業をしていて、編集の途中で動作がもたつくことが頻繁にありました。
かなりのストレスでした。
そこで思い切って32GBにアップ。
その後さらに64GBに増設すると、重たい案件を扱っても不安は消え、作業が滞ることが一切なくなったのです。
「増設してよかった」と心の底から思っています。
不安が消えるということが、これほど大きな安心感につながるのかと強く実感しました。
総合的に考えて、Ryzen 9800X3Dを活かし切るなら、GPUはRTX5070Ti、メモリは少なくとも32GB、ストレージは2TBのGen.4 SSD、冷却は静音空冷、そしてエアフローに優れたケースを組み合わせる。
私なりの結論はここにあります。
この構成であれば、ゲームも編集も、そして配信も安定して楽しめる。
全方位で万能な構成なのです。
最終的に私が感じたことは、一芸に特化したマシンではなく、あらゆる用途を柔軟にこなす強さこそが、このゲーミングPCの本質だということです。
趣味をメインに選んだつもりが、仕事でも心強い武器になった。
つまり、仕事と遊びの境界を越えて力を発揮してくれる存在なのです。
静音性と冷却力のちょうどいい落としどころモデル
ゲーミング用PCをいくつか体験してみて、一番落ち着いて使えたのは、静かさと冷却力のバランスがしっかりしているモデルでした。
最終的に私が選んだのはRyzen 9800X3Dを中心に据えた空冷構成のPCです。
長時間の仕事やゲームでも安心して向き合える存在であり、やっと自分に合った落としどころを見つけたように感じました。
素直に言うと、派手な最新技術や圧倒的な性能にも惹かれました。
でも、毎日触れる道具として求めていたのは、結局のところ静かで安定した環境でした。
そこに気づけただけでも大きな収穫だったと思います。
CPUについて改めて感じたのは、発熱制御が思った以上に扱いやすいことです。
TDP120Wと聞けば多くの人が「冷やすのは大変」と思うかもしれません。
ただ、適度に大きな空冷ファンを載せれば驚くほど落ち着いた動作をしてくれます。
水冷のような派手さはないにしろ、余計なメンテナンスを気にせず使える。
それが私のように忙しい日常を送る人間には本当にありがたいのです。
とりわけ耳障りな高音のファンノイズから解放されたとき、「これだ」と心の中で呟いてしまいました。
昔、自宅の古いPCでプレイ中に急にファンが甲高い音を立てて、集中力が一気に削がれた経験が何度もありました。
その経験があるからこそ、今回のDEEPCOOL製の大型空冷クーラーを載せたモデルは印象深いものでした。
ささやかですが、この安らぎは何にも代えがたい。
正直、こういう小さな安心感の積み重ねこそが、毎日触れる道具に一番必要だと思います。
加えて、ケースの作りが予想以上に重要だと悟らされました。
Lian Liのピラーレス構造のケースを試したとき、空気がフロントからリア、さらにはトップへと綺麗に流れるのを感じたのです。
GPUとCPUの熱が衝突せず、スムーズに処理されていく感覚は快適そのものでした。
結果として長時間の使用でも息苦しさを感じない。
これは単なる部品組み合わせ以上の価値であり、冷却設計の妙を体感した瞬間でした。
特に最新GPUであるRTX5070TiやRX9070XTを使っても、システム全体の熱が過剰に膨らまず安定していたのは驚きでした。
昔の世代であればGPUが熱を帯びるとCPUまでつられて暴走するのが当たり前で、時にブルースクリーンを食らったこともありましたが、今はそうした不安が薄れています。
「これだけ冷えるなら空冷で十分だ」と素直に思えたのは、この安定感のおかげです。
ただ一つ注意すべき点として、冷却を過剰に重視するあまりアイドル時の静かさだけを追求すると、負荷がかかった瞬間にファンが急加速して耳障りになる場合があります。
他メーカーのモデルで試したとき、突然ジェットエンジンのように唸る音を出され、「何だこれ」と思わず口にしてしまったこともありました。
大事なのは静音性のピーク時の保たれ方と、立ち上がりの自然さです。
その両立こそが日常的に快適に感じられるかどうかを決める。
ありがたいことにRyzen 9800X3Dは、その辺りの課題を上手くカバーしてくれます。
GPUがフル稼働してもそれにつられてCPUが大きく跳ね上がらず、温度上昇が緩やかなのでファンRPMが不必要に荒ぶらない。
だから爆音に悩まされることがないのです。
ちょっとした違いですが、それが大きな快適につながります。
さらに個人的に見逃せなかったのが、ストレージとの相性です。
Gen.4規格の2TB SSDなら余計なヒートシンクも不要で、ケース内の収まりが綺麗です。
着実に安定を求める方が、ストレスの少ない日常につながります。
だからこそ私が最終的に選んだ構成はシンプルです。
Ryzen 9800X3Dを核にして、大型の空冷クーラーをしっかりと装着し、ケースは空気の通りを重視したものを合わせる。
水冷の圧倒的パフォーマンスも魅力的ではありますが、実際に使ってみると「ここまで快適ならこれで十分」と感じています。
冷却の安定。
私がたどり着いたのは派手さに振り回されず、極端に走らない堅実な選択でした。
Ryzen 9800X3Dを中心にしたゲーミングPCは、空冷をきちんと整えれば驚くほど力強く、なおかつ静かに付き合える。
ケースのデザインで変わるRyzen 9800X3Dマシンの印象
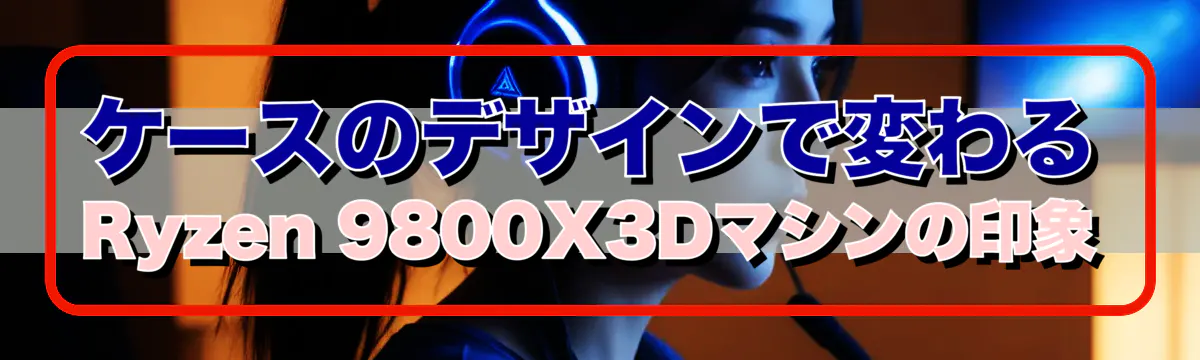
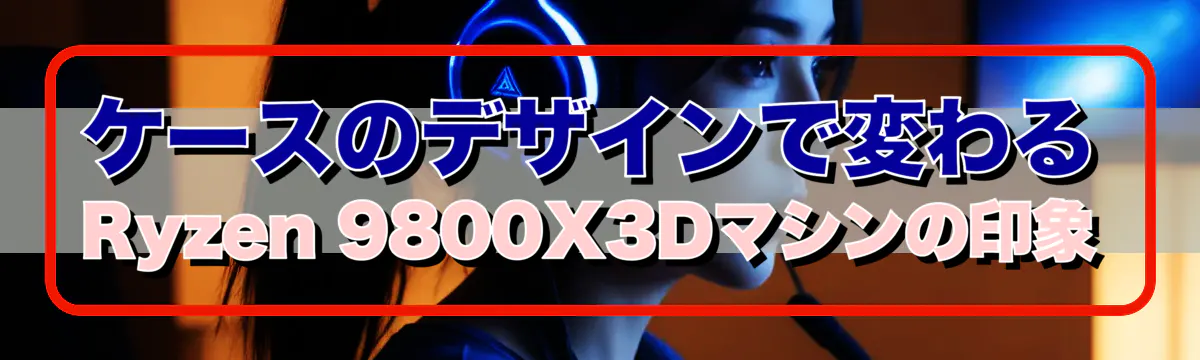
ガラスパネルで中身を魅せる派におすすめの選び方
Ryzen 9800X3Dを本当に活かすためには、ケース選びを軽視してはいけないと痛感しました。
私が行き着いた最終的な答えは「強化ガラスのデザイン性と冷却性能の両立」こそが重要だ、というものです。
見た目が良ければワクワクはしますが、数週間も使えば格好だけでは通用しない現実に直面します。
特に発熱。
これを甘く見ると、音もうるさくなるし、ゲーム体験そのものがストレスに変わるんです。
ガラスパネルの魅力は否定できません。
RGBメモリやAIOクーラーのポンプヘッドが光を放つ姿は、やはり気分を高めてくれるものです。
長い時間をかけてパーツを組んだ努力が、報われたと実感する瞬間です。
でも実際には、見とれている暇もないときがある。
3時間もFPSを続ければ、内部温度は上昇し、ファンは悲鳴を上げる。
そのときの騒音、かなり堪えましたね。
「やっぱりデザイン重視しすぎたか」と心の中で苦笑いしてしまったんです。
その経験から、私はフロントパネルが全面ガラスではなく、エアフローを考慮したメッシュ構造を選ぶようになりました。
外観と冷却、その中間地点に落ち着く判断です。
カタログで見ているだけでは分からないことでした。
実際に自分の手で組み、熱暴走に近い環境に遭遇して初めて気づけたのです。
「多少デザインを妥協しても安定動作のほうが快適」、この実感は声を大にして言いたいところです。
だから知人に相談されたら必ず「映えと冷却の両立を探すのが一番だ」とアドバイスします。
大型ケースもまた心を惹きつける要素が多いです。
正直、初めてそれを完成させたときは心が躍りました。
若い頃、自作PCを初めて動かした瞬間に似た感覚を思い出したほどです。
ただし現実は重さが襲ってくる。
高級感の裏にある重さ。
そこに向き合う覚悟が必要だと学びました。
特に展示会やLANパーティーのようなイベントに持ち込む場面を想像すると、大型ケースは現実的ではありません。
私自身、一度展示に出すためにケースを運んだことがあるのですが、あのときの疲労感は今でも思い出します。
階段の上げ下げで息が切れ、角をぶつけそうになってひやりとしました。
「次はどうするか」と真剣に考え込みました。
ここは人によって最優先の基準が分かれる部分だと思います。
もちろん、GPUの存在感も無視できません。
RTX 50シリーズやRadeon RX 90シリーズは、箱から出した瞬間に「でかっ」と声が漏れるほどのサイズです。
これにARGBファンを組み合わせると存在感は一層引き立ちます。
ただし、光を楽しむには環境も大切です。
昼間に窓際で光らせても反射で台無し。
思った以上に映えないんです。
夜、部屋の照明を落とすとまるで別世界。
光の演出ひとつでマシンの印象がここまで変わるのかと、感心してしまいます。
やはり「環境とのセット」で初めて美しさが成立するんですね。
Ryzen 9800X3Dの特性も忘れてはいけません。
このCPUは発熱管理を間違えると、本来の力を十分に発揮してくれません。
高負荷時にクロックが安定せず、せっかくの3D V-Cacheの強みを活かせない瞬間が生まれてしまう。
だから選ぶべきは冷却とガラスを両立できるケースです。
私が使用したNZXTの新モデルはその点で優秀でした。
特にトップと背面の排気力。
何時間も高負荷で回しても安定していました。
その安心感は格別でしたね。
安心感。
ケース選びにおいては見た目に流されたい気持ちはあります。
テンションが上がりますから。
でも、結局はデザインだけに振り切ると不満が積み重なる。
逆に冷却だけを突き詰めても、心が躍らない。
それを私は身をもって体験しました。
だから今は、見た目と性能、その両方を満たすかどうかを最優先にしています。
見た目でワクワクし、冷却で安心できる。
まとめると、Ryzen 9800X3Dを最大限活かしたいなら、「ガラスパネルで心を満たしながら、しっかり冷却を確保する」こと。
この一線を守るだけで、格段に自分のPCライフは変わります。
プレイ時間がただの暇つぶしではなく、日常に小さな贅沢を与えてくれる特別な時間に変わるんです。
そう実感しています。
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SV


| 【ZEFT R60SV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CO


| 【ZEFT R60CO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GS


| 【ZEFT R61GS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63Y


| 【ZEFT R63Y スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CQ


| 【ZEFT R60CQ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | be quiet! SILENT BASE 802 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
インテリアに馴染む木目調ケースの実例
ゲーミングPCのケースを選ぶとき、私はどうしても性能とデザインの両立を重視してしまいます。
どれだけ高性能なパーツを揃えたとしても、ケースが無骨で異物感を放っていれば、家の中で浮いてしまう。
逆にインテリアに溶け込むケースを選べば、それだけで使うたびに心地よさを得られるのです。
つまり、これからのPC選びにおいては「見た目と生活空間の調和こそが最終的な満足度を大きく左右する」と私は考えています。
私が実際に使ってみて驚いたのはFractal Designの木目調ケースでした。
初めて見たときは「PCケースなのに家具みたいだな」と感じたのですが、組み込んでみるとその印象は確信に変わりました。
パソコンというより、一つのインテリア。
リビングに置いてもまったく違和感がないうえ、むしろきちんと整えている空間という印象を与えてくれる。
観葉植物や絵画を加える感覚に近いのかもしれません。
ただの機械ではなく、部屋の一部になっていると実感できました。
なじむ存在。
特に印象的だったのはケース内部の設計です。
しかしこのケースは見た目の良さと同時に、内部のエアフローが非常に計算されており、通気口もデザインの一部として自然に配置されていました。
単なる穴ではなく、むしろ意匠として美しい。
その結果、冷却性や耐久性と、見栄えの両立を実現していたのです。
実際に数時間ゲームをしても不安を感じなかったので、これは本当に完成度が高いと感心しました。
安心できる構造でした。
一方で、課題も当然あります。
Corsairのモデルを試した時にはデザインには大きな魅力を感じながらも、パネルの着脱にずいぶんと手間取りました。
正直なところ「ああ、もっと簡単に外せればなあ」と思わず口から出てしまったくらいです。
苦労の跡も含めて愛着になる。
昔、組み立て家具を汗をかきながら組み上げ、完成後に妙に誇らしい気持ちになったあの感情に近いものがありました。
背景に映る部屋の雰囲気は、自分の印象そのものにも直結します。
木目調のケースは単なるパソコンではなく、生活空間の一部として自然に収まり、オンラインで誰かと話しているときに「清潔で落ち着いた環境にいる人」と見られる効果まで生み出していると感じています。
これは性能の話ではなく、生活の質に直結する要素です。
だから私は、今後ますますこのタイプのケースを求める人が増えていくはずだと考えています。
あるモデルでは、木目調の外観とガラス越しの柔らかなRGBライトが見事に調和していました。
派手さを前面に押し出すのではなく、むしろ木目によって光が包み込まれるような雰囲気になる。
例えるなら、スポーツカーを光沢ではなくマット塗装にして大人っぽい雰囲気に仕上げるイメージでしょうか。
性能をアピールしながらも居住空間では落ち着きを保つ。
静音性の面でも驚かされました。
Ryzenのフル稼働時はどうしてもファンがうなりを上げるものだと覚悟していましたが、このタイプのケースは静音設計の工夫が随所にあり、ファンの回転音が気になりにくい。
数時間作業していても耳が疲れないのです。
豪快な力を持ちながら静かにそこにいる、という落ち着いた存在感。
私は「まるで大きな猛犬を飼っているのに、なぜか安心できる」という奇妙な安心感を覚えました。
強さと静けさ。
その両立に感動したのです。
テレビやゲーム機が並ぶ中に、PCも自然に置かれるようになった。
私は実際にリビングに導入してから、空間の雰囲気が劇的に変わりました。
どこか仕事モードに入りやすく、同時に趣味としてのゲームもスムーズに楽しめる。
数値には表れにくいけれど、とても大切な変化でした。
最後にどう選ぶべきか。
私はハイスペックなCPUを搭載するのであれば、性能を最大限引き出す冷却や内部設計は当然として、同時に生活に溶け込むデザインを考慮したケースを選ぶのが最も後悔の少ない方法だと思います。
木目調のケースはまさにその答えを体現した存在であり、強い力を秘めながらも柔らかく共存してくれる。
Ryzen 9800X3DのようなCPUには、こうしたケースが最もふさわしい舞台だと私は思っています。
後悔しない買い物です。
だから、これからPCを新しく買おうとする人には、性能だけではなく生活との調和も考えてケースを選んでほしいと強く伝えたいです。
RGBライティングでゲーミング感を演出するコツ
ゲーミングPCのライティングについて、私は強く「満足度は性能だけでは決まらない」と実感しています。
やはり光の演出があるだけで、机に向かうときの気持ちが違うのです。
性能に直結するわけではありませんが、長時間パソコンに向き合う際に気分を支えてくれるのは確かで、結局のところ日々の体験を心地よくしてくれる存在だと思います。
ある程度年齢を重ねた今だからこそ、その違いが鮮明にわかるようになったとも感じます。
ただ、最初からなんでも派手に光らせればいいという単純な話ではありません。
以前、初めて全色点灯のレインボーモードを試したときは「おお、すごい」と思いましたが、数日で落ち着かなくなってしまいました。
気分が疲れるんです。
そこで大切なのが、色合いの整え方と動きの自然さ。
寒色だけで統一すれば仕事場でも違和感がなく、逆に赤やオレンジを挟めば気分が上がる。
私のお気に入りは、CPUクーラーとケースファンを白と淡いブルーで合わせた構成でした。
派手ではないけれど、落ち着いた美しさがあり、まるで職場の空間になじむインテリアのように感じられます。
Ryzen 9800X3Dのパワーを静かに支える光。
そう口にした瞬間、気分がふっと軽くなったのを覚えています。
長く愛せる仕上がり。
ソフトウェア面の進化も見逃せません。
今はRGB制御ソフトのおかげで、光の強さやパターンを緻密に設定できます。
特にブリーズモードの柔らかな脈動は、派手すぎずに存在感を保ち、疲れた目にも優しい。
その自然なリズムが、仕事の合間にも心地よさを与えてくれる。
十数年前は光るか消えるかだけの単純な仕組みでしたから、この進化の実感は格別です。
ケース選びも慎重にしたいところです。
私が使ってみて本当に良かったのはピラーレスタイプでした。
強化ガラスのおかげで中の光が自然に広がり、見える景色に奥行きが出ます。
ガラスにぼんやり浮かぶ反射。
このささやかな効果が所有の満足感を増してくれるのです。
ただし、ケーブルが散らかっているとすべてが台無し。
だからこそ裏配線を地道に調整するひと手間が、完成度を決める大きな要因になる。
かつて私も失敗しました。
まるで子供のおもちゃ箱みたいで、一目で「やってしまった」と思いました。
一方で、BTOショップであらかじめ統一設定がされたモデルを手に入れた時は、その手間が省かれたありがたさに心から感動しました。
やはりバランスと調和。
これがすべてを決める。
未来のライティングについては、AIの役割がさらに増すでしょう。
もうすでに、ゲームジャンルやプレイ状況に合わせて色が変わる仕組みは存在しています。
それが環境音や操作内容と連動する日が来るのは時間の問題でしょう。
自分にセンスがなくても、AIが勝手にプロのような仕上がりにしてくれる未来を考えると、心が躍る。
いや、すぐそこに来ています。
要は、RGBライティングを楽しむコツは調和と落ち着きにあると思います。
派手さをひたすら追い求めるのも最初は楽しいですが、長く楽しみたいなら全体のまとまりを重視すべきです。
そのためにケース選びや配線整理に時間をかけて、全体的に整える意識が必要なのです。
小さな積み重ねで日常の気持ちを支えてくれることを私は強く感じています。
気分が上がる瞬間。
働く場所にも合う安心感。
光がRyzen 9800X3Dの性能をさらに引き立て、心まで豊かにしてくれる。
私はそう確信しています。
Ryzen 9800X3D搭載ゲーミングPCに関するよくある質問
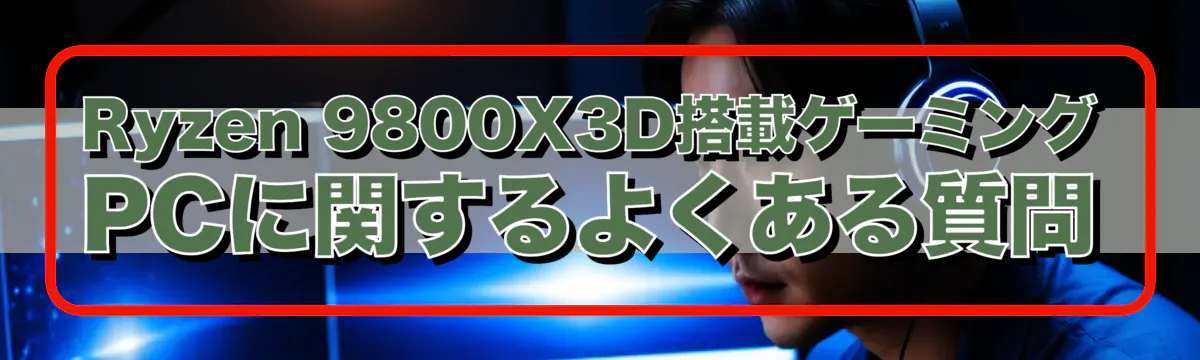
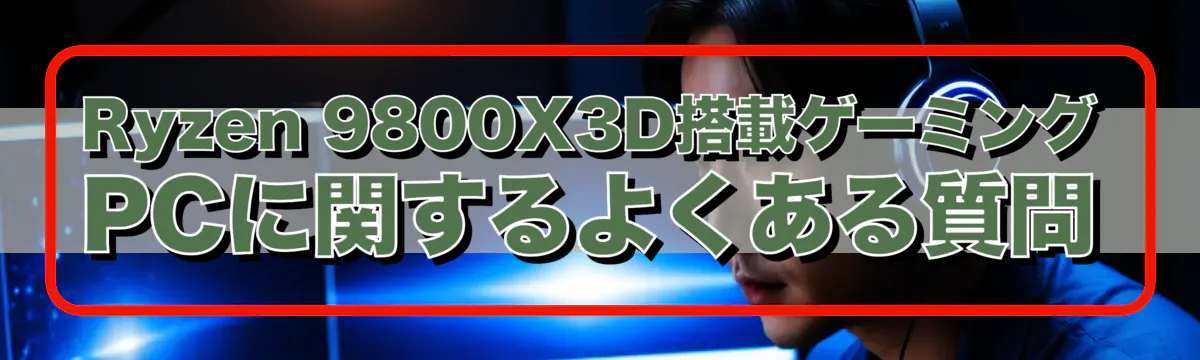
Ryzen9800X3DとCore Ultra 7、使ってみての体感速度の差は?
実際に数週間ほど自宅で両方のCPUを使い比べてみて、私は最終的にRyzen 9800X3Dのほうにしっかりと気持ちが傾きました。
ゲーム中心でPCを選ぶなら、やはりこの安心感と滑らかさは他に代えがたいと感じたからです。
Core Ultra 7も優れた性能を持っているのは間違いありませんが、少なくとも私の生活スタイルでは「楽しみの時間を支えてくれる存在」としてRyzenが一歩抜きん出ていました。
ゲームをしているときに画面が一瞬でもカクついたり、フレームが落ち込んだりすると、その瞬間に一気に気持ちが冷めてしまうんです。
これは長年ゲームを続けてきた方なら共感いただけるはずです。
Ryzen 9800X3Dはそれを極力感じさせない。
長時間のプレイ中でも映像がきれいに滑らかに流れ、余計な不安を抱かずに世界観に没頭できるのです。
正直、ここで差が出るとは思っていませんでした。
机上のフレームレート比較で「せいぜい数値が少し勝っている程度」と見えていた差が、実際に遊んでみると体感として驚くほど大きい。
たとえば最新のAAAタイトルをWQHD解像度で動かしてみました。
Core Ultra 7との差は数字で言えば平均20fpsくらい。
それだけ聞けば「大差ないじゃないか」と思うかもしれません。
ただ実際の現場では違います。
重いレイトレーシングをオンにした場面や敵が一斉に出てくる激しいシーンになると、その数字以上の違いを体が感じ取ってしまう。
映像が流れるように途切れないこと。
それが没入感に直結します。
この一点が、私にとっての決め手でした。
一方で、仕事の場面ではCore Ultra 7に惹かれる瞬間もありました。
意外でしたが、この点は確かにCore Ultra 7が頼もしく感じられました。
「あれ?これなら仕事用だけならCoreでも十分じゃないか」と正直思ったくらいです。
だからこそ、私は使う人それぞれの優先順位次第だと痛感しました。
クリエイティブ寄りの作業や資料作成が中心の人であればCore Ultra 7の魅力は大きいでしょう。
省電力性の高さも含めて合理的な選択肢になります。
一方で、私のように限られた自由時間をゲームで心から楽しみたい人なら、Ryzen 9800X3Dの安定した強さこそ武器になる。
その選び方に「正解はひとつじゃない」と強く思ったのです。
先日、休日に朝から夜まで10時間以上、途中で休憩を挟みながらゲームをやったことがありました。
ところがRyzen 9800X3Dは空冷クーラーでも問題なく安定して動き続け、最後まで落ち着いた安心感のまま過ごせたんです。
この経験は大きかった。
趣味としてゲームをするなら、静かで快適な環境で没頭できることが何よりの贅沢だと心底思いました。
さらに驚いたのは、メモリを32GBから64GBへ増設した際の伸びやかさです。
Core Ultra 7では「あまり差がないのかな」と思っていたのですが、Ryzenではそのリソースを余すことなく活かし切っている印象がありました。
これは数字以上の安心につながります。
余裕がある、と自然に感じ取れるのです。
もちろん万人に同じ結果を勧めるつもりはありません。
しかし私は40代に入ってから一層、「限られた時間をどう心地よく過ごせるか」が重要になってきました。
昔のように新製品のスペック表を見比べて一喜一憂するより、自分がどう感じるかを大切にしたい。
焦らされないこと、安定していること、信じて任せられること。
これらが今の自分にとっての価値になっています。
安定した時間。
信じられる相棒。
私の中でこの二つを満たすのはRyzen 9800X3Dでした。
だからもう迷いはありません。
もし誰かに「ゲーム中心でPCを選ぶならどっちか」と聞かれたら、私は迷わずこう答えます。
Ryzen 9800X3Dだ、と。
性能の比較表を眺めて論じるより、自分の五感で確かめた経験こそ何よりの答えでした。
そしてその結論に至るまでの過程自体も、PCという存在が日常をどう支えるのかをあらためて考える良い機会になったのです。
……正直に言います。
私はこのCPUに惚れ込みました。
心から楽しめる時間を支えてくれるからです。
ゲーム配信をするならメモリはどのくらい必要?
ゲーム配信を快適に続けたいなら、私の結論として32GBのメモリは「基準」として欠かせないと思います。
16GBあれば一見十分に感じるかもしれませんが、それはあくまで遊ぶだけの話。
配信となると要求は一気に変わります。
ゲームが年々重くなるうえに、配信ソフトやチャットアプリ、ブラウザも同時に動かす。
そうなると16GBでは息切れが早い。
安心して配信したいなら、はじめから32GBを選ぶことで余裕が持てるのです。
私自身、16GB環境でFPSを配信していた頃は何度も悔しい思いをしました。
急に映像がカクつくたびに焦って「また止まったか」と心の中で叫んでいたものです。
その度に視聴者を待たせてしまう申し訳なさは、正直言うと今でも苦い記憶として残っています。
配信は楽しく盛り上がるものであるはずなのに、機材の限界に引っ張られて気持ちばかりが前のめりになる。
あれは辛かった。
思い切って32GBに増設したとき、はじめて「安心感」と「余裕」を取り戻した気がしました。
最近のBTOパソコンの多くは、32GBが標準搭載されているので買う段階で迷わず選べるようになっています。
特に難しいことを考えなくても、多くの配信者にとって満足できる環境が最初から手に入るのはありがたい話です。
しかもメモリは後から追加できます。
最初から過剰に積まなくても安心してスタートできる点で、32GBは現実的でバランスのいい落としどころだと思います。
ただ、64GBという大容量を検討すべき場面もあります。
私がその必要性をひしひしと感じたのは、配信しながら同時に動画編集まで突っ込んでやろうとしたときでした。
OBSで4K録画を動かしながらPremiere Proを扱っていたら、タイムラインがもたついて作業の流れが何度も途切れてしまったのです。
その後64GBを導入したら、処理の重さでイライラすることが一気に消え去り、画面の中で映像が滑らかに進む感覚に正直わくわくしました。
とはいえ配信者全員が64GBを必要とするわけではありません。
コストパフォーマンスが合わない。
だから私は、人に勧めるときも必ず「まずは32GBで十分」と伝えます。
自分に必要なタイミングが来たときに増設すればいい。
やっぱり一番大事なのは安定した環境を持つことです。
どれだけ盛り上がっていた配信でも、映像が途切れたり反応が遅れたりすれば、その瞬間に視聴者は冷めてしまいます。
信頼を積み上げるのは時間がかかりますが、失うのは一瞬。
だからこそ、配信環境は無理のないラインで確実に押さえておくことが重要です。
その意味で32GBは欠かせない基準点であり、活動の幅を広げる人には64GBという選択肢が次の一歩として待っています。
私自身40代になり、時間の大切さを強く実感するようになりました。
だからこそ余計な不安やストレスは徹底的に排除したい。
配信やクリエイティブな作業は楽しむためにやっているのであって、機材の制約に縛られるためではありません。
配信機材にどこまで投資するのかは、単なるスペック競争の話ではありません。
むしろ自分の活動や時間の質をどう守るかという考えに直結しています。
私は32GBを「普段の基盤」と位置づけ、64GBは「攻めの武器」として捉えています。
慣れてきたら徐々にステップアップすればいい。
これが私なりの実感であり、信じている方法です。
安心して作業できること。
楽しんで続けられること。
この二つを両立させるために、メモリ選びは見過ごせない要素です。
特にRyzen 9800X3Dのような強力なCPUを組み合わせる場合、その性能を活かすには32GBをきちんと積んでおきたい。
もし動画編集や同時処理を本気でやりたいなら、その次の段階として64GBを考えればいいだけです。
シンプルにまとめるなら、ゲーム配信だけなら32GB。
配信プラス動画制作まで突っ込むなら64GB。
そういう選び方が一番ストレスがないと私は思っています。
結局、環境選びは「自分がどう時間を過ごしたいか」に尽きます。
私はそう自問自答しながら、これからも迷いの少ない環境を組んでいきたい。
そうすれば、配信の画面を通して味わえるのは、不安のない純粋な楽しさだけ。
楽しさの純度。
これが私が最終的に求める答えです。
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SM


| 【ZEFT R60SM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67H


| 【ZEFT R67H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60TB


| 【ZEFT R60TB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RY


| 【ZEFT R60RY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN EFFA G08FB


| 【EFFA G08FB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
PCIe Gen5 SSDの速さ、実際に体感できる部分はどこか
私が実際にPCIe Gen5 SSDを使ってみて率直に感じたのは、確かに必要な場面はあるものの「誰にでも必須ではない」ということです。
最新世代のスペックを見れば、読み込み速度が14,000MB/sを超えるといった派手な数字が並び、従来のGen4 SSDの倍近い性能と説明されます。
確かにインパクトはありますが、数字だけを見て「本当に体感できるのかな」と半信半疑になっていたのが正直な気持ちでした。
最初に印象的だったのはゲームでした。
数十GB単位のデータを読み込むオープンワールドのタイトルで、起動の速さに驚かされました。
ロード画面を見ながらコーヒーを飲もうとしたら、その前にキャラクターが動き出している。
こういう時は声が漏れますよね。
「おいおい、もう始まってるのか」と。
拍子抜けというより、むしろ慌てるほどでした。
しかし一方で、小さな容量のFPSやMOBAではほとんど違いを感じず、GPUやCPUを換装したときに感じるような劇的な変化まではありません。
あくまでタイトルによりけり。
実際にはそういうものです。
仕事に関してはさらに顕著でした。
私は映像編集の案件で数百GBの素材を扱うことがありますが、Gen4 SSDではコピーに時間がかかり「いつ終わるんだろう」と思わずため息が出ることもありました。
120GBを超えるカット素材を整理するとき、待たされずに次の編集に移れる感覚はまさに効率そのもの。
それまでの「無駄に待たされる時間」がごっそりなくなり、集中が途切れない状態の快適さが、結果的に仕事全体の質まで変えてしまうのだと痛感しました。
待ち時間に耐えていた自分がいかに生産性を削られていたのか、嫌というほど思い出させられましたね。
しかし良いところばかりではありません。
最大の懸念は熱です。
Gen5 SSDは高温になりやすく、冷却をきちんと整えなければすぐに性能が抑え込まれます。
小さなケースで簡易ファンをつけただけの環境では、せっかくの速度が台無しです。
ヒートシンクや専用の冷却機構を備えた製品でなければ真価は発揮できないのです。
これは「高性能な設備には適切な環境が必要」という、ビジネスの世界でもよくある話と同じ構図でしょう。
良い人材を採用しても働く場が整っていなければ力を発揮できないのと似ています。
価格の高さも悩みどころです。
今のところ同じ容量ならGen4 SSDの倍程度の値段を覚悟しなくてはならない。
最新のハイエンドBTOパソコンでも標準構成はGen4 SSDの方が圧倒的に多い理由は単純で、大半の利用シーンではGen4で十分だからです。
だからこそ私自身、ゲーミング用途ではGen4で何も困っていません。
ロード画面が数秒長いだけでは、プレイの楽しさや勝敗に影響することはほとんどありません。
ところが一方で、映像制作やデータ分析など、短縮した数秒が積み重なって一日トータルで何十分も変わってくるような職種では話が別です。
その数十分が締め切りを守れるかどうかに直結する。
そういう意味で「時間をお金で買う投資」としては、大きな価値があると感じます。
ただし、SSDだけが高速なら良いわけではありません。
システム全体のバランスが重要で、GPUやCPUといった他の要素も揃っていなければ「SSDだけ豪華」というチグハグな構成になってしまう。
私は過去に、ストレージだけ高級なものを選び、GPUの性能不足で作業が滞るという失敗をしたことがあります。
今振り返ると笑えますが、当時は本当に焦りました。
結局のところ資金配分の最適化は重要で、これは仕事の投資判断にもそのまま通じます。
ほぼすべてのユースケースで不安もなく、価格との釣り合いも良いのが事実です。
ただし毎日数百GBのデータを扱い、数秒単位の短縮がチーム全体の成果に影響するような環境であればGen5 SSDに投資する理由はしっかりと存在します。
そのときは冷却環境を整え、性能を生かす土台を作ってから挑戦すべきです。
性能先行で導入して環境が整っていないと、宝の持ち腐れになりますからね。
一番大切なのは、自分の使い方を冷静に見直すことだと思います。
性能の高さに目を奪われるだけではなく、実際の生活や仕事の中でその速度をどう生かすのかを考える。
その先に意味のある投資が成立します。
結局のところGen5 SSDは「憧れ」で買うものではなく「必要性」で選ぶべきものなのです。
スピードの先にあるのは効率です。
そこで生まれる余裕が自分の時間に跳ね返ってくる。
だからこそ私は声を大にしてこう言いたい。
BTOと自作、実際の予算感や用途別でどちらが得なのか
Ryzen 9800X3DをベースにゲーミングPCを考えると、どうしても目の前に立ちはだかるのがBTOにするか自作にするかという二択です。
私の実体験を踏まえると、落ち着いた選び方をするならBTO、遊び心や探求心を優先するなら自作という住み分けになります。
私自身、数字ばかり追っていた時期もありましたが、実際に手に取って組んだり、サポートに助けてもらったりするなかでようやく気づいたことがあります。
BTOを選んだ場合、Ryzen 9800X3Dに最新のミドルハイGPU、32GBのDDR5メモリ、そして2TBのGen4 NVMe SSDを積んだモデルで27~30万円程度が相場です。
しかも不思議なほど多くのメーカーで似たような価格帯に収まる。
言い換えるなら、もう価格勝負にはなりにくい部分があるわけです。
それに対し、自作ならうまくセールやタイミングを狙えば25万円前半に抑えられる可能性があります。
ただ実際には、その差は数万円程度に留まることが多い。
「あれ?結局そこまで安くなってないぞ」と思う瞬間がある。
そういう経験を何度もしてきました。
だから私は安さだけを理由に自作を推すことはしません。
危うい賭け方だと感じるのです。
使い方を考えてみると、例えばeスポーツタイトルを快適に動かしたい人にとっては、やはりBTOが無難です。
これが一番大きい。
私も深夜にフレンドと対戦しているとき、もしPCがいきなりトラブルを起こしたら…想像するだけでげんなりします。
サポート窓口に預ければ修理して戻してくれるBTOの安心は、何物にも代えがたいものです。
自作と比べれば、責任を分散できるというところも大きな魅力ですね。
一方で、RPGや動画編集、重たい作業を重視する人には、自作の夢が残っています。
冷却方法を空冷にするか水冷にするか、自分の好きなケースを選び、さらにストレージを複数積んでRAIDを組むといった自由度。
これこそ自作ならではです。
私も昔から「冷却は納得いく形で管理したい」と思っていましたから、その点で非常に心を動かされます。
制御する実感こそが、自作の魅力なんですよね。
実際に私は、最近BTOで9800X3DとRTX5070Tiを組み合わせたモデルを導入しました。
届いた箱を開けて電源を入れた瞬間の静けさに驚かされたんです。
オフィスで使ってもファンの音が全く気にならない。
自作でそこまで静音に調整しようと思えばBIOSを触って細かく設定を詰め、ファンカーブを作り込まないと無理です。
プロの技術力を実感した瞬間でした。
「やはり餅は餅屋だな」と素直に思いましたよ。
でも自作の醍醐味も忘れていません。
私はゲームのインストール数が多いので、2TBのNVMe SSDを2本揃えてRAID 0を組みました。
BTOでは選べなかった構成です。
起動してゲームを立ち上げたとき、読み込み時間が数秒縮んだだけなのに体感的にはとんでもなく快適で、なんだか作業のテンポまでも軽やかになった。
これは自分で組んだからこそ味わえる満足感でした。
ただし、自作には明確な壁もあります。
組み立て、配線、BIOS調整、OSインストールまで軽く5時間以上はかかりますし、思ったようにケーブルが通らなくて夜中に汗だくになり、イラッとして工具を放り出したくなる時も多い。
けれど、そんな苦労すら楽しんで笑える人じゃないと自作の本当の面白さって理解できないのかもしれません。
不思議な達成感があるんです。
BTOも進化しています。
最近は冷却方式やケース形状も自由度が上がり、ユーザーが好みに合わせてカスタマイズできる幅が広がっています。
例えば空冷だけでなく一体型の簡易水冷までラインナップに入ると、もはや自作とそこまで大差がなくなる。
ここまで来ると「これならBTOで十分じゃないか」と感じる人も増えるでしょう。
その変化を私は楽しみにしています。
結局、選び方はシンプルです。
長時間の安定動作とサポートを重視するならBTOが良い。
私のように日中は仕事で忙しく、夜はすぐ遊び始めたいという人にとっては、一番効率的な答えです。
多少カスタマイズ範囲は狭まっても、必要十分な構成で長く安心して使える。
それが最大の価値だと思います。
逆に「自分だけの1台を作りたい」と徹底的にこだわりたい人には自作がうってつけです。
自分で考え抜いた冷却設計や配線でパーツが綺麗に収まった瞬間は何物にも代えがたい満足ですし、趣味としての熱量も大きな力になります。
私の友人も徹夜で組み上げた話を笑いながらしてくれますが、その充実感は聞いているだけで伝わってきます。
情熱ですよね。
Ryzen 9800X3Dを核にPCを選ぶのであれば、この二択の本質は驚くほど単純です。
安定と効率を求めるならBTO。
自分自身のこだわりや冒険心に賭けたいなら自作。
大切なのは、ライフスタイルや価値観と照らし合わせて、心から納得できる方を選ぶこと。
そうしないと、せっかくの高性能PCなのに「こんなはずじゃなかった」と感じてしまう恐れがあります。
私はその確信を持ってお伝えしたい。
最後は、自分がどんな時間を大切にしたいのか。
そこに尽きるのだと思います。