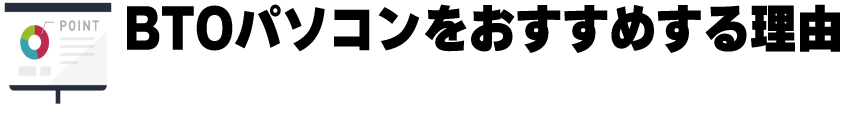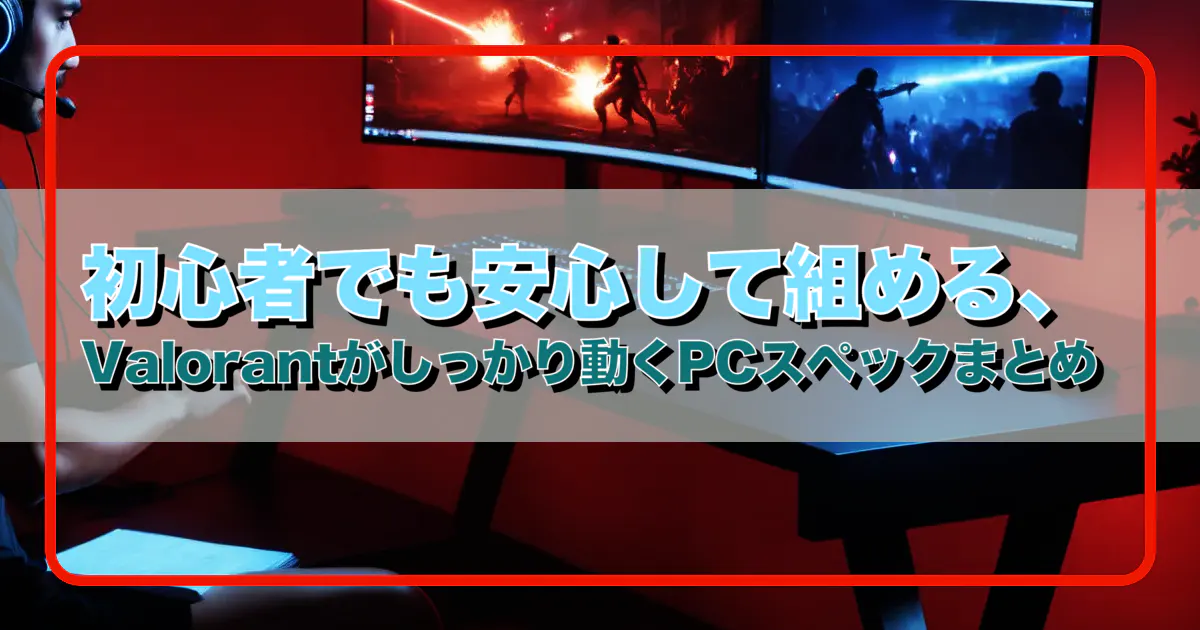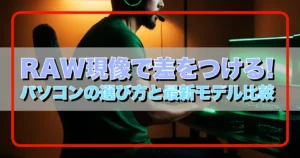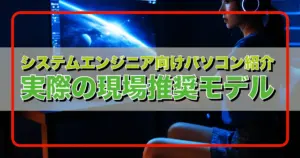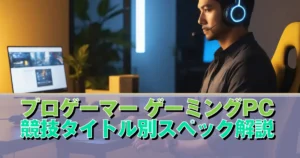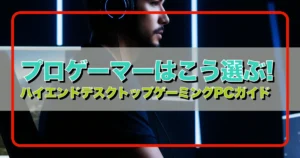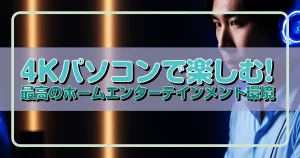Valorant を快適に遊ぶために必要なCPUの基準

Core i5やRyzen 5で実際どれくらい快適に動かせるか
これが率直な実感です。
私は実際にフルHD環境で144Hz対応ディスプレイを接続して試しましたが、設定をある程度上げても平均で200fps前後を記録できました。
数値だけ見ると「本当にそこまで余裕あるのか?」と首をひねりたくなるかもしれません。
ところが実際にプレイすれば驚くほど動きが滑らかで、視点移動にももたつきがなく、応答の速さと見やすさに素直に安心しました。
FPSは一瞬の反応で勝敗が決まるもの。
だからこの安定感は非常に大きな意味を持つのです。
特筆すべきはValorantが見た目に反してCPUへの依存度が高いことです。
GPUをハイエンドにせずとも、CPU性能がしっかりしていれば十分なフレームレートを維持できる。
これは数多のゲームを触ってきた身からすると珍しい特徴で、個人的には面白いバランスだと感じました。
私の感覚では、コスト抑制と安定性の両立を狙うならCore i5やRyzen 5の現行世代がもっとも理にかなっています。
GPUについても正直なところ、ミドルクラスの一枚を組み合わせればプレイには不足しません。
肩ひじ張らずに楽しめる。
そういう安心感がありました。
ただし条件を厳しくすると限界が見えてきます。
WQHD解像度で165Hzクラスのモニターを選んだ場合、マップによってはフレームが頭打ちになり「あれ?」と違和感を覚える場面もありました。
フルHDであれば余裕がありますが、高解像度と高リフレッシュレートの両立はさすがにこのクラスのCPUでは苦しい。
4K環境に挑むとなれば完全に力不足です。
ここは割り切るしかありません。
過去に私自身がRyzen 5環境で配信を同時に行ったことがあります。
OBSを起動してエフェクトを数枚重ねた瞬間にfpsが急激に落ち込み、実況者としての冷や汗を実感しました。
「ここまで負担が大きかったのか」と驚かされたのを覚えています。
シンプルなプレイなら全く問題なし。
けれど配信を含めるならRyzen 7以上は必須です。
余裕をもつことで安心できる。
これはCore i5にもそのまま当てはまります。
ゲーム専用で割り切るなら十分。
けれど複数タスクを意識する人にとっては、やや心もとないんです。
とはいえ、コストとパフォーマンスのバランスを考えるとこのクラスはやはり優秀だと思います。
GPUやメモリに回せる予算ができるのは魅力的で、システム全体としての体感を底上げしてくれるからです。
Valorantは描画負荷が軽いわけではありませんが、エンジンの完成度が高いため、高画質設定でも意外なほど軽快に動きます。
戦闘が入り乱れるシーンでもCore i5やRyzen 5が100fpsを割り込むのは稀でした。
これによって低遅延を求めるシューター環境で120fps以上を維持できることが、プレイヤーからすると非常に大きな安心感につながってくる。
fpsが乱れると一気に集中力が乱れるものです。
あの息苦しさ。
経験した人ならわかるでしょう。
最終的な判断基準は明快です。
フルHD解像度でValorantを滑らかに遊ぶだけなら、Core i5やRyzen 5で十分。
迷う必要はありません。
144Hzモニターと組み合わせればストレスなく楽しめますし、そのうえで余った資金をGPUやメモリへ回す方が、日々の使い勝手や快適さを一段引き上げてくれます。
逆に「映像表現をもっと豪華に楽しみたい」とか「配信も同時にやりたい」と考えている方は、素直に上位CPUに投資した方が良い。
中途半端な我慢よりも、後悔の少ない選択をすることが結果的に納得感を生みますから。
勇気を出して一段上を選ぶのか、それともコスト重視で賢く楽しむのか。
用途によって決めるべき方向性ははっきりしています。
私自身も二つの環境を比べて、フルHD&競技志向のプレイに限定するならCore i5やRyzen 5で十分満足できています。
そして、高解像度や映像品質へのこだわりが強いときには、やはり上位モデルに目が向きました。
要するに、自分の求めるプレイスタイルと環境を冷静に見つめ、そのうえで最適なCPUを選ぶことが大事なのだと思います。
これが私の実感です。
だからこそ、自分がどんな遊び方をしたいのか、それを真剣に考えて選んでほしい。
配信や動画編集もするならRyzen 7を検討したい理由
もし後輩に率直なアドバイスをするなら、配信や動画編集を考えるならばRyzen 7を選んだ方が間違いが少ない、と私は迷わず伝えると思います。
ゲームだけならRyzen 5で十分という場面も確かにあります。
しかし40代にもなると、時間の重さが若い頃とは違う実感として迫ってきます。
エンコードに長時間待たされ、そのせいで深夜にまで作業が押し込み、翌朝の会議でどんよりした頭を抱えた時ほど、その判断が甘かったと痛感させられることはありません。
だから私は余力のある構成を用意することが、最終的には精神的にも生活的にも余裕をもたらすのだと学びました。
私自身も以前はRyzen 5を使ってゲームをしていました。
Valorantも当時は快適に動作し、特に不満はありませんでした。
けれども配信ソフトを起動して通話アプリを立ち上げ、さらにブラウザで調べ物をしながら進めると、思いがけないところで動作がもたつくんです。
240Hzのモニターまで投資したのに、肝心のフレームレートが落ちてしまった瞬間の心の落ち込みようといったら…。
まさに徒労感でしたね。
その後Ryzen 7に切り替えて得られた安心感は、今もはっきり覚えています。
例えば配信をしながら裏で動画のエンコードを動かしてもゲームはカクつかない。
音ズレも見当たらない。
映像の劣化や粒子感も消え、くっきりと描かれた画面が広がる。
初めてそれを体験した時に、私は思わず声に出しました。
数字ではなく体感の差。
実際の作業がどれだけ楽になるかが心に響いたんです。
それで後悔の繰り返しでした。
特に動画編集を始めたばかりの頃、短い映像を一つ書き出すのに驚くほどの時間を費やすはめになり、その待ち時間の長さに心をすり減らしていました。
正直、作る気力まで奪われていったのです。
あの頃に余裕のある環境を選んでいたら、もっと早く成長できただろうと思わずにいられません。
その経験があるから私は今、人に強めの言葉で「迷うなら上位を選んでおけ」と伝えるんだと思います。
最近のソフトは日々進化し、AIによる補正や字幕生成など当たり前のように搭載されるようになりました。
GPUだけに任せて安心していたら、CPUが悲鳴を上げて結局作業が止まるということもあります。
Ryzen 7の余裕ある能力は、現在だけでなくこの先も支えとなる。
これを単なるスペック面の安心と片付けるのではなく、未来への投資と捉えてください、と私は自分の体験をベースに語りたいのです。
特に私が実感しているのは「時間の価値」です。
能力不足の環境だと、作業が待ち時間に取って代わられ、その時間はただ失われていくばかりです。
40代になり、家族とも過ごす時間の一分一秒が重く愛おしくなると、その無駄が胸に刺さります。
だからこそ、これから機材を整える人には真剣に伝えたい。
「迷う必要はない、Ryzen 7を選びなさい」と。
待たされる時間が減れば、その分の余裕を必ず実感できます。
さらに言えば、Valorantそのものも間違いなく重さを増していくはずです。
実際にUnreal Engine 5への移行が進められている現状を考えると、今後のアップデートでRyzen 5が力不足になる日が早く訪れると予想できます。
せっかく環境を整えても長く持たなければ意味がない。
快適な環境。
そして持続する安定感。
その流れにストレスが入り込まないだけで、趣味の時間が見違えるほど豊かになるのです。
最終的に言いたいのは、Ryzen 7は性能評価以上の安心感をもたらしてくれるという一点に尽きます。
カタログやベンチマークで示される数字以上に、実際の生活がどれだけ安定し、どれだけストレスのない時間を得られるか。
それを体感するともう戻れません。
だから私は全力でこう伝えます。
「安心できる環境を選んで後悔することはない」と。
コストと性能の落としどころとしてCore i7が狙い目
だから私は迷っている人にはCore i7を強く勧めています。
単純にゲームだけではなく、毎日の生活や仕事のあらゆる場面で違いが出てくるからです。
Core i5を選んで最初は満足していても、数年後にアップデートや環境の変化で「あれ、そろそろ厳しいかも」と感じる瞬間は必ずやってきます。
そのたびに余計な買い替えを強いられるぐらいなら、最初からちょっと背伸びしてCore i7にしておく方が精神的にも経済的にも結果的に楽なんですよね。
私自身が過去に経験しました。
最初は「値段を抑えても十分だろう」とCore i5を選び、数年間は問題なく使えていました。
でも新シーズンのゲームやWindowsアップデートが重なると、突然足を引っ張られるような感覚が出てくる。
あのとき、正直ため息が出ました。
財布にグサッとくる感じです。
それに比べると、Core i7にしてからの安心感は大きい。
ゲーム中のフレームレートが安定しているのはもちろん、ちょっとした場面でも違いを感じます。
例えば長めのオンライン会議をしながら、裏で資料をまとめたり動画を視聴したり。
あるいは子どもが宿題の調べ物でブラウザを何十個も開いたままにしているのを横目で見つつ、自分の作業を続けるときでもストレスがほとんどないんです。
私はその「余裕」にとても救われています。
特にValorantのような競技性の高いゲームでは、わずかな安定性の差が集中力の持ち方に直結することを体感しました。
Core i5だとフレームレートは出ているはずなのに、長時間のプレイで小さな引っかかりが出始めて気持ちが乱れる。
このときに「ああ、自分が欲しかったのは数字以上の安定感なんだな」と実感しました。
安心感。
信頼できる土台。
こうした感覚はゲームだけではありません。
私は在宅勤務が多いのですが、たまに社内プレゼンを「配信形式」で行うことがあります。
以前の環境では途中で途切れるのではと心配しながらやっていましたが、Core i7のPCに替えてからは「もし止まったらどうしよう」という無駄な不安がなくなりました。
これは本当にありがたい。
もちろんさらに上を見ればCore i9やRyzen 9といった怪物のようなCPUもあります。
しかしあのクラスになると消費電力も冷却装置も含めて別世界です。
静音性を追求した水冷システムを組みたいとか、極限まで性能を引き出すことにロマンを感じる人なら良いですが、私はそこまでやろうとは思っていません。
仕事と家庭をバランスよく回しながら、その合間にゲームを快適にやりたい。
そういう現実的な立場の人間には、Core i7がベストバランスなんだと思います。
さらにここ数年でUnreal Engine 5を使ったゲームが増えてきました。
もし240Hzのモニターに合わせて競技をやろうと思うなら、CPUに一定以上の力がなければ映像は滑らかに映りません。
その意味でCore i7は、本当に余裕を持たせてくれる存在です。
これは数字やカタログスペックではなかなか表現しきれない部分なのですが、実際に姿勢を正してゲームをしていると「これが本来の滑らかさか」という違いが分かります。
私は40代という年齢もあり、パソコンを一度買ったらできるだけ長く使いたいと思っています。
どれかひとつだけのためではなく、全部を見据えた末に辿り着いたのがCore i7です。
買い替えで余計な時間を奪われず、自分がやりたいことに集中できる。
その安心感は心の余裕にもつながってきます。
だから私は声を大にして言いたいのです。
「迷っているならCore i7にしておけ」と。
無理をして最高級モデルを買う必要はありません。
でも必要最低限ギリギリの選択をして後になって困るのは、自分自身です。
最初にCore i7を選んでおけば、その後数年間は大きな不安を抱えずに過ごせる。
私は過去の失敗から、それを身をもって学びました。
快適さは投資だと思います。
Valorant の動作を大きく左右する最新グラフィックカードの選び方
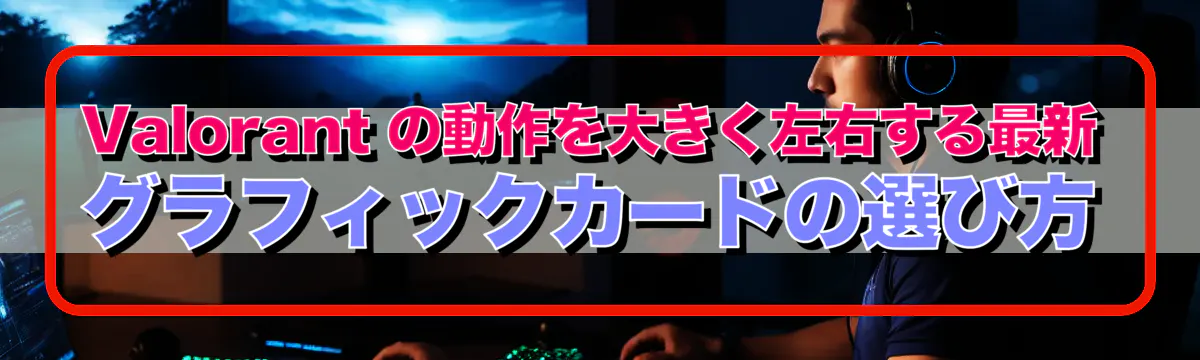
RTX 4060 Tiや4070で144fpsを安定させられるか実際のところ
RTX 4060 TiでValorantを144fpsで動かすことは十分に可能です。
自分自身が実際に4060 Tiを試したときに、そのことを痛感しました。
数字上は申し分ない性能なのですが、勝負どころのシーンで一瞬フレームが落ちると「ここで揺らぐか…」と胸がざわつく。
些細な揺らぎのはずなのに、気になって仕方がなかったのです。
以前、私はフルHD中設定で4060 Tiを搭載したPCを組み、平均220fpsほど出ていたので「よし、これなら大丈夫だろう」と安心していました。
ですが派手なエフェクトが重なったとき、一瞬144fpsを割り込む場面が出てしまったのです。
その当時のプレイには支障はなかったのに、不思議と心にひっかかりが残りました。
「もし大会の大事なラウンドでこの瞬間が来たら」と想像すると、落ち着かなくなる。
結局、性能そのものではなく、揺るぎない安心を求めている自分に気づかされたのです。
安心感を買う、その一言に尽きますね。
加えて忘れてはいけないのがCPUとのバランスです。
GPUだけを強化してもCPUが追いつかなければフレームは安定しません。
Core Ultra 5と4060 Tiの組み合わせでも144fpsは狙えます。
しかし、私は相談を受けた友人にはよく「長く見据えるならCore Ultra 7と4070にしてはどう?」と答えています。
シンプルに性能だけでなく、アップデートや設定変更への柔軟さも確保でき、数年先も安心して付き合えるからです。
Valorant自体は軽めのタイトルではありますが、Unreal Engine 5に切り替わったことを考えれば今後必要なリソースは少しずつ増えていくでしょう。
日々ライトに遊ぶ人なら大きな影響はないかもしれません。
しかし、数年後の変化にそなえておきたい人や、勝負にこだわる人であれば、余裕を持った構成こそ保険になります。
ギリギリの計画は必ずどこかで崩れます。
だからこそ「今は大丈夫」ではなく「先々の安心」を含めて環境を選ぶことが大事だと思うのです。
実際に昨年のeスポーツ大会で4070が公式採用されているのを見たときは、心の底から納得しました。
本気の勝負の場では、不安要素を残さないことこそ最大のパフォーマンスに直結します。
採用されているという事実自体が「この性能を基準にしていい」という安心を与えてくれるのです。
信頼の裏付け。
さらに印象的だったのは、友人が組んだ最新環境に触らせてもらった時のことです。
4070とRyzen 7 9800X3Dを組み合わせたマシンでしたが、300fps近くまで伸びる瞬間を体感したのです。
数値が跳ね上がるのはもちろん驚きましたが、実際のプレイ感覚がこれほど軽快になるとは思っていませんでした。
マウスを動かした瞬間から応答がスッと返ってくる。
余裕のあるフレームは、ストレスを消し去り、ゲームに没頭させてくれるものでした。
体験そのものが「快感」としか言いようがなく、良い環境が人の気持ちをここまで変えるのかと実感しました。
とはいえ誤解はしてほしくありません。
4060 Tiが悪いカードというわけではないんです。
コストを押さえて144Hzの環境を安定させたい、という人には自信を持って「これで十分ですよ」と勧められます。
実際、同価格帯でこれほどのパフォーマンスを発揮することは驚きですらあります。
ただ、人間とは欲が出るものです。
せっかくゲーミングPCを買ったら「165Hzや240Hzも試したいな」と考え始めるのです。
そのときに「もう少し上を選んでおけばよかった」と後悔しないためにも、4070を視野に入れておく意義は決して小さくはありません。
PCのパーツ選びをしていると、ついついfpsや数字の比較だけに目が行きがちです。
しかし、実際に毎日使って感じるのは「不安に振り回されず集中できること」がいかに大切かということです。
私は4060 Tiでも144fpsを満たすこと自体には全く不満は持っていませんでした。
その違いは小さく見えて、心には大きな影響を及ぼします。
結局のところ、どちらの構成を選んでもValorant自体は楽しめるはずです。
ただし、長く使っていく中で「性能に余裕があることで心にも余裕が育つ」ことを理解して買えば、購入後に迷うことは少なくなり、愛着を持って機材と向き合えると思います。
私は最終的に4070を選んで良かったと今でも感じています。
プレイに臨むとき胸を張れる環境がある。
それだけでパフォーマンスも気持ちも確実に変わるのです。
自分を支えるのは、自分が信じられる環境だと、私は心から思います。
Radeon RX 7800 XTならWQHDや4Kでも余裕を持ってプレイできる
WQHDや4Kといった解像度でValorantをできる限り快適に遊びたい人にとって、私が実際に試してみて安心して選べると感じたグラフィックカードはRadeon RX 7800 XTです。
正直なところ、フルHDでのプレイならここまでの性能は不要だと感じます。
結果、せっかくの楽しみが削がれてしまうんですよね。
そこをしっかり支えてくれる力を見せてくれたのが、このRadeon RX 7800 XTだったのです。
安心感がありました。
最初にWQHDモニターへ環境を移したとき、私は旧世代のGeForce RTX4060 Tiを使って挑戦しました。
しかし、思ったようにフレームが伸びず、理想とのギャップにモヤモヤ。
投資対効果を感じた瞬間です。
Valorantは軽いタイトルだと多くの人が口にします。
けれどUnreal Engine 5へ切り替わった後、光の表現力やオブジェクトの質感は明らかに変化し、処理の重さも確実に増した。
つまりWQHDや4Kでfpsを安定させたいなら、中?上位のGPUが欠かせなくなる場面が多くなったということです。
その中でRadeon RX 7800 XTは、フルHDなら余力を持て余すほどパワフルで、WQHDでは理想的なバランスを見せ、4Kも設定次第で十分実用的に戦える。
まさにちょうどいい立ち位置と感じました。
絶妙なんです。
4Kに挑戦するとき、多くの人は思わずさらに高額なハイエンドGPUを検討すると思います。
私も最初はその方向に考えが傾きかけました。
ところが実際にRadeon RX 7800 XTを使ってみて気付いたんです。
必ずしも最高峰モデルでなくても十分に競技の場へ立てるパフォーマンスがある。
最新FPSでも中?高設定で60?100fpsが安定して出る。
映像美を楽しみながら実用性をも満たすという経験は、背伸びしすぎない選択肢の良さを身にしみて感じさせてくれました。
これが大きな安心要素でした。
ただし気を付けるべき点もありました。
とくに電源ユニットは軽視できません。
あの冷や汗は嫌な思い出です。
すぐに850Wゴールド認証電源へ移行したところ、システム全体の安定性が落ち着き、急にPCが頼れる存在へ変わってくれました。
電力不足は足腰の弱さと同じです。
やはり土台を固める大切さを痛感しました。
土台の重要性ですね。
もう一つ大事なのがケースのエアフローです。
高リフレッシュでの長時間プレイではGPUが高温になることも珍しくありません。
しかしRadeon RX 7800 XTを入れると熱がこもって、ファンが常に全開。
集中力を削られました。
思い切って正面がメッシュ構造のケースに変えたところ、温度が平均で7度下がり、ファン音も静かになった。
性能だけでなく設計や環境の調和が欠かせないのだと知りました。
快適さはトータル設計から。
このGPUをどんな人に勧めたいかと改めて考えると、やはりWQHDや4KでValorantを長く楽しみたい人にうってつけだろうと思います。
映像の華やかさと競技性、どちらも犠牲にしないラインをしっかり押さえてくれるからです。
一方で、重量級タイトルや動画編集、3D制作を頻繁に扱う方なら、さらに上位モデルを検討するべきでしょう。
使い方を踏まえた判断が肝心です。
冷静な判断。
いろいろ調べた末、私は最終的にRadeon RX 7800 XTで落ち着きました。
理由は単純で、解像度を上げて快適に遊べる環境を長く維持したかったからです。
他の候補も検討しましたが、このクラスが持つ性能とコストの均衡に勝る選択肢は見つかりませんでした。
そう、やっぱりこれだと。
結局のところ、自分がどの解像度でどの程度の満足を長く得たいのかを考えることが一番大事です。
そのうえでWQHDや4Kを視野に入れるなら、Radeon RX 7800 XTはとても頼もしい相棒になってくれる。
私はこの選択を後悔していませんし、むしろ新しい体験に踏み出すきっかけとなりました。
そこで味わえる安心感こそ最大の魅力です。
単なるスペック競争に流されるのではなく、自分の生活スタイルや時間の過ごし方に合った環境づくりが本当に大切。
静音性や温度、電源供給やケースの空気の流れ。
そのすべてが一体となって快適さを形づくるからです。
だからこそ、Radeon RX 7800 XTは単なる部品ではなく、安心して任せられるパートナーだと私は強く感じています。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60HS

| 【ZEFT R60HS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IF

| 【ZEFT R60IF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65T

| 【ZEFT R65T スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GR

| 【ZEFT R60GR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59N

| 【ZEFT R59N スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
初心者でも扱いやすいおすすめのグラフィックカード候補
特にValorantのような競技シーンを意識するタイトルであれば、最新世代のミドルレンジGPUを選ぶのが一番納得できる判断だと私は確信しています。
ハイエンドモデルの圧倒的なパワーには一瞬心を揺さぶられますが、実際の試合でその全力を体感できる機会はそう多くないのが現実です。
冷静になって振り返れば「ここまで投資しなくても良かったな」と後悔するケースに行き着いてしまう。
だからこそ必要な性能をしっかり満たしつつも、堅実な選択をすることが最終的に長く続く安心と満足に結びつくのだと思っています。
私が実際におすすめするクラスは、今の世代でいうとGeForce RTX 5060TiやRadeon RX 9060XTあたりです。
価格的にもまだ現実的な範囲で、解像度がフルHDやWQHDであれば240fps前後を安定して狙える。
Valorantは軽いゲームとよく言われますが、Unreal Engine 5に移行した今、旧世代のカードではフレームの落ち込みが勝負どころで目立つこともあるんですよ。
かつて私も負けを喫したその一瞬を忘れられません。
その経験からも、無理なく戦える環境を作るのが強さにつながると実感しました。
私はしばらくRadeon系を使っていたのですが、最近思い切ってRTX 5060Tiに乗り換えました。
そのときの応答速度には心底驚かされました。
Reflex機能の効果なのか、マウスの動きが直結するように弾が飛んでいく。
ほんの一瞬の振り向きざまに勝てた瞬間、正直に声を上げてしまいました。
「やっぱり買い換えて良かった!」と。
数字だけでは測れない、自分の手応えとしての満足感がそこにはありました。
一方で、Radeon RX 9060XTの良さもちゃんと認めたいです。
特にFSR 4によるアップスケーリングの仕組みは賢く作れていて、設定を上げても見栄えが崩れにくい。
私は配信をしながら遊ぶことも多いのですが、意外なほど映像が乱れなかった。
CPUやメモリに負荷のかかるタイミングでも滑らかに映像がついてくる。
そのとき感じたのは安心だけじゃなく、配信を視聴している人への責任感も少し救われた気がしました。
映像品質が落ちると、自分のプレイ以前に伝える体験への信頼を失うものですからね。
高価格帯GPUのパワーは眩しく映るけれど、Valorantを中心に考えると間違いなくオーバースペック。
目指すべきなのは派手な数字ではなく、安定。
そのうえで最近のアーキテクチャは消費電力や静音性もしっかり改善されているので、深夜の練習時間でもファンの音ひとつに気を削がれることがありません。
PCを組む上で忘れてはいけないのがGPUだけに偏らないことです。
CPUはCore Ultra 5やRyzen 5以上が望ましい。
メモリは最低でも16GB、できればDDR5にすることで裏で配信や通話アプリを動かしながらでも余裕が出てきます。
ストレージにはGen4 NVMe SSDを選べば、起動やロード時間で待たされるストレスを大きく減らせるんですよ。
小さな違いに見えるかもしれませんが、こうした細部を詰めることで集中力を途切れさせない快適な時間が増えていく。
これは私自身が組んだ環境で味わった実感です。
もちろん、もし4K解像度で最高画質を突き詰めたいのならRTX 5080やRadeon RX 9070XTといった上位モデルが候補になるでしょう。
しかし競技性を重視するゲームでは条件が違います。
大会を意識するなら中価格帯のGPUが一番の現実解。
価格と性能のバランスの点で見ても、5060Tiや9060XTあたりの立ち位置の納得感は本当に抜群です。
私がたどり着いた構成は明快です。
そして冷却と電源には余裕を持たせる。
これに尽きます。
この組み合わせがあることで、余計な心配ごとに頭を取られることなく、試合の一瞬に全神経を注げる。
忘れられない場面があります。
勝敗が決まる一瞬で、もし性能に不安があったら集中できなかったでしょう。
その時、私は環境に救われました。
「備えは裏切らない」そんな言葉が心の中で響きました。
こうした体験が、私をこの構成へと導いたんです。
結果として私は、無理をせずに安心して長く戦える環境を選ぶことこそが最適だと確信しました。
派手ではないかもしれません。
でも地に足のついた安定こそが、本気で勝ちに行く人に必要な武器だと思います。
誤魔化しのない選択。
大人として納得できる投資。
そして最後に残るのは、無駄なく勝負に挑める満足感。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49113 | 100929 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32430 | 77302 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30414 | 66101 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27399 | 68249 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26736 | 59644 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22140 | 56240 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16704 | 38983 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16133 | 37823 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15994 | 37602 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14766 | 34575 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13862 | 30555 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13317 | 32041 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
Valorant プレイにちょうどいいメモリ容量と規格の考え方

16GBで十分か、それとも32GBにすべきタイミング
実際に私も16GBで数年間プレイしてきましたし、当初はそれで十分だと信じていました。
でも、一度大きなストレスを味わうと、考え方ががらりと変わるのです。
ある日のことを今でもはっきり覚えています。
私は16GBのPCでValorantをしながらDiscordで友人と会話し、Chromeでいくつか動画を開いていました。
そこに配信ツールを一つ立ち上げたら、とたんに動きがカクつき始めて画面が固まる。
あの瞬間の苛立ちと焦りは、言葉では言い尽くせません。
「なんで今落ちるんだよ!」と本気で声を上げました。
仲間に迷惑をかけるのも嫌でしたし、自分自身の集中が切れてしまうことが本当に悔しかった。
そうした経験を重ねて、私はようやく32GBに増設しました。
するとそれまでのもたつきが嘘のように消えて、心からほっとしたのです。
やっと安心できると感じました。
メモリというのは、CPUやGPUのようにスコアやフレームレートという分かりやすい指標にすぐ表れるものではありません。
それなのに、裏でしっかりと支えてくれている。
私はそれを身をもって実感しました。
数値だけを見て「まあ16GBでいいだろう」と決めるのは簡単ですが、いざ自分の環境で同時に複数の作業を走らせてみると、一瞬の引っ掛かりが大きなストレスになるんです。
プレイそのものを邪魔された時にわかる大切さ。
机上の理論では伝わらない重みがあるのです。
さらに最近はDDR5の普及も進んでおり、速度と容量をバランス良く備えたメモリが比較的手に入れやすくなりました。
逆に言えば、今あえて16GBにこだわる理由も以前ほど強くはない気もしています。
ただし、用途が限られている場合は決して32GBが絶対条件ではありません。
例えば、弟に勧めたのは16GBの構成でした。
弟はとにかくValorantしかしません。
動画もスマホでしか見ないタイプです。
結果は当然快適。
「本当にこれで十分だよ」と笑いながら言われた時、私は妙に納得しました。
環境次第なんだな、と。
しかし未来を考えると、16GBが苦しくなるシーンは確実に増えていきます。
ValorantがUnreal Engine 5に移行し、描写の美しさが増すたびに裏の処理は重くなる。
ゲームが進化すれば、それを支えるハードも相応に要求水準が高まるのは自然なことです。
正直、今後数年を安心して過ごしたいなら32GBの方が確実に余裕があります。
将来への備え。
ちょっとした保険のような発想です。
実際に32GBにすると、仮想メモリを頻繁に使わずに済みます。
するとストレージへの負荷が減り、動作が滑らかになる。
NVMe SSDのように高速な部品を入れていても、やはり物理メモリの速さには敵いません。
この点は意外に大きいもので、私は増設後に初めてその違いを肌で感じました。
そして、どのタイミングで切り替えるべきかというと明確に二つだと思います。
一つは配信や動画編集を始めたとき。
もう一つは画面解像度をWQHDや4Kに上げる場面。
高解像度化はGPUだけでなく、CPUやメモリも確実に圧迫します。
16GBでは息苦しいとすぐに分かるでしょう。
余裕があるほうがアイデアや楽しみの妨げにならない。
一方で、純粋にValorantだけをプレイするのであれば、今でも16GBで困ることはほとんどありません。
だからこそ、要は自分がどんな遊び方をするのかによって決まります。
シンプルです。
当時「コストを節約しよう」と安易に16GBにしてしまった。
その時は確かに得した気がしましたが、後から追加の出費をすることになり、結局は遠回りだったのです。
なんとも苦い経験。
次に同じ選択を迫られたら、迷わず32GBを選びます。
あのゲームが止まった瞬間の悔しさは二度と味わいたくありませんから。
結果として今の私から伝えたいのは、「プレイに集中したいなら32GB、用途が限られているなら16GBでも良い」ということです。
両者のどちらかを決める基準は、あなたがPCをどう使い、どんな時間を過ごしたいかという一点に尽きるのだと思います。
ゲームを心底楽しむ。
そのための環境づくりに、メモリは欠かせないものだと私は言い切れます。
安心感。
次の一手。
DDR5?5600が主流になり始めている背景と理由
最近のPCパーツを見渡していると、どうしても気になるのがDDR5-5600です。
速度と安定性のバランスが優れていて、しかも価格も手頃。
派手さはないですが、結局のところ長く付き合うなら安心感こそ大切なのだと痛感します。
数年前にDDR5が登場したとき、初めてその値札を見て私は思わず「これは普通のユーザーには当分無理だな」とつぶやきました。
当時は新しさよりも高額さが目立ち、「少しは安くなるまで様子見だな」と考えていたのです。
ところがどうでしょう。
今となっては自作PCでもBTOパソコンでも、ほとんど標準といっていいほどDDR5が選ばれています。
その中で5600が事実上の基準になっている現状を見るにつけ、技術の進化と市場変化のスピードの速さに目を見張ります。
私が特に安心したのは、Intelの最新Core UltraやAMDのRyzen 9000シリーズなど、主要なCPUが正式にDDR5-5600へ対応を打ち出したことです。
メーカーが公式に「この速度なら問題ない」と明言しているのですから、互換性の心配で悩まなくて済む。
これは本当にありがたい。
自作や構築の経験がある人なら、安定動作を担保できることがどれほど大きいか、よく分かるはずです。
迷ったら5600でOK。
この安心感は決して小さくありません。
実際に私自身も半年ほど前にCrucialのDDR5-5600を導入してから使い続けています。
これまで発熱による不具合もなければ、突然のフリーズに悩まされたこともありません。
思い返せば、DDR5の初期モデルである4800を導入したときは不安定な挙動や相性の壁に頭を抱え、「新規格はやっぱり怖いな」と肩を落とした経験もありました。
それゆえ、今の5600の安定感には心底驚いているのです。
快適。
もうそれしか言いようがありません。
性能面での意味合いも見逃せないのです。
たとえばValorantのようにCPU性能に強く依存するタイトルでは、メモリ速度がほんの数fpsの差として効いてくることがあります。
その数fpsが勝敗を分け、時には試合の流れを大きく変える。
そう思うと、単なる「数字の遊び」ではなく、実利用に結びつく性能差であることを強く実感します。
私は何度もそうした小さな差が大きな差になる瞬間を体験してきました。
価格面を考えても今のDDR5-5600はとても現実的です。
登場当初のDDR5は高嶺の花とさえ感じられるほど高額で、手を伸ばすのに勇気がいりました。
しかし量産効果によって価格が下がり、特に5600クラスは大量に市場に流通しているため値段が安定しています。
ユーザーの裾野を広げた大きな要因は、やはりこの価格のこなれ具合だと私は考えています。
ここで「せっかくだからもっと上を」と意欲的になる人がいるのも理解できます。
6000や6400あたりを検討する声も耳にします。
ただ、実際にその領域へ踏み込むと電圧の調整や細かな相性問題など、途端に難易度が跳ね上がります。
ある程度玄人向けの領域と言ってもいいでしょう。
挑戦する楽しさを追求する人にとっては魅力でも、安定した環境で快適に遊びたい、あるいは仕事にも使いたい人にとっては余計なリスクにしかなりません。
無理は不要。
私の正直な意見です。
仮に次世代のCPUやマザーボードが6400以上を標準とする時代がすぐ来たとしても、5600が突然使えなくなるわけではありません。
容量やモジュール規格はそのまま活かせます。
環境更新の際には「今ある5600を引き継いで、必要になれば段階的に足す」という作戦が取れる。
こうした柔軟さを持っているのは大きな魅力です。
先を見据えた安心感があります。
最近PCショップを覗くと、展示機の多くがDDR5-5600を32GB(16GB×2)構成で組んでいます。
気付けば「これぞ標準構成」と言えるほど定番化しているのです。
そして、なぜそうなっているのか自分なりに考えると、価格と安定性のバランスに優れているからだと納得します。
32GBあればゲームも作業も心置きなくできるし、特別な事情でもなければこれ以上を求める理由は薄い。
また、スマートフォンの世界と照らし合わせても似た傾向が見えます。
ハイエンド端末を追い求める人は一部にいますが、大多数はミドルレンジモデルで十分と感じています。
必要十分でコストパフォーマンスが高い。
だからこそ支持される。
PC業界の標準がDDR5-5600へとシフトしてきている今の状況も、その延長線上にあるように思います。
ユーザーが日常で求める安心感とコストの釣り合いを取れば、自ずとこの選択肢に落ち着くのでしょう。
私が出した結論は極めてシンプルです。
ゲーミングPCとしてValorantなどの対戦ゲームを遊ぶにせよ、仕事用のPCとして長時間稼働させるにせよ、DDR5-5600を32GB搭載しておくのが最も安全かつ現実的です。
特別な準備や調整をせずとも、ひとまず安心して使えるベースが確保される。
それこそが多様な用途を支える土台になるのだと実感します。
迷ったら5600。
それで大丈夫。
安心して使えるメモリメーカーと安定動作の目安
Valorantの環境を快適にするために欠かせないのは、やはりメモリの選び方だと私は考えています。
以前、安さにつられて聞いたこともないブランドのメモリを購入してしまい、プレイ中にいきなりゲームがクラッシュしたことがありました。
集中して真剣に撃ち合っている最中に、突然の強制終了。
あの瞬間の落胆といったら本当に言葉になりません。
せっかくの大事な時間をそんな無駄で台無しにしてしまったことを思い返すと、今でも胸の奥にモヤモヤとした悔しさが残っています。
だからこそ、信頼できるメーカーを選ぶことが何より大事だと強く思うようになったのです。
おすすめできるメーカーとして最初に挙げたいのはCrucialです。
Micron傘下という基盤の強さもあり、数多くの実績が裏付ける安定性があります。
その堅実さには助けられてきました。
余計な心配をせずに済むというのは、結果として大きな安心感に繋がります。
その点では、長時間プレイにも配信にも不安がないですね。
次にG.Skillの存在を無視することはできません。
派手な見た目が好みではない人もいるでしょうが、ゲームを「遊び」と捉えるなら、こうした視覚的要素が気分を上げるきっかけになるのも事実です。
自分のデスク環境を整えるたびにワクワクした気持ちにさせてくれるんです。
そしてSamsung。
このメーカーに関しては、もはや説明が要らないほどでしょう。
PC業界全体で広く信頼され、安定と耐久性で長い実績を誇っています。
まさに「堅実」という言葉がふさわしい。
私は仕事でも家庭でも道具の信頼性を第一に考えるようになったのですが、その意味でSamsungのパーツは非常に頼りがいのある選択肢でしたね。
長期間の利用を考えても、不安材料が極めて少ないのです。
では容量はどうか。
現在のスタンダードはやはり32GBだと感じます。
DDR5-5600の32GBを搭載しておけば、配信をしながらでもゲームの動作が滑らかで、プレイ中に気を取られることなく集中できます。
16GBでも一応は動作しますが、ボイスチャットやブラウザ、配信ソフトを同時に動かすと負荷が積み重なり、どうしても重さが目立つことがあります。
私の知人も16GB環境で配信をしていましたが、視聴者から「見ているとカクついている」と指摘されて本人がかなり落ち込んでいました。
それが32GBに切り替えた途端、滑らかで安定した環境になったそうです。
この話を聞いたとき、私自身も強く納得しました。
やはり最初から余裕を持った構成を選ぶほうが、結果として後悔をせずに済むのだと。
意外に大事なのが購入先の選び方です。
国内の大手BTOメーカーにはそれぞれ強みがあります。
たとえばパソコン工房はパーツ選択肢の広さが魅力で、わざわざ自作に手を出さなくても納得のいく構成に仕上げやすい。
そしてドスパラは対応の早さに定評があり、納期が短いので「今すぐに使いたい」という人にとっては非常にありがたい。
実際、以前私も急ぎで必要だったときに利用しましたが、本当に助かりました。
また、特筆したいのがパソコンショップSEVENです。
国内生産にこだわりつつ、採用される部品はすべて実績のあるブランド。
自分が依頼した時にも「この安心感は他とは違うな」と思いました。
最初に名前だけを聞いたときは少し疑っていましたが、実際に利用すると、その堅実さに納得せざるを得ませんでしたね。
プロゲーマーや配信者が愛用する理由にも得心がいきました。
私はこの経験から、安定性を確保できる環境こそがプレイの楽しさを底上げするのだと痛感しました。
ハード面で不安を抱えていると、どうしても「今日はうまく動くかな」と余計な心配が頭から離れません。
ですが自分が信頼を置けるメーカーのメモリを選び、信頼できるショップから購入することで、そうした負担から完全に解放される。
精神的な余裕はゲームだけでなく、日常の気持ちにもプラスに働きます。
安定したパソコンほどありがたいものはない。
だから私がおすすめするのは、CrucialやG.Skill、Samsungといった信頼性の高いブランドのDDR5-5600で32GBを選ぶ構成。
そして購入先は、パソコン工房、ドスパラ、もしくはパソコンショップSEVEN。
この三つの選択肢に集約してしまえば、大きな失敗を避けられます。
安心できる選び方を最初にするだけで、そのあとの時間も気持ちも守れるんです。
これが結果としてコストパフォーマンスにも繋がっていく。
要は「長期間安定して動く安心を手に入れる」ことこそが最も重視すべき点だと私は思います。
安いものに目がくらんで結局は使いづらくなり、大切な時間をトラブル対応に吸い取られるくらいなら、本当に信頼できるものを選んだほうがいい。
確かな品質と、信頼できる購入先。
この二つを満たすことで、私はようやく後悔のない環境を作れると実感しましたし、その快適さを味わった一度目の瞬間から「最初からこうしておけばよかった」と心から思いました。
だからこそ断言できます。
Valorantを安定して最高の状態で遊びたいなら、ここで紹介したブランドと購入先があなたにとって最適解です。
Valorant 向けPCのストレージ構成と冷却をどう考えるか


NVMe SSDは1TBあれば足りるのかの実際
インストール容量なんて数十GB程度ですし、最初の頃は録画データをいくつか保存しても余裕があると感じるでしょう。
動作も軽快で、余計なストレスを感じない。
最初は十分そうに思えますよね。
ところが、使っていくうちに現実は違う方向へ転がっていきます。
配信ソフトを入れたり、仕事の連絡用にボイスチャットツールを使ったり、気分転換に別の有名ゲームを追加したり。
気付いたらSSDの残り容量がだんだん削られていきます。
ソフトの入れ替えに振り回される日々。
とても煩雑で、正直面倒なんです。
私自身、過去に1TBでパソコンを組んだ経験があります。
けれども気楽に大型タイトルを数本入れたら、ある日突然200GBを切ってしまったんです。
ある夜、Windowsのアップデートで「空き容量不足」の警告が出た瞬間、背筋が凍ったことを今でもはっきり覚えています。
疲れて帰宅した夜に、貴重な自由時間を容量整理に費やさなきゃならない。
速度面では問題ありません。
最近のPCIe Gen4やGen5対応SSDなら、1TBモデルでも十分な性能が出ます。
ロード時間の短縮は目に見えて、体感的にも本当に快適です。
速度については不満を抱かないでしょう。
だからこそ浮き彫りになるのは容量という根本的な問題です。
容量だけは後からどうしても足りなくなります。
ここ数年で、100GBを超える大容量ゲームは当たり前になりました。
さらに動画編集に手を出そうとすると地獄です。
フルHDや4Kの素材なんてひとつで数十GBを軽く突破してくる。
私もValorantのプレイ動画を保存していたのですが、あっという間にフォルダがパンパンになり、泣く泣く外付けHDDへ逃がしました。
あれは正直つらい。
やりたいことを存分に楽しめないだけで、ストレスは積み重なります。
とはいえ、全員が最初から2TBや4TBを用意すべきとは思いません。
価格差も無視できないですから。
1TBで始めてみて、足りなくなったら増設していく柔軟な構成のほうが現実的です。
M.2スロットを余裕を持って確保しておき、将来に備える。
それなら将来の拡張もしやすく、容量別に役割を分けて効率的に使えます。
実際その構成はかなり便利でした。
ただ、新しいGen5対応SSDは熱の課題がネックになります。
普段使いで安定して動作するかどうか。
ここが最終的に一番大事だと実感しています。
つまり、Valorantだけを考えるなら1TBで言うことなし。
でも、長期的に見ればこの考えは甘いんですよね。
数年経てば少なくとも動画保存や別のゲームに挑戦することは十分あり得る。
結局、1TBが足りなくなる未来は避けられない。
容量不足のせいで本来の楽しさが削がれてしまうのは、本当にもったいないことです。
私からの提案はシンプルです。
最初から余裕を持つこと。
最低でも2TBあれば安心できると思います。
実際、私が最初から2TBを選んでいたら、容量不足に悩まされる経験は避けられたでしょう。
迷っている人ほど大きめを選んだほうが、後々のストレスは格段に減ります。
結局のところ、容量不足との戦いは思った以上に精神的に堪えるものなんです。
心の余裕につながる選択こそ、一番の正解です。
それがストレージの真実です。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56KA


| 【ZEFT Z56KA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09G


| 【EFFA G09G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56O


| 【ZEFT Z56O スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DAG


エンスージアスト級のパワーを備えるゲーミングPC、プレイヤーの期待に応えるマシン
バランスドハイパフォーマンス、最新技術と高速32GB DDR5メモリで圧巻のパフォーマンスを誇るモデル
話題のCorsair 4000D Airflow TG、隅から隅まで計算されたクールなデザイン、美しさも機能も両立するPC
Ryzen 9 7950X搭載、プロセッシング性能の新境地を切り開く、ハイエンドユーザーに捧げるゲーミングPC
| 【ZEFT R56DAG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Gen4とGen5 SSDの速度差と選び方のポイント
Gen4のSSDで十分過ぎるほどの読み込み速度が出せるので、性能を余らせてしまうくらいなんですよね。
私自身、実際に試してみて「Gen5じゃなきゃ駄目だ」と感じた瞬間は一度もありませんでした。
これが率直な答えです。
確かにカタログスペックの数値はGen5の方が魅力的です。
リード速度が理論値で14,000MB/sを超えて、Gen4の倍近い性能だと言われています。
しかし実際の利用シーンをあれこれ試してみても、その性能差を体感できる場面なんてほとんどないんです。
Valorantの起動時間にしても、Gen4なら一瞬でロードが完了しますし、試合中の快適さが変わるわけでもない。
fpsがドンと上がるわけでもなく、映像が突如として綺麗になることもない。
だから、数字の上での派手さばかりを追いかけてしまうと「自分が求めていたものは何だろう?」と疑問が残るのです。
私はそこに強い違和感を覚えました。
何より厄介なのは性能よりもむしろ価格と熱の問題です。
Gen5 SSDってとにかく発熱が大きいんですよ。
私が導入したときは、PCケースのエアフローが不十分でサーマルスロットリングが何度も発生しました。
つまり、温度が下がらないせいで逆に速度が制限され、肝心の性能が落ちてしまうんです。
結局、大きめのヒートシンクを追加したり、ケースファンの配置を見直したりで、時間もお金もかかってしまいました。
素直に言えば「なんでわざわざ最先端を選んだのか」と後悔したんですよ。
あのときの苦労は忘れられません。
それに比べてGen4 SSDの安定感は特筆すべきだと感じています。
各メーカーから成熟した製品がそろっていて、発熱に神経質にならなくても問題なく動きますから、精神的にも安心できます。
BTOショップでも、Gen4なら2TBクラスの容量を積んでも比較的手頃な価格ですし、Windowsや主要タイトルをインストールしても余裕がある。
この扱いやすさが大きいんです。
もちろん将来を見据えるとGen5 SSDが必要になる時代は来るでしょう。
例えばUnreal Engine 5をベースにした大規模なオープンワールドタイトルが増えれば、ロード時間の短縮は没入感を高める重要な要素になると思います。
そうした未来像に備える意味でGen5を検討する人を否定するつもりはありません。
むしろ新しい技術をいち早く体験したいという気持ちは理解できます。
ただ、私自身がよく遊ぶゲームは軽快な対戦ものばかりですし、現状ではCPUやGPUに予算を割いた方が確実に効果を体感できます。
だからGen5は私にとって今の優先順位ではないんです。
思うんですよ。
数字やレビュー動画に振り回されると、本当に大事な選択を見誤るなと。
性能が十分に出ている環境なのに、さらに上を追いかけてしまい、結果的に出費ばかり増える。
冷却対策で余分に悩みまで抱えてしまう。
私はそういう遠回りはもうしたくない。
Gen4で十分です、これが私の本音なんです。
ここ1年ほどGen4 SSDをメインで使っていて、正直ストレスを感じたことは一度もありません。
PC全体のバランスを考えたときに、まさに「ちょうど良い」のです。
そしてSSDにかかるコストを抑えたおかげで、その分GPUに投資できたことが、ゲーム体験を一段上のレベルに導いてくれました。
改めて実感しましたね。
お金をどう振り分けるかが一番大切なのだと。
近い将来、Gen5 SSDが当たり前になるのは間違いありません。
すでに一体型クーラーを搭載したモデルも出てきていますし、価格も着実に下がってきています。
数年後には「Gen5こそ標準」という時代がやってきて、Gen4は旧世代扱いされてしまう。
その流れは誰も止められません。
でも、少なくとも今この瞬間、Valorantを快適にプレイするためだけならGen4 SSDが最適解です。
熱の心配がなく、予算を圧迫することもない。
そしてロード時間も十分に速い。
迷う必要なんてありません、Gen4で良いんです。
Gen5 SSDが持つ圧倒的な数値は確かに夢がありますが、それを活かせる環境が整っていない現状では魅力が十分に引き出されない。
コストや発熱の悩みを背負うぐらいなら、私は迷わずGen4を選びます。
Gen5は未来の投資、あるいは新技術そのものを趣味として楽しみたい人向けでしょう。
そして、その整理こそが購入判断を楽にしてくれる。
これが私のたどり着いた答えです。
安心感。
この2つを基準に考えるなら、今は間違いなくGen4を選ぶべきだと私は感じています。
空冷と水冷、どんな使い方をする人に合うのか
冷却方式をどう選ぶかというのは、PCを長く安定して使いたい人にとって避けて通れない問題です。
私も若い頃は勢いでパーツを買い集め、深く考えずに組み立てていました。
性能を追い求める一方で、冷却を軽視した結果、突然の電源落ちや不安定な挙動に泣かされたことがあります。
だからこそ今では、落ち着いて言い切れるのですが「安定してPCを最後まで使い切りたいなら冷却を軽く見てはいけない」と。
ストレージや電源に気を配るのと同じくらい、冷却はシステム全体の土台を支える要素だからです。
初めて自作した頃は、見栄えや性能ばかりに目が行き、正直冷却の種類まで深く考える余裕がありませんでした。
机の下で一日中ゲームを回しっぱなしにしても、熱暴走で止まることがない。
その安心感を体で覚えた経験が、私を空冷信者に近い立場にしてしまったのだと思います。
信頼できる安堵。
さらに空冷は懐事情にも優しい存在です。
本体価格が手頃で、構造の単純さゆえに大きなトラブルが少ない。
ファンが壊れたとしても簡単に交換が効きます。
そのため長期的に見てもわざわざ大きな投資を繰り返さなくていい。
日中は仕事に追われ、夜は趣味として少しでもゲームをしようという私のような生活スタイルでは、この扱いやすさと余計な心配を生まない安心がありがたいのです。
もし毎回トラブルで時間を削られてしまったら、せっかくの趣味が台無しですからね。
一方、水冷は不思議な魅力を放っています。
CPU温度が安定したまま静かに動き、夜中の作業でも耳障りな音がしない。
しんとした部屋で音楽を小さく流しながら仕事をするとき、冷却ファンのうなる音がないだけで驚くほど集中できるものです。
さらにケースの中が整理され、配管や配光の輝きで雰囲気も大きく変わる。
正直言って、いい年齢になった今でも「格好いいものは格好いい」と感じてしまいます。
大人の満足。
ただ、やはり現実的な壁もあります。
私は以前、360mmの簡易水冷を導入して配信環境を整えていました。
導入して2年ほどは抜群に安定し、静かで頼もしい相棒でした。
しかし3年目に入ったあたりからポンプの異音が出始め、そこから一気に不信感が募りました。
液漏れのリスクや寿命の短さは知識として持っていましたが、実際にその兆候を耳で聞くと、とてつもない不安が押し寄せます。
数年ごとに交換が必要になるシステムは、費用だけでなく心労まで生むものなのだと痛感しました。
「やはり自分は空冷でいい」と感じた瞬間でした。
ケース選びも冷却方式を語るうえで避けられません。
最近はデザイン重視のケースが増え、思わず見た目だけで手に取ってしまうこともあります。
しかし冷却パーツの収まりを無視すると痛い思いをします。
私は過去に、外観に惹かれて購入したケースに、大きなヒートシンクが物理的に入らないという失敗をしました。
そのときは本当に悔しかったですね。
だから今では「先に冷却パーツのサイズを確認してからケースを選ぶ」という鉄則を忘れません。
順序を誤らないことの大切さを身をもって学びました。
加えて忘れてはならないのはCPU以外の発熱です。
特にGen5 SSDは本当に熱を持ちます。
それを甘く見ると速度低下がすぐに起こり、安定していた作業環境が一気に崩れてしまう。
動画編集や配信をしているときなどは顕著で、サーマルスロットリングによって作業効率が落ちてしまいます。
だから私は必ずヒートシンクや小型ファンを追加し、SSDもしっかり冷やすことを意識しています。
PC一台の健康を考えるならCPUだけでなく全体の冷却設計に目を配る。
それが長く安心して使うために欠かせないのです。
教訓。
そう考えると、整理は意外とシンプルになります。
費用や長持ちを重視するのなら空冷。
静かさや見栄えを追求したいなら水冷。
それぞれに分かりやすい特徴があり、間違った選択というものはありません。
今のPC性能であれば、ゲームも作業もどちらでも十分こなせます。
ただ私自身のスタンスを率直に示すなら、やはり空冷です。
余計な不安を抱えずに済む、その安定こそが私にとっての最大の価値だからです。
けれど、これはあくまで私の感じ方に過ぎません。
静音にこだわりたい人や、ケース内部を美しく見せたい人にとっては、水冷はかけがえのない選択になり得ます。
だから私は水冷を否定する立場ではなく、それぞれのスタイルに合った選択を後押ししたいと考えています。
最終的に残る問いは「どこに安心を求めるか」。
人によって答えは違いますが、安定を望むなら空冷、ロマンを追うなら水冷。
この二択に尽きるのだと思います。
私がこれからも選び続けるのは、やはり堅実で頼れる空冷です。
Valorant に適したPCケース選びとデザインの工夫


強化ガラスケースと木目調ケース、それぞれの使い勝手
強化ガラスのケースには確かに魅力があります。
内部のパーツが光とともに浮かび上がり、ひとつの完成された作品のように感じられる瞬間があるのです。
LEDで彩られたファンを眺めながら、「これが自分の手で組み上げた一台なんだ」と実感できる。
その高揚感は格別ですが、同時に配線の整理を怠れば一気にその美しさが台無しになり、手間と神経を要求されます。
正直、見映えを整えるために何度もケーブルを束ね直し、汗をかいた記憶があります。
でも振り返ってみると、その面倒さの先にある達成感は大きく、まるで仕事で一つのプロジェクトを形にしたときの感覚に近いのだと思います。
一方で、木目調のケースが発する穏やかな雰囲気も年齢を重ねるにつれて心地よく感じるようになってきました。
華やかな光で自己主張するのではなく、部屋にしっとりと溶け込む。
家具と並んだときに違和感がない姿は、大人の落ち着きを感じさせてくれるんです。
家族が集うリビングや書斎に置いても自然で、使う人の年齢や環境に寄り添ってくれるのが木目調の良さだと私は思います。
自宅に長く置き続けるものだからこそ、空間との調和は外せない大前提です。
以前、私は三面ガラスのケースに挑戦したことがあります。
友人が家に遊びに来たときに「すぐにゲーミングPCってわかるな」と笑ったのを今も覚えています。
確かに存在感は抜群で、その時は満足でした。
しかし、毎日の仕事でその部屋に座るとき、異様に浮ついた感じがして落ち着かない。
好きで選んだはずなのに、自分の暮らしとは噛み合っていない気がして、違和感を覚えたのです。
そこから私は木目調にも目を向けるようになりました。
実際に導入してみたら、驚くほど自然に部屋に馴染み、しかも十分な冷却能力を備えていることに舌を巻いたのを覚えています。
性能と見た目が両立するものなんだなと、少し感心しました。
冷却に関して言えば、強化ガラス製がわずかに優れる場面もあります。
メッシュ仕様のケースと比べれば分かりやすい差が出ることもあるでしょう。
ただし、快適に144fps以上を狙うような環境を整えるためには、ケースの素材よりもファン配置、エアフロー設計、さらにはCPUクーラーやGPUの冷却効率といった基礎部分が本質だと私は考えます。
ここを軽視してケースそのものに期待を寄せすぎるのは、少し的が外れていると思うのです。
むしろケースは方向性を決める器に過ぎず、冷却力全体の構成力こそが真価を決める。
これは何度も組み替えを経験して痛感したことです。
デザインと実用性、この二つをどうバランスさせるかが結局のポイントとなります。
自分の生活空間にどのように溶け込ませたいのか、どんな時間をそこで過ごしたいのか。
この問いに答えることがケース選びとも直結します。
ガラス越しに光を楽しみたいのか、家具のように落ち着かせたいのか。
その選択こそが所有の形を変える。
だから迷うんです。
最近、面白いトレンドも見かけます。
木目調をベースにしながらも片側にだけガラスを入れるハイブリッド型の登場です。
利用者の嗜好がどんどん多様化している証拠であり、それにメーカー側が柔軟に応えてきているのだと思います。
こういう発展の仕方を見ると、この先も選択肢はさらに増えていくだろうと予想がつきます。
最終的な判断はどうするか。
私が行き着いた考えはこうです。
ゲームプレイそのものを演出として楽しみたい人には強化ガラスが合う。
光の効果を最大限に取り込みながら一体感を得られる喜びは確かに大きいです。
一方で、部屋との調和を優先したい人には木目調がしっくりくる。
家具として並べても違和感がなく、自分の時間を静かに楽しみたい人にとっては大事な要素になります。
どちらを選んでも後悔はしない。
ただし、自分の暮らしの中で伸び伸びと過ごせるかどうか。
それが決定的な分岐点です。
実際に体験を重ねてわかったのは、ケース単独で快適さを決めるわけではないという事実です。
CPUやGPU、そしてファンの取り回し方こそがパフォーマンスを左右し、ケースはその環境を支える一要素に過ぎません。
だからこそ私は「部屋に長く置いていて気持ちが落ち着くか」を最優先にするようにしています。
それが結局、仕事や遊びを快適に続ける土台になるからです。
ゲーミングPCは単なる機械ではなく、暮らしに共にある存在。
そう感じるようになったのは、40代という年齢も関係しているのかもしれません。
安心できる選択。
共に時間を過ごす相棒。
それが私にとってのケース選びの基準であり、これからも揺らぐことはないと確信しています。
エアフロー重視のケースは初心者におすすめできるか
私が過去に何度も自作PCを組んできた中で痛感したのは、パーツの性能や見た目よりも「熱対策こそが安定運用の核心」ということです。
かつて夏場に部屋が蒸し風呂のようになり、PCが唸りを上げてゲームがカクつき始めた瞬間の焦りは今でも忘れられません。
そのとき初めて、冷却を軽視した自分の甘さに本気で後悔しました。
そうした経験から今言えることは、安心して長くPCを使いたいなら最初から冷却性能を重視することが欠かせない、ということです。
とりわけ自作初心者には、冷却環境が整ったケースが合っています。
理由は明快で、空気の流れがしっかりしていればパーツへの熱負荷が減り、長持ちするだけでなく挙動も安定するからです。
FPSのようにフレームレートの安定が勝敗に直結するようなゲームではその差は顕著に現れます。
些細な温度差が快適さを左右する。
まさにそういう世界なんです。
組み立ての最初は誰でも配線に悩みます。
私もケーブルを綺麗にまとめられず、ミスボックスを開けてはため息をついていました。
しかし、エアフロー設計が工夫されているケースなら、仮に配線が少し乱れていても自然に空気が巡るように作られている場合が多いのです。
この安心感は本当に大きく、小さな工夫が動作安定に直結すると知った時、「仕事での段取りも同じなんだよな」と自分に置き換えて頷いたのを覚えています。
効率と堅実さ、それが後の信頼につながる。
それをPC作りから学んだ瞬間でした。
思い出深いエピソードがあります。
以前、同僚からBTO構成を頼まれたとき、彼は「見た目を最優先でガラス張りにしたい」と強く希望していました。
私は正直、冷却を軽視したいかにも危ういリクエストに内心ヒヤヒヤしました。
それでも何とか説得し、前面がメッシュ構造のケースに落ち着きました。
完成後は冷却がしっかり効いて、予算を抑えた空冷クーラーでも驚くほど安定して動いたのです。
あの安心感は今も心に残っています。
逆にもし密閉傾向のケースを選んでいたら、夏には必ず「熱い、うるさい」と文句を言われていただろうと思います。
いや、本当に冷や汗でした。
ただ一方で、エアフロー重視のケースはどうしてもデザインが控えめになりがちで、キラキラした演出を楽しみたい若い人には少し物足りなく映ることもあります。
とはいえ、地味でも安定性を優先したいのが本音です。
見せるPCも悪くない。
でも、パフォーマンスが乱れるよりずっといい。
結局そこに落ち着くんですよね。
安定して動くPCと向き合っている時間の方がよほど価値があるのです。
最近はメーカー側も工夫を凝らして、デザインと冷却性能を両立した製品を増やしています。
この前、木目調のパネルを前面に備えながらもメッシュ構造で通気性を確保したケースを見かけました。
リビングにも置きやすく、家族の目にも自然に馴染む。
そういう配慮が随所に感じられ、40代の私からすると「メーカーの姿勢」が何よりありがたい心遣いに見えるのです。
あれなら堂々と家に置ける。
ちょっと嬉しいポイントでした。
長い目で見た際の利点も重要です。
例えば今の用途は軽いゲームだけでも、数年後には動画編集や重量級タイトルを遊びたくなるかもしれません。
そのとき、冷却に余裕のないケースだと、結局買い替えに迫られる羽目になります。
それは本当に無駄です。
私自身、拡張を見据えて余裕のあるケースを選んでいたことで、後にRTX5070クラスへGPUを載せ替えても問題なく使い続けられました。
未来への投資。
これこそが最初の一台に大切な視点だと強く感じています。
初心者が「大は小を兼ねる」と安直にフルタワーを選んでしまうと、意外な落とし穴にはまります。
物理的な大きさに振り回されるのです。
私も過去に調子に乗ってフルタワーを選び、机の下に収められず呆然としたことがあります。
あれは惨敗でした。
結局サイズと冷却性能のバランスを取るならミドルタワーこそ王道。
それが存外に重要なポイントなんです。
最初の一台にふさわしいのは、十分な吸気口を備えたミドルタワーです。
これであれば冷却もしっかり効くし、設置場所に悩むことも少ない。
RGB演出で派手にもできれば落ち着いたシンプルな見た目も選べます。
好みを反映しながらも「冷却」と「扱いやすさ」の両立を考える。
この2点を押さえるだけで、初心者の失敗は格段に減るのです。
そして最終的に断言できるのは、エアフローに配慮したケースは無駄のない投資だということです。
Valorantのようなライトなゲームでも、安定したfpsこそが快適なプレイを支えるものですし、見た目ばかりに引きずられて熱に悩むより、冷却を基盤に据える方が圧倒的に気持ちが楽になります。
心の余裕。
だからこそ私は声を大にして言いたいのです。
最初に冷却環境を整える。
それが、長く自作PCを楽しむための一番確かな近道です。
経験を重ねた今、胸を張ってそう言えます。
些細な後悔を繰り返すより、一歩早く先手を打つ。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FD


| 【ZEFT R60FD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67A


| 【ZEFT R67A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67E


| 【ZEFT R67E スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62O


| 【ZEFT R62O スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CB


| 【ZEFT R60CB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
RGB付きケースで見た目と実用性を両立させるコツ
RGB付きのケースを選ぶときに私が強く意識しているのは、見た目の華やかさと冷却性能の両立です。
正直に言えば、派手に光らせて「自分の城だ」と満足したい気持ちは誰にだってあると思います。
私も若い頃は「どうせ組むなら光らせなきゃ」と勢いで考えていた時期が確かにありました。
ただ、一度でもファンの騒音にイライラしたり、ゲーム中に急にフレームレートが落ちて集中を削がれたりした経験をすると、考えはガラリと変わるものです。
だから結局は派手さより安定性が大事だと学ぶことになるんです。
私が痛感したのは数年前の出来事です。
静音性を意識して選んだCPUクーラーも電源も、すべて水の泡になった気分でした。
そのときに強く胸に刻まれたのは「光を演出するときは必ず風の流れと一緒に考えなきゃダメだ」というシンプルだけど重要な真理でした。
あの失敗以降、私は必ずデザインの前にエアフローを確認する癖を身につけました。
これは失敗からしか学べない教訓ですね。
エアフローを確保したうえでRGBを魅せるのは、思った以上に効果的です。
フロントから冷たい空気を吸い込み、トップや背面から排気する。
最近のマザーボードには専用のソフトウェアがあって、照明の同期も簡単にできるので、一体感のある美しさが実現できます。
初めて統一ライティングを完成させたとき、思わず「これは見事だ」と声が出てしまいました。
いや、本当に感動するものです。
ただし光の演出は、加減を誤ると家族からのクレームを招きます。
実際に妻から「まるで家がクラブみたいで落ち着かない」と文句を言われたことがあります。
あのときは苦笑いするしかなかったですね。
そんな経験を経て学んだのが、ARGBに対応したケースで光を柔らかくして雰囲気を整える方法でした。
控えめに設定すれば書斎にもしっくりと馴染むし、仕事部屋にも違和感がない。
本当に大人の遊びとしてちょうどいいさじ加減なんです。
遊びの中にも品を持たせる、それが我々世代の楽しみ方だと思います。
さらに印象に残っているのは、会社のLANパーティでの出来事です。
同僚がチームカラーに合わせてRGBを調整していて、会場中が盛り上がったんです。
まるで照明演出のある舞台装置のようになり、ただのケースが空気を変える存在へと化けた瞬間でした。
その場にいた全員が「これがRGBの力か」と感じたと思います。
光は自己満足で終わらず、周りを巻き込めるものなんだと改めて思いました。
もちろん、ケースで忘れてはいけないのは配線整理です。
裏配線がごちゃついていると、いくら外側を華やかに演出しても台無しになりますし、エアフローを阻害して温度管理まで悪化します。
私も以前はケーブルを面倒くさがって適当に収納し、その結果として熱暴走させてしまったことがあります。
ところが一念発起してケーブルを徹底的に束ね直した結果、ケース内がすっきりと整って気持ちまで晴れやかになったんです。
安定性。
落ち着き。
この二つを大切にした上でRGBを演出するのが理想だと私は思います。
Valorantのように軽めのゲームでさえ、通気の悪いケースではパフォーマンスが乱れることが十分にあり得ます。
結局のところケースは基盤であり土台です。
光で遊ぶ楽しみを十分に味わうためにこそ、冷却性能を軽視すべきではありません。
特に配信や動画制作などで「見せる」使い方をする人にとっては、RGBケースはまさに武器にもなる存在です。
見栄えを軽く扱うと損をしますよ、と声を大にして言いたいです。
最終的にまとめるなら肝は二つです。
二つ目は「冷却性能を犠牲にしない設計を選ぶこと」。
なぜなら、大人になると時間は本当に大切だからです。
限られた休みの中で、ストレスなく快適に遊びたい。
その横で、自分のPCを眺めたときに思わず誇らしい気持ちになれる。
その瞬間が今の私にとって最高のご褒美なのだと実感しています。
色と光は自己表現の一つです。
でも日常の中で邪魔に感じてしまうようでは台無しです。
使う人の目的と生活の環境に合わせて、ちょうどよい光り方を探すことが大事だと私は思います。
そしてそこに少しだけ遊び心を加えて、必要な整理も怠らない。
Valorant 用ゲーミングPC構築でよくある疑問と答え
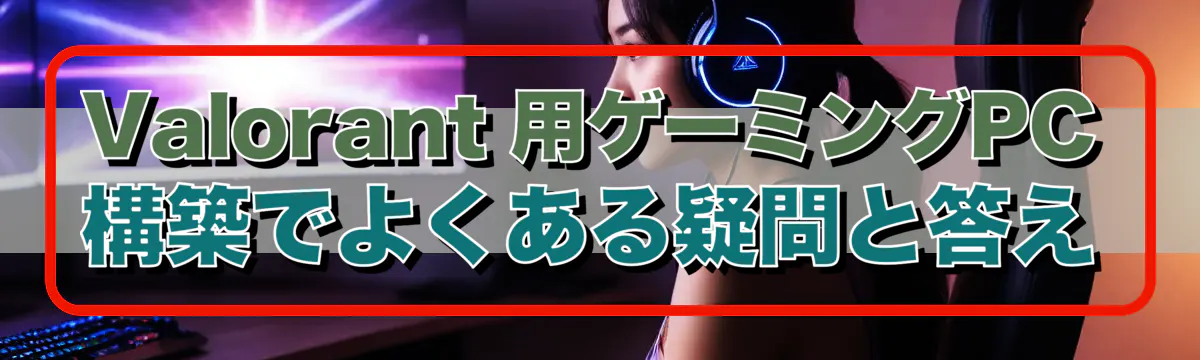
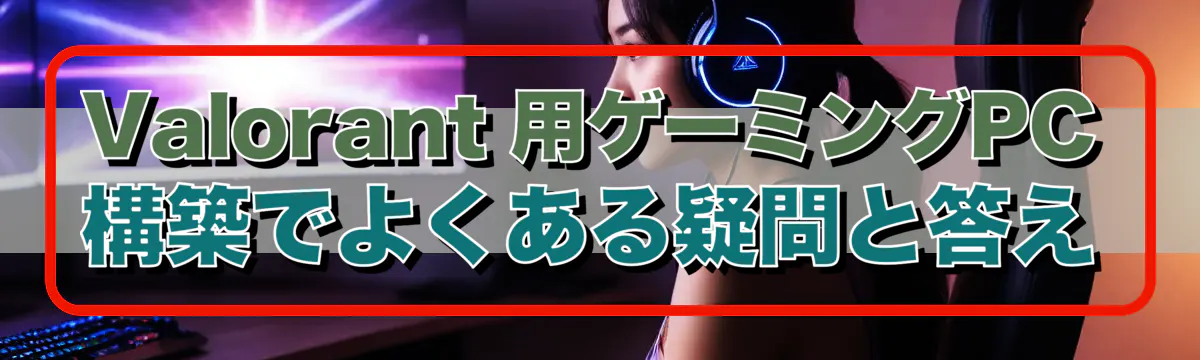
FortniteやApexも同じ構成で快適に動くのか
ただ、Valorantで快適だったからといって、そのまま同じ感覚を持ち込むのは危険だと私は身をもって知りました。
特にGPUやメモリで数年後の使い心地に雲泥の差が出るため、初期投資の重みを実感させられます。
Fortniteを初めて触ったとき、私は正直ショックを受けました。
Unreal Engine 5の映像は本当に綺麗で感動したんです。
ただ、設定を最高にするとミドルクラスのGPUが悲鳴をあげ、フレームレートの落ち込み方に「え、ここまで下がるのかよ」と頭を抱えました。
思っていた以上の負荷に完全にやられた気分でしたね。
ApexはApexで違った意味で手強い相手でした。
マップの広さからCPUとGPUの両方に負担がかかるので、片側だけ性能が良くてもダメなんです。
私は「CPUに余裕があるから大丈夫だろう」とたかをくくっていましたが、甘かった。
動きの重さにストレスを感じながら、「バランスこそ命」という当たり前を痛感しました。
ある時、Core Ultra 7 265KとGeForce RTX 5070を組み合わせて遊んでいたんですが、Valorantでは平均250fpsくらい出ていて最高でした。
でもFortniteを最高設定にした瞬間、フレームが140fps前後に落ちて「競技プレイどころじゃないな」とつぶやきました。
Apexでは中画質にすれば170fpsくらいで何とか遊べたものの、Valorantの軽快さを知ってしまった後だと、あのスムーズさを同じように求めるのは難しいのだなと、無念さが残りました。
改めて思うのは、結局どのレベルで「快適」と感じたいのかがすごく重要だということです。
ValorantはCPU性能さえ確保できれば驚くほど軽く楽しめるので、ある意味で「油断しやすいゲーム」と言えます。
でもFortniteやApexはGPUの性能がすべてを左右します。
私は一度、価格を重視して妥協した結果、数か月後に「また組み直しか…」と頭を抱えたことがありました。
メモリの容量も侮れません。
Valorantなら16GBで十分なんですが、ApexやFortniteを遊びながら裏で配信ソフトやブラウザを複数立ち上げていると、一気に心もとない。
私はしばらく16GBのまま粘っていましたが、ゲーム中にカクつきが発生して「またかよ…」と苦い顔を何度もしました。
32GBに換装してからは別世界の快適さ。
ようやくイライラから解放されて、胸をなでおろしました。
ストレージも頭の痛い問題でしたね。
Fortniteのアップデートはとにかく大きくて、かつて500GBのSSDでやりくりしていた私は、数か月ごとに空き容量不足でゲームを消したり再インストールしたりを繰り返し、心底うんざりしていました。
「またアンインストールかよ」とため息をつくことが通常運転でした。
最終的に2TBのNVMe SSDに組み替えたときの解放感は、正直忘れられません。
「これでようやく落ち着ける」そんな安心感がようやく訪れました。
夏場の冷却対策にも泣かされた思い出があります。
Valorantくらいならそこまで熱の心配はいらなかったのですが、Apexを長時間フルパフォーマンスで遊ぶとGPU温度が80度近くまで上がり、ファンが烈しく回って「爆音」としか言いようのない状態に陥りました。
「このままじゃ壊れるかもしれない」と不安になり、ケースごと買い替えました。
風の通りを意識して吸気と排気を見直したことで、温度が安定してフレーム落ちも減ったときは「やっぱり投資してよかった」と心底思いました。
こうして振り返ると、どうしてもGPUだけに注目が集まりがちですが、実際はCPU・メモリ・ストレージ・冷却・電源・ケース、全部が支え合うことでようやく環境が整うんです。
どれか一つでも抜ければ、それがはっきりと弱点になる。
私は身をもってそれを学びました。
Valorantの軽さに惑わされず、FortniteやApexを基準にして1ランク上の部品を選んでおくことで、長期的に満足できる環境が整うと確信しています。
最後に率直な思いを残します。
Valorantを動かせるPCなら確かにFortniteもApexも楽しめます。
ただ、それを同じ質で味わうならGPUやメモリの底上げ、冷却やストレージの余裕が必要不可欠です。
無理のない範囲で少し先を見越して組むこと。
これが後悔のないゲーミングPCづくりの秘訣だと私は考えています。
安心感。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
高fpsを狙うならどのパーツに優先して予算を回すべきか
その理由は、Valorantのように描画負荷がそこまで重くないゲームでは、GPUだけを強化してもCPUが追いつかず、フレームレートが伸び悩んでしまうからです。
グラフィックボードはそこそこ性能があるのに、古いCPUのせいで撃ち合いの瞬間に画面が一呼吸遅れる。
あの違和感にイライラして、思わず深いため息をついたことを今でも覚えています。
その短い一瞬に何度もやられたあの日々、あれはトラウマに近い経験です。
とはいえ、GPUの存在を軽んじて良いわけでもありません。
Valorantは軽い方だと言われますが、200fps以上を安定させたいなら、やはりミドルレンジ以上のカードが欲しくなるところです。
体がスッと軽くなるような、そんな安堵の感覚でした。
240Hzモニターと併せて使うと「今度こそ思う存分やれる」という余裕が生まれました。
そう実感しました。
そして、見落としがちな要素がメモリです。
正直、8GBでは全然足りません。
敵が迫ってくる場面で一瞬カクついたときのストレスといったら本当に言葉になりません。
その後32GBにしたときは、肩の力が抜けるような解放感がありました。
性能以上に「これなら安心してプレイできる」という精神的な余白を得たのが大きかったと思います。
安心感があるかどうか。
結局そこなんです。
ストレージも忘れてはいけません。
フレームレートには直結しないものの、快適さを維持するには欠かせない基盤です。
昔500GBのSSDを使っていた頃は、アップデートのたびに容量不足と格闘し、別のゲームを削除させられる日々でした。
正直、毎回ため息でしたね。
Valorant用途なら明らかにオーバースペックでした。
机上の理想より、実用性と安心のバランスを優先する方が私には合っています。
冷却の問題も重要です。
どれだけ性能の良いCPUを使っても、冷却がおろそかでは意味がありません。
若い頃は水冷を夢見て導入したこともあります。
ただ、実際に長期間使ってみると、メンテナンスの手間や不安の方が大きくなりました。
今は静音性と手軽さを兼ね備えた空冷クーラーに落ち着いていますが、これが大正解です。
ケース選びも同じで、強化ガラスで飾りつけたい気持ちは残りつつ、効率的なエアフローを両立した製品を重視するようになりました。
派手さより堅実さ、そんな心境の変化でしょうか。
冷却をきちんと整えないと「せっかく高いパーツを買ったのに本領を出せない」という後悔に直面します。
だから冷却は決して軽視できません。
要です。
私が繰り返しPCを構築してきた経験から、優先度ははっきりしています。
CPUを中心に投資し、次にGPU、そしてメモリ。
最後にSSDと冷却を整えて全体の安定性を確実にする。
これが最も費用対効果の高い配分です。
結局、CPUを軸に考えれば、その他のパーツ選びは自然と方向性が見えてきます。
心配や迷いから解き放たれる感覚さえあります。
40代になった今、改めて振り返ると一番身に染みるのは「妥協して買い直すことほど無駄が多い」という現実です。
どうしても目先の予算で抑えたくなる気持ちはあります。
しかし、そこで妥協すると買い直す羽目になり、結局コストも時間も倍増します。
ならば最初から腹を決めて余裕のあるCPUを選ぶ方が、長期的な安心につながるのです。
妥協は敵。
勝つための準備とは、突き詰めればこうした細かい部分の積み重ねなのだと、年齢を重ねてこそ理解できるようになった気がします。
大事なのは、CPUを中心にした堅実な構成。
それこそが答えです。
準備次第。
積み重ね。
自分が安心して戦える環境を揃え、余計な不安を排除する。
自作とBTO、初心者が選ぶならどちらが安心か
Valorantを快適に遊ぶためにPCを選ぶのであれば、私が強くお勧めしたいのはBTOパソコンです。
正直に言えば、自作PCを楽しむ気持ちはよく分かりますし、私自身も昔は時間を割いて毎週のように秋葉原へ足を運んでいた時期があります。
でも、今は家庭や仕事の両立に追われ、そうした余裕は少なくなりました。
限られた時間をどう使うか。
そこで私がたどり着いた結論がBTOです。
私がそう思う最大の理由は、購入してすぐに安定した環境でプレイができることです。
FPSのようなゲームにおいては、一瞬の判断が勝敗を大きく左右します。
ほんの小さなラグや不安定さが致命傷になることだってあります。
以前、深夜の試合でラグが出た瞬間、大事な勝負を落として悔しさのあまり椅子を蹴り飛ばしたこともありました。
あのときの情けなさと怒りは今でも鮮明に覚えています。
だからこそ、不安要素を取り除けるBTOの安心感は大きいのです。
もちろん、自作PCには自作ならではの魅力があります。
理想のケースを探し、配線を工夫して美しく仕上げて、冷却効率を試行錯誤するあの過程は、プラモデルを夢中で組み立てていた学生時代を思い出させてくれるものでした。
完成した瞬間の「やったな」という達成感は格別です。
しかし、初心者にとっては電源は入るのに画面が映らないとか、メモリの相性で何度もブルースクリーンになるなどの細かいトラブルに直面することも多い。
そうなれば休日にリフレッシュするつもりが、気づけば一日中不具合に悩まされて気持ちがすり減ってしまう。
私は昔、「もういい加減にしてくれ」とつぶやきながら夜中にマザーボードを見つめていたことだってあります。
BTOの良さは、そうした不安や余計な苦労を、最初から回避できる点にあるとつくづく感じます。
人気のあるモデルは組み合わせが安定しており、販売店側も動作検証を済ませている。
短時間で結果が欲しいときにこれほど頼れる選択肢はありません。
届いたその日に問題なく動き、焦りや不安が一気に吹き飛んだあの感覚は今も忘れられません。
かといって、自作を否定するつもりはありません。
店頭でピカピカのケースに目を奪われたり、低騒音ファンや大型クーラーを吟味して性能を突き詰めたりするときの楽しさは格別です。
温度を思った通りに下げられたとき、思わず「よっしゃ!」と声が漏れてしまう喜びは自作ならではです。
ただし、Valorantを快適に遊びたいという目的だけであれば、正直そこまで手間をかけなくてもBTOで十分です。
実際に、現代のBTO構成は驚くほどバランスが取れています。
例えばCore Ultra 5やRyzen 7クラスのCPU、そしてRTX 4060TiやRX 7600XTなどのGPUを組み合わせたモデルなら、144Hzや240Hzといった高リフレッシュレートもしっかり支えられます。
メモリは16GB以上、ストレージは1TBクラスのSSDを選べばロード時間も短く、ゲームのテンポを壊されることはほとんどありません。
この構成で十分。
お店の経験とノウハウが反映されているため、自作で陥りがちなアンバランスな構成になりにくい点も魅力です。
一番重要なのは性能の芯を外さないことです。
BTOであればその部分を販売店が理解して最適化してくれるため、初心者にとっては最短距離で安心を得られるのです。
かつて私のBTO機で冷却ファンから異音が出たときには、すぐに相談窓口に連絡するだけで新品と取り替えてもらえました。
その時味わったのは心からの安堵でした。
正直なところ、若かりし頃の私は完全な自作派でした。
だからこそ、無駄なトラブルに時間を奪われることなく、安定して遊べる環境を持てるBTOは、私にとって今の生活にぴったりの選択でした。
安心感と効率性、その両方を兼ね備えているからです。
届いたその日に電源を入れ、すぐにプレイが始められる環境があるだけで十分に価値があります。
余計なことに邪魔されず、ただ純粋にゲームを楽しむことができる。
そしてもし時間や気持ちに余裕ができたときに、自作という世界に挑戦してみればいい。
そのときに築いた一台は、きっと自分だけの特別な存在になるはずです。
だから私は声を大にして言います。
最初の選択は、とにかくBTOで間違いない。