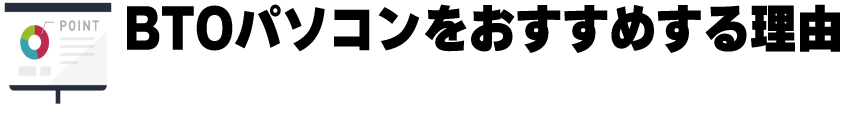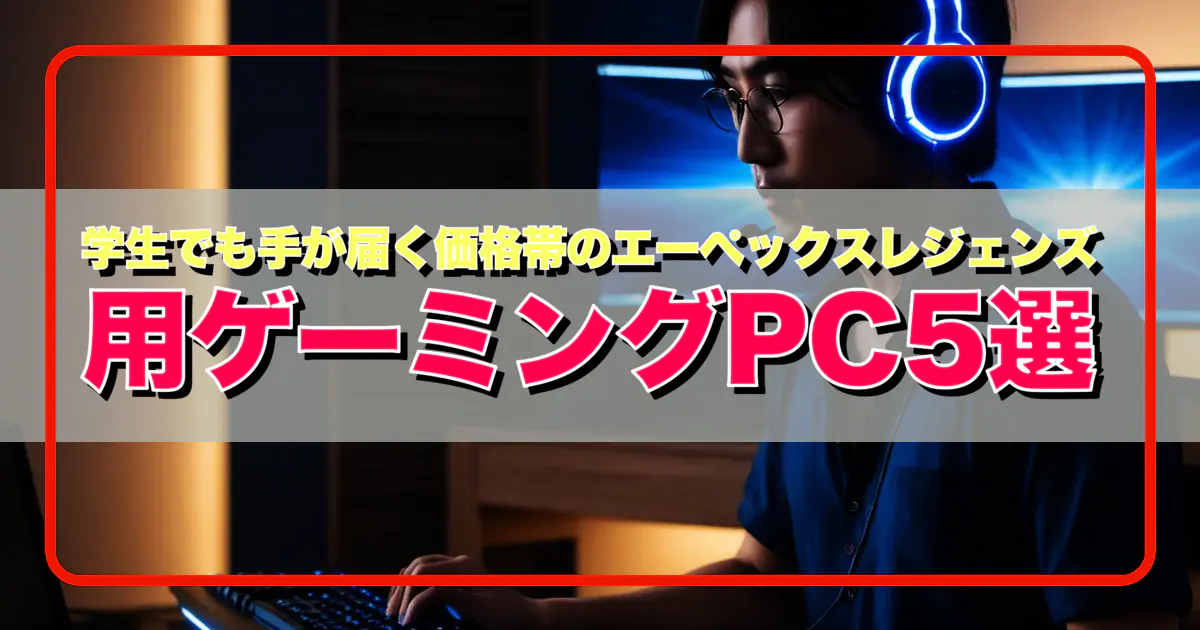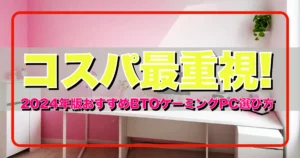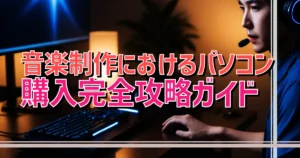学生向けに考えるApex Legends用ゲーミングPCの選び方
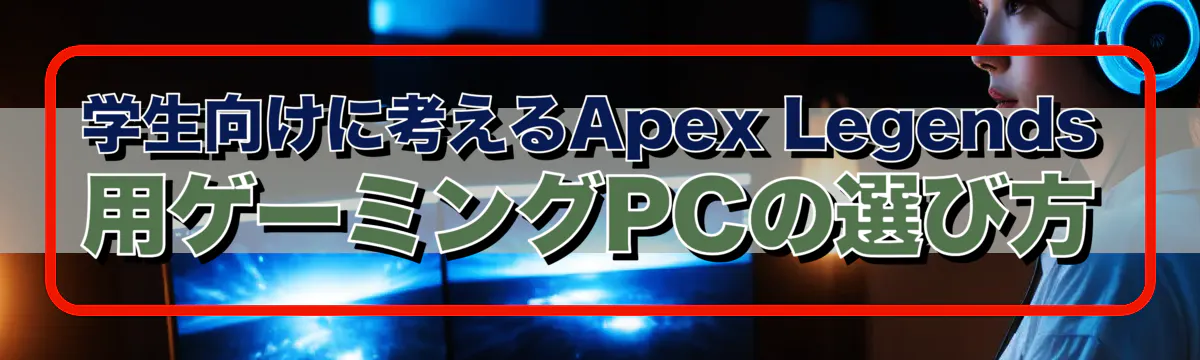
フルHDで快適に遊ぶために必要なスペックはどのあたり?
フルHD環境でApex Legendsを快適に楽しむために大切なのは、スペックをやみくもに高いところに振るのではなく、自分がどんな遊び方をしたいのかを見極めてバランスを取ることだと思います。
私はこれまで数台のゲーミングPCを自分のためにも友人のためにも検討してきましたが、やはり最後に満足感を決めるのは派手な性能表ではなく、実際に毎日安心して動いてくれる安定感なのです。
一瞬のカクつきや処理落ちが勝敗を左右するApexでは、それこそ命取りになるという場面を何度も見てきましたし、そういうとき「あぁ、やっぱり構成の選び方が全てだ」と感じることが少なくありません。
最初に考えるべきはGPUです。
ここでケチると後で必ず後悔します。
RTX5060Tiクラス以上であれば、フルHDの環境で144fpsはしっかり出ますし、設定を絞れば200fpsあたりまで伸びる。
それならほとんどのユーザーが快適に遊べるレベルになります。
私は以前、友人のPCで実際にその組み合わせを触ったとき、思わず「これなら文句の出ようがないな」と声に出してしまいました。
Radeon派の方ならRX9060XTクラスが同等の選択肢で、価格を少し抑えたいという学生さんにも本当にちょうどいい。
華やかで高価なモデルではなく、身の丈に合ったモデルを選ぶことが長期的には一番満足度が高い、とこれは胸を張って伝えたいところです。
安さに魅かれるのは自然なことです。
私も同じ失敗をしたことがあります。
その経験があるからこそ、しっかり動くクラスを選ぶことが一番の近道だと強調したいのです。
CPUについては少し肩の力を抜いて考えて大丈夫です。
Core Ultra 5やRyzen 5の現行世代で十分。
上位のCore Ultra 7やRyzen 7を選んだとしても、フルHDに限れば劇的な変化はほぼない。
もちろん余裕があればそれはそれで安心ですが、「ここに無理して投資するのはもったいない」と私は率直に思います。
メモリに関しても、16GBで動作自体は問題ありません。
ただし私は配信をしながらプレイする学生を何人も見て、16GBでは動画ソフトとゲームを並行した瞬間にぎりぎりになる様子を目の当たりにしました。
だから今の時代、32GBを積んでおいた方が安全策です。
正直に言えば私も32GB環境ですが、録画やマルチタスクで「ああ、助かった」と感じた場面が何度もありました。
余裕とは決して無駄な贅沢ではなく、安心を買うための保険です。
ストレージに関しては最低でも1TBのNVMe SSDをと強く言いたい。
500GBモデルを使っていた頃、アップデートのたびに容量がパンパンになり、その度に「どれを消すかな」と悩むストレスを抱えていました。
私はそういう時間が本当にもったいないと痛感しました。
ゲームをする時間を気持ちよく過ごすために、最初から余裕を持った容量を選んでおくこと。
これ以上に効率的な投資はありません。
冷却とケースも軽く見てはいけません。
最近のCPUは発熱が抑えられているので、トップクラスの空冷を使えば十分だと私は考えています。
私自身も水冷を導入したことがありましたが、メンテナンスも手間ですし結局トラブルで泣いたこともあります。
その後、静音性の高い空冷に切り替えたときの快適さと安心感は想像以上でした。
ケースについてはデザイン性に誘惑されがちですが、エアフローを軽視するとプレイ中の安定性が一気に崩れる。
だから今の私は「見栄えよりも実用を優先すべし」と強く言います。
144Hzモニターで実際に200fps前後をキープしたその快適さに驚き、思わず「これでこの価格なら十分どころかお得すぎだ」と本音が出ました。
こうして体験してみると、ゲームに集中できる環境がいかに重要か改めて実感します。
最終的に私が勧めたい構成は明確です。
GPUはRTX5060TiかRadeon RX9060XT、CPUはCore Ultra 5かRyzen 5、メモリは32GB、ストレージは1TBのNVMe SSD、冷却は扱いやすい空冷。
これがフルHDでApexを存分に楽しむための現実的で安心できるスタンダードです。
学生でもギリギリ無理なく手の届く範囲で、しかも安心して長く使える構成。
必要な部分にはきちんと投資し、それ以外は無駄をそぎ落とす。
そのバランス感こそが結局一番後悔のない選び方につながります。
だから断言します。
見た目の派手さよりも信頼できるバランスを。
余計な不安を抱えることなく、長く気持ちよく遊べる環境を選ぶことこそが、Apex Legendsを本当の意味で楽しむための近道です。
安心感。
これこそ大事なのです。
CPUはCoreシリーズとRyzen、使いやすさに違いはある?
インテルのCoreシリーズとAMDのRyzenシリーズ、どちらも現行の中位クラスを選べばApex Legendsのようなゲームは十分快適に遊べます。
にもかかわらず、多くの人が悩んでしまうのは、将来の拡張性や安心感、ちょっとした使い勝手の差に目が行ってしまうからだと私は感じています。
そうした細部の違いこそが、40代の私にとっては案外大きな要素になるのです。
私は昔からインテルのCoreシリーズを長く使ってきたので、ドライバやソフトの相性で困った経験が少なく、そこに信頼を置いています。
特に仕事用の資料作成やオンライン会議、そして休日のゲームをすべて一台で済ませたいと考えると、トラブルに巻き込まれにくい安心感がとても大切です。
若い頃は多少の不具合も「まあ仕方ない」と笑って乗り越えてきましたが、今はその時間すら惜しく感じてしまう。
だからこそ、心の支えになるのはインテルの安定感なのです。
一方でRyzenシリーズの魅力は明確です。
少し同じ価格帯で比較しても、処理能力の余裕や遊びの幅が出やすく、実際にゲーム中のフレームレートの安定性に驚かされることすらあります。
例えばApexを長時間プレイするとき、映像が安定したままで落ち込みが少ない瞬間に「これがRyzenか」と心の中でつぶやいてしまう。
あれは数字で測れない満足感ですね。
ApexのようにCPU負荷がそこまで高くないゲームでは、Core Ultra 5とRyzen 5を横並びで比較しても、劇的な違いを感じるのは難しいのが実際のところです。
結局大事になるのは「将来、自分がどんな作業をそのPCでしたいか」という一点です。
動画配信や編集をやる予定がある方は、IntelのAI処理対応やエンコードの速さにメリットを感じるでしょう。
状況次第です。
私の知人でCore Ultra 7を選んだ人がいます。
Apexと動画編集を両立させたいという理由からの選択だったのですが、初めて動画をエンコードした時に「こんなに早いのか!」と笑顔で叫んでいました。
その姿を見た時は、こちらまで思わず嬉しくなってしまいましたね。
フルHDで240Hzを維持する環境に浸った時など、「これは自分に合っている」と実感しました。
こうした体験は机上のスペック比較よりもずっと心に残ります。
今の市場を冷静に見渡すと、昔のように「Intel=安定」「AMD=挑戦」という図式は通用しません。
それはすでに過去の話です。
いずれも十分に成熟した製品で、日常的に使う中で大きな違和感を覚えることはまずありません。
BIOSの調整もほんのわずかで済むようになり、今やユーザーにとってもありがたい状況です。
だからこそ選び方の基準はシンプルで「自分は性能のどこに重点を置きたいか」だけです。
学生さんからゲーミングPCの相談を受けたこともありますが、Apexを快適に遊ぶだけなら中位クラスのCPUで十分です。
Ryzen 5 9600やCore Ultra 5 235クラスを選べばプレイに困ることはほぼありません。
多くのケースではCPUより先にGPUが性能的な限界に達して買い替えになるので、CPUに過剰投資するよりはGPUに予算を振り分けた方が現実的です。
要するに大事なのはバランスだと断言できます。
多少性能に余裕があると安心なのは分かりますが、その余裕が実際に生活にどれだけ価値をもたらすのかを冷静に考える必要があります。
どちらのCPUを選んでも現行ミドルクラスならまず困りません。
だから最後に頼りになるのは「自分が何を優先したいか」というシンプルな問いです。
私はそう思います。
CPUに悩むより、自分が日常で求めている体験をイメージしてみる。
その体験を後押ししてくれる選択ができた時、納得感が得られます。
安心感と満足感。
この二つを得られる選び方こそが最終的には正解なのだと、私は40代になってようやく理解しました。
ゲームを楽しむだけならどちらを選んでも十分。
ただし一歩先に踏み込むなら、自分のやりたいことに合わせてCPUを選んでみる。
その程度のシンプルな考えでいいのです。
だから声を大にして言います。
CPU選びで必要以上に悩まなくても大丈夫。
自分に一番合った体験を支えてくれるものを素直に選んで、それで満足してしまえばいいんです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43437 | 2442 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43188 | 2247 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42211 | 2238 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38943 | 2058 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38866 | 2030 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35977 | 2177 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33203 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32721 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29522 | 2021 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 2155 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23298 | 2192 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23286 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 21046 | 1842 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19684 | 1919 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17893 | 1799 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15428 | 1963 | 公式 | 価格 |
快適プレイに必要なメモリ容量の基準
エーペックスレジェンズを快適に遊びたいなら、メモリへの投資こそが一番効果的だと私は考えています。
しかし本当にストレスなく楽しみたいなら、やはり32GBがベストです。
これは私が身をもって学んだことです。
昔の私は「16GBで十分だろう」と軽く考えていました。
本音を言えば、32GBなんて大げさだと思っていたんです。
タスクマネージャーをのぞくとメモリ使用率は常に90%超え。
余裕のなさを突きつけられて、愕然としましたね。
そして思い切って32GBに増設してみると……驚くくらい滑らかに動き出した。
あのときの感動、今でも忘れられません。
やっぱり安定第一。
最新GPUや高性能CPUを積んでも、支えるメモリが細いと本来の力は発揮できません。
車で言えば、立派なエンジンを載せているのにタイヤが貧弱でまともに走れないようなものです。
見落とされがちだけれど大切な存在、それがメモリなんです。
学生や若手社会人がゲーミングPCを選ぶときも同じです。
さらに余裕があるなら32GBにしておいた方が、中期的な満足度が大きく変わります。
「後から増設できる」と思うかもしれませんが、その間はシングルチャネルで効率の悪い状態を我慢することになる可能性が高い。
だからこそ最初から16GB×2の構成にしておけば、気持ちよく使い始められるんです。
最近はただ遊ぶだけじゃありません。
配信をしたり、動画を録画してSNSに投稿したりするのが当たり前になっています。
録画ソフトを立ち上げて、VCで仲間と話しながら、同時にブラウザで攻略記事を開いたりする。
その瞬間、あっという間にメモリは埋まりきってしまいます。
16GBの壁は案外すぐにやってきて、プレイ中に映像がカクついて「せっかくいいシーンだったのに…」と頭を抱えたことも多い。
その悔しさを知っているからこそ、私は32GBを推すんです。
仕事柄、若い社員や後輩からPC購入の相談を受けることがよくあります。
彼らは「コストは抑えたいけれど、動画編集や配信もしたい」と口をそろえる。
そういうとき、私は必ず「将来の後悔を避けるために32GBにしておいた方が気持ちが楽だぞ」と伝えています。
パソコンは毎日使う仕事道具であり、同時に大切な遊び相手でもあります。
妥協してイライラを募らせるより、安心して使える環境を最初に整えることが、結局一番効率的なんです。
今のBTO市場を見ても、DDR5-5600あたりが主流で搭載されています。
正直、クロックや規格による差を肌で感じる場面は多くない。
安心感ってこういう積み重ねで生まれていくものだと思います。
スペック表よりも、毎日使い続けてストレスにならないことが最優先だと私は強く感じますね。
余裕。
CPUやGPUだけではなく、メモリへの負荷もじわじわ上がっていく流れは止められません。
SNSや動画配信という文化が根付いた今、32GBを前提とした環境を整えておく方が長期的な費用対効果も高い。
いずれ「ちょっと余ってるくらいでちょうどいい」時代になるでしょう。
私はそう確信しています。
私の一番の教訓は、妥協して後悔するより安心を先に買う方が絶対にいい、ということです。
せっかくゲームをするのなら、「なんでこんなにカクつくんだ」と不満を抱く時間なんて無駄でしかない。
必要な環境を整えることは、自分の時間と気持ちを守る投資にほかならないんです。
結局のところ、16GBは最低限。
これは間違いのない選択だと、胸を張って言えます。
予算を抑えつつ楽しめるApex Legends向けPCの選び方

RTX 3060 Tiクラスのグラボは学生にちょうどいい性能?
RTX4060 TiクラスのGPUは、学生にとって現実的かつ後悔しにくい選択肢だと私は思います。
高すぎるハイエンドモデルを狙えば財布に大打撃ですし、逆に安さだけで飛びつけば数ヶ月先には動作に不満が出てしまう。
結局、心から納得できるのは性能と価格の釣り合いが取れているこのラインなのだと実感しています。
思い返せば20代の頃、アルバイト代をかき集めて初めて自作PCを組んだとき、私は価格にだけ目を奪われた結果、性能不足のGPUを選んでしまいました。
ゲームを始めても敵を見つけた瞬間に画面がカクつき、反応しきれないまま倒される。
モニタの前で何度も悔しさをかみ締めました。
その経験があったからこそ、今にして思えば「多少の余裕を持った構成が結局は一番お得だ」ということに気付けたんです。
フルHD環境で144fps前後を安定して出せるというのは本当に大きな意味があります。
学生の多くにとってはこれが快適さのボーダーラインであり、突き詰めすぎなければ十分満足できる水準です。
もちろん「もっと上」を追い求めれば果てしない世界が広がっていますが、日常的に遊ぶ環境で過不足なく安定して動いてくれることこそが肝心。
私は過去に冷静さを欠いて高性能モデルを手にしたこともありましたが、いざ普段のプレイ環境に戻ると、その超性能を発揮する場面はほとんどなかったんですよ。
なんだったんだ、あの投資は。
3060 Tiの価格帯は学生にも比較的手が届きやすいという点で光ります。
最新世代のRTX 50シリーズやハイエンドRadeonと比べると負担が抑えられるのに、まだまだ性能に余裕がある。
中古市場やBTOパソコンの構成にもうまく混ざり込んでいるため、工夫次第でさらに手頃に入手できるのも現実的です。
その分浮いたお金をモニタやマウス、キーボードに回した方が結果的に満足度が高くなる。
そして忘れてはいけないのが、アップデートに耐えうる余裕です。
Apexはサービス開始から現在まで何度も改修と調整が繰り返され、そのたびに少しずつ要求スペックが上がってきた歴史があります。
性能ギリギリのGPUを選ぶと、次のパッチで泣く羽目になる。
つまり描画を一段階落とし、「せっかくの映像美を犠牲にする」選択を強いられるんです。
その点、3060 Tiクラスなら高めの設定でも余裕があり、半年や一年で不満を感じない見通しが持てる。
これは精神的にも安心です。
安定感。
もちろん弱点もあります。
4Kで120fpsを目指したいときには力不足ですし、プロや配信者が使うような最高峰の環境と比べれば一歩も二歩も劣ります。
でも学生にとってそれが本当に必要かと問われれば、大半の人はそうではないでしょう。
大切なのは手持ち資金の中でどこに線を引くかを考えること。
その答えとして3060 Tiは「背伸びしすぎない手ごろな選択肢」と言えるのです。
最近はeスポーツの大会配信やプロ選手の環境を見ることで、夢を膨らませる若い人も多いと思います。
ただ、スポンサーやサポートのある彼らの環境を自分たちですぐに真似しようとするのは無理があります。
限られた予算の中で最大限に快適な構成を探すのが現実的な道です。
そのとき、性能とコストのバランスに優れた3060 Tiこそが最適な落としどころだと私は信じています。
実は私は一度、高額なハイエンドGPUに手を出してしまったことがあります。
買った瞬間は満足感にひたれましたが、結局プレイの大半はApexのランク戦。
要求されるのは144fps前後での安定性で、それ以上の性能を発揮させる場面は本当に少なかった。
数字は確かに誇らしいのですが、実用面では持て余してしまうんですよね。
その時思いました。
人間の欲にはキリがないんだ、と。
だからこそ、声を大にして言いたいです。
高すぎず、安すぎず、それでいて求められる快適さをしっかり支える。
大げさかもしれませんが、「ちょうどいい」という言葉がこれほど似合うGPUもそう多くはありません。
限られた資金を後悔なく使うための、優れた投資先であると私は確信しています。
迷ったら3060 Ti。
学生にこそ胸を張ってそう勧めます。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49113 | 100929 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32430 | 77302 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30414 | 66101 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27399 | 68249 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26736 | 59644 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22140 | 56240 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16704 | 38983 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16133 | 37823 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15994 | 37602 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14766 | 34575 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13862 | 30555 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13317 | 32041 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 6700 XTを選ぶときに気をつけたいポイント
Apex Legendsを遊ぶという目的で考えたとき、Radeon RX 7700 XTは確かに「悪くない相棒だな」と思えるグラフィックボードだと感じています。
価格と性能のバランスが優れているので、特にWQHDや144Hzモニターを前提にゲームを楽しみたい人なら、十分に満足のいく体験を得られるでしょう。
今を楽しむ分には安心できても、未来志向で考えたときに少し心配になる存在です。
私が最初に気にしたのはVRAMの容量でした。
12GBという数字は表向き余裕がありそうに見えますが、実際に高解像度のテクスチャを優先する設定でAAAタイトルを動かしてみると、思ったより早く頭打ちを感じる場面が出てきます。
Apex Legends程度の軽快なタイトルなら大きな問題はありませんが、最新の重量級ゲームを視野に入れると、数年後に物足りなく感じる可能性は否めません。
この「今はいいけど先は不安」という感覚、正直に言えば、私自身も手に取って確かめたときに強く抱いた印象です。
未来を見据えて選ぶ人ほど引っかかる部分だと思います。
熱と消費電力の問題も見逃せません。
夏場に長時間ゲームをしていると、PCケース内部に熱がこもり、じわじわと体感温度まで上がる瞬間があります。
正直に言うと、夢中でプレイしている最中に急にファンの音が唸り始めると、冷静に戻されるというか、なんだか白けた気持ちになるんですよね。
冷却に関してはエアフローの確保や空冷クーラーの選択を軽んじないこと。
逆にここをおろそかにすると、熱でクロックが落ちて動作がぎこちなくなったり、耳障りな騒音で集中力を削がれるなんて事態に直面します。
経験者として胸を張って言えるのは、快適かどうかの境界線がこの部分で決まってしまうという現実です。
次にドライバですが、ここは注意が必要です。
AMD製GPUを長く使ってきた私としても、何度か苦い思いをしています。
あるアップデートを適用したら、影の描画が急に不安定になって動きがカクつき、修正版を待つしかないという状況に陥ったことがありました。
自分の環境で問題がなくても他人が同じ環境で困るケースもあり、トラブル回避が難しい部分です。
「なぜ今こんな不具合が?」と額に手を当ててため息をついた夜を、私は忘れていません。
こうした「ちょっとした安定性の揺らぎ」が、安心感を左右するんです。
一方で、このカードにも確かに魅力はあります。
新品価格は上位モデルより手が届きやすく、それでいてApex Legendsや多くのeスポーツタイトルを快適に遊べるスペックを備えているわけです。
それに対して40代という立場から考えると、財布だけでなく時間にもシビアだからこそ、「この満足感が数年後も維持できるのか」との思いが強くなります。
今は良い。
でも数年後はどうだろう、そういう問いかけが必ず頭に浮かぶんです。
電源ユニットの選択も忘れてはいけません。
これが意外と軽視されがちなのです。
6700 XTはピーク時に約300W近く消費するため、私は以前600W電源で試したことがあるのですが、そのときはフルロード時にファンが一気に全開になり、不安定さを全身で感じました。
750Wクラスを用意すれば安心感はぐっと増します。
電源をけちらないこと、ここは声を大にして強調したい。
Apex Legendsをはじめ、軽快に遊べるタイトルを中心に楽しみたいなら、このGPUは確かに満足度の高い選択となります。
ただし、大作ゲームを長期的に堪能しようとするなら、割り切りが必要になります。
「今を楽しんで、その後は潔く買い替える」そんなスタンスをとれるかどうかで、このカードの価値は大きく変わるのです。
私の率直な気持ちを言えば、割り切るなら快適。
逆に未来を託すなら不安。
そういう位置づけです。
心からおすすめできるのは、Apex専用や気軽に楽しむためのPCゲーム環境を求める人です。
こういう人にとっては迷わず提案できる製品です。
しかし「最新のAAAタイトルも数年後にストレスなく遊びたい」と考える人には、ほかの候補を探す労力を惜しまない方が賢明だと私は思います。
最後に一言だけ。
だからこそ、勧めるときには「今を楽しむための道具」と割り切る考えを忘れないでほしいのです。
安さと快適さを重視しすぎて未来に過剰な期待を抱かない。
その姿勢こそ、Radeon RX 7700 XTをもっとも賢く使いこなす方法だと私は信じています。
未来志向か。
今の楽しさか。
どちらに重きを置くかで、このGPUの価値は決まります。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FD

| 【ZEFT R60FD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67A

| 【ZEFT R67A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67E

| 【ZEFT R67E スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62O

| 【ZEFT R62O スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CB

| 【ZEFT R60CB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
価格とパフォーマンスを見て選びたいBTOメーカー
ほかにも候補はいくつもあり、情報を追いかけていると迷いが生まれるものですが、実際に自分で試して時間をかけて比べてみると、結局はこの三つに絞られてしまう。
私はそれを自分の経験で痛感しました。
ここは注文してから届くまでが早い。
以前、週末の疲れを発散しようと「今度の休みにApexをやろう」と思いつき、金曜の午後に注文しました。
そうしたら日曜の午前には届いたんです。
余計な待ち時間がない。
正直、待たされるのが苦手な私にとってはこれ以上ない相棒になりました。
その時の感覚は「よし、今夜から遊べるぞ!」と心の中でガッツポーズしたくらいです。
性能にも不満はなく、価格も他社に比べてお手頃。
納期が早いということが、これほどまで日常のワクワク感を高めてくれるのかと、あの日実感しました。
次にマウスコンピューター。
私がこの会社に感じているものは言葉通りの安心感です。
昔、仕事用ではなく家族向けにPCを買ったことがあったのですが、ちょっとした設定のことで問い合わせたんです。
そのとき電話に出てくれた担当の方が本当に親切で、専門的な内容を難しい言葉で押し付けるのではなく、私や家族でもきちんと理解できるようにかみ砕いて説明してくれました。
その姿勢に対して、私はなんだか人柄を感じました。
サービスというより「人とのつながり」。
それ以来、友人や同僚から「BTOパソコンってどこがいい?」と相談されたら、自然とマウスをすすめるようになりました。
夜中でも静かに動いてくれるモデルが多いのも魅力で、子どもが寝ている横で小さな音しか立たないのはかなり助かります。
実際、静かさというのは派手ではありませんが、長く使うほど大きな価値になるんだなと気づかされました。
そしてパソコンショップSEVEN。
最初の印象は正直なところ「地味だな」でした。
ただ、少し掘り下げて調べてみると印象が変わったんです。
購入したときにパーツ構成を見て驚いたのが、細かい部品の型番やメーカーがすべて公開されていることでした。
これなら「自分がどのパーツを買ったのか」が明白にわかります。
実際そのパソコンをパーツ好きの友人に見せたとき「これは手堅い選択だな」と言われ、私自身も胸を張れる気持ちになりました。
お問い合わせのやり取りをしたときも丁寧で、通り一遍の対応ではなく人間的な誠実さが伝わってきて、むしろそのやり取りのおかげで信頼感が急に増したことを今でも覚えています。
ですが、実際に組み込まれているパーツの質や検証の徹底ぶりを知ると、その価格差は「なるほど、ここまで見てくれているからこそなんだ」と納得できるんです。
安く見せることだけに走らず、見えない部分までしっかりやる姿勢に心を打たれる。
そう感じました。
そうやって振り返ると、それぞれの個性はとてもはっきりしているんですよね。
ドスパラはスピードと価格の軽快さ。
思い立ったときにすぐ欲しい人には文句なしです。
マウスはサポートの丁寧さと使い続ける安心感。
長く穏やかに付き合いたい人向けなんです。
そしてSEVENは品質と誠意の透明性。
パーツの一つにまで自分自身で納得したい人にはここが合うと私は思います。
私の知人たちを見ても、この三つは綺麗に性格が出ています。
私はせっかちな性格なのでドスパラ。
すぐに手に入れたいんです。
同僚は子どもが小さいので静音を重視してマウス。
夜中の家の空気を考えると理にかなっている。
それぞれが違うけれど、それぞれが満足している。
結局のところ、大切なのは「自分が何を求めているか」をはっきりさせることだと思います。
安心感。
納得感。
これが最後に残る要素です。
だからこそ「これなら自分が気持ちよく遊べる」と思えるかどうかだけが最終判断になります。
私の場合、ドスパラ、マウス、SEVEN、この三つを経験して、ようやく余計な迷いを手放すことができました。
他の選択肢も悪くはありませんが、Apex Legendsを思い切り楽しむという観点で言えば、悩む必要はほとんどない。
つまり──この三社さえ見ておけば十分なんです。
私は今、そのことを強く実感しています。
長く安心して使えるApex Legends対応PC構成

DDR5メモリ32GBが実際に役立つシチュエーション
ゲームを単に遊ぶだけでなく、配信や動画編集、さらには将来のアップデートに備える意味でも、この余裕は決して無駄ではありません。
むしろ必要な準備だと痛感しています。
16GBの頃は配信しながらプレイすると、数時間で挙動が重くなってきて「またか」とため息をついたものです。
心臓が縮むようなカクつき。
集中力を奪われ、勝負どころで凡ミス。
これが毎回でした。
ところが32GBに切り替えると、まったく状況が変わったのです。
配信中にWindowsアップデートが走っても「ま、何とかなるか」と肩の力を抜いて構えられる。
その安心は本当に大きいです。
バックグラウンドの常駐プロセスは想像以上にゲームの敵です。
セキュリティソフトのスキャンやクラウドサービスの自動同期など、自分が意識していなくてもリソースを奪っていく。
16GBのときは頻繁に突発的なカクつきに悩まされ、正直、理不尽に思えました。
遊んでいるだけなのに、なぜ我慢しなきゃいけないんだってね。
でも32GBではあの嫌な瞬間がぐっと減った。
さらに高解像度環境でも差が出ます。
WQHDや4Kは映像が美しくなる代わりに、テクスチャや描画の要求が急に跳ね上がる。
私は友人と同じGPUを使用して比較しましたが、16GB環境のときはマップロードで数秒遅れを取ることがありました。
戦闘開始直後にまだ画面が止まっている悔しさ、いや忘れられませんよ。
32GBにしてからは読み込み時間が明らかに短くなり、その一瞬の差で勝敗が変わる世界で優位に立てるようになりました。
勝負の世界では命取りになる数秒なんです。
録画や編集でも違いは大きく出ました。
私は趣味で試合を録画し、簡単に編集して仲間と共有しているのですが、16GB時代は正直イライラする場面が多かった。
高ビットレートの素材を扱うとシークがカクつき、エフェクトをちょっと追加するだけで作業が止まる。
ところが32GBになってからは複数ソフトを並行で動かしても動作が安定していて、作業そのものが楽しく感じられるようになったのです。
まるで肩の力が抜けて気持ちが軽くなったようでした。
将来性も無視できません。
ゲームの推奨スペックはどんどん上がる傾向があります。
ある別タイトルでは大型アップデートの際に必要メモリが16GBから一気に20GB近くまで引き上げられたのを知っています。
そのとき16GBのPCを使っていた人たちはずいぶん苦労していました。
私は余裕を持って眺めていられたので「入れておいてよかった」と心から思いました。
アップデートのたびに「また買い替えか」と悩むのはもうこりごりです。
余裕を持った投資は、未来の安心につながると実感しました。
もちろんすべての人に32GBが必要とは限りません。
私もそういう遊び方しかしないなら、増設には踏み切らなかったと思います。
ただし、配信や録画を並行したい人、あるいはこれから高解像度でのプレイに挑戦する予定がある人にとっては、このメモリ増設は大きな後押しになるはずです。
実際、私の後輩がBTOパソコンの構成を相談してきたことがありました。
グラフィックボードに全予算を突っ込みたがっていた彼に対して「バランスを考えなよ」とアドバイスし、メモリを32GBにするよう勧めました。
結果、動画編集も快適にでき、Apexのプレイも安定。
彼から「先輩のアドバイスがなかったら危なかったです」と感謝の言葉をもらったとき、これほど嬉しいことはありませんでしたよ。
DDR5メモリ32GBはただの数字ではありません。
その先にあるのは、ストレスなく好きなことに集中できる自由、そして仕事や趣味を両立させる安心感。
この快適さを知ってしまった私には、もう戻ることはできません。
だから迷いなく選びます。
年齢を重ねた今だからこそわかる。
安定している環境こそが最大の財産なのです。
これが、私自身の確かな実感です。
1TB NVMe SSDを選ぶときにチェックしておきたい点
1TBのNVMe SSDを選ぶとき、私はまず「安心して長く使えるだろうか」という観点で考えます。
容量だけを見れば確かに1TBは十分だと感じますが、結局のところ大事なのは安定性やメンテナンス性、そしてちゃんとサポートしてもらえるかどうか。
容量が多ければよいという発想の時期もありましたが、これまでの経験から言えば、それ以上に重要なのは土台としてしっかり機能することです。
つまり、スピードと発熱対策、そしてメーカーの信頼性。
この三つが揃って初めて「買ってよかった」と長く感じられる、そういう買い物になるのだと思います。
特に最近のゲーム事情を見ていると容量への不安を抱くのも無理はありません。
大作ゲームほどインストールサイズは膨れ上がり、アップデートのたびにデータが追加されるからです。
Apex Legendsを中心に遊んでいる私も、最初は「1TBじゃ絶対足りない」と身構えていました。
でも実際に運用してみると、複数のゲームを入れても意外と余裕があるものです。
無理に大容量モデルへ投資しなくても、価格と容量のバランスの面で1TBが現実的なラインだと理解しました。
ただ、私がこれまでに強く痛感していることがあります。
特に以前、安さだけで選んだSSDを使ったときは最悪でした。
ロードの遅さからイライラし、結局は買い直す羽目になったんです。
「ストレージはただの物置ではない」――あの時の失敗が、今でも私の頭に焼き付いています。
ロードの速さは、遊んでいる本人にとってダイレクトに効いてきます。
試合ごとの切り替えが早いApexでは、ロード中のわずかな待ち時間が熱量を削ぎ、モチベーションを下げる原因になります。
だからこそ、私は今は確実にGen.4対応を選ぶようになりました。
Gen.5も気にはなりますが、現状では発熱が大きく、価格も跳ね上がる。
冷静に考えて「いま欲しいのは将来の性能ではなく、いま快適に遊べるSSDだ」と割り切っています。
Gen.4が落ち着いた選択肢。
ここは私の譲れない実感です。
そして忘れてはならないのが放熱の問題です。
M.2 SSDは便利で小型ですが、とにかく熱を溜めやすい。
昔、ヒートシンクをつけずに連日長時間プレイしたとき、気づいたら速度が落ちていました。
その時の後悔、「あのとき冷却していれば…」という思いは今もあります。
だから今では必ずヒートシンク付きか、マザーボードの冷却機構を確認しています。
少しの気配りが、長期的な安心につながる。
経験から言って間違いありません。
ブランド選びもとても大切です。
過去に安さを優先してノーブランド品を買ったことがありましたが、ファームウェア更新もなく将来性も見えず、データを抱えながら不安に耐える毎日でした。
あの頃は本当に疲れましたよ。
「やっぱり信頼のあるメーカーにしておけばよかった」と思いました。
今ではBTOパソコンで名のあるメーカー製のSSDを選べるオプションが増えているので、それがとにかくありがたい。
ブランドの持つサポート体制と商品保証、この安心感が最終的に一番大切だと身をもって実感しています。
正直、最初は「1TBって少ないんじゃないか」と疑っていました。
特に動画キャプチャを取る習慣があるため、容量不足になると想定していたんです。
その結果、管理がずっと楽になり、容量を無駄に気にせず遊べるようになったんです。
あの決断は思いがけず合理的で、コストにも優しいものでした。
さらに心強いのは、拡張性が確保されていることです。
最近のマザーボードには追加スロットがあり、後から1TBや2TBを追加して用途ごとに分けられる。
録画データはここ、作業ファイルはここ、過去のタイトルはここ。
そんな風に用途別に割り振れる柔軟さが、私の大きな安心材料になってきました。
一度も不便を感じたことがありませんし、むしろ「困ったときは増設すればいい」という心の余裕が持てました。
安心感。
私はやっぱり最終的にSSDに求めるのは、容量の多さではなく長く信じられる堅実さです。
それならコストも性能も折り合いがよく、PC全体の寿命まで引き上げることができますよ。
「まあこれでいいだろう」ではなく「これで間違いない」と言える製品を持ちたいのが本音です。
最終的に私は、実体験を通して「1TBのGen.4 NVMe SSDを名のあるメーカーから選ぶ」ことを強く勧めます。
それが安心の近道ですし、毎日のプレイを長く楽しく続けていける最大の力になると、今では自信を持って言えるのです。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
空冷と水冷、自分に合うのはどっち?
エーペックスを快適に遊ぶためにゲーミングPCを用意するとき、冷却方式をどう選ぶかは実は思った以上に結果を左右します。
私の率直な結論は、普段使いと価格バランス、そして扱いやすさを考えるなら空冷が安心で信頼できるということです。
もちろん、静かさや冷却性能を追求したい場合は水冷が魅力的ですし、そこに価値を見いだす方には十分な選択肢になるだろうと思います。
要は何を最優先にしたいか、それだけなのです。
私が最初に自分で組んだマシンは、かなり大ぶりの空冷クーラーを搭載していました。
真夏になるとさすがに心細さを感じる瞬間はあったのですが、基本は安定して動き、安心してゲームができました。
夜中にファンの音が唸り声のように部屋に響くようなこともなく、メンテナンスといえば数か月に一度ファンの埃を払う程度で済んでいたのです。
ああ、この安心できる感じ。
今も鮮明に覚えています。
ただし年月が経つと状況は変わるものです。
数年前に新しいPCを組んだ際、私は思い切って簡易水冷を選びました。
360mmラジエーターを取り付けたときの印象は強烈でした。
エーペックスを数時間連続で遊んでいてもCPU温度が落ち着いている感覚があり、その安定性には素直に驚かされました。
正直に言えば、「おお、静かだな」と声が漏れたくらいです。
以前のようにファンの轟音に悩まされていた頃を思い出すと、笑ってしまうほどの違いがありましたね。
実際に私はケースの内部で干渉が起き、「ああ、またやり直しか」と独りごちたこともよく覚えています。
さらに、やはり財布に響く。
GPUを少し上位にするか、水冷を導入するかは、どちらも魅力的だからこそ悩ましい。
お金の使い道は結局どちらかを諦める形になるんです。
ここで一度整理してみたいと思います。
エーペックスの負荷は大部分がGPUに集中するのが実情です。
CPUの温度自体は大型の空冷クーラーでも十分に抑えられ、極端な不安定さを感じる機会はほとんどありません。
実際、私もCore Ultra 7やRyzen 7クラスのCPUを空冷で使いましたが、不具合に悩まされた記憶はほぼなし。
だから学生や社会人一年目のように限られた予算でPCを考えるのであれば、空冷で十分に戦えるのです。
これは私が何度も実感したことであり、一つの答えとして伝えたいところです。
最新世代のハイエンドCPUをオーバークロックし、RTX 5080クラスのGPUを載せて4Kでフレームレートを限界まで引き上げようとするなら、もう空冷だけでは限界が見えてくる。
電力消費と熱の量が一気に膨れ上がります。
そのステージでは水冷こそが頼れる存在です。
実際、私の仲間の一人も空冷から240mm水冷に切り替えました。
するとファンノイズが一気に減り、「あれ、こんなに静かだっけ?」と驚いていました。
夜中に遊んでいても、周囲に気を使わずに済む安心感。
まるで喫茶店に漂う雑音がふっと消えたような感覚だったと言います。
数値の性能比較では見えない部分ですが、こうした快適さは生活に根付き、確実に満足へつながるのです。
整理すると、普段使いや限られた予算でエーペックス用のPCをつくるなら、空冷で十分に満足できることは間違いありません。
使いやすく、壊れにくく、コスト面でもありがたい。
対して水冷は「もう少し上を望む人」「静かさも極めたい人」への選択肢になります。
資金に余裕があるのなら試す価値がありますが、空冷を選んだからといって大きな後悔があるわけではない。
この事実を伝えたいのです。
だから私は今も基本は空冷を選びます。
しかし時折「贅沢をしたい」と思う瞬間に水冷を導入することもある。
まあ、ご褒美ですね。
そう整理すればもう迷いません。
安心感とコストのバランス。
挑戦と静けさの心地よさ。
この二つの価値観のどちらを取るか。
私にとっては、これからも空冷が軸であり続けます。
ただ、時に水冷というぜいたくに手を伸ばすこともある。
デザインにもこだわりたいApex Legends用ゲーミングPC
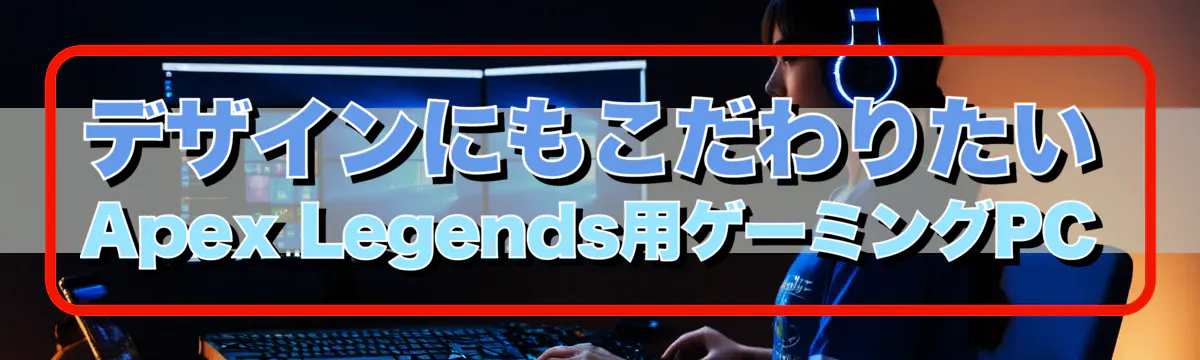
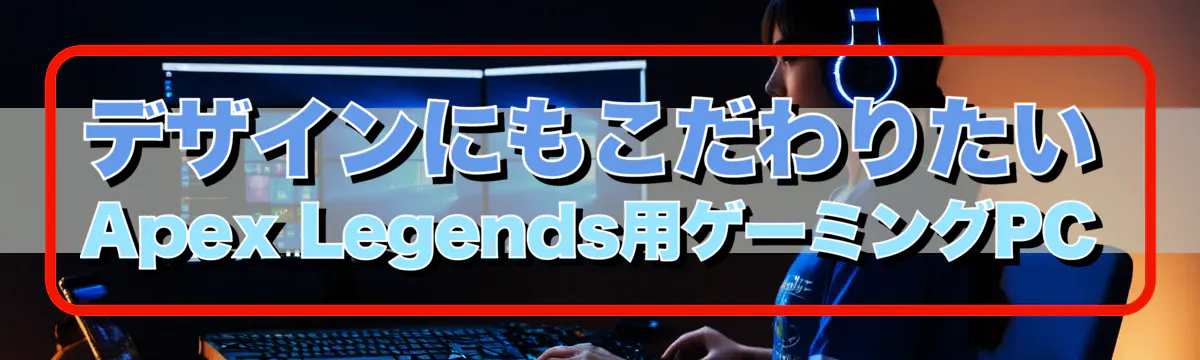
強化ガラスケースは見た目と実用性の両立が可能?
それでも実際に数年使い込んでみると、真夏の長時間稼働でも安定して動作し続ける姿を目の当たりにして、見た目と実用性能の両立をようやく理解しました。
正直なところ、あの瞬間に「もう古い先入観のままではいられないな」と素直に認めざるを得なかったのです。
側面一面がガラス仕様になっているケースは、設置したときの存在感がとても大きいです。
中のパーツがそのままディスプレイのように見えるうえ、ライティングを工夫すれば部屋の空間に華やかさを与えてくれます。
私は仕事帰りに街のショーウィンドウをぼんやり眺める時間が好きなのですが、その雰囲気を自室に持ち込めたように感じたときには正直ワクワクしました。
従来の「PC=黒い箱」という固定観念は完全に崩れ去った瞬間です。
眺めて楽しむ余裕があるなんて、昔は考えもしなかった。
ただし見た目ばかりに意識を向けるのは危険です。
特に冷却への懸念は誰もが抱く点だと思いますし、私も同じ悩みを持っていました。
しかし最近のケースはフロントやボトムに幅広いメッシュ加工を取り入れており、大口径の140mmファンをいくつも搭載可能になっています。
結果として、以前感じていた閉塞感は驚くほど軽減されました。
メーカーが試行錯誤を重ねて機能性を追求していることが手に取るように分かり、その努力を信頼するきっかけにもなりましたね。
私の環境でも、真夏に何時間もゲームを起動し続けていてもGPU温度は70度台後半で安定しています。
試しにApexをWQHDで回してみましたが、ファンの音が気になるほど大きくなることはありませんでした。
本音を言うと、ここまで静かで快適に使えるとは想像していなかった。
苦笑いするしかありませんでした。
最近はデザインの幅も非常に広がっています。
透明パネルとエアフロー重視の構造を両立したモデル、木目調のパネルを取り入れて家のインテリアに馴染ませたモデルなど、従来なら特殊な製品とみなされていたものが自然に市場に並ぶようになりました。
リビングに置いても違和感なく、家族も「意外にいいね」と口にしてくれたのは自分でも驚きでした。
明らかにPCケースの文化そのものが変わってきていると感じます。
カラフルな光が夜の部屋を包むと、どうしても落ち着かないんです。
若い人には映える演出かもしれませんが、40代になったいまの自分には違和感が残りました。
だから私は基本的にライティングを切るか、単色で温かみのある光だけ残すようにしています。
そのほうが夜に仕事を進めるときも集中しやすい。
大人の落ち着いた距離感で楽しむ、これくらいが心地いい。
ガラスそのものの良さはやはり耐久性にあります。
アクリルは傷が入りやすく時間の経過とともにくすんでしまいますが、強化ガラスは何年経っても透明感を失いません。
そしてその透明感が与えてくれる高級な雰囲気は、所有する満足感を確かに支えてくれています。
指紋はやはり気になりますが、クロスで軽く拭き取るとすぐに元通りになります。
この小さな嬉しさが案外長く続くものなんですよね。
安心感があります。
業界全体の動向を見ても、この方向性はより加速していくでしょう。
軽量で割れにくい次世代ガラスや、自動制御機能と組み合わせた最新ケースが確実に広がるはずです。
実際にeスポーツ大会の現場では、ガラスケースが一斉に並んだ光景をよく見ます。
昔なら珍しい存在だったはずが、今や当たり前。
今後は温度センサーや照明制御をケース自体に組み込み、ある程度は自動で管理できる仕組みも当たり前になっていくのではと想像しています。
まるで家電の一部になっていくような流れ。
信頼できる選択でした。
ゲーミングPCを検討している人にとって、強化ガラスケースは単なる見た目の美しさを超えた意味を持ちます。
冷却性、耐久性、そして部屋に溶け込むデザイン性。
性能とデザインの両輪が同時にバランスしたときに得られる快適さは、ただの機械以上の満足感を私に与えました。
そこでようやく、仕事も趣味も支えてくれる一つの「大人の道具」として愛着が芽生えたわけです。
結局のところ、強化ガラスのPCケースは長期的に見ても損のない投資です。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56KA


| 【ZEFT Z56KA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09G


| 【EFFA G09G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56O


| 【ZEFT Z56O スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DAG


エンスージアスト級のパワーを備えるゲーミングPC、プレイヤーの期待に応えるマシン
バランスドハイパフォーマンス、最新技術と高速32GB DDR5メモリで圧巻のパフォーマンスを誇るモデル
話題のCorsair 4000D Airflow TG、隅から隅まで計算されたクールなデザイン、美しさも機能も両立するPC
Ryzen 9 7950X搭載、プロセッシング性能の新境地を切り開く、ハイエンドユーザーに捧げるゲーミングPC
| 【ZEFT R56DAG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
RGBライティングを取り入れる魅力と注意点
ゲーミングPCを選ぶとき、私は性能だけでなく外観にもかなりこだわります。
長時間ゲームに没頭するとき、例えばApexのような緊張感のあるタイトルでは、とくに環境そのものが集中力を支えると実感してきました。
単なる仕事机で戦うよりも、光やレイアウトで気持ちを切り替えられる空間の方が、はるかに気持ちが前に出るんです。
RGBライティングはまさにそのスイッチのような役割を果たしていて、光が空間に加わるだけで「よし、やるぞ」というモードに入れる。
私はそれを軽視できません。
ただ、良い面ばかりではないのも事実です。
RGBを導入したとき、最初に出てきたのは感動よりもトラブルでした。
各社の制御ソフトがうまく連携せず、光を変えるどころか同期すらまともに働かない。
私はその不安定さにかなり苛立ちました。
こういう手間になると「本当に必要だったのか」と自問したものです。
しかも派手に点灯させるとわずかに電力負担も熱も増える。
熱に敏感な最新GPUや高速SSDを積むなら冷却に余裕を持たせないとダメなので、光が逆にプレッシャーになりかねない。
最初に夢見ていた「雰囲気アップ」のはずが、実際には余計なストレスになることもあるんですよ。
それでも私がRGBを続ける理由は、自分らしさを反映できるからです。
配信をする人には特に意味が大きいと思います。
光の演出は視聴者への自己紹介みたいなもの。
黙々と性能重視の無骨なPCを使うスタイルもありですが、私は配信画面に鮮やかなライティングが映り込むだけで「この人は演出にこだわってるな」と親近感を覚えたりします。
その感覚を覚えてからは、自分の光もどうしたら映えるか、考えるようになりました。
実際、ケース選びは相当悩みました。
三面ガラスで全面的に光をアピールしたいのか、それとも木目と組み合わせて落ち着いた雰囲気を出したいのか。
最初は見た目だけで選んで失敗しました。
何度も買い替えた末に、私はエアフローがしっかりしたメッシュタイプに落ち着きました。
光をしっかり外に届けつつ熱もしっかり逃す。
見た目と性能の両立にようやく納得できた瞬間でした。
CorsairのARGBコントローラーを導入したときは、正直感動しました。
マザーボード付属のソフトでは実現不可能だった微妙な発色が可能になり、自分好みに細かく調整できる。
その自由度の高さに「あぁ、こういう未来を待っていたんだ」と胸がすっとしました。
夜は暖色で落ち着かせて、休日には鮮やかな青や赤でテンションを上げる。
後付けで組み直す手間は本当に大変です。
そこで見えてきた課題が静音性でした。
RGBファンを多くつけ過ぎて、光は華やかになったのに夜中にファンの音ばかりが気になってきたんです。
家族からも苦情が出ました。
そのとき私は回転数制御用のソフトを導入し、ファンを減速させながら配置の工夫で効率的に冷却するように変更。
結果的に、光の鮮やかさを損なうことなく静音化を実現できました。
結局必要なのはバランスなんですよね。
派手すぎてもダメ、控え過ぎても物足りない。
その加減こそ経験でしかつかめません。
先日、ある展示会で未来のライティング技術を体験しました。
今はもう既にゲーム音やシーンに合わせて色が変化する仕組みが当たり前になりつつありますが、これからはAIがもっと深く入ってくるようです。
プレイヤーの心拍数、発声の大きさ、緊張感の度合いまで読み取ってライトが変わる。
もしそれが実装されたら、私たちが普段見ている画面と周囲の光が完全に一体化するんです。
想像しただけで期待が膨らむ。
いや、本当にワクワクしますね。
だから結局のところ、私が言いたいのはシンプルです。
RGBライティングはただの飾りではありません。
プレイ環境を左右する大切な要素であり、集中や気持ちの高まりを与えてくれるものです。
その一方で、冷却や静音の工夫を怠ると一気に不快要素になってしまいます。
私は「見た目か性能か」ではなく「見た目と性能の両立」を基本とすべきだと信じています。
まずしっかり性能を確保する。
それこそが真に意味のあるRGBの使い方です。
ときどき思います。
光の調整に熱中している自分を、若い頃の自分が見たら笑うかもしれないなって。
無駄だと言われるかもしれないけれど、快適な環境を整えることがこれほど仕事や趣味のモチベーションを支えてくれるとは、40代になって改めて実感しました。
焦って成果を求めるより、落ち着いた空間を整えた方が集中できる。
そういう年齢になったのかもしれません。
大切にしたい気持ちです。
それは性能の数値やレビューの星数だけでは得られません。
自分で環境を作り、自分のスタイルを形にしていくからこそ心に残る。
静音性と冷却を両立させるためのケース選び
エーペックスのような対戦ゲームを本気で楽しむために重要なのは、パソコンケースの選び方だと私は強く思っています。
性能の良いパーツを揃えても、ケースが良くなければ宝の持ち腐れになる。
これは、実際に何度も自分で組んで、遊んで、不満を抱えてきた経験の中で痛感したことです。
片方に偏れば必ずストレスが生まれる。
熱は敵だし、うるさすぎる騒音も敵なんです。
だから、ケース選びは甘く見ると後悔することになります。
あるケースが私に鮮烈な印象を残しました。
フロントに木目のパネルがあしらわれたモデルです。
第一印象は「どうせ見た目重視のファッションケースだろう」でした。
ところが実際に使ってみると違ったのです。
しっかりと熱が逃げる設計になっていて、内部温度が安定している。
そのうえ音も静かで、家具として部屋に馴染む落ち着いた雰囲気を持っている。
想定以上の出来栄えに思わず唸りました。
正直、まいったなと。
空気の流れが自然に作られているか。
これこそがケース選びにおける最大のポイントだと今でも思います。
例えばGPUに負荷がかかるとき、吸気が正面からすっと入り、背面や天井にスムーズに抜けていく。
その自然な循環があるおかげで、ゲームの最中でもパフォーマンスを落とさず快適に遊べます。
逆にそれがうまくいかないケースを使った時には、熱のこもりが目に見えてゲーム体験を悪化させてしまいました。
最近のケースは裏配線用に広いスペースが確保され、ケーブルが整理しやすくなっています。
配線がよれるだけでエアフローが滞り、グラフィックカードの温度が数度上がることもあったのです。
ケーブルを整えることは単なる見栄えの問題ではなく、冷却性能に直結している。
それを実感した瞬間、「これはもう手を抜けない」と自分に言い聞かせました。
水冷か空冷かという議論は長い間続いていますが、正直、最近は高性能な空冷で十分対応できる場面が多いと感じています。
確かに極端なハイエンドCPUをフル活用する人なら水冷の方が安心かもしれません。
しかし、ほとんどのユーザーにとって空冷の最上位クラスを選べば必要十分です。
しかも静か。
遊んでいて耳に余計な負担をかけないことが、どれほど助かるか。
静音を最優先にして作られたケースには、内部に吸音材が貼られたものがあります。
夜に使っても、隣室で寝ている家族に迷惑をかけずに済む。
この安心感は想像以上に大きいです。
小さな音の有無で、プレイへの没入度が変わる。
快適な環境を整えることが、心の余裕を作る。
一方で、見た目を重視する人も少なくありません。
RGBライティングで華やかに演出したり、メッシュフロントで光を美しく透過させたりするケースは、所有する満足感があります。
大切なのは「見た目に振り切っても、冷却効率を犠牲にしないモデルを選ぶ」ことです。
冷却性能をさらに確保するために確認したいのは、ファンの増設スペースです。
フロントに140mmファンを追加できるか、トップに余裕があるか。
その設計の違いで、長時間プレイ中の安定性が大きく変わる。
高負荷が続くゲームを数時間やると、吸排気の動きが本当に効いてきます。
小さな差が大きな違いになる。
ここに気付くかどうかで、ケース選びの成否が決まると私は信じています。
私が最終的にたどり着いた答えは、静音と冷却の両方を満たすことです。
その上でケーブル管理のやりやすさや外観を考慮すれば、後悔しない一台が出来上がる。
それしかない。
ゲーミングPCとは性能数値だけの競い合いではないと私は思っています。
何時間でも心地よく遊べる環境こそが価値で、音に邪魔されず、温度に不安を抱えず、さらに自分らしいデザインを楽しめる。
その投資こそがゲームの世界をもっと深く楽しませてくれるのだと、私は信じています。
要するに私が言いたいのは一つ。
静音性と冷却性、その二つをきちんと両立させること。
それが、心から楽しめる環境を作る本当の鍵なのです。
結局そこに尽きるんですよ。
Apex Legends用ゲーミングPCに関するよくある疑問
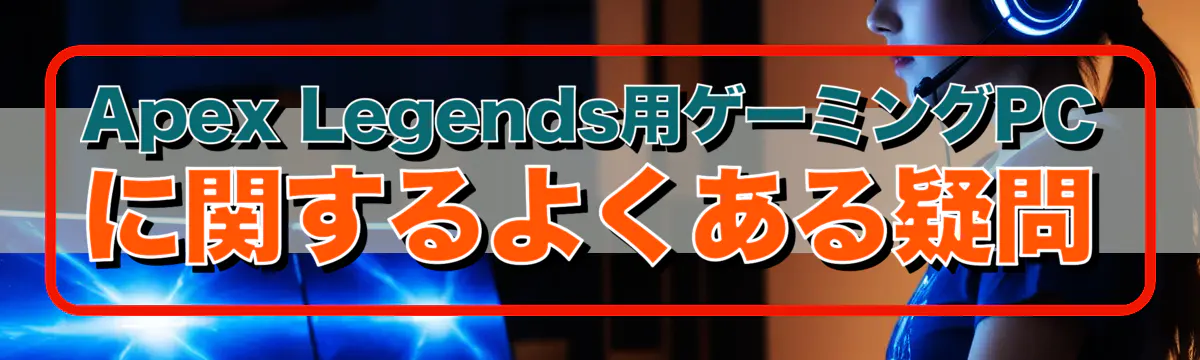
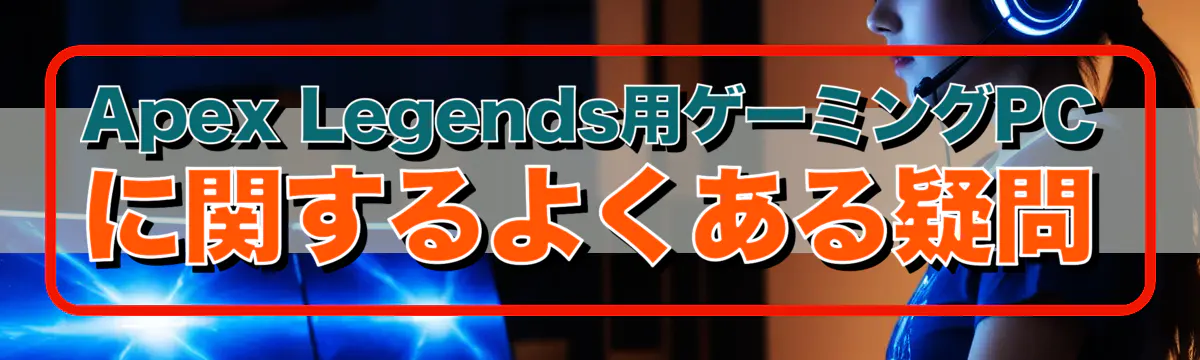
安めのゲーミングPCでも快適に遊べるのか?
安めのゲーミングPCでもApex Legendsは楽しめるのか、多くの人が気になるところだと思います。
私の結論としては、しっかりポイントを押さえて選べば、十分に快適に遊べるということです。
もちろん最新の4K環境や最高設定での映像美を堪能したいならハイエンドが必要になりますが、勝つために大事なフレームレートや安定感の確保であれば、そこまで背伸びをしなくても現実的に達成できます。
私も実際にBTOショップで手頃なPCを購入して遊んだことがあります。
正直、「まあ入門機だし、そこまで期待できないだろう」という程度の気持ちで買ったのですが、実際に設定を調整してプレイしてみると想像以上に快適に動いて驚きました。
影の設定やアンチエイリアスを少し抑えただけで144fps前後を安定して体感できて、「この価格でもこんなに戦えるのか」と何度も考え直すほどでした。
思い込みで判断せず、自分で試してみることの大切さを痛感しましたね。
GPU性能は中ランクでも十分ですが、VRAMの余裕は見逃せません。
今は8GBでもまだ何とかなる状況ですが、アップデートのたびにゲームが重くなるのはよくある話です。
特に試合中に僅かなカクつきが起これば、それが命取りになるのは皆さんもご存じの通りです。
私も一度だけ画面が固まって相手にやられて、机を叩きたくなる思いをしたことがあります。
あれは本当に嫌な経験でした。
ただし録画や配信を同時にしたい人は別。
私自身、手頃なCPUで配信したことがありましたが、自分の画面はサクサク動くのに、配信映像がカクついてしまうという事態に直面しました。
その時は「安く済ませたつもりが、結局中途半端になった」と苦い思いをしたのをよく覚えています。
やはりやりたいことを明確に決めて、その条件に合ったCPUを選ぶことが必要です。
もう一つ忘れてはいけないのが冷却です。
水冷の高級モデルまでは不要ですが、エアフローをどう確保するかは極めて大事です。
私は夏場にケース内の熱がこもってしまい、フレームレートが落ちた経験をしました。
その時は目の前で勝負がかかっていたのに動きが鈍って、本当に悔しかった。
見た目が格好いいガラス張りのケースに目を惹かれる気持ちは理解できますが、実用性の部分を軽視すると必ず痛い目を見ます。
冷却環境は軽視してはいけない、本音からそう思います。
容量面も侮れません。
当初は500GBのSSDで足りるだろうと思っていたのですが、あっという間に残りがゼロに近づきました。
Windowsや日常のアプリだけで想像以上に容量を食いますし、Apexもアップデートが続けば数十GB単位で肥大化していきます。
本来ならゲームに没頭したいのに整理に時間を使わされる。
これじゃ本末転倒です。
だから今は最初から1TBを選ぶようにしています。
その安心感と余裕は、ほんの数千円の差額以上の価値があります。
さて、安いゲーミングPCの力はどの程度まで頼りになるのか。
私の体験では、フルHD・中?高設定・144Hzで安定という条件ならしっかり応えてくれます。
ただしWQHDや4Kも見据えて滑らかさを損なわずに楽しみたいとなると一気に難しくなりますね。
つまり安価モデルでどこまで快適さを許容できるか、自分自身の優先順位としっかり向き合うことが重要です。
正直な話、安いPCでもApexは十分に楽しめます。
勝ちたいならフレームレートと安定性を重視すべきで、それなら入門機でも十分な環境が整います。
見た目重視や映像の豪華さを求めるなら当然別の世界ですが、コストパフォーマンスで勝負したい学生や、家庭の出費と両立しながら趣味を楽しみたい社会人にとっては、「安めのモデルこそ合理的な選択肢」だと私は強く感じています。
要は、正しく選べば問題なしということです。
それを土台にして必要に応じてグレードアップしていけば良いのです。
もし若い頃の自分に会えるなら、きっと私はこう言います。
「無理をして高級パーツを買うな。
大切なのは続けられる環境だ」と。
心からそう思います。
ゲームを遊ぶという行為は、必ずしも最高級の環境を整えることと同義ではありません。
楽しみたい気持ちと、予算や生活との折り合いをどう付けるか。
そこで自分なりの正しい線引きをすれば、安価なゲーミングPCでも十分に満足できる体験が得られます。
これが私が心の底から感じている実感なのです。
でも無理は禁物です。
安心して遊ぶためにこそ、まずは現実的な環境を選ぶこと。
それこそが長く快適にゲームを楽しみ続ける秘訣だと、私は胸を張って言えます。
グラフィックカードはGeforceとRadeon、結局どちらを選ぶべき?
大会の中継や配信を見ていると、選手の多くが疑いなくGeForceを使っていて、そこには説得力があります。
多くを語らずとも、「それが現場の答えなんだな」と実感せざるを得ません。
とはいえ、最初から硬い話ばかりでは読み手も疲れると思います。
だからここで一度、私自身の体験を振り返ってみたいと思います。
数年前、私は長く使っていたRTX 4070クラスのカードから、RadeonのRX 7800シリーズの後継モデルに乗り換えたことがありました。
その時の印象はいまも鮮明です。
静音性と消費電力のバランスが実に優れていて、深夜の長時間プレイでも耳に残るファンノイズがほとんどなく、集中して遊べたことをよく思い出します。
それが快適さにつながり、思わず「Radeonも意外といいな」と声に出してしまったくらいです。
その時のストレスは想像以上でした。
私も40代になり、プレイできる時間が以前より限られているからこそ、途中で環境が不安定になるのはどうしても我慢できない。
試合に勝てるかどうかは運ではなく、環境によっても決まると身をもって感じました。
こればかりは趣味だからと言って妥協できる部分ではありません。
安定こそが必須条件だと強く思わされました。
私が20年近くPCを触ってきた中で痛感しているのは、ドライバ更新の速さと対応範囲の広さです。
新作ゲームや新エンジンがリリースされるたびに、ほかのどこよりも早く最適化されて対応している。
そのたびに、「これなら大会でプロが使うのも納得だ」と心の中で頷いてきました。
逆にRadeonはこの数年でようやく安定と信頼を得つつあるものの、対応のスピードではまだ追いついていない印象を持っています。
仕事後の短い時間に大切に遊んでいる身としては、余計なトラブルに振り回されるのは本当に避けたい。
ただ、Radeonだって確かに魅力があります。
高解像度の映像体験を重視する人には、コストパフォーマンスの高さが大きな強みです。
昨年、試しにRX 7900シリーズで4K環境を体験したとき、画面に広がる世界の美しさには思わず息をのむほどでした。
ただし本気で勝ちにいきたい時、やはり頼れるのはGeForceです。
やっぱり大会でGeForceが多く選ばれるのも納得。
今ならRTX 5070や5070Tiあたりが性能と価格の両面で最もバランスの良い選択肢でしょう。
勝負を意識する人には非常に心強い存在です。
とはいえ予算を重視する若いプレイヤーや学生にとっては話が違います。
私も若い頃はとにかくお金がなく、どれだけ安く理想に近い環境を作れるかがすべてでした。
そうした視点で考えれば、Radeonの魅力は確かに大きい。
「限られた予算で最高の映像を楽しみたい」と思えば、自然にRadeonを選んでも納得できます。
だからこそ選択を決めるのは性能比較の数字そのものではなく、自分の価値観と目的なのだと私は思います。
要するに、勝ちたい人ならGeForce。
映像の美しさに心を傾けたい人ならRadeon。
それだけのことなんです。
どちらが正しいかではなく、自分が何を大事にしたいかという話。
私自身はこれまで何度も買い替えてきた中で、優先順位によって自然と方向性が決まってきました。
妥協せず勝ちたいならGeForce。
趣味の時間をゆったり楽しみたいならRadeon。
この整理で迷うことがなくなります。
そして40代になった今、私がもっとも強く考えるのは「限られた時間をどう生かすか」に尽きます。
仕事があり、家庭があり、自由にできる時間は確かに少なくなった。
でもその中で遊ぶなら、やはり価値ある時間にしたいと願うんです。
そのための安心を求めるならGeForceこそ最適な選択肢ですし、深い映像体験を求めるならRadeonが答えになります。
結論はとてもシンプルなんです。
迷わなくていい。
勝ちたいならGeForce。
それが今の私の答えです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GU


| 【ZEFT R60GU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65O


| 【ZEFT R65O スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56BM


| 【ZEFT Z56BM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IF


| 【ZEFT R60IF スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AL


エンターテインメントに最適、実力派ゲーミングPC。ミドルクラスを超えるパフォーマンスで驚愕体験を
32GB DDR5メモリ搭載、抜群のバランスで高速処理と頭脳プレイを実現するマシン
スタイリッシュなキューブケースに白をまとう。小さな筐体から大きな可能性を引き出す
Core i7 14700Fで、応答速度と処理能力が見事に融合。中核をなすパワフルCPU
| 【ZEFT Z47AL スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
学生にとってBTOと自作、どちらがメリット大きい?
学生がゲーミングPCを手にするとき、私が考えるもっとも現実的で堅実な選択肢はBTOパソコンです。
BTOであれば購入してすぐに使える安心感がありますし、特に初めて自分だけのPCを手にする学生にとって、メーカーのサポート体制が整っていることは大きなメリットになります。
日々の学生生活は課題に追われたり試験の準備を進めたり、ただでさえ時間が足りない中で過ごしているわけです。
そこにトラブル解決まで加わってしまうと、心に余裕がなくなりゲームどころではなくなる。
そのリスクを減らせるのがBTOであり、だからこそ現実的で価値のある選択だと私は感じています。
もっとも、自作PCの魅力を一切否定するつもりはありません。
私も若い頃、初めて自作に挑戦したときの緊張感は今でも胸に焼き付いているのです。
電源を入れた瞬間にファンが回って、画面にBIOSが映った時の安堵と高揚感。
あの体験は今振り返っても格別でした。
正直、あの瞬間ほど心が震えた出来事は社会人になってからあまり出会っていません。
安価な中古パーツをかき集め、予算ギリギリの寄せ集めみたいな一台でしたが、そのぶん思い出として強烈に残っているんです。
あれは私にとって原点みたいなもの。
心の支えです。
ただ現実を直視すれば、今の自作が昔と違って常に安上がりになるわけではないんですよね。
特に昨今のグラフィックカードは高止まり傾向で、RTX50シリーズやRadeon RX90シリーズは学生が簡単に手を出せる価格ではありません。
個人でパーツを揃えると費用の負担が大きいのが現実です。
それに比べ、BTOはメーカーが一括仕入れをしているため、同じ性能帯ならセットとして価格が抑えられていることが多い。
CPUやSSDを含め全体のバランスも整っていて見積もりが立てやすい。
財布にも心にも優しいのがBTOという選択肢なのです。
さらに違いを強く感じるのは保証の部分です。
BTOメーカーはたいてい初期不良交換や修理保証が付いています。
万が一の際に問い合わせ一つで助けてもらえるのは本当にありがたい仕組みです。
学生時代、突然PCが壊れてレポート提出に間に合わなくなった経験があり、そのときの焦りと不安は今でも忘れられません。
正直、自作だと自分の責任で解決するしかなく、その重さが初心者には酷です。
だからこそサポートの厚みを軽視してはいけない。
サポート込みで考えると、やはりBTOが安心だと痛感しています。
ただし自作に触れることで得られる知識や経験はかけがえのない財産です。
例えば予算が限られていれば、グラフィックボードを中位に抑えるかわりに冷却を工夫し、本来以上のパフォーマンスを引き出すことができます。
自作が無駄な遊びだと考えるのは早計で、むしろ人生経験として残る強い武器になるのです。
実際、私は最近とあるBTOメーカーのPCを見て驚かされました。
その構成はRTX5070TiとCore Ultra 7を組み合わせたもので、絶対的にハイエンドと呼べるわけではないのですが、ケースのエアフロー、電源の安定性、冷却設計など全体がバランスよく整えられていた。
自作でも同価格帯で似たような構成は作れるかもしれませんが、そこまでスムーズに組み合わせるのは簡単ではない。
率直に言って「やっぱりプロの手際は違うな」と感じました。
効率の良さに思わずうなずいた瞬間でした。
ですが、自分のこだわりを思う存分形にできるのはやはり自作です。
光るケースで個性を出したいとか、特定メーカーの冷却ファンを揃えて見た目の統一感を徹底したいとか。
こうした遊び心はBTOでは難しい。
学生時代、一人の友人がアルバイト代を費やして理想的なケースを選び抜き、完成したPCを自慢していた姿を覚えています。
正直羨ましかった。
だけど心から「これが自作の醍醐味なのだな」と思いましたし、その自己満足こそが特別な価値なんだと思います。
手間暇かけたからこそ愛着が深まる。
Apexを快適に楽しみたいなら、やはりBTOが有利だと思います。
届いたその日から遊べますし、何かあってもサポートがある。
ただ、もしパソコンを深く理解し、トラブルに直面しても自力で乗り越えるような経験を求めるのなら、自作に軍配が上がります。
どちらが正解、というわけではないんです。
学生にとって一番大切なのは、自分にとって今、本当に価値があるのはどちらかを冷静に見極めることだと思います。
準備に時間をかけず、安心して使用したいなら迷わずBTOを選ぶべきです。
迷う気持ちもわかります。
ただ選ぶべき軸は本当にシンプルです。
そこに尽きるんです。