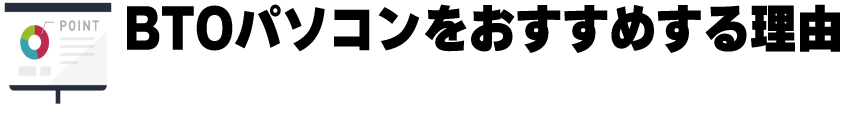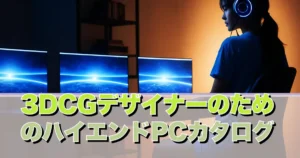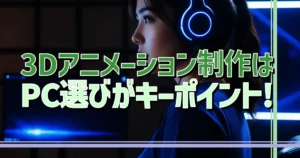クリエイターPCで求められるGPU性能のちょうどいい基準
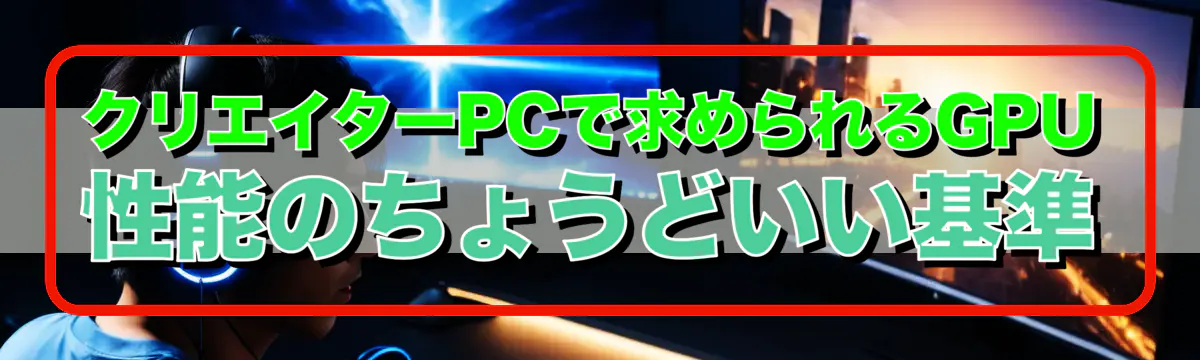
映像編集や3DCG制作をストレスなく進めるためのGPU選び
4K映像編集や3DCG制作のように負荷の大きな仕事をすると、やはりGPUの性能が作業全体の質を決めると実感してしまいます。
パワー不足のGPUを使うとプレビューですらまともに動かず、作業の途中で手が止まる。
これを何度も経験した私は「中途半端なものを買うと絶対に後悔する」と断言したい。
数秒のエフェクトをかけただけで、処理待ちがズルズルと長引く。
あの時間ほどイライラするものはないんですよね。
作業をしているつもりが、実質的にはパソコンのご機嫌待ちをしているような感覚。
あの時の胸のすっとする感じは今でもはっきり覚えています。
思わず「これだよ、欲しかったのは」と声が出てしまったほどです。
映像編集において一番ネックになるのがVRAM不足です。
プロジェクトが重くなるほど顕著で、気付いたときにはソフトが落ちて作業が飛んでしまう。
私は最低でも12GB、できるなら16GBは欲しいと感じています。
メモリが足りない瞬間に「もうこの機材は戦力外だな」と悟らされるのです。
これは本当に冷や汗をかく瞬間です。
3DCG制作においても状況は似ています。
私はBlenderを普段から使いますが、RTX4070Tiだと複雑なシーンで描画に時間がかかりリズムが崩れることがありました。
試しにRTX4090を触ったとき、その差は衝撃的でした。
AIを活用したレンダリングの速度が桁違いで、まるで別世界と言わんばかり。
でも、納期や効率を考えると「この差に払う価値はある」と思わざるを得ませんでした。
お金で時間を買うとは、まさにこのことだなあと痛感しました。
とはいえ、誰もが最上位モデルを必要としているわけではありません。
フルHDや2Kの制作が中心で、素材やレイヤー数がそこまで多くないのであれば、RTX4070クラスで十分。
むしろ持て余す性能を追いかけるのは浪費だと思います。
実際、私は「落とし所は4070前後が一番いい」という考えに落ち着いています。
無理に最初から突っ込む必要はありません。
ここで見落とされがちなのが、GPUの追加機能です。
最近はゲーム実況をしながら生配信したり、AIによるノイズ除去を裏で走らせたりする場面も多くなっています。
この場合、単にコア数やクロックが高ければ良いという話では終わらない。
新しい世代のハードウェアエンコード機能こそ効いてきます。
数字に目が行きがちですが、大事なのは自分の仕事の実態に役立つかどうか。
つまり、GPUは「スペック表ではなく実用面での相棒」という位置付けで見るべきなのです。
ここを勘違いすると、後々必ず後悔する。
私は自分の経験から、4K以上の編集や複雑な3DCGを本気でやるならRTX4070Ti以上。
けれどコストとのバランスを考えるなら4070が妥当。
この二択で悩む人は多いと思いますが、大事なのは「自分の作業に最もフィットするのはどれか」を冷静に見極めることです。
性能不足は制作のリズムを狂わせ、逆に性能が合っていると驚くほど快適に表現の幅が広がっていきます。
これだけは間違いないなと実感しています。
最終的には「GPU選びは機材選びではなく、仕事環境をどうデザインするかの判断」だと私は思っています。
躊躇して妥協すると、必ずどこかで足を引っ張られる。
逆に納得して選んだGPUは、毎日の仕事を心強く支える相棒になってくれる。
だからこそ仕事をする大人として「ここは絶対に外せない」と思うんです。
安心感って大事です。
自分が信じられる環境こそ武器です。
私はGPUを選ぶ時、単なるスペック比較ではなく「日々を支えてくれる道具」としての視点で見ています。
それこそが、成果物の質に直結し、自分のキャリアにも跳ね返ってくる重要な部分だからです。
スペックの数字に振り回されるのではなく、自分の仕事をどう広げたいか。
その答えを探すことが何よりのポイント。
これだけは胸を張って言えます。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 49113 | 100929 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32430 | 77302 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30414 | 66101 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30336 | 72701 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27399 | 68249 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26736 | 59644 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22140 | 56240 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20092 | 49985 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16704 | 38983 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16133 | 37823 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15994 | 37602 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14766 | 34575 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13862 | 30555 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13317 | 32041 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10916 | 31429 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10743 | 28303 | 115W | 公式 | 価格 |
AI処理を日常作業に組み込むときのグラフィック性能の現実
AI処理を業務に組み込むなら、私はRTX4070Tiクラス以上のGPUを選んだ方が安心だと考えています。
その理由はとてもシンプルで、実際に使ってみるとGPUの処理性能とVRAMの容量への依存度が思った以上に大きく、スペックが足りないと処理の待ち時間が積み重なり、仕事のリズムを簡単に崩してしまうからです。
動画編集と比べても負荷の掛かり方が全く違っており、わずかな遅れに見えても後から効率全体に大きく影響してきます。
私はこれを身をもって思い知らされました。
数字だけ見れば大したことがないと感じるかもしれません。
しかし実際は違います。
繰り返し作業の現場では、この20秒が何度も積み重なっていくんです。
50カット作成すればトータルで15分超。
正直なところ、待っている間に集中力は削がれるし、時間を無駄にしている感覚が重くのしかかる。
私はこの時、安さを追うよりも余裕のあるGPUを選ぶことが、精神的な安定にも直結すると痛感したのです。
「AIなんて遊びの延長だろう」と私は当初思っていました。
ところが実際に業務へ組み込もうとすると、それまでと全く違う世界が立ち現れます。
初めて触れるときは確かに驚きが大きく、遊んでいるような感覚に近い楽しさがある。
しかし一歩踏み出して業務ツールにしようとすれば、GPU不足で止まったり遅れたりする場面が必ず出てきます。
その瞬間に一気に現実味が増し、プレッシャーを否応なく感じさせられるんです。
さらに厄介なのは、AIの進歩が軽量化ではなくむしろ高負荷の方向に進んでいることです。
例えばAdobeの生成AIフィルター。
アップデートのたびに精度が上がり、便利さも確実に増しました。
しかし同時にGPU使用率は確実に上昇しました。
つまり、いま快適だと思える環境は、数か月後には物足りなくなる。
技術が進化するほど、必要なスペックも上がっていく。
この現実を繰り返し突きつけられて、私は未来を見越して準備することしかないと理解しました。
とはいえ、勘違いしてほしくないのは「とにかく最上位モデルを買え」という話ではありません。
RTX4070Tiは性能とコスト、そして電力のバランスが最も取りやすいラインだと私は実感しました。
これ以上のモデルは確かに性能は高いですが、価格や導入後の電力負担、発熱対策などを考えると現実的ではない。
逆にそれ以下のモデルにすると、最初は我慢できても業務が重なれば必ず「遅いな」とストレスを感じる結果になります。
つまり実務利用を考えるなら、4070Tiクラスこそ落としどころだと私は断言できます。
私は40代に入ってから特に「余裕の価値」を深く考えるようになりました。
無理に最高性能に手を伸ばす必要はない。
でも「待ち時間に振り回されない」という感覚は、毎日の生産性を守るために不可欠。
この意識が年齢を重ねるにつれて強くなってきましたね。
現場に運用を持ち込んで初めて、そのシビアな要求水準に直面します。
私はGPUを選ぶ過程で、理屈よりも体験で学んだ現実の重みをひしひしと感じました。
そして今でははっきりと言えます。
安心感。
これこそが投資に値する一番の理由なんです。
自分の時間を奪われない、焦りを感じない、その余裕こそ長く働くほどに大切な資源になる。
新しい製品を見て欲しくなる気持ちは否定しませんし、私もその誘惑に揺らぐことはあります。
それでも最終的に私が優先するのは、毎日の現場で「待たされずに済む」という確かな安心。
それがどんなに気持ちを楽にするか、身をもって知ったからです。
焦りをなくす選択。
私はこれからもGPUを含む道具選びでは、過剰なスペックよりも「余裕を買う」という視点を第一にしていきたい。
世の中の流れや新製品の出現に一喜一憂するよりも、自分の仕事の質を落とさないための現実的な投資を積み重ねるほうが、健全で持続可能だと強く実感しています。
高解像度出力を安定して扱えるGPUの選択ポイント
数値で示される演算性能だけを追いかけるのではなく、実際に安定して使えるかどうかこそ肝心です。
特にVRAMの容量は、編集を支える土台のような存在です。
12GBを切るとプレビュー中に途切れたり、レンダリングが不意に止まったりして、それまで積み上げてきた作業の流れがガタッと崩れます。
その経験をしてからは、私は数字以上に「余裕のある環境」を選ぶことの価値を強く意識するようになりました。
私自身、RTX4070を長く使っていた時期には苦い経験がありました。
Premiere Proでカラーグレーディングを少しかけただけで再生が止まり、何度も作業をやり直すことになったのです。
あの絶望感といったらありません。
時間ばかり奪われ、肩は凝るし、息の詰まるような思いをしたものです。
ところがRTX4070Tiに切り替えた瞬間、同じ作業がフルスクリーンでリアルタイムに動き出しました。
その時、「これだ!」と思わず声が漏れました。
数字では測れない快適さ。
GPUの評価をベンチマーク一辺倒で語る人は多いですが、私はそれだけではまったく不十分だと痛感しています。
机の上での数値ではなく、実際の現場での使い心地。
編集のリズムを壊さない安定性。
そういうものが日々の生産性を大きく左右するのです。
もう一つ忘れてはいけないのがドライバの安定性です。
私は長年NVIDIAのStudioドライバに助けられてきましたが、かつて他社製のGPUを試した際、挙動が不安定で肝心のプレゼン直前に画面が乱れたことがありました。
あの時の冷や汗は本当に忘れられません。
「やっぱり安定して動く環境って、何より大事だ」と骨身に染みました。
信頼できる道具があることこそ、仕事における最大の保険になるんですよね。
さらに気を付けたいのが出力ポートの規格対応です。
4Kや8Kの最新モニターをちゃんと動かしたいなら、DisplayPort1.4だけでは心許ない。
私は実際にHDMI2.1対応GPUで8K映像をプロジェクターに映したことがありますが、その時の鮮明さ、滑らかさ、そしてクライアントの驚いた顔が今でも忘れられません。
単なる映像出力と思ったら大間違い。
ここでも差がはっきり出ます。
仕事で複数モニターを同時に使う人ならなおさらです。
私もデュアルモニター環境で作業していた際、安価なGPUではフレームが落ち、プレビューがコマ送りのようになったことがあります。
その度に集中力が切れ、ため息ばかりついていました。
電源やCPUには投資している人でも、GPUの帯域には無頓着な場合が多い。
でも、実際に現場で苦労するとよく分かるんです。
GPUの帯域幅が編集の安定性を左右するのだと。
焦燥感。
機材選びは数字だけでは判断できません。
日々実務に追われながら私は「数字で見えない快適さ、安心感、そして信頼こそが真の価値だ」と思うようになりました。
夜中に一人で編集している時にGPUが安定して動く。
それだけで気持ちに余裕が生まれます。
そしてその余裕が、結果としてクオリティの高い仕事に結びつくのです。
けれど実体験ではまるで別物。
こんなにも違うのかと最初は驚きました。
性能表の数値だけでは決して見えてこない部分。
数値には現れないけれど、隣にいて安心できる存在。
そういう支え方をしてくれるのが適切なGPUです。
だから私は、もしWQHD前提であればRTX4070Ti以上を、4K映像編集や本格的なCG制作を織り込むならRTX4080以上を迷わず選ぶべきだと考えています。
中途半端にスペックの低いGPUを採用すると、必ずどこかでストレスが噴き出します。
私自身、そこで苦しんだからこそ断言できます。
そうすることで結果的に効率よく、精神的にも安定した作業環境を確保できるのです。
GPUはただの部品ではなく、仕事と生活リズムに影響を及ぼす相棒です。
机に向かう度にその存在を頼もしく感じ、安心できる。
だからこそ、私は経験を込めて「妥協しない選び方」を心から勧めたいのです。
最終的に良い仕事を持続して続けるためには、そこで妥協してはいけない。
最新GPUをクリエイターPCで実際に使ってみた印象
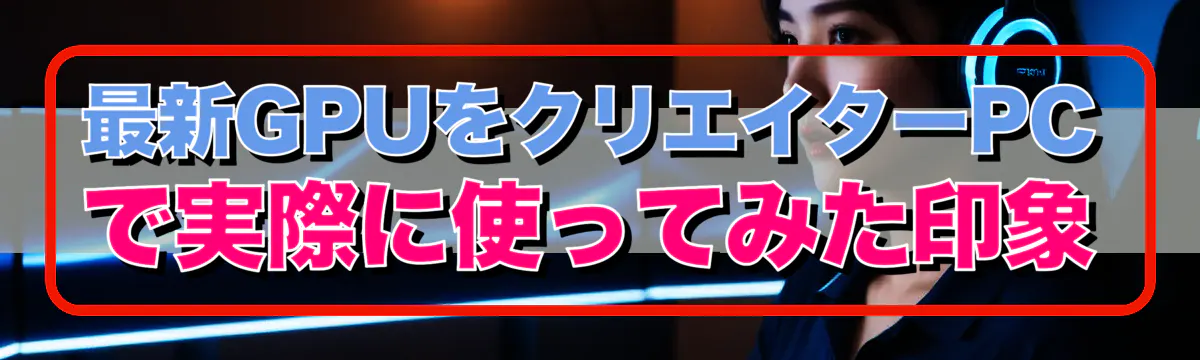
GeForce RTX 50シリーズを使って気づいたメリットと課題
導入してからというもの、まず感じたのは作業の流れが驚くほどスムーズになったことです。
もちろん新しい技術を取り入れるときは手間もお金もかかりますが、それ以上に得られるものがあると強く実感しました。
特に仕事のスピードと安定性の部分は、これまでの世代から明確に変わったと言えます。
RTX 5090を実際に使ったとき、最も大きかったのがレンダリングの待ち時間です。
以前なら「ちょっとコーヒーを淹れてこようか」と考えるくらい待たされた重い処理が、気づけばあっという間に完了している。
これには本当に驚かされました。
数字だけでは表しきれない作業フローの快適さ。
それこそが導入の価値なんだと実感しました。
厳しい納期に追われる現場で、中断せずに作業を続けられることの意味は大きいです。
納期遅延は信用を失う大きなリスクであり、クライアントからの信頼を守るためには一秒でも早い処理が必要。
そのプレッシャーの中で「これなら間に合う」と感じられるのは安心感に繋がるんです。
現場ではこの「ちょっとした安心」が仕事の質を左右します。
正直に言えば気になるのは消費電力と発熱でした。
5090を導入したとき、これまで使っていた850W電源では全く足りず、1200Wクラスに換装する羽目になったのです。
当初は「さすがにここまでは必要ないだろう」と思っていました。
しかし実際に稼働させるとGPU使用率が90%を超えることも多く、結局は余裕のある電源がなければ安定しないことを思い知らされました。
さらに冷却対策には手を焼きました。
静音ケースを選んでも内部の温度上昇は避けられず、結果的にファンの音が気になることに。
まさに高性能の代償。
性能を取るか快適さを取るか、これは悩ましい問題です。
メーカーごとの違いも体感しました。
ASUS製は冷却性能が優れていて、長時間でもクロックが落ちにくいのが魅力的だった一方、カード自体がかなり大きく、ケースに収めるのに苦労します。
逆にMSI製はサイズが抑えられているので省スペース環境に適していましたが、その分冷却では多少不安を抱きました。
こういう部分は机上のスペック表だけでは絶対にわからない点で、やっぱり事前の調査は欠かせないと痛感しました。
選択は環境次第。
この一言に尽きると思います。
AIで画像生成する際、レスポンスが速いことは日常業務の効率に直結します。
小さい差が積み重なって業務全体のスピードアップにつながるんです。
この効果は侮れない。
ただし、大規模なCG制作やAI動画生成のような重作業では5070では物足りず、5090が不可欠になる場面もあります。
それでも軽作業や画像加工といった普段使いの業務であれば5070で不満はほぼありません。
ここで強調したいのは、自分の用途をどこまで明確にできるかという点です。
正直、私も最初は「せっかく買うなら最高性能を」と思って5090を選ぶ気持ちが強かったんです。
しかし実際には「どんな規模の案件が多いのか」「納期はどれくらい厳しいのか」といった具体的な仕事の条件がGPU選びの基準になることに気づきました。
見栄や勢いで選んでも苦しむのは自分。
冷静な判断こそ必要です。
ただ、やはり納期が厳しく、データ量の多い案件を抱えている人にとっては5090の存在は心強い。
選択の焦点は「案件の種類」と「作業の重さ」です。
両者のバランスを誤らなければ、どちらを選んでも後悔はないはずです。
私が辿り着いた結論はシンプルです。
案件の負荷と納期に合わせて5070と5090を使い分ける。
それだけで、仕事の進め方が驚くほど変わります。
任された仕事を確実に仕上げるためには、安定して成果を出せる環境を整えることがプロに求められる責任。
仕事をする以上は、最適な一枚を選ぶ判断を誤ってはいけないんです。
安心感。
これこそがRTX 50シリーズを導入する最大の理由だと、私は心から感じています。
Radeon RX 90シリーズを選んでみて分かった魅力と注意点
先日、作業環境を刷新しようと意を決してGPUを入れ替えました。
今回選んだのはRadeon RX 90シリーズです。
Premiere Proを使って8K映像を扱った際、以前はわずかながら気になっていたタイムラインでのカクつきがほぼ解消され、流れるような再生が実現したのです。
このときの安心感といったら、表現しづらいほどで、正直胸を撫で下ろしました。
効率アップのイメージが一気に広がり、肩の力が抜けるような気分になったのを今でもはっきり覚えています。
40代も半ばを越えると、新しい機材に挑戦するたびに「失敗したら嫌だな」と足が止まりがちになります。
でもその一方で、「やってみなければ分からない」という気持ちも根強く残っていて、その狭間で揺れる。
今回ばかりは、リスクを取って良かったと心から言えます。
挑戦に踏み切った自分を素直に褒めたいと思いました。
実際、GPUの稼働率は概ね70%前後で落ち着き、CPUへの負担が極端に跳ね上がる場面もありませんでした。
動画編集は思った以上に長期戦になります。
そのときに小さな部分が安定していると、集中力の持続に直結するんですよね。
長時間でも淡々と作業できる。
これが何よりありがたい。
ただ当然ですが、弱点もありました。
特に3D関連作業です。
Blenderで物理シミュレーションを走らせたとき、RTX系では軽やかに処理できる場面が、Radeon環境では妙に引っかかることが少なくなかったのです。
ある瞬間にGPUがまるで沈黙したかのように固まったとき、思わず「ちょっと勘弁してくれよ」と独り言が漏れました。
改めて得意と不得意が分かれる製品だと肌で実感しましたね。
幸い私は3D制作を仕事の主軸にしていないので致命的な問題にはなりませんでしたが、3Dが主役の方には迷いが生まれるだろうと思います。
用途との相性、大事です。
気になる点はもう一つ。
消費電力です。
フル稼働時には450Wを超えることも実際にあり、それに伴い電源ユニットも高容量かつ高品質なものに交換せざるを得ませんでした。
さらに冷却対策も不可欠で、水冷や風通しの良いケースを用意しなければ、熱があっという間にこもる。
性能は非の打ちどころがないのに、環境が整っていなければストレスの種になってしまう。
結局、私の方も電源とケースを一式入れ替える羽目になり、「最終的にこっちが本体より高くついたんじゃないか」と苦笑いしました。
それでも描画力については一言でいうと圧巻でした。
複数のカラーグレーディングを重ね合わせても処理落ちが起きず、自然な発色が目の前に広がる。
夜中に作業することもありますが、その豊かな色彩はむしろ疲れをやわらげ、やる気を少し取り戻させてくれるのです。
最高の時間でした。
映像業界の現場では近年、Radeon Proシリーズが選ばれるケースもあり、その技術が家庭用・一般用製品にも降りてきている現状を見ると、まさに流れが変わり始めていると感じます。
自分の机の上でその一端を体験できたこと自体、この歳になってもまだ進化の波に触れられるんだなと嬉しくなりました。
ワクワク感に勝る力なし。
よくよく振り返ると、私はそもそも「万能な一台」を探していたわけではありませんでした。
自分が最も多くの時間を費やしているのが動画編集とカラー調整。
その領域で裏切らないものが欲しかったのです。
そう考えればこの選択は正しかった。
もしあなたが3Dレンダリングを日常的に行い、その結果が仕事の成果に直結する立場ならば、素直にRTXを選んだ方が良いでしょう。
しかし映像やカラー調整を重視するならば、Radeon RX 90シリーズが大きな手助けになるはずです。
私が行き着いたのはシンプルな答えです。
動画やグラフィック中心ならこのGPUは強力な武器になる。
逆に3D寄りならば、無理なく別の選択をした方が後悔は少ない。
妥協ではなく、自分が実現したい表現にフィットした機材を選ぶ。
これこそ満足を得る近道だと痛感しました。
年齢を重ねると失敗したくない気持ちが強くなります。
だからこそ今回の選択は、自分にとって間違いなく正解の一歩でした。
そして改めて実感しました。
機材選びのすべてを決めるのは「目的」です。
レビューや派手な数字に惑わされるよりも、日々の自分の過ごし方や作業の優先順位を見つめること。
結局、大人になってからの買い物で重要なのはそこだけなんですよね。
目的を見失わないこと。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60TI

| 【ZEFT R60TI スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63I

| 【ZEFT R63I スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YC

| 【ZEFT R60YC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BA

| 【ZEFT R60BA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster COSMOS C700M |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
動画編集向けGPUを実機で比較して感じた差
レンダリングのベンチマークスコアや数値的な性能差を見比べることも大切ですが、実際には長い時間ソフトと向き合い、映像を切り貼りし、何度もプレビューを確認する。
そのときに再生が止まらないかどうかが心を支えるのです。
これは性能表からは絶対に伝わらない部分で、経験した人なら皆うなずいてくれるはずだと自負しています。
私自身、これまで何度かGPUの買い替えを繰り返してきました。
RTX4060から始まり、4070、そして最終的には4090まで使ってきたのですが、それぞれで感じたのは「数字ではなく体感差」の大きさでした。
4070に切り替えた瞬間に、色補正ツールのスライダー操作に対する反応がワンテンポ遅れず返ってきたときの快感は忘れられません。
小さな差に見えても、1時間、2時間と作業を続ければ体の疲労感が全く違うのです。
「おー、これはストレスが減るな」と声が出たほどでした。
実際、RTX4060を使っていた頃は、「まあこんなものか」と自分を納得させる場面が多かったのですが、4070に変えたらその納得が単なる我慢だったと気づかされました。
自分でも知らないうちに編集時間が伸び、イライラを抱え、効率を落としていた。
こうした実感を得たことで、GPU選びには妥協してはいけないと確信するようになりました。
さらに、私が甘く見ていたのがVRAMの容量です。
ところが4Kマルチカメラ編集や複数の素材を重ねる作業では、8GBだとどうしても処理が引っかかる瞬間があり、そのたびに「ああ、これか」と思わされる。
見えないところでGPUが悲鳴を上げているのがこちらに伝わるようで、その圧力は数字以上に精神的な重みを持ちます。
「無理させてるな」という感覚です。
そして、4090を初めて実機で使ったときの衝撃は今も鮮明に覚えています。
8K ProRes素材をDaVinci Resolveでロードした瞬間、普通にリアルタイム再生できてしまう。
笑うしかなかったです。
「本当に今の時代はここまで来たのか」と驚きと嬉しさが入り混じり、思わず一人で声を上げてしまいました。
以前の3080では待ち時間が長すぎて心が折れそうになっていたのに、たった一世代変わるだけでこの変化。
投資額は確かに大きいですが、その精神的な解放感に比べれば十分に見合います。
ただし、4090や4080を導入したときに困ったのが発熱と騒音です。
特に小型ケースで4080を使ったときには、いくら吸排気を工夫してもファンの音が収まらず、静かな部屋で作業していると耳障りになりました。
正直、「うーん、これじゃ集中できないな」と独り言を漏らしたくらいです。
性能に満足しながらも同時に環境づくりの難しさに直面し、GPUの選び方は単に性能だけではなく、静音性や省電力といった観点も必要だと痛感しました。
ここはぜひメーカーに期待したい部分ですね。
Adobe Premiere Proで4070を使ったときも、私は十分に満足しました。
特にエクスポートの速さは見事で、待ち時間が一気に短縮され、夜中の書き出し作業で「ああ、助かった」と心底思いました。
出張の前日に納期ギリギリの案件を抱えているとき、30分削れるだけでもどれほど気が楽になるか。
数字の性能よりも、その安心感に胸をなでおろす瞬間の価値は大きいのです。
私は声を大にして言いたいのです。
GPUを選ぶ基準はベンチマークスコアではなく、タイムラインの滑らかさであると。
それによって作業の楽しさや集中力が保たれ、結果的に効率が大きく変わります。
GPUは道具ではありますが、同時に長時間の戦いを一緒に乗り越える相棒でもある。
その相棒に中途半端な選択はできないのです。
したがって、私の結論はこうです。
フルHDから4Kを編集する方なら4070が最もバランス良い選択です。
コストと性能の比がちょうど良く、安心して長時間向き合える環境を作れます。
そして8Kや重いカラーグレーディング、多層エフェクトを日常的に処理するなら、迷わず4090を導入すべきです。
確かに高額投資ではありますが、ストレスの削減と得られる時間の価値を知れば、決して高すぎる買い物ではないと思います。
長時間の編集は心も体も大きく削っていきます。
だからこそGPU選びにおいて妥協は禁物です。
私が体験を重ねてたどり着いたのは、その一点でした。
自分にとっての最良の相棒を選ぶこと。
それが編集を続けていく上での最大のカギだと確信しています。
安心感がある環境。
作業に没頭できる余裕。
この二つを得られることこそが、長く映像制作を続けるために最も大切なことだと私は思っています。
コストと性能バランスで選ぶクリエイターPC向けGPU
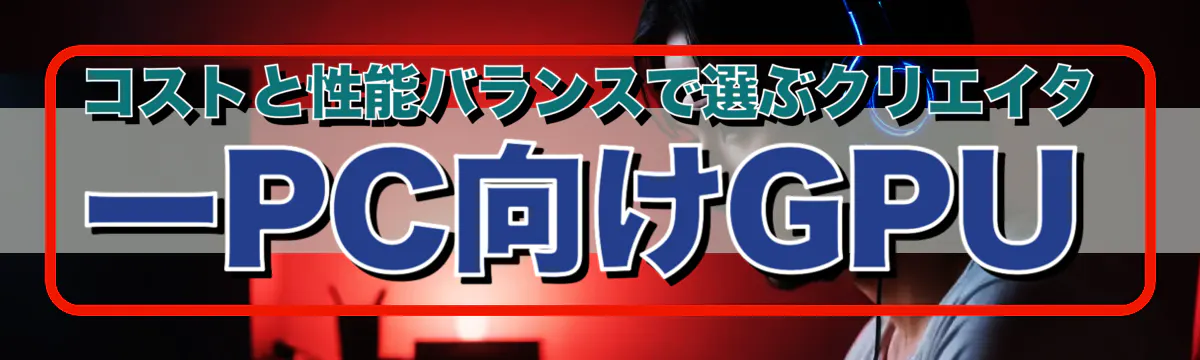
ミドルレンジGPUで実際にどこまで作業がこなせるか
私自身がRTX4070を導入して最初に驚いたのは、10分ほどの4K映像に複数のエフェクトを重ねても再生がカクつかず、プレビューが流れるように動いてくれたことでした。
その時、胸の内で思わず「やるな」とつぶやいてしまった記憶があります。
ただし、夢ばかり見てはいけないのも事実です。
After Effectsで3Dコンポジットを組むような場面や、本格的なレンダリング処理を伴うプロジェクトでは、その余裕が一気に削がれてしまいます。
つまり、本当に映画や大規模CG制作を目指すなら、結局はハイエンドGPUへの投資が避けられないというのが現実なのです。
ゲーム実況やYouTube編集の範囲なら頼もしい相棒になってくれるのですが、それ以上に踏み込めば「さあどうする」と腹を括る場面が訪れます。
現実は厳しい。
面白さを感じたのは、生成AIを駆使した補助機能を試したときでした。
ノイズ除去やカラー補正などの処理は信じられないくらい速く、それこそ魔法に近い感覚で「今の、すぐ終わったよな」と思うほどでした。
しかし一方で、AIによるフレーム補間や自然言語からモーショングラフィックスを作るような重たい作業に挑戦した瞬間、PCの中からうめき声が聞こえるようでした。
GPUもCPUも容赦なく負荷を抱え込み、「これはまだ日常作業に実用できないな」と首をかしげたのを今でもはっきり覚えています。
新しい技術の眩しさと同時に、残酷なまでの限界を突きつけられる。
そんな二面性を実感しました。
思い返せば、以前私はRTX4060からRTX4070へと買い替えました。
その時「これで数年は戦える」と胸を張っていたんです。
正直なところ、安心感がありました。
スマートフォンの世界で、1年で一気に旧機種扱いされるあのスピード感と同じ構造だと痛感しました。
それでも私なりに導き出した答えははっきりしています。
今のところ動画編集を行うなら、RTX4070クラスのGPUを軸に考えるのが最も現実的です。
これより下のクラスへ妥協すると、作業のたびに小さなストレスが積み重なり、気づけば「なんで最初から投資しなかったのか」と後悔することになりがちです。
逆にさらに上位モデルを選んでも、費用対効果という視点に立てば疑問が残る。
結局のところ、性能とコストがちょうど交わる中間地点がミドルレンジ上限のモデルであり、そこが非常に実用的な選択肢となるわけです。
ただし、これはすべての人に共通する正解ではありません。
映像制作でも大規模なCGを扱う方にとってはハイエンドGPUは必要不可欠でしょうし、カット割りや簡単な編集しかしない場合ならもう少し下のクラスで十分役目を果たします。
ですが、私自身が日常的に作業に向き合っていて思うのは「これ以上はストレス」という明確な境界線があること、そしてその先に少なくとも数年は耐えてくれる余裕があるかどうかが非常に大事だということです。
これを軽視すると、結局また追加の投資に迫られてしまう未来が見えてしまいます。
厄介なものです。
技術革新の流れは誰にも止められません。
そして止めるべきものでもないのでしょう。
私たちができるのは日々変わり続ける新しいツールを捉え直し、自分の仕事にとって必要な範囲と余裕をしっかり見極めることです。
進化を追いかけながらも、自分の時間や心の安定を守れる地点を見つけるしかありません。
私はそう痛感しています。
仕事に集中するための道具。
私にとってそれは、今のところRTX4070クラスのGPUです。
だから今は胸を張ってこう言えるんです。
でもハイエンドに飛びつく必要もない」。
ミドルレンジ上限、これこそ現状の私にとって最適解であり、間違いなく信頼できる相棒です。
予算15万円前後で考えるバランスの良い構成例
予算15万円ほどでクリエイター向けのPCを組むとき、一番大切なのはGPUだけにお金をかけずに全体のバランスを意識することだと、私はこれまでの経験から強く思っています。
性能の派手さに目を奪われてGPUだけ豪華にしてしまうと、実際の作業効率は思ったほど伸びず、逆に処理が重く感じてイライラしてしまう。
そういう苦い思いをしたことがあるんです。
パソコンは数字ではなく、日常的にストレスなく作業できるかどうか、それが本質だと思いますね。
GPUを選ぶなら、私は現実的にGeForce RTX 4060 Tiが最適だと考えています。
理由は単純で、性能と消費電力、静音性のバランスがとても良く、これぐらいのクラスであればAfter EffectsやDaVinci Resolveを使って4K映像を編集しても、プレビュー再生が途切れにくい。
実際、Premiere Proでタイムライン再生をしたときもカクつかず動いてくれました。
その瞬間、ああこれだ、欲しかったのはこの安定感だと心から思ったのを覚えています。
けれど実際に見積もりを組んだら、他のパーツに予算を回せなくなり、メモリが16GBしか積めなかった。
結果、4Kの映像素材を扱うとすぐにカクつき、編集がまともに進みませんでした。
これに尽きますね。
私が改めて選び直したのはRTX 4060 Tiに予算を抑えて、その分メモリを32GBに増設する構成でした。
この判断が功を奏しました。
マルチカメラ編集やカラーグレーディングといった負荷の高い作業でも目立ったカクつきが減り、作業の途中でタスクマネージャーを開いてメモリ使用率を眺めながら「よし、間違ってなかった」と小さく安堵しました。
こういう納得感って、仕事のモチベーションにも直結するものなんですよ。
忘れてはいけないのがSSDです。
ここを軽く見てはいけない。
私は以前、価格を優先して1TBのSATA SSDに妥協したことがあります。
でもそれが大失敗で、キャッシュや素材のコピーに余計な時間がかかり、編集作業のリズムが何度も途切れました。
その後、思い切って1TBのNVMe SSDを導入したら、一気に作業効率が変わった。
大容量素材を読み込んでも一瞬で準備が整い、書き出しもストレスがない。
GPU、メモリ、SSD。
この三つがしっかり揃ってこそ、限られた15万円前後の予算でも実戦で使える環境が整います。
どれか一つに極端にお金をかけるよりも、それぞれを適切に組み合わせて三本柱を崩さないこと。
それが快適さを決定づけると思います。
派手さではなく地道な安定性。
特に近年は生成AIやPhotoshopの新機能のようにGPUの計算能力を利用する場面が一気に増えています。
こうした流れにもしっかり対応できるのがRTX 4060 Tiクラスです。
上を目指し始めればRTX 4070や4080が視野に入りますが、それをやると予算が跳ね上がり、結局「ここまで要らなかった」と感じてしまう可能性が高いんですよね。
必要十分な性能を確保しつつ背伸びしすぎないこと、これは私が痛い経験をしてから強く意識していることです。
私が最適解だと考える構成ははっきりしています。
GPUはRTX 4060 Ti、メモリは32GB、そしてSSDは1TB NVMe。
このシンプルな組み合わせです。
一見、地味に思えるかもしれませんが、実際の現場作業では抜群に効いてきます。
安心できるし、現実的。
この構成を組めば、編集業務だけでなく最新のクリエイティブワークにも柔軟に対応できます。
私は仕事柄、複雑なプロジェクトを扱うことも多いのですが、この環境にしてからは作業中に余計な不安が減り、本当に集中できるようになりました。
その違いは大きい。
私はこれまで幾度もパーツ選びで迷い、時に失敗し、また学び直してきました。
40代になった今、思うのは、高すぎる性能を追いかける必要はないけれど、必要な箇所を見極めて田舎の職人のように誠実に予算を振り分けていくことこそ成功への鍵だということです。
高望みしても結局のところ実務で役立たなければ意味はない。
最終的に必要なのは、使っていて安定し安心できる環境です。
安心感。
信頼できる作業環境。
PCパーツを調べているとついスペックばかり追いがちですが、私が身をもって学んだ教訓は、見た目よりも実効性を重んじること。
一見派手ではないけれど結果が出る。
だから私はこれからも変わらないであろう答えを持っています。
GPUはRTX 4060 Ti、メモリは32GB、SSDは1TB NVMe。
この鉄板の組み合わせ。
15万円という予算の中できちんと安心して働ける自作PCを実現するなら、この構成がベストだと胸を張って言えるのです。
そして最後に一言。
長期間安心して使えるGPU世代を見極める方法
私は実際に自分で試したうえで、今後数年間を安心して乗り切るためには、NVIDIAのRTX40シリーズの中でも最低でもミドルレンジ以上を選ぶべきだと感じています。
単純な計算能力があるかどうかの話ではなく、大切なのは十分なVRAMを備えているか、最新のエンコード技術やアクセラレーション技術に対応しているかどうかです。
現場のソフトウェアは進化をやめませんし、その進化に乗れるかどうかで作業効率だけでなく気持ちの余裕まで変わってしまう――私はそう痛感してきました。
過去に私は実際、RTX4060 TiとRTX4070を使い比べたことがありました。
当初は「予算を抑えたい」という気持ちが強く、4060 Tiを導入したのですが、4K動画を本格的に扱い始めるとすぐに違和感が出てきました。
複数の素材をタイムラインに並べると再生がスムーズにいかず、気づけば小さな引っかかりにイライラして集中力を持っていかれる。
数日間は正直、気分が滅入りましたね。
あのときは作業する気力そのものも落ちていました。
そこで4070に切り替えてみたら、まるで別物でした。
同じ環境にもかかわらず動作がなめらかになり、呼吸が一つ楽になるような感覚で「あ、やっと肩の力が抜けた」と思えたんです。
性能差以上に、ストレスから解放された安堵感が鮮烈に残りました。
これは単なる快適さの問題ではなく、心の余白を守る投資なんだと感じた瞬間でした。
GPUを選ぶときに数字ばかりに目を向けてしまいがちですが、その姿勢は危険です。
ベンチマークの数値は参考にはなりますが、自分が実際に使うソフトがどういう前提で設計されているのか確認しなければ意味がありません。
最新のエンコーダーに対応していれば、それだけでレンダリングの時間が半分になることも珍しくなく、同じ一時間の作業が三十分で終わるという状況もあり得ます。
この効率化の恩恵が積み重なれば、一年で換算すると膨大な削減になることを、私は実体験として知りました。
VRAMの容量も後々大きな分かれ道になります。
安価なモデルを手にしがちですが、プロジェクトが膨らむにつれて「もう容量が足りない」と叫びたくなる瞬間が訪れるのです。
もしそこで足りなくなれば、作業の途中でGPUを差し替える羽目になり、コストも時間も二重に失う。
これは本当にもったいない経験で、私自身、かつて一度だけ同じ轍を踏んでしまい、心底後悔しました。
それ以来は「安さ」だけに釣られないようにしています。
数年前、リモートワークが一気に社会に定着したときと同じ勢いを感じます。
そうなると、GPUが制作基盤そのものを支える役割に変わりつつあり、Tensorコアや十分なVRAMがあるかどうかが今後の作業の余裕を決めるのです。
それが今は当たり前の判断基準になっています。
安心感が欲しい。
それだけのために上位モデルを選ぶというのは、決して贅沢ではないと考えます。
CUDAコアの数値だけ眺めるのではなく、自分が走らせるソフトが次に何を要求するのか、その先を意識しておくことが、自分自身を助ける近道です。
無駄な不安を抱きながら仕事をするより、余力をもった環境で機嫌よく作業を進められることの方が、社会人にとってはよほど大切な価値ではないでしょうか。
振り返ると昔の私は、CPUのアップグレードばかりに心を奪われていました。
しかし実際には、作業を重くしていた原因の大半はGPU側にありました。
動作がもたつくのはGPUのボトルネックが原因であることを理解するまでに無駄な時間を費やしてしまったんです。
だから今ははっきり言えます。
無理をしてでもGPUは上の世代を選ぶべきだと。
これは机上の分析ではなく、実体験が染み付かせた答えなのです。
実際に私は「RTX4070以上を選んでおけば、まずは間違いない」と強く思います。
確かに価格を抑えたモデルには手を伸ばしやすい魅力があり、財布の事情からつい揺れることもあるでしょう。
ですが、その価格差で得られる安心と効率を数年にわたって考えれば決して高い投資ではない。
むしろ精神を削られるストレスの方がコストとして大きいのです。
だから私はあえて断言します。
悩む時間がもったいない。
4070以上を選んだ瞬間に、肩から大きな荷物が落ちていくような感覚を味わえるはずです。
納得感が残る。
その確かな手応えは、単なる性能差を超えて、日常的に制作を楽しませてくれるのです。
クリエイターPCを組むときに考えたいパーツの組み合わせ
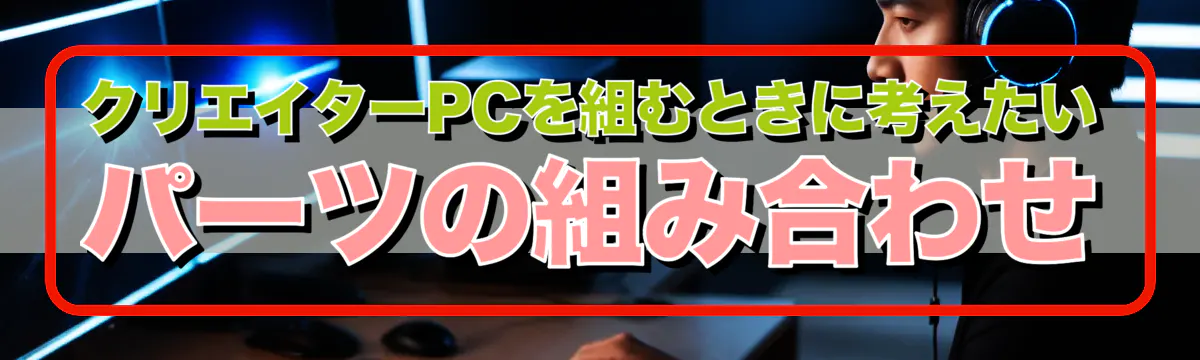
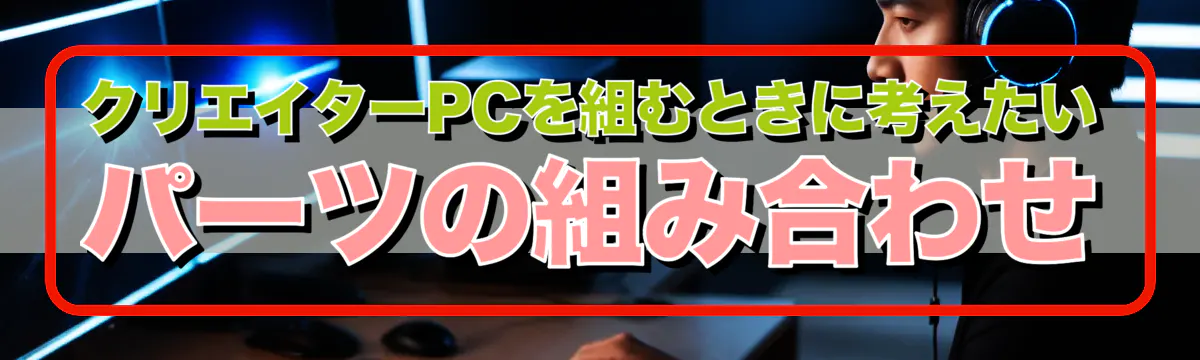
GPUを十分に活かすためのCPUとメモリの選び方
GPUの性能を余すことなく発揮させるには、やはりCPUとメモリの存在を軽く見てはいけない、私は強くそう感じています。
かつて映像編集用に最新のGPUを導入して期待を膨らませたものの、CPUを妥協したせいで処理が遅く、再生がカクついて思うように作業が進まず、胸の奥でイライラが募っていくのを抑えられませんでした。
結局のところ、CPUの力がなければGPUは力を出し切れない。
だから私は今、PC構成を考える上で「まずCPUを軽視しないこと」を最優先に伝えたいのです。
特に編集作業では「わずかな待ち時間」が重なって集中が削がれる感覚が何よりつらい。
Adobe After Effectsで複数のエフェクトを重ねたとき、GPUだけなら十分対応できるだろうという自信も、実際にはCPUがついてこられず、再生は止まりがちになり、心が折れそうでした。
あの瞬間、「頼むからもう少し動いてくれ」とパソコンに語りかけるほどでしたよ。
CPUの不足がどれだけ作業の進行を壊すか、身をもって知ったんです。
さらに、メモリの影響も軽んじてはならないものです。
かつて32GBで複数のPremiereプロジェクトを並行処理していたとき、たびたびフリーズに見舞われ、そのたびに「またか…」と小さくため息をついていました。
あの体験は今でも鮮明に心に残っています。
安心感。
CPUは全体を取り仕切る指揮官のような存在です。
そしてメモリは次に必要な情報を抱えた影のサポーター。
GPUは、CPUとメモリが整えた環境を受けて華やかに活躍する主役。
どれが欠けても流れは滞り、GPUは眠ってしまう。
だから「GPUだけよければ大丈夫」という誘惑に流されてはいけないと、私は失敗を通じて痛烈に学んだのです。
CPUのマルチスレッド性能とGPUの描画力が噛み合い、レンダリング速度が明確に伸びた瞬間、体が震えるほど嬉しかったのを覚えています。
私の中で「これならやれる」と喝采を叫びたくなるほどの手応えでした。
もちろんノート向けの省電力モデルは魅力があります。
持ち運べる利便性や電力削減の恩恵は無視できない。
しかし、本気のクリエイティブ作業では一気に限界が顔を出してしまう。
CPU性能を惜しんだ構成では、結果的に出力速度に倍以上の差が生じ、時間と労力を無駄にする羽目になる。
そのギャップを目の前で見せつけられたときに、「安さや手軽さを優先することで、逆に損をしてしまうんだな」と痛感しました。
効率。
実際にどう選ぶべきか、迷う方も多いと思います。
経験からいえば、4K編集や3D制作など重めの用途では、12コア以上のCPUと64GBのメモリが理想的です。
一般的な編集業務やそこまで負荷の高くない用途でも、最低でも8コアCPUと32GBメモリを用意しておけば長期的に安心でしょう。
理由は明確で、その構成なら今だけでなく数年後のソフトウェアの進化やデータ増加にも堪えられるからです。
PCは買ったそのときが最大性能ではなく、年月とともに負荷が増すもの。
だからこそ余裕を持って選ばなければいけないんです。
私自身も「そこまで必要ないだろう」と甘い見積もりで組んで、後悔を重ねました。
年々増える容量、進化するソフトにPCがついていけなくなり、そのたびに追加で投資する羽目になった。
後から買い足して辻褄を合わせる心労は計り知れませんでした。
そこで私は嫌というほど身に沁みました。
「最初にしっかり投資しておけば良かった」と。
振り返れば、一番の学びは「GPU一筋では未来はない」という現実でした。
GPUの力は確かに圧倒的です。
しかしその力を支えるCPUとメモリの存在を忘れてはならない。
映像編集や3D制作で結果を出そうとするなら、3者の調和がなければならない。
今の私が言えるのは、この一言に尽きます。
だから声をかけたい。
本気でGPUの力を引き出したい人に。
CPUを脇役扱いするべきではない。
数字の見栄えだけで判断するのではなく、全体の均衡を見ること。
これが肝心です。
私はそう確信しています。
最終的にはバランス。
すべてはそこなんです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43437 | 2442 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43188 | 2247 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42211 | 2238 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41497 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38943 | 2058 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38866 | 2030 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37621 | 2334 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35977 | 2177 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35835 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34070 | 2188 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33203 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32833 | 2082 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32721 | 2173 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29522 | 2021 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28802 | 2136 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25683 | 2155 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23298 | 2192 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23286 | 2072 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 21046 | 1842 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19684 | 1919 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17893 | 1799 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16192 | 1761 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15428 | 1963 | 公式 | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CO


| 【ZEFT R60CO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GE


| 【ZEFT Z55GE スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WX


| 【ZEFT Z55WX スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FT


| 【ZEFT R60FT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BC


| 【ZEFT Z52BC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
作業スピードに直結するストレージの性能と構成
パソコンの作業効率を大きく決めるのは、やはりストレージの構成だと強く感じています。
CPUやGPUの性能を追い求める人は多いですが、実際に長時間の作業や重い処理をしてみると、最後に作業の快適さを左右するのはストレージの速度や使い分け方です。
私はこれまで多くの現場でその違いを経験してきました。
そして最も安定して成果を出す方法として、システム用と作業用のNVMe SSDを分けるやり方こそ、一番信頼できる答えだと確信しています。
当時はまだコストを抑えようと安価なSATA SSDを使っていたのですが、プレビューを再生するとカクつきが止まらない。
あの時の苛立ち、今でもはっきり覚えています。
スペック表の数字だけでは分からない落とし穴があまりにも大きかった。
実作業の厳しさ。
その後、試行錯誤を経て今の環境はかなり改善されました。
システム用にPCIe Gen4接続の高速NVMe SSDを入れ、作業データ用に別のNVMe SSDを割り当て、バックアップには大容量のHDDを組み合わせています。
この構成にした途端、ソフトの起動が一瞬、数十GB単位の素材読み込みもほとんど待たされない。
あの時のストレスがうそのように消え、作業に集中できる環境になりました。
正直、この変化には感動しましたね。
ただ、何も考えずに「SSDなら全部速い」と思ってしまうのは危険です。
私自身、そう思い込んで痛い目を見たことがあります。
例えば、GPUがPCIeの帯域を大量に使っているのに、そこへ無理に複数のSSDを挿して性能が頭打ちになるケース。
理屈では知っていても、まさかここまで影響するとはと驚きました。
机上のスペック表を眺めているだけでは分からない。
やはり実際に何度も構成を組んで、実務で試さないと本当の答えにはたどり着けないと痛感しました。
最近使ったSamsung 990 PROの体験も忘れられません。
4K映像を編集するとプレビューがスムーズで、映像が途切れることがない。
もちろん発熱はそれなりにあるので、ヒートシンクやエアフローを意識する必要がありますが、きちんと冷却対策をしてやれば安定性も文句なし。
一方で、私は今でもHDDを手放してはいません。
バックアップやアーカイブにおいては依然としてHDDが現実的な選択肢だからです。
半年、一年と寝かせて保存するデータはSSDよりもHDDのほうが安心できる部分もあります。
大切な素材を丸ごと預ける場面では、まだまだなくせない存在です。
SSDとHDD、それぞれの得意分野を見極めて使い分けることが、結局はベストなんだと思っています。
若いころの私は、正直な話「新しい規格=正義」で、速さこそが正義だと信じていました。
新しいSSDが出れば飛びつき、速いベンチマーク結果を見ては自分を納得させていました。
求められるのは安定的な作業環境であり、バランスです。
速度と同じくらい、信頼性とコストも大事。
長時間作業を続けたときに精神的に疲弊しない構成でなければ意味がないんです。
安心感。
そして今、辿り着いた結論はシンプルです。
システム用NVMe SSDと作業用NVMe SSDを分け、保存用は大容量HDDに任せる。
この手堅い組み合わせに勝る方法はありません。
派手さはありませんが、確実に作業を支えてくれる基盤。
それこそが現場で求められる答えなのです。
もしこれからPCを組んでクリエイティブな作業に挑もうとする方がいたら、私が迷わずおすすめするのはこの構成です。
なぜなら効率的で実用的であり、何よりも安心して作業に没頭できる環境を与えてくれるからです。
途中で映像が止まらない、エクスポートが遅延しない、保存に不安を抱かない。
その積み重ねが仕事の成果に直結します。
この「中断されない」という安心の大きさは、実際に体験するまでは分かりにくいものですが、一度味わってしまうともう戻れません。
いうなれば作業を支える土台であり、信頼できる道具です。
システムと作業用にNVMe SSDをしっかり分け、保存用途をHDDに委ねる。
これこそが時間を無駄にせず、安定した結果を出すために最も現実的で強力な方法だと、今の私は胸を張って言えます。
効率を追うだけではなく、安心して続けられる仕組みを用意すること。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
安定動作のために重視すべき冷却とケース設計
安定したクリエイターPCを作る上で、本当に大切なのはやはり冷却とケースの設計だと強く感じています。
どんなに高性能なパーツを積んだとしても、冷却が甘ければその力は発揮されません。
むしろ中途半端な設計で熱がこもれば、突然の停止や処理落ちを引き起こす。
それはただの数字上の話ではなく、私の仕事そのものを止める深刻な問題でした。
数年前、私は高性能GPUを手に入れて心が躍っていました。
けれど初めてのレンダリングでクロックダウンが発生し、画面が固まり、額にじんわりと汗がにじみました。
あのときの絶望感はいまだに忘れられません。
せっかくの投資が台無しだと歯噛みしましたし、なぜもっと冷却設計を考えなかったのかと悔やみました。
特に最近のハイエンドGPUは電力も発熱も桁違いに大きい。
純正のクーラーが立派に見えても、それを活かせるかどうかはケースのエアフロー次第なのです。
透明パネルで見栄えを優先したコンパクトケース。
正直オシャレではありますが、実務では恐ろしくて使えません。
私は実際にRTXシリーズを導入した際、安易にスタイリッシュなケースを選んだことで痛い目を見ました。
レンダリング中にファンが悲鳴を上げ、温度が急上昇。
クロックダウンが起きるたびに進行中の作業のテンポが落ち、「頼むからこれ以上邪魔しないでくれ」と思わず机を叩きたくなりました。
結局そのケースを諦めることになりましたが、その失敗は大きな教訓です。
吸気と排気の流れを素直に作れるケースこそが最適なのだと。
ただ、冷却ファンをやみくもに増やせば良いという話でもありません。
内部の空気がスムーズに流れなければ、ファンの数が多くても熱は滞留します。
あの時財布を痛めてまでした投資を思い出すと、本当に腹立たしい気持ちになったものです。
無駄使いでした。
その後、私はFractal Designのケースに買い替えました。
これが衝撃でした。
側面パネルや前面のエアフローがしっかり考えられており、GPUを全力稼働させても安定した温度に収まってくれるのです。
60度台で安定して動き続ける様子を確認したとき、胸を撫で下ろしました。
「ようやく安心して作業できる」とホッとしたのです。
それに静音性まで兼ね備え、作業中の集中が途切れない。
環境そのものが一気にレベルアップしました。
もちろんCPUクーラーも忘れてはいけません。
私はかつて高さ制限を見落としたケースを選び、泣く泣く購入したばかりの空冷クーラーを諦めたことがあります。
あの時は自分に呆れ、頭を抱えました。
ただ、逆に言えばそうした失敗があったからこそ、ケースとクーラーの相性を徹底的に確認するようになりました。
簡易水冷をケース上部に配置すると、熱の流れ全体が改善されると実感したのもその後の学びです。
長時間のレンダリング作業や映像編集は、やはり冷却が安定していなければどうにもなりません。
私はこの数年、冷却とケースの設計にしっかりこだわってから、不意の停止や強制再起動に悩まされたことが一度もなくなりました。
以前は作業途中で止められるたびに胃の奥が痛くなるようなストレスを感じていましたが、それも今では遠い記憶です。
気持ちに余裕が生まれると、結果的にアウトプットの質までも高まる。
これは誇張ではありません。
実際に身をもって体験しています。
見た目か安定性か。
私は以前、その選択を誤りました。
けれども今ならはっきり言えます。
美しい外観に心を奪われるより、通気性を優先するべきだと。
オシャレなケースは確かに目を引きますが、冷却を犠牲にしてまで選ぶ理由にはなりません。
パーツが安定して働き、静かに、力強く動き続ける。
その安心感こそが、仕事を支える本当の武器なのです。
歳を重ね、経験を積んだからこそ気づく価値観なのかもしれません。
40代の今、私ははっきりとそう断言できます。
揺るぎない作業環境が、最終的に成果物のクオリティを高めるのだと。
結局、安心して取り組める環境こそが最大の生産性なのだと気づいたのです。
落ち着き。
実用性。
この二つがPCを選ぶ際の軸になった今、私は無駄な迷いを持っていません。
クリエイターPCのGPU選びでよくある疑問
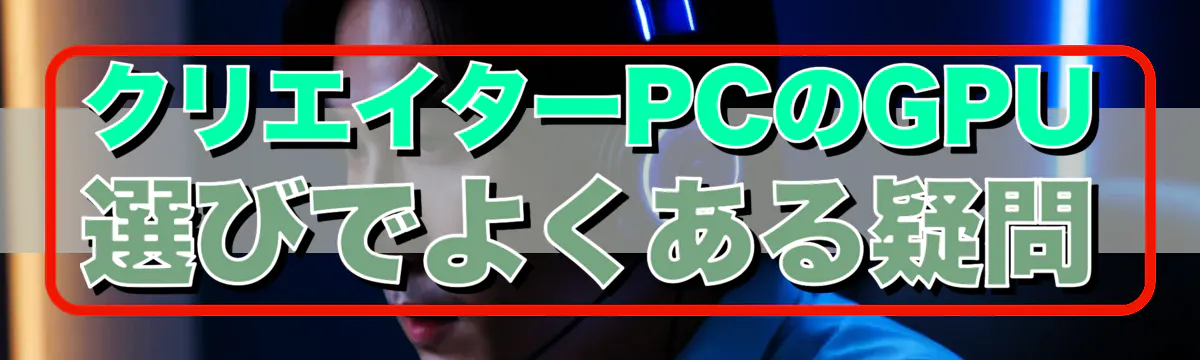
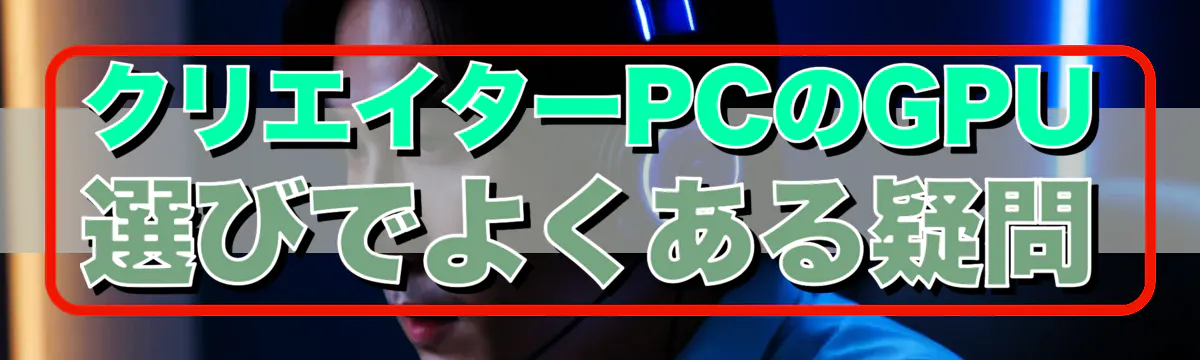
動画編集に最低限必要なグラフィックカードのクラスは?
CPUやメモリももちろん大切ですが、実際に編集画面で感じる滑らかさや作業のテンポを支えてくれるのはGPUであり、そこが弱いと効率だけでなく気持ちの余裕まで奪われてしまいます。
私は過去にそれを痛感し、今は強く「GPUにしっかり投資すべきだ」と考えています。
例えば、フルHD編集であればRTX4060クラスが最低限、4K編集を主軸とするならRTX 4070以上が現実的なラインです。
なぜこれほど差があるのかというと、動画編集ソフトが持つGPU依存度の高さに理由があります。
特に複雑なエフェクト処理や書き出しの際には性能差がそのまま時間差に現れ、1プロジェクトあたりの作業リズムまで変えてしまうのです。
そして何より厄介なのは、数分の遅れやカクつきが積み重なることで集中力が途切れ「もういいか」と妥協しそうになる瞬間が増えることです。
仕事への満足度。
そこまで直結します。
同じタイムラインを扱っているはずなのに、RTX 4070ではまるで映像の流れが生き物のように自然で、ストレスがほとんどなくなったのです。
しかし新しい環境に切り替えた途端、その違和感がフッと消え失せ、心地よさすら感じるほどになりました。
さらに最近はAIを活用したノイズ除去や緻密なカラー補正など、GPUを酷使するツールを使うことが増えています。
RTX 4070以上のカードでこれらを扱うと、PCはただの機械ではなく信じられる相棒のような存在に変わります。
自分のスキルを支え、裏切らないツールだと実感できるのです。
たとえばPremiere ProやDaVinci Resolveといった主要なソフトは、アップデートのたびにGPUメモリを積極的に使い切る前提の仕様へと進化しています。
これは最新ゲームが高精細なグラフィックを前提にハードウェア性能を限界まで要求する状況に近く、足りない性能を工夫で補うのはほぼ不可能です。
つまり「今は大丈夫だから問題ない」という考えは危うく、数年先を見越した選択こそが安心を生むのです。
とはいえ、すべての人にハイスペックなGPUが必要だとは思いません。
例えばYouTube向けに簡単な動画を作る程度であれば、RTX3050でも充分使えます。
ただし実際の現場では、編集途中でブラウザや他のアプリも開いたり、何度も書き出しを試したりするものです。
実用性と余裕のバランス。
私もよく「コスパを優先すべきか、それとも余裕のあるGPUを選ぶべきか」と聞かれます。
正直なところ、迷うくらいならワンランク上を選んだ方が精神的に負担が少ないです。
理由は単純で、パフォーマンスに余裕があれば新しい案件や予想外の負荷がかかっても余裕を持って対処でき、慌てずに済むからです。
特に4K編集は分かりやすく差が出ます。
プレビューが滑らかであるかどうかは、効率だけでなく映像のクオリティ確認にも直結します。
プレビュー再生がガタつくと、映像の違和感を見落とし「おそらく大丈夫だろう」と妥協してしまい、最終書き出し後に大きな修正対応が必要になる。
そのリスクを避けるためにも、大抵の場合はRTX 4070以上を使うのが賢い判断だと私は感じています。
さらに進んで8KやRAW素材を扱う流れが強まっていることを考慮すれば、RTX 4080クラスを選択肢に入れる意義は明らかです。
私自身も「ここまでは要らないかも」と感じながら「でも将来に備えるなら今なのかもしれない」と考え、ひとつ上の性能を検討しました。
そんな意味を持っているのです。
最終的に私が考える指針はシンプルです。
これによって安心して数年間は戦える環境を手にでき、余計な不安を抱えずに作業へ集中できます。
未来志向の選択。
AI処理やCG制作に安心して使えるGPUはどれ?
AIやCG制作に本気で取り組むなら、私はRTX4080以上のGPUを選ぶべきだと考えています。
処理待ちで何分も手が止まることがなくなり、仕事のリズムが途切れないことがどれだけ大きな意味を持つかを実際に体感しました。
集中力が削がれないまま一日を駆け抜けられることは、ただ性能が高いという以上に精神的な支えになります。
以前、私はRTX4070TiとRTX4090を同じ案件で試しました。
軽めの編集作業や生成なら4070Tiでもそこそこ対応できますが、本格的にAI画像生成や複雑なエフェクトを扱おうとすると途端に限界が見えてきます。
GPUのファンが回りっぱなしで、使用率は常に高止まり。
見ていて「もうこれ以上は無理をさせられないな」と思わず口にしてしまったほどです。
それに比べると4090は別世界。
余裕のある環境がこれほどまでに作業の安心感を生むとは、正直想像を超えていました。
最近は多くの人がStable Diffusionやローカルの大規模言語モデルを試していますが、そこで必ずぶつかるのがVRAMの壁です。
私も最初はVRAM12GBの環境でなんとかやりくりしていました。
しかし現実として、モデルを分割して読み込むしかなく、動作がもたつき、エラーが頻発して強制終了。
仕事にならない日が続いたのです。
24GB以上になるとその状況は一変しました。
読み込みの失敗は激減し、推論開始から完了までの待ち時間もスムーズで、まるで渋滞が一気に解消した道路を走っているような快適さ。
あの差を味わってしまうと二度と12GBには戻れません。
VRAMこそが性能の肝。
もちろん4090となると値段が現実的な壁になります。
私も購入時は「さすがに高すぎるだろう」と相当躊躇しました。
周囲からも「投資額に見合うのか」と問いかけられました。
そこで候補に浮かんだのがRTX4080Superです。
このモデルは実にバランスが良く、特に8K素材を扱ったときも安定感が抜群でした。
重たいシーンでViewportを回してもカクつくことがなく、思わず「やっとストレスから解放された」と独り言が出たくらいです。
そうした体感的な快適さが生産効率に直結します。
スペック表以上に、その実務における差は大きな意味を持つのです。
ここ数年でAppleのMシリーズを搭載したMac Studioも存在感を増してきました。
実際に持っている同僚からは「熱も少なくて快適」と聞きますし、使いやすいUIも魅力的です。
特にDaVinci ResolveのようにCUDA最適化が効くソフトは、8Kでも驚くほど軽快に動作することがあります。
Appleが悪いわけではなく、むしろ優秀だと思いますが、現時点での優位性はNVIDIAだと私は断言します。
時間は有限だと痛感します。
実際の制作における最大の敵は、待ち時間にあります。
GPUが数分単位で処理をしている間に作業者が手を止める、その繰り返しが積もれば膨大なロスになるのです。
高価なRTX4090や4080Superを導入するのは、単なる贅沢や自己満足ではありません。
私の場合、購入してからタスクを一日で終わらせるスピードが以前より格段に早まりました。
そのおかげで浮いた時間を別案件の検討や次のアイデア出しに回すことができ、仕事全体の質が確実に上がりました。
これは金額以上に得難い価値でした。
だから私は断言します。
AI処理やCG制作を本気で取り組むなら、RTX4080以上が現実的かつ最適な選択肢です。
コストとパフォーマンスのバランスを考えれば4080Superが妥協点として非常に優秀で、圧倒的な効率を求めるなら4090が唯一の答えになるでしょう。
確かに価格は高額です。
私は導入してから毎日のようにその恩恵を実感しており、購入を決断した過去の自分を今でも褒めてやりたい気持ちです。
これが、私の結論です。
もうAIの処理落ちに悩まされることはありませんし、制作で立ち止まる不安もない。
私はもう迷わない。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56KA


| 【ZEFT Z56KA スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09G


| 【EFFA G09G スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56O


| 【ZEFT Z56O スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R56DAG


エンスージアスト級のパワーを備えるゲーミングPC、プレイヤーの期待に応えるマシン
バランスドハイパフォーマンス、最新技術と高速32GB DDR5メモリで圧巻のパフォーマンスを誇るモデル
話題のCorsair 4000D Airflow TG、隅から隅まで計算されたクールなデザイン、美しさも機能も両立するPC
Ryzen 9 7950X搭載、プロセッシング性能の新境地を切り開く、ハイエンドユーザーに捧げるゲーミングPC
| 【ZEFT R56DAG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
4Kや8K編集をこなすにはGPUの性能がどれくらい必要?
正直に言いますと、映像編集における快適さはGPUの性能に大きく左右されると私は感じています。
解像度が4Kであれ8Kであれ、実際に作業を進める中では、その差が作業効率や精神的な余裕にまで影響してくるのです。
これまで何台ものPCを試しながら環境を整えてきましたが、最終的にたどり着いた実感は「妥協なくGPUへ投資することが結果的に一番の近道だ」という、非常にシンプルで逃げ道のない答えでした。
編集の途中で映像がカクついたり、再生すらままならない状況に陥ると、ただ苛立つだけでなく、自分の集中力やテンションまで大きく削がれてしまいますから。
だからこそ、ここに手を抜く選択肢はないと断言したいのです。
数年前のことになりますが、私が初めて4K編集を本格的に取り入れたときの話です。
当時は、今使っているGPUのままでもなんとかなるだろうと軽く考えていました。
しかしいざタイムラインに複数の4K動画を並べた瞬間、映像はカクつき、プレビュー解像度は落とさざるを得ず、まともに作業が進まない状態に陥りました。
心の中で「ああ、仕事にならない」とつぶやいたのを今でも覚えています。
実際にRTX4070以下の性能では厳しく、試行錯誤の末にRTX4070へ切り替えたときの胸の軽さは忘れられません。
やっと安心して作業が進められる環境を手にした、そんな安堵でした。
もっとも、8K編集ではそのレベルの安心感など簡単に吹き飛ばされます。
最初に8K RAWの映像データに触れたとき、私は正直「これは過酷すぎる」と言葉を失いました。
これがまるで別世界だったのです。
タイムラインが素直に追随し、プレビューは流れるように進み、カラーグレーディングも引っかかりなく操作できる。
あまりの違いに「これぞGPUの底力か」と思わず声が漏れてしまいました。
この差は、数字や仕様の比較だけでは到底伝わりません。
人力で黙々と荷物を運び続けていたところに、ある日突然フォークリフトが現れたような感覚でした。
効率化という言葉では足りず、心身への負担が軽くなることで生まれる余白の価値に気づくのです。
結果として、作業のスピードが上がるだけでなく、仕上がりを見直す余裕や新しいアイディアを試す余白まで手に入る。
さらに言えば、GPUは単に編集だけでなく、レンダリングやエンコードの時間短縮にも大きくかかわってきます。
現在はCPUとGPUの組み合わせでハードウェアアクセラレーションを効率的に活用できる環境が整っているため、これがうまく動作すると納品前のレンダリング時間が文字通り半減してしまうこともあります。
昔は納品前の徹夜作業が当たり前で、締め切り直前の胃の痛みと戦っていました。
それを思い返すと、今の環境がどれほどありがたいか身に染みて感じます。
「もう後戻りできないな」と苦笑しながら思わず口元が緩むことさえありました。
もちろん、こうした高性能GPUを導入するうえで無視できないのが電力と発熱の問題です。
RTX4080や4090は圧倒的な性能を誇りますが、消費電力の高さと発熱量が大きな課題になります。
かつて私も十分な電源ユニットを用意せずに導入した結果、PCが安定せずに作業が中断されるという痛い目を見ました。
結局、電源もケースのエアフローも見直すことになり、その時「準備不足は結局高くつく」と身に染みたのです。
だから今の私は、GPUを検討する同僚や知人に次のように話しています。
それ以上の負荷をかけるつもりがあるなら、4070Tiを選び余裕を持たせること。
そして複数ストリームを扱ったり、エフェクトを多用したりする本格的な映像制作ではRTX4080以上を検討すべきだと。
ただし導入の前には必ず電源と冷却を見直すべきだと伝えています。
GPUは単体の性能だけで成り立つものではなく、システム全体とのバランスで初めて真価を発揮できるからです。
私は心から思います。
機材選びで後悔はしたくない。
投資すべきところには投じ、削れる部分では割り切る。
そうした取捨選択の姿勢こそが、制作を仕事として続けるために必要な態度だと。
編集作業は繊細で、少しのカクつきや不安定さで全体のリズムが崩れてしまいます。
逆に、しっかりとした環境の安定感があれば、作業に没頭しながら自分らしいクリエイティブな力を発揮できる。
それが最終的には作品の完成度に直結します。
信頼できる環境がそこにあることの大切さ。
そして最後に強調したいのは、妥協しない選択は必ず自分を救うということです。
映像編集は想像以上に体力を消耗し、精神力を求められる仕事です。
だからこそ、GPUというのは単なる性能や数値の誇示ではなく、長時間にわたる制作活動を支える守りの存在になるのです。
私はそこにこそお金をかける意味があると信じています。
もしこれを読んでいるあなたが新しいマシンを検討しているなら、カタログスペックの数字だけで決めずに、ぜひ実際に編集やレンダリングを試し、その体感の違いを味わってみてほしい。
その実感の中にこそ、機材選びの本当の意味が隠れています。
コストを抑えたいときにおすすめできるGPUは?
コストを抑えてGPUを導入するとき、私が現時点で最も安心しておすすめできるのはRTX4060クラスだと考えています。
なぜそこまで言い切れるのか。
それは値段と性能の釣り合いがちょうどよく取れており、日常的に業務で使う場面で「これなら十分だ」と思える手応えをしっかり感じられるからです。
動画編集やRAW現像の作業を支える計算性能とVRAMを持ちながら、過剰に財布を圧迫しない。
そんな堅実な選択ができるのが、このクラスの良さだと私は実務を通して実感しました。
過去にRTX4060と3070を並べて比べたことがあります。
確かに4K編集になると3070が優位でした。
しかし私の現場の多くはフルHDやQHDが中心で、その範囲なら3060との差は思ったほど開かなかったのです。
正直「あれ、意外に変わらないな」という感想でした。
効率重視で考えるのなら「3060で十分じゃないか」と肩の力が抜けた瞬間でした。
もちろん、予算に余裕があれば3070やそれ以上を選択するのも魅力的です。
ですが仕事道具という観点で言えば、必要に迫られた時点で上位モデルに移行すれば良い。
最初の一台としていきなり上を目指す必要はないと私は思います。
むしろ柔軟さを持って迎え入れる方が長い目で見て健全です。
ただ時代の変化も頭に入れないといけません。
最近は生成AIやエフェクト処理など、GPUへの負担が増えるワークフローも少なくない。
GPU本体の安さだけを見て飛びつくと、電力や発熱による追加コストが後から重くのしかかるリスクがあります。
電源ユニット強化、冷却装置追加。
同じ予算感で考えていたはずが、気付けば大幅な出費へと化けることがあるのです。
これは見落としがちな落とし穴ですね。
その点、RTX4060はシステム全体とのバランスが良い。
TDPが抑えられており600W程度の電源ユニットで十分に余裕を持って動作できます。
だからGPU本体だけではなく、運用コストまで含めて「この一枚でいい」と納得できる。
安心感。
昨年、友人に「YouTube動画編集用のPCを新しく組みたい」と相談を受けました。
スペック表と価格の間で散々悩みながら、一緒にパーツショップを巡ったことを今でも覚えています。
友人は本心では上位モデルを欲しがっていました。
ただ現実的に冷却コストや発熱の問題と睨み合ううちに、最終的に3060を選んだのです。
その結果は大成功。
Premiere Proでの書き出しは安定し、配信ソフトを同時に動かしても止まらない。
その姿を見たとき、私は思わず「やっぱりこれで良かったな」と声が漏れました。
背伸びして高級GPUを構えるよりも、堅実な一枚を信じて日々の作業を地道に積み重ねること。
それがビジネスシーンで本当に必要なことなのだと。
納期に追われる現場だからこそ、大事なのは誤作動の心配がなく毎回安定して働いてくれる環境です。
そのありがたみを痛感しました。
振り返って思うのは、数字上のスペックやベンチマークの差ばかりを追うのではなく、自分が今どんな作業を多くこなしているのかを冷静に捉えることの重要さです。
机に向かってキーボードを叩き、実務を積み重ねるからこそ「これが今の自分には最適だ」と腑に落ちる瞬間が訪れる。
RTX4060を使っていると、その理解が腹の底から染み込んでくるようでした。
結局のところ、GPU選びとは自分の状況と向き合うこと。
私にとっては3060がまさにその存在でした。
肩ひじ張らず、それでいてしっかりと仕事を支えてくれる一枚。
だから迷っている人に伝えたいのです。
性能で周囲に格好をつけるよりも、毎日の作業を支えてくれる存在を選んだ方が結果として良い。
このバランス感覚を、もっと多くの人に味わってほしいと思います。
その先に続く日々の安心と、積み重ねていける成果が待っているのです。